「お茶の出し方」さえ工夫できる…スープストック創業者が語る新規事業で成功する人の考え方
プレジデントオンライン / 2023年9月21日 17時15分
■当事者意識から出発した新規事業は強い
「新規事業をやろう」と思って始めた新規事業が上手くいくところを、僕はあまり見たことがありません。なぜか。事業をやることが目的化した事業には、当事者がいないからです。
新しい事業は、リソースがないなかでゼロから生み出さないといけない。生み出したあとも、ちゃんと運営して継続拡大させていかないといけない。きっと、上手くいかないことだらけでしょう。
そのときに、「これは“私”がしたいことだ」という当事者意識を誰も持たないでいると、みんなでボールを渡し合って終わってしまうことが多いのです。
逆に言えば、「“私”はこれがしたいんだ」という当事者意識から出発した新規事業は強い。リソースがなくても、なんのお膳立てがなくても、困難を突破していくことができます。
■「何かチャレンジしたい」未経験で絵の個展を開催
私は33歳のときに、絵の個展を開きました。新卒で三菱商事に入社してから10年経ち、「このままただサラリーマンをやって死んでいくのは嫌だな」という思いがはっきりしたんです。それで、「何かチャレンジしたい」と思って、長年憧れていた絵の個展をやりました。1996年のことです。
そのときの私は、プロのアーティストでも何でもありませんでした。学生時代にイラストをちょこちょこ描いていたぐらいで、絵というような絵は1枚も描いたことがない。キャンバスを買ったこともなければ、筆も持ったこともない。アート業界に知り合いもいないので、個展を開くといったって何から手を付けていいかわからない。
ギャラリーと美術館の違いすらわかっていなかったのでしょう、若い人の初個展としてはあり得ないぐらい広い会場を借りてしまった。もちろん費用も相当かかりました。いま思うと本当にゾッとします。その広さの会場を埋めるために、1年間で70点作品を描きました。週に1枚以上ですから、かなりのハイペースです。朝4時に起きて、出社前に描く。当時は娘が生まれて、まだ2歳ぐらい。いま思い返すと、何もかもが無茶苦茶でした。
■合理的な理由や真っ当な理屈は何もない
それでも何とか開催にこぎつけ、おかげさまで作品は全部売れて、その後も4回ほど個展を開くことができました。
個展をやったのは、新規事業のためでもビジネスのためでもありません。ミッションもビジョンもゴールもありませんでした。合理的な理由や真っ当な理屈は何もなく、ただただ、現状を突破したかった。何かに出会いたかった。やりたいからやった――そんな感じでした。
この体験で得た、「自分で思いついて自分で作って人に直接手渡す」という喜びは、とても大きかった。それでいい気になって、これはビジネスでも同じことができるはずだと考えて、新規事業がやりたいという意欲が湧いてきました。
元々、都市開発事業部という部署で天王洲の開発を担当していたんですが、個展を開いたときに所属していたのは情報産業部グループという部署で、リアリティはゼロ。もっと手触り感のある、リアリティのある職で働きたいという思いが強くなったんですね。
そのときたまたま、情報産業グループの常務と、三菱商事が株主だった日本ケンタッキーフライドチキン(KFC)の社長が、「一緒にプロジェクトができたらいいですね」とパーティーで話していたという情報をキャッチしました。私はすかさずKFC向けのシステム開発の企画書を作って常務に提案、なんとか出向させてもらいました。それがSoup Stock Tokyoの創業に繋がっていきます。
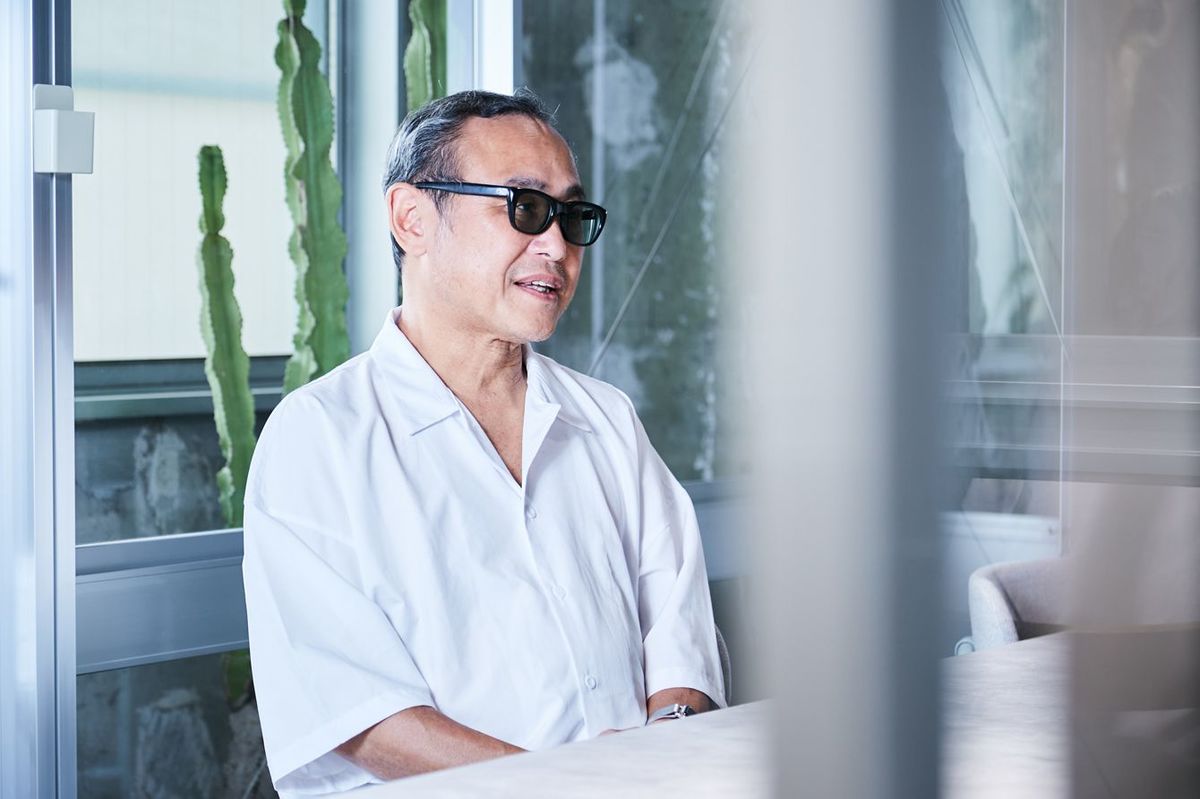
■利益を超えた理由が必要
いま、新規事業はますます成功しづらくなっています。高度成長期は拡大の時代でしたから、成功と失敗の確率は7:3ぐらいだったと思います。しかし、停滞の時代のいまは、4:6。6割が失敗すると思ったほうがいいでしょう。単純にお金を儲けたいだけなら、マカオのカジノにでも行ってルーレットで黒か赤のどちらかに賭け続けているほうが勝率は高いぐらいです。
負ける可能性のほうが高いゲームにそれでも挑戦するには、利益を超えた理由が必要です。それは、個展をやったときの私のように、「私はこれがしたい」という個人的な理由かもしれないし、「社会にはこれが必要だ」というソーシャルな理由かもしれません。
私は、J型とS型という表現をよく使います。J型とは、人生・自分ごと。S型とは、ソーシャル・システム。個人的な体験であるJ型が入り口となりながら、S型の意義を世の中と共有して、ビジネスとしてのシステムを構築していく。こうしてJとSの両足で前に進んでいける人には、「突破力」があります。
球を持ってひたすらゴールに向かう力、泥をかぶってでも歯を食いしばって球を守り抜く力、そう言えばいいでしょうか。突破力があれば、新規事業に成功するチャンスは高まります。
会社のリソースが足りない、予算がつかない、上司がダメ……。そんな不満を言っているぐらいだったら、新規事業なんてやらないほうがいい。相手のせいにしたら終わり。他人のせいにするのが一番簡単です。
新規事業を認めてもらえない、新規事業が上手くいかないのは、その商品やサービスが必要だということを、あなたが上司や会社や社会に説得できていないからです。
■経営会議で泣きながらプレゼン
武宏くん、という人がいます。私が社長をしていたスマイルズのセレクトリサイクルショップ事業PASS THE BATONの店長を務めたあと、新宿でBar toiletという小さなバーを始めました。
彼は、新規事業を提案するにも、今の現場で認められなければ資格がないと感じていた。そこでまずは自分の実力を示すためにPASS THE BATONで高い業績を上げ、店長としてのMVPに。表彰式で表彰されて壇上から降りたその足で、隠し持っていたBar toiletの企画書を副社長に手渡しました。
「自分には娘が2人いる。娘たちが将来大きくなって、『チャレンジしたい』と自分に相談してきたとき、自分がチャレンジしていないとそれに答えられないから、自分はチャレンジしたいんです」
表彰式のあと行われた経営会議で彼はこう言って、泣きながらプレゼンしました。飲食業の大変さを肌でわかっている私たちも、「わかったわかった、やろう」と言うしかなかったです。
彼のような当事者意識があれば、あとはもう球を渡して走っていくのを見守り、相談を受けたり、軌道修正のアドバイスを少ししてあげるだけでいい。とにかく球を持って走り、ゴールに球を置くんだというのがはっきりしているから、何も心配はありません。
会社が「新規事業をやらなきゃ」と利益を目的に始めても、誰が泥かぶってでも球持ってずっと走り抜くのかとかその人の動機づけがない。真ん中がボッカリなくて、手段しかない仕事は、うまくいかないでしょう。
■「暇つぶし」か「表現」しかすることがなくなる
私は、これからの時代は「ピクニック紀」になると思っています。ピクニックには、草原と自分と他者しかいません。スポーツのような勝敗はなく、目的も目標もなく、ただただ野原で遊び、交流する――ピクニック紀は、そんな世界です。
ピクニック紀は仕事がどんどん減っていく時代でもあります。気候変動や少子化が進み、AIやロボットがますます発展していくなかで、人から与えられる請け負いの仕事はどんどん減っていくからです。
仕事量の減少にあわせて、働き方も変わります。仕事は全部プロジェクトベースになり、私たち全員がフリーランスになる、そういうイメージです。
これからの人間は、「暇つぶし」か「表現」しかすることがなくなると言われています。30代の人も、60代の人も同じです。ピクニック紀で何よりも大事なのは、「自分は何者か」を確立すること。そして、その自分の価値によって他者とつながることです。
想像してみてください。ピクニックをしている人に、あなたが「私は○○会社の部長です」と言っても、「で?」と思われるでしょう。でも、「料理が好きです」「ギターが弾けます」「詩人です」と言ったら、その人は面白がってあなたをピクニックに招き入れてくれるはずです。
いままでの数十年は、仕事にかまけて自分のことを考えなくても済んだ時代でした。でもこれからのピクニック紀は、当事者意識を取り戻して、自分の人間としての価値、幸せ、在り方を考えなくてはいけない時代です。そうしなければ、社会の一員になることもできません。過酷な時代だと思います。

■新規事業は自らを表現する仕事
こうした時代背景を踏まえると、新規事業は自らを表現し、自分自身の価値を他者に示していく方法のひとつだとも考えられます。
「表現」と言うと、アーティストやミュージシャンといった特別な存在がイメージされるかもしれません。でも、どんな服を着たいか、どんな話し方がしたいか。何を作りたいか、何を描きたいか。そんな、日常生活という小さいスケールのなかで自分の意思みたいなものを切り出したり発揮したりすることも、表現のひとつ。
新規事業をシステマチックなスケールの大きい産業と捉えるのではなく、もっと、江戸時代の個人商店みたいな、「ヒューマンスケール」に自らを表現する仕事だと考えてもいいと思うのです。
私は最近、「新種の老人」と名乗って、YouTubeをやっています。北軽井沢にある自宅のひとつでの生活を自分で撮って、音楽も編集も自分で担当しています。登録者数も再生回数も微々たるものですが、自分が楽しくやっていることを誰かが楽しく見てくれていると思うと、幸せなものですよ。
■「こうじゃなきゃいけない」ってことはない
失われた当事者意識を取り戻すには、日々の仕事のなかで、「自分がその仕事をするのは誰のためか、何のためか」「自分だったらどうするか」を問い続けるといいと思います。
小さいことでいいんです。例えば、私はお客さんが来たとき、あえて黒豆茶を選んで出しています。将来、奈良にある実家を旅館にしたい。そのとき地元の黒豆茶を出したいと思っていて、そのためのちょっとした実験なんです。
お客さんにお茶を出す、というちょっとした行為でも自分を表現することはできる。自分を中心に据えてどうするかを考えるクセがついていなければ、普通にペットボトルのお茶を出していたでしょう。絶対的なルールや規範なんてないのだから、どんな仕事にも自分の意志を入れればいい。

最初の個展を開いたとき、手伝ってくれた女の子がこうつぶやいたことが今でも忘れられません。
「『こうじゃなきゃいけない』ってことはないわよね。」
すげえいい言葉だなと思って、私自身、「こうじゃなきゃいけないってことはない」という気持ちで、これまで頑張ってきました。
何でも自分で決める当事者意識を持つ。請け負い仕事でやっていてはだめです。
----------
スマイルズ 代表
1962年、東京都生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事入社。2000年スマイルズを設立、代表取締役社長に就任。「Soup Stock Tokyo」のほか、ネクタイ専門店「giraffe」、セレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、海苔弁専門店「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」を展開。「生活価値の拡充」を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案している。23年に社長交代を行い現職。著書に『成功することを決めた』、『やりたいことをやるというビジネスモデル―PASS THE BATONの軌跡』、『新種の老人 とーやまの思考と暮らし』など。
----------
(スマイルズ 代表 遠山 正道 構成=奥地維也)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
カルトかハーレムか「イエスの方舟」の"真実"描いたドキュメンタリー映画公開 若き監督が"方舟の地元"で語る
RKB毎日放送 / 2024年7月16日 17時34分
-
就活生必見!“成功するキャリア”の選び方は? ――リクルート出身スタートアップ社長 加藤史子さんに聞く
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月13日 9時0分
-
HERALBONY、BAUM、よなよなエールが新規参加! 54のブランドが集まる蚤の市『パスザバトンマーケット Vol.16』2024年7月20日(土)~21日(日)、品川・THE CAMPUSで開催
PR TIMES / 2024年7月9日 12時45分
-
高知東生59歳、逮捕後の“自分の第二章”で再認識「やっぱりエンターテインメントでしか生きられない」
日刊SPA! / 2024年6月26日 8時51分
-
HERALBONY、BAUM、よなよなエールが新規参加!54のブランドが集まる蚤の市『パスザバトンマーケット Vol.16』2024年7月20日(土)~21日(日)、品川・THE CAMPUSで開催。
PR TIMES / 2024年6月18日 14時45分
ランキング
-
1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分
-
2iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分
-
3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分
-
4「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分
-
517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録
ロイター / 2024年7月16日 9時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











