"手術はまるでお祭り"脳卒中患者を24時間365日受け入れて治療にあたる「アクティブな大阪の医者」の信念
プレジデントオンライン / 2023年9月29日 17時15分
※本稿は、千船病院広報誌『虹くじら 03号』の一部を再編集したものです。
■脳神経外科の手術は、まるでお祭り
脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)を疑われる患者が運び込まれると救急に緊張が走る。時間との勝負だからだ。
まず優先するのは、採血である。
脳血管に詰まった血栓を溶かすt-PAという薬がある。点滴で投与すると、約3分の1の患者に効果がある。t-PAを投与できるのは脳梗塞発症後4時間半以内だ。救急に搬送されてから60分以内の投与開始を目指す必要がある。適応するかどうかの判断は血液検査による。結果が出るまで、30~40分。まず採血をしないと、その判断が遅れてしまう。
採血の後、放射線科でMRI(磁気共鳴画像)やCT(コンピュータ断層)を撮影、脳で何が起きているのか調べる。
意識混濁の原因が脳の血管の詰まりではなく、破れたことならば、開頭手術がありうる。またt-PAで出血性の副作用が出た場合も手術だ。
手術が要るとわかればオペ室は準備に追われ、開頭が始まると緊張感は最高潮に達する。脳の柔らかさは木綿豆腐ほど。崩さないように細心の注意を払いながら、脳みそを分け、深部にある破れた血管を処理する。手術時間は4~5時間。終わればみんなグッタリだ。
「脳神経外科の手術は、まるでお祭り。みんなでわっしょいわっしょいとやって、嵐のように過ぎていく。メリハリのあるところが自分の性に合っています」
患者が運び込まれてからの怒涛の数時間をこのように表現したのは、千船病院脳神経外科部長の榊原史啓である。
千船病院は2021年4月、一次脳卒中センター(以下PSC)の認定を受けた。PSCは脳卒中患者を24時間365日受け入れて、t-PA静注療法などの急性期診療を行う。
新たにPSCの認定を受けるというミッションを掲げた千船病院の脳神経外科が、連携する兵庫医科大学病院から招いたのが榊原だった。
■「ベテラン部長、中堅、伸びる若手」で体制をつくれるか
最初に来たときの印象をこう語る。
「千船病院はメディカルスタッフ(医師を除く医療従事者の総称)がとても優秀です。看護師は協力的で、リハビリのスタッフもやる気のある人ばかり。これならすぐ立ち上がるなと」
千船病院がPSCを立ち上げたのは、2020年3月に大阪府知事から「地域医療支援病院」の承認を受けたことと関係している。地域医療支援病院は、地域医療の確保を目的とした地域の基幹病院のことだ。地域のかかりつけ医らを支援するため、相応しい構造設備を備えていることなどが条件になる。副院長の樋口喜英は次のように説明する。
「今後ますます高齢の方が増えていくことを考えると、成人病やがん、骨折などでも地域のニーズに応えられる病院になっていく必要がある。その中でも、脳卒中の受け入れは地域から強く求められていたものの1つでした」

以前は、千船病院は脳卒中の受け入れに積極的ではなかったと、樋口は振り返る。
「脳神経外科は相当にハードです。全体をマネジメントするベテラン部長と、脂がのってバリバリ働いてくれる中堅、そしてこれから伸びる若手というバランスならうまく回るのですが、以前の脳神経外科は体力も技術もある中堅が不在で、対応できなかった」
大阪市西淀川区で脳神経外科の救急を受け入れているのは千船病院だけだ。千船病院が救急隊からの要請を断ると、患者は淀川を渡って福島区の病院まで搬送されるケースが多かった。
脳梗塞は治療が遅れるほど後遺症が残りやすくなる。地域医療支援病院を名乗るからには、救急隊からの要請やクリニックからの紹介を受け入れられる体制を構築することが急務だった。
「脳神経外科の医師は患者を受け入れるほど負担が増しますが、それをものともしないくらいアクティブな先生がいないとPSCは立ち上がらない。そう考えていたところに榊原先生が来た。求めていた人が加わったことで現実に動き出したんです」
■防衛医大から海上自衛隊、そして脳神経外科医へ
救世主となった榊原はどのような医師なのか。
出身は大阪府茨木市だ。医師という職業を意識したのは、中2で塾に入ったときに受けたIQテストがきっかけだった。本人は当時をこう振り返る。
「おそらく私にやる気を出させようとしたのでしょう。『キミ、このIQなら医者か弁護士になれるよ』と。それで調子に乗りました」
学区トップの進学校に入学するが、そこで現実を思い知る。まわりは自分より優秀な生徒ばかり。将来は官僚や経営者として活躍するだろう級友たちになかなか敵わない。ならば違う土俵で彼らを助ける役に回ろうと、医師を目指すことを決めた。
現役のときは志望校の医学部に落ちた。一浪して猛勉強したが、不合格。ただ、受験時期が違う防衛医科大学校には受かっており、二浪はせずに入学を決めた。
防衛医科大学校は防衛省の管轄で、医官となる幹部自衛官の育成を目的に設置されている。大学医学部と同じく卒業時には国家試験を受けて医師資格取得を目指すが、カリキュラムやキャンパスライフは大きく異なる。
「全寮制で、下級生は上級生と2人1部屋。軍隊のイメージそのまんまで、『声が小さい』と言われては後ろから蹴られるような毎日でした。私のときは65人が入学して、夏には1割が辞めていた。つらかったですが、おかげでストレス耐性がつきました」
2006年に卒業して海上自衛隊医官となった後は、防衛医科大学校病院で2年間研修。そこで出会ったのが脳神経外科だった。
もともと頭を使うより手先を動かすほうが好きで、外科医になることは決めていた。1年目は呼吸器外科で学んだ。肺がんは脳に転移することもあるので、脳についても勉強しようと翌年は脳神経外科に。そこで“わっしょいわっしょい”の世界に触れた。
「『終わったら飲みに行くぞ』というノリで、みんなでワーッと手術をするんです。語弊があるかもしれませんが、高揚感があって刺激的。自分はこの道を極めようと思いました」
研修が終わった後は自衛隊横須賀病院で2年間勤務した後、大学病院に戻り、脳神経外科医としての経験を積んだ。
医官になって9年目、転機を迎えた。防衛医科大学卒業生にとって、この「9年目」は大きな意味がある。卒業後、医官として9年間の勤務を義務づけられている。その期間が終了するのだ。
一人前の外科医として通用するという自信はあった。ただ、脳神経外科界で“匠の手”と呼ばれる上山博康や谷川緑野が所属する札幌禎心会病院脳神経外科――通称「上山塾」――に2年間、国内留学して、自信を粉々に砕かれた。
「手術のやり方がまったく違いました。たとえば大学病院のときはズバッと皮膚を切ってましたが、上山塾では皮膚の構造を考えながら切る。膜の上で剥がすようにして切ると出血が少ないんです。何から何まで洗練されていて、芸術作品のようでした」

国内留学すると、その半分の期間を医官として継続するのが内規だった。脳神経外科のない自衛隊舞鶴病院で隊員の健康診断などを担当した。それも重要な仕事だが、手術をしなければ外科医として腕がなまってしまう。1年後、渇きを癒すようにして手術ができる病院に転職した。
転職先として選んだのは兵庫医科大学病院だった。兵庫医科大学には、カテーテル治療で有名な吉村紳一がいる。脳神経外科医としてステップアップするためにカテーテルの技術も身につけようと選んだ転職先だった。
兵庫医科大学では1年半で130件の外科手術の術者を経験。そして2020年、千船病院PSC立ち上げを打診された。
■「バカヤロウ。そんなことで脳卒中センターができるか!」
2020年4月、千船病院にやってきた榊原が手始めにやったのは、救急隊や近隣のクリニックへの挨拶まわりだった。体制を強化して積極的に受け入れる方針であることを伝えると、たいていは「助かります」と喜ばれた。
むしろ壁があったのは院内の体制だった。
挨拶まわり効果で件数が増え始めた時期のある日の午後、脳出血を疑われる患者の受け入れ要請がきた。榊原が手術室にいくと、麻酔科医が「今埋まっている。他の病院に転送してほしい」と拒否。口論になった。
「バカヤロウ。そんなことで脳卒中センターができるか!」
大声を出したが、麻酔科医も譲らない。榊原は仕方なく転送の準備を始めた。
そこに駆けつけた樋口の証言だ。
「麻酔科の先生は患者の安全第一で、予定外の対応を行うことによって生じる様々なリスクは避けたい。一方、榊原先生は運ばれてくる患者へのスピーディな治療を第一に考える。両方とも真剣だから自然に声が大きくなったのでしょう。結局、麻酔科の先生に折れてもらい、受け入れてもらうことにしました」
脳卒中の患者を受け入れるという、病院の方針が伝わると現場も軟化する。この一件以降、麻酔科も柔軟に対応してくれるようになった。
■週6日は当直あるいはオンコール状態だが「普通に寝ていた」

榊原はこう語る。
「私は別に大変じゃなかったですよ。苦労されたのは、樋口先生を含め千船病院の幹部たちでしょう。いろいろ調整に骨を折っていただきました」
特に看護部では、人員配置を大きく変えて、脳卒中患者に対応した。榊原自身の負担も相当なものだ。PSC認定要件の1つは、脳卒中診療に従事する医師(専従でなくても可。前期研修医を除く)が24時間7日体制で勤務していること。
この要件を満たすため、週2日は当直に入った。1日は兵庫医科大学から応援に来てもらえたが、あと4日は外科や内科の当直医に任せ、榊原自身はいつでも駆けつけられるように待機していた。
「脳卒中で運ばれてくるのは、せいぜい夜11時まで。それ以降は発症してもご家族が寝ていて気づきません。気づくのは起きてからなので、朝6時ごろの搬送が意外に多い。夜中はお呼びがかからないから、普通に寝ていましたよ」
本人はケロリと語るが、週6日は当直あるいはオンコール状態。PSCは榊原のハードワークなしに立ち上がらなかったことがよくわかる。
その甲斐あって認定が下り、手術件数も増えた。2019年は約40件だったが、2020年は80件と倍増。手ごたえを感じた榊原は、「人がいればもっと患者さんを受け入れられる」と医局に増員を要請。2年目はさらに医師が1人増え、実際、手術件数は120件まで伸びた。
■持続的に支えられる体制構築を
ただし、榊原のマンパワーに依存していたことは否めない。榊原が、2022年に兵庫医科大学に戻ると、途端に手術件数が減った。
この事態を受けて、榊原は2023年4月に千船病院に戻ってきた。現在、PSCをふたたび軌道に乗せるべく奮闘中だ。
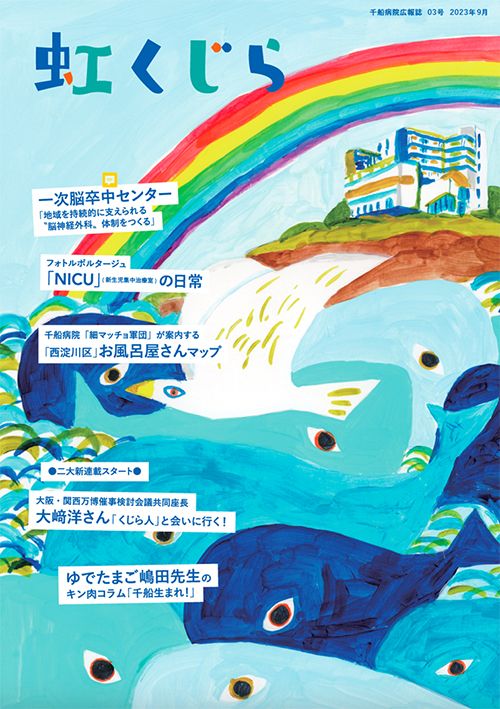
単に元に戻すだけではない。2021年9月に榊原は、兵庫医科大学でカテーテルの修練を積み、カテーテル専門医の資格を取得した。
専門医になれば、詰まった血管にカテーテルを入れて血栓を除去する脳血栓回収療法を行える。脳血栓回収療法は、t-PAの適応外や投与後に効き目がなかった症例に適応できる。
榊原の目線はあくまで高い。
「カテーテル中心の時代になっても、自分はやはり手術が好き。個人的には、またどこかに国内留学して腫瘍の手術を学びたい。そのためには、私がいなくても千船病院脳神経外科が地域を持続的に支えられる体制をつくる必要があります。まずはそこに全力投球です」
榊原がふたたび去るときが、千船病院脳神経外科が真の意味で脳卒中に関して地域の基幹病院になるときなのだろう。
(虹くじら編集部 取材・文=村上敬)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
Caseline導入により救急外来で初期対応の確定までの時間が10分へ短縮。オンコール医師の病院への駆けつけが約50%削減
PR TIMES / 2024年7月12日 14時15分
-
メディカルノートと柏葉脳神経外科病院、医療講演会『脳神経医療イノベーションフォーラム 医療の先にある絆~神経科学の拠点病院を目指して~』を開催しました。
PR TIMES / 2024年7月5日 18時15分
-
「女帝・小池百合子知事はまた公約不履行」突っ込まれそうな"無痛分娩の助成"…病院の受け入れが無理筋なワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 10時15分
-
未知の染色体転座切断点を探せ!世界の血液学会の“女性ヒーロー”三谷絹子氏を特集 DOCTOR'S MAGAZINE ドクターズマガジン7月号発刊
PR TIMES / 2024年6月29日 10時15分
-
「攻めのリハビリ」を実践するために“いい医者連携”が必要なのはなぜか【正解のリハビリ、最善の介護】
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月26日 9時26分
ランキング
-
1実は「ポイ捨て」しまくっていたキャベツの栄養 科学で解明「芯はおいしくない」と思うなかれ
東洋経済オンライン / 2024年7月15日 15時0分
-
2「子どもは無料」で簡単につられる大人たちの盲点 企業側の仕掛けには「わかったうえで」乗りたい
東洋経済オンライン / 2024年7月16日 9時0分
-
3カップみそに入ってる「白い紙」は捨てる?捨てない? 気になるギモンをメーカーが解説!…正解は?
まいどなニュース / 2024年7月16日 14時35分
-
4「これは奇跡...」破格の1人前"550円"寿司ランチ。もうこれ毎日通いたい美味しさ...。《編集部レポ》
東京バーゲンマニア / 2024年7月16日 7時2分
-
5“新しい働き方”として定着すると思いきや…コロナ禍を経た今になって、強硬な「リモートワーク廃止論」を示す企業が現れた理由
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 7時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











