若くして頭角を表すと成功できない…87歳・医大名誉教授が力説する「人生の勝者」となるために必要な考え方
プレジデントオンライン / 2023年11月12日 18時15分
※本稿は、高田明和『孤独にならない老い方』(成美堂出版)の一部を再編集したものです。
■答えが出ない時は時間にまかせる
政治家 ペリクレス
年を取ると、時間の意味を再認識します。
たとえば、大学にいた時、学内がもめ、収拾がつかなくなったことがあります。誰が考えても解決方法がないのです。私も「これは四次元の連立積分方程式のようなもので、解がない」などと冗談めいたことを思ったものです。
しかし、今も大学は存続しています。つまり、なんらかの方向で解決したのです。それが時間の力なのです。
このようなことは、あらゆる分野の、すべての出来事でいえるでしょう。
どんな問題があっても、たとえば来年の4月1日は必ず来るのです。その時には、問題も、ある状態になっています。その意味で、解決しているのです。
来年の4月1日に、問題がまだ続いている可能性もあります。それは「続いている」というように解決したのです。
多くのことは非常に複雑にからみ合っています。何が正しく、何が間違いかという単一の結論はありません。「時が来たらこうなった」というのが、唯一の答えになるのです。
■ふっと思ったことは正しい
仏教では、物事は因縁(いんねん)によって決まると考えます。因縁とは、すべてが宿命的に決まっているということではありません。
自分の努力、周囲の動き、社会の仕組みなどに、自分が過去にしたことの結果が微妙にからみあって結末を迎えるということです。
つまり、時間は因縁と現実の相互作用の中を進んでゆくのです。
中川宋淵(そうえん)老師は「私たちが見ている世界の裏では、因縁の嵐が吹いている」と言っておられました。
因縁は現実を支配していますが、その全貌は決して見えません。結果しか見えないので、人はそれを見て、時に「奇跡だ」と言うのかもしれません。
因縁は、最終的には現実の社会を動かしているので、私たちは、その大きな変化を感ずることもあります。それが予感とか直観と呼ばれるものです。
臨済宗(りんざいしゅう)天龍寺派管長だった関牧翁(せきぼくおう)老師は「ふっと思ったことは正しい。邪念で解釈するから間違うのだ」と言っておられました。
私はふっと思うことが多く、この言葉には感謝しています。そして、ふっと思ったことの真実性は、時間が証明してくれるのです。
時には待つことが最善の解決策になります。
■将来どうなるかは、誰も予測がつかない
すべてのことは、時が来ればうまくいく。
小説家 ヘンリー・ミラー
時間がどのような結論を出してくれるかは、誰にもわかりません。また、時間が出す結論は、必ずしも自分の思い通りではありません。
「おかしい、不思議だ」と感じても、それは、自分の思い通りにならなかっただけです。おかしく、不思議なのが現実なのです。
私たちの得られる情報は限られています。その限られた情報の中でも、自分に都合のよい情報ばかりを集めがちです。
その結果、私たちは見通しを誤り、「人間は何をするかわからない」などと人間批判をしたりします。しかし、それは的外れでしょう。
人間は未来を知ることができないのです。将来どうなるかは、誰も予測がつかないのです。
わからないことを心配したり恐れたりしても、事態は解決しません。筋違いの言動をして事態を悪化させたり、不安が高じて心を病んだりするだけです。
だから、ヘンリー・ミラーは「時が来ればうまくいく」と言ったのです。
私は、人生訓のすべては、この言葉に尽きていると思います。

■不安を手放し、「なるようになる」と腹をくくる
多くの人が同じことを言っています。
たとえば、頓知(とんち)話で知られる禅僧の一休宗純(いっきゅうそうじゅん)は、「なるようにしかならない」と言いました。
「何が起こるかわからないが、なんらかの形で解決される、私たちは、それを知らないだけだ」という意味です。
ビートルズの歌『レット・イット・ビー』もそうです。
レット・イット・ビーとは、苦難の時に「マザー・メアリー」が与えてくれる知恵の言葉です。「放っておきなさい」「なんとかなります」「あるがままに」といった意味でしょう。
マザー・メアリーは普通、「マリア様」と訳されますが、必ずしもそうでなく、「お母さん」と考えてもよいのではないでしょうか。
■未来は私たちのものではなく、なるようになる
ヒッチコック監督の映画『知りすぎていた男』で、女優のドリス・デイが歌う『ケ・セラ・セラ』も同じです。
ケ・セラ・セラとは「Whatever will be, will be」つまり「なるようになる」という意味です。
子供の時、「きれいになれる? お金持ちになれる?」と聞くと、母親は「なるようになるのよ」と答えます。
娘になって、恋人に「将来うまくいくかしら」と聞いても、彼は「なるようになるんだよ」と答えるのです。
そして自分が母親になり、子供から同じように聞かれた時も「なるようになるのよ」と答える、という歌です。

まさしく、未来は私たちのものではなく、なるようになるのです。
それなのに、私たちは未来を知る手がかりを探します。「歴史が教えてくれる」と言う人もいますが、同じことは再び起こりません。
「歴史から半分学べ、全部学ぼうとすると間違う」といわれますが、その通りだと思います。
私は、未来がわからなくても、未来を好ましいものに変えようと努力することが大切だと思っています。
将来どうなるかは誰にもわかりません。
心配したり恐れたりしても、事態は解決しないのです。
■消し去る、熟成させる、別のドアを開く…時間の働き
ピアニスト フジコ・ヘミング
年を取るにつれ、時間の働きの精妙さに感じ入ることも多くなります。
たとえば、私は学生時代、今思えば信じられないような行為をしたものです。たくさんの人に迷惑もかけました。
不思議と大事に至らず、留年などもせずにすみましたが、よく切り抜けられたものだと思います。
時間には、消し去る、熟成させる、別のドアを開くなどさまざまな働きがあります。私が今日あるのも、そういう時間の助けによるところが大きいと感じています。
■米国で定年を迎えていたらと思うとゾッとする
私は大学院で妻と共同研究をしていました。当時は医学部が少なく、卒業後も二人で研究を続ける道は、日本にはありませんでした。
そこで、米国に行くことにしたのです。米国の状況をあまり理解しないまま、永住のつもりで渡米しました。
しかし、当時の米国の人種差別は強く、日本人教授の下には米国人の部下が来なかったりしました。親しい米国人もできにくく、定年後は孤独に耐えかねて帰国したり、ロサンゼルスの日本人街に移住する人も多かったのです。

やがて私も帰国を考え始めますが、もう日本に居場所はなく、本当に帰国できるかどうか危ない状況でした。
生まれ故郷に新設された医科大学の教授になり、そこで妻も一緒に働けるようになったのは、偶然がいくつも重なった奇跡のようなことだったのです。
今でも、「もし、あの時に帰国できなかったら、今頃、米国のどこでどうしていただろう」と想像して身の毛がよだつこともあります。
米国で定年を迎えていたら、今のように本を書いたり、講演をしたり、若い人と研究をしたりする晩年は、とても望めなかったでしょう。
同時に、米国生活のような危険な道も、今の生活を実現するための伏線だったのではないか、とも思うのです。その細い道は時間という神様が選んでくれたのかもしれないと感じています。
私は偏った性格で、HSPでもあります。そのため、大変苦しみました。
■危険な性格や才能が今日の自分を支えている
一方、だから活躍できたところもあるのです。私の性格は研究、執筆、指導などには向いているらしく、帰国後も順調に仕事ができました。人にできない仕事も多少はできたと思っています。
そういう仕事をするには、他人にはない異常さが必要だと思います。見方によれば非常に危険で、失敗の可能性も大きい人生でしょう。
しかし、危険な性格や才能が今日の自分を支えているのは事実です。そう考えると、自分が異常な性格を持ち、危険な道を歩んできたのは、運命の大きな力がそうさせたのではないかと思わざるを得ません。
私の周囲にも、若い頃から温厚で人望のある一群の人たちがいました。勉強もでき、将来を嘱望(しょくぼう)されていました。
しかし、多くの人が、平凡な人生を送ったようです。優秀だというレッテルを張られたために、嫉妬と反感の渦に巻き込まれ、いらざる争いで苦労し、結果的にそうなってしまったのだと思っています。
■あせらずに「長い目で見る」賢さを磨く
人生は、予想もできない苦難に満ちています。中国でも「直木(ちょくぼく)はまず伐(き)られ、甘井(かんせい)はまず竭(つ)つく」といわれます。
まっすぐに伸びた木はすぐに伐採(ばっさい)されて木材にされてしまう、おいしい水が湧く井戸はすぐ飲みつくされてしまう、というのです。目立つと引きずりおろされてしまうから注意しろという格言です。
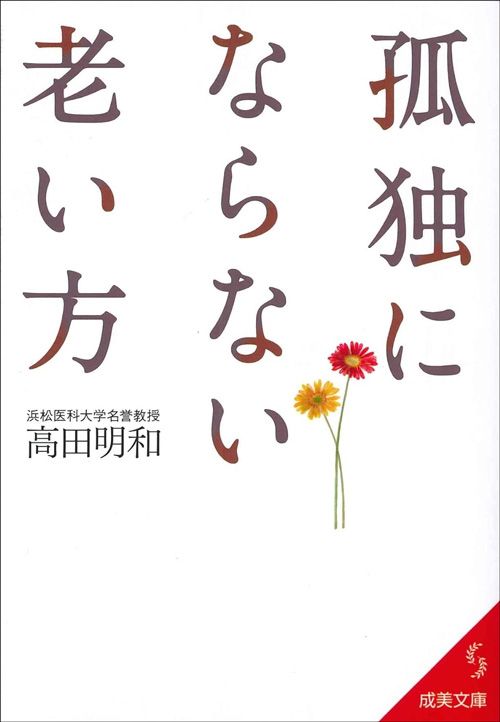
私が案外しぶとく生き延びたのは、失敗男だと思われたからかもしれません。
最近、やっと落ち着いて過去を客観的に見ることができるようになりました。すると、欠点だらけで、あまり能力もないのに、なんとか生きてきた自分をいとおしく思うようになれたのです。
これも時間の働きだと思います。ビジネスでは、往々にして、時間をコストとして扱います。しかし、人生では、時間は決定者、神様なのです。
先に頭角を現すと嫉妬の渦に巻き込まれ、
成功できないことも多いのです。
----------
浜松医科大学名誉教授 医学博士
1935年、静岡県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業、同大学院修了。米国ロズウェルパーク記念研究所、ニューヨーク州立大学助教授、浜松医科大学教授を経て、同大学名誉教授。専門は生理学、血液学、脳科学。また、禅の分野にも造詣が深い。主な著書に『HSPと家族関係 「一人にして!」と叫ぶ心、「一人にしないで!」と叫ぶ心』(廣済堂出版)、『魂をゆさぶる禅の名言』(双葉社)、『自己肯定感をとりもどす!』『敏感すぎて苦しい・HSPがたちまち解決』(ともに三笠書房≪知的生きかた文庫≫)など多数ある。
----------
(浜松医科大学名誉教授 医学博士 高田 明和)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「70歳でヨボヨボの人」と「70歳で快活な人」は何が違うのか…米国の実験が証明した"若々しさ"の源
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 8時15分
-
"何もしない時間"に耐えられない人が多すぎる…寝ても疲れが取れない人が今すぐ取るべき「休息」の種類
プレジデントオンライン / 2024年6月13日 8時15分
-
不登校の9割は3週間で解決できる…問題が長引く家庭が見落としている「再登校を叶える5つの条件」
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 10時15分
-
だから「マイナ保険証」利用率は6.5%どまり…岩田健太郎「成功か失敗か吟味しない日本のお役所体質の残念さ」
プレジデントオンライン / 2024年5月29日 16時15分
-
だから「優秀な社員」ほどどんどん辞めていく…部下のやる気を吸い取る"残念な上司"のヤバすぎる口癖
プレジデントオンライン / 2024年5月23日 9時15分
ランキング
-
1吉野家 「シュクメルリ鍋」のグランプリ祝福に松屋感謝 “電撃訪問”のお礼返しにSNS「リスペクト精神すばらしい」「何このやさしい世界」と感動
iza(イザ!) / 2024年6月17日 15時28分
-
2M&A仲介大手「全社株価急落」の深い理由 高額手数料や悪質ダイレクトメールにメスも
東洋経済オンライン / 2024年6月17日 10時0分
-
3キッコーマン「みぞれあん たっぷりおろし」1万9000本を自主回収…開栓時に噴き出すおそれ
読売新聞 / 2024年6月17日 17時30分
-
4「シャープ」は世界に誇る技術をもちながら、なぜ台湾企業に売られることになったか【プロの投資家が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 8時15分
-
5万博開幕まで300日前 一般向け前売り券販売伸び悩み、機運醸成が課題
産経ニュース / 2024年6月17日 20時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












