なぜマスコミはパレスチナ支持なのか…テロリストの娘を起用したTBS番組が無視した「ユダヤ人迫害の歴史」
プレジデントオンライン / 2023年11月19日 9時15分
■ネタニヤフ政権はハマス殲滅を目指している
10月7日、イスラム組織ハマスがガザからイスラエルを奇襲攻撃した。これに対して、イスラエルのネタニヤフ政権は、ハマスの壊滅まで戦うとして報復攻撃を展開している。
この事件を日本のマスコミも一斉に報じたが、中には首をかしげたくなるような報道もあった。特に10月11日にBS-TBSの「報道1930」が、元日本赤軍リーダーである重信房子氏の娘、重信メイを起用した際にはネット上でも多くの批判が沸き起こった。
日本のマスコミは中東情勢やパレスチナ問題に疎いのではないか。
今回の戦争には、歴史、宗教、人種差別などの背景があるが、日本のマスコミはそのような問題に関する知識も関心も欠けていると感じる。
ユダヤ人の2000年にわたるディアスポラ、ポグロム、ホロコースト、そして建国後の4次にわたるアラブとの戦争の歴史を振り返れば、ネタニヤフ政権がハマスを殲滅するまで攻撃を止めないという論理が理解できる。
ハマスによる今回の攻撃を「第2のホロコースト」ととらえているからである。
■ユダヤ人は人間として扱われなかった
私は、50年前にフランスに渡り、その後スイスやドイツなどでも研究生活を続けたが、ヒトラーがヨーロッパを支配した時代を研究対象としていたので、なぜユダヤ人がナチスに弾圧されたのかという問題に強い関心があった。
50年前のヨーロッパでは、ユダヤ人に対する根強い差別を日常生活の中で体験したが、この差別は、残念ながら今のヨーロッパでも続いている。
キリスト教が広まったヨーロッパ社会では、キリスト教徒はユダヤ教徒を軽蔑してきた。こうして中世以来、ユダヤ人は差別や迫害の対象となり、就くことのできる職業も限定された。
極論すれば、人間として扱われなかったのである。それだけに、ユダヤ人は宗教的にも、人種的にも強固なアイデンティティを確立していった。
■「ユダヤ人は死に値する」ヒトラーの演説
このユダヤ人蔑視の感情や行動は、19世紀後半のヨーロッパで拡散する。
ユダヤ人はセム語系統の民族であって、西欧のアーリア民族に比べて劣っているという人種主義思想となったのである。
これが「反ユダヤ主義(Antisemitism、アンチセミティズム)」である。
そして、ロシアなどでユダヤ人迫害(ポグロム)の嵐が吹き荒れた。
20世紀になって、この思想にとりつかれたのがヒトラーである。
1920年8月13日にホーフブロイハウスで行われたナチ党集会で、ヒトラーは演説し、「ユダヤ人は国家を建設する力を持っていない。ユダヤ人は労働意欲を持たない。人種としてあらゆる欠陥を持っている。放浪の民で独自の文化がない。ユダヤ人は、諸国家で寄生虫として生き、権利を享受しながら義務を果たさない。ユダヤ人は死に値する」と断言した。
1933年1月に政権に就いたヒトラーは、ユダヤ人迫害を実行に移し、アウシュビッツ収容所などで、600万人を虐殺した(ホロコースト)。

■ユダヤ人の受難の歴史
そもそもユダヤ人はどのようにして各地に散っていったのか。
古代のユダヤ人の歴史は『旧約聖書』に記述されている。ヘブライ人は紀元前1500年ごろに世界史に登場。ヘブライ人の最初の家長であるアブラハムが、カナーン(今のパレスチナ)に移住し、そこに約1600年住んだという。
ヘブライ人は、紀元前17世紀ごろにエジプトに進出し、紀元前13世紀ごろにはエジプトから追い出されて(いわゆる「出エジプト」)カナーンに戻り、ダビデ、ソロモンの時代に繁栄する。
■ユダヤ人は各地に離散した
しかし、その後、アッシリア、新バビロニアに征服され、バビロンに強制移住された(いわゆる「バビロン捕囚」、紀元前586~538)。捕囚を解かれたヘブライ人(このころからユダヤ人と呼ばれる)はカナーンの地に戻った。
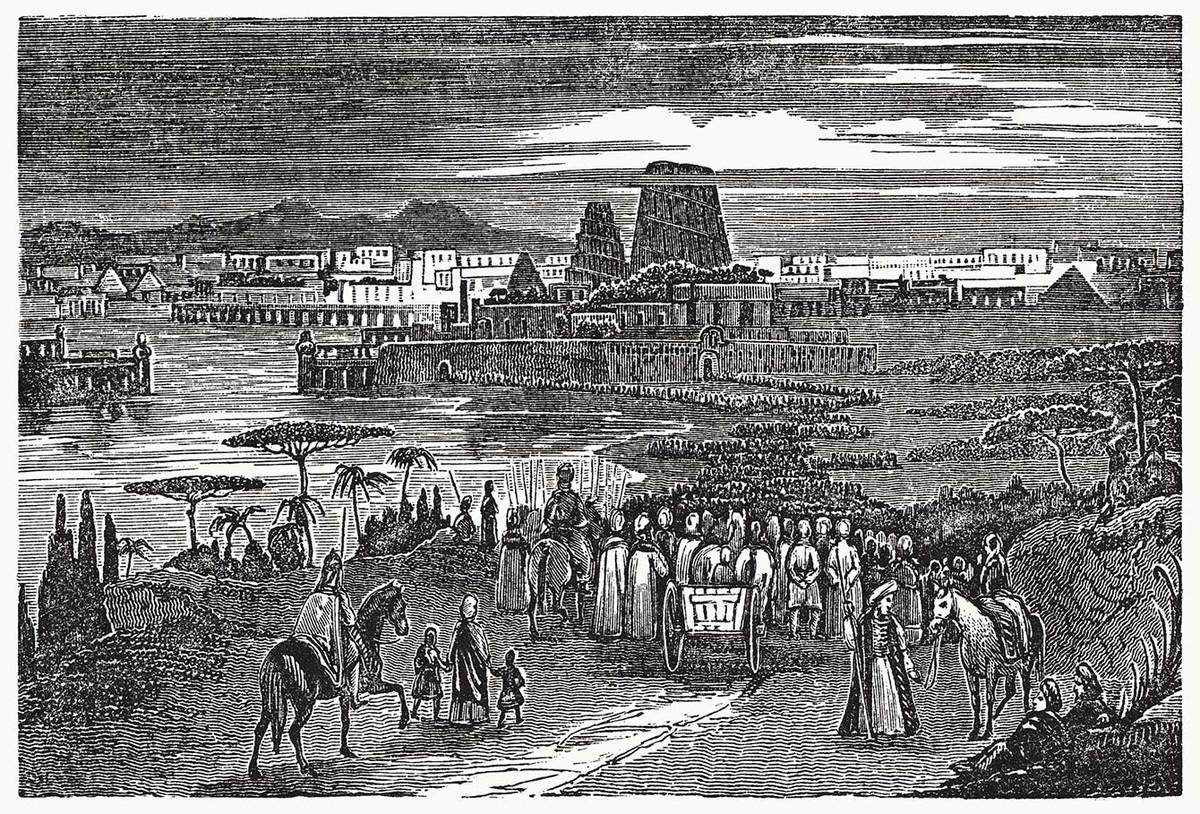
このころ、中東はペルシア帝国が支配したが、その後、ローマ帝国が勢力を拡大し、カナーンはローマの属州となった。紀元66年、ユダヤ人がローマに対して武装蜂起するが、ローマに鎮圧され、ユダヤ人は殺害されたり、奴隷にされたりした。その後、ユダヤ人はカナーンの地から追放され、各地に離散した(ディアスポラ)。カナーンも、ペリシテ人の名前から「パレスチナ」と改名された。
こうして、ユダヤ人は各地に散り、ユダヤ教を民族の絆として、それぞれの地で少数派として生活することになった。
■ロスチャイルド家が支援した「シオニズム運動」
19世紀後半から吹き荒れた反ユダヤ主義の嵐、ポグロムに心を痛めたハンガリー出身のユダヤ人ジャーナリスト、テオドール・ヘルツルは、ヨーロッパ以外の地にユダヤ人が安住できる国家を作ろうと考え、行動に移した。これがシオニズムである。
シオンとは、エルサレム南東にある丘の名前である。ユダヤ系財閥のロスチャイルド家は財政的にこの運動を支援した。
シオニズム運動が飛躍したのは第1次世界大戦の時である。当時のイギリスはドイツと戦っていた。そのドイツの同盟国がオスマントルコであり、これを後方から攪乱(かくらん)するために、アラブ人の力を借りようと考えたのである。
そこで、アラブが協力すれば、見返りに戦後にアラブに独立を認めると約束した。これが1915年7月に交わされた、「フセイン・マクマホン協定」である。
■イギリスの「二枚舌外交」
しかし、イギリスはこの協定と矛盾する外交を展開した。1916年、三国協商を結んでいたイギリス、フランス、ロシアの三国は、戦後にオスマン帝国を分割して管理するという秘密協定を結んだ。ロシアは、1917年のボルシェヴィキ革命のために、途中で秘密協定から離脱。この協定が、「サイクス・ピコ協定」と呼ばれる。
さらに、1917年11月には、イギリスは、戦後、パレスチナにユダヤ人国家を建設することを認めるとユダヤ人に宣言した。ロイド・ジョージ内閣のバルフォア外相が、ロンドンのユダヤ人財閥ウォルター・ロスチャイルドに書簡を送って約束したもので、これを「バルフォア宣言」とよぶ。イギリスは、シオニズム運動に迎合し、ロスチャイルド家などからの戦費の支援を期待したのである。
■パレスチナ人は難民に
第1次世界大戦後、パレスチナはイギリスの委任統治領となり、バルフォア宣言に従って、多くのユダヤ人の入植が開始された。そして、第2次世界大戦後の1948年5月14日にパレスチナにイスラエルが建国され、シオニズムは目的を成就した。
しかし、その結果、居住地から追い出されたパレスチナ人は難民となってしまった。
パレスチナ人にとっては、「ナクバ(大厄災)」の日である。
イスラエル建国に反対するアラブ諸国は、翌日イスラエルに侵攻した。これが第1次中東戦争であるが、戦争はイスラエルの勝利に終わり、翌年前半に、国連の仲介で停戦が成立した。

1956年10月29日、エジプトのナセル大統領がスエズ運河の国有化を宣言したため、イギリスはフランスとイスラエルにも出兵をうながし、第2次中東戦争となった。
戦争はエジプトの敗北で11月7日に終わったが、国際世論の支持を受けたエジプトはスエズ運河の国有化に成功した。
■「6日戦争」でガザ地区を占領
1964年にはパレスチナ解放を目指すPLO(パレスチナ解放機構)がアラブ人によって組織された。
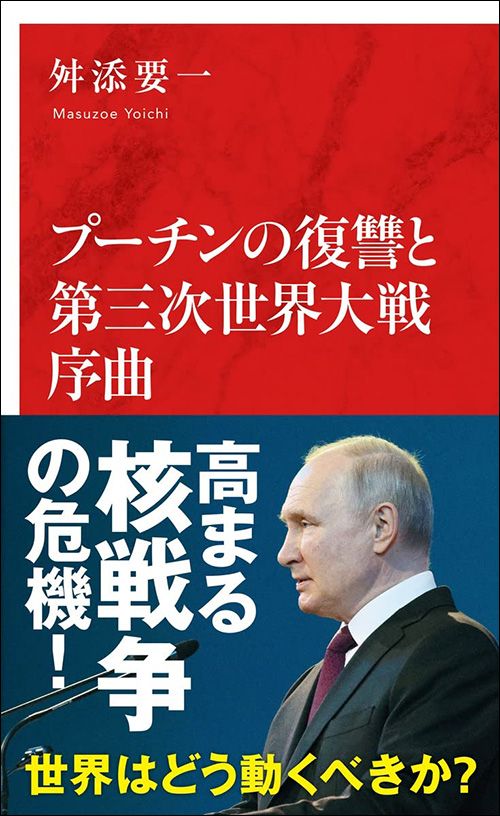
1967年6月5日、イスラエルは、アラブ諸国を奇襲攻撃し、エジプト、シリア、ヨルダン、を撃破し、ヨルダン川西岸、ガザ、シナイ半島、ゴラン高原を占領した。6月10日には戦争は終わったが、これが第3次中東戦争であり、「6日戦争」と呼ばれる。
この大勝利で慢心したイスラエルに対して、1973年10月6日、エジプトがシナイ半島に、シリアがゴラン高原に奇襲攻撃をしかけ、アラブの軍事力を過小評価し、油断していたイスラエル軍は後退を余儀なくされた。
イスラエルは反撃に出て、シナイ半島中間まで戻したところで、アメリカの仲介で10月23日に停戦した。開戦の日がユダヤ教の祝祭日ヨム・キプールの日であったため、「ヨム・キプール戦争」と呼ばれるが、これが第4次中東戦争である。
■「インティファーダ(対イスラエル蜂起)」が頻発していた
4次にわたる戦争の後、アラブとユダヤの対立を終わらせようとする動きも出てきた。
まず結実したのが1979年のキャンプ・デービッド合意である。イスラエルのベギン首相とエジプトのサダト大統領が、アメリカのカーター大統領の仲介によって、単独和平を達成した。
次いで、米ソ冷戦終了後の1993年9月13日、ノルウェーの仲介で、オスロ合意が成立し、イスラエルとPLOは、「パレスチナ暫定自治宣言」を調印した。
両者は相互に承認し、PLOはイスラエルの生存権を認め、PLOはテロを放棄した。そして、暫定自治宣言によって、ヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ暫定自治政府が樹立され、着実にパレスチナの自治の拡大へと進むことが期待された。
しかし、イスラエル軍の撤退が予定通りに進まなかったり、新規にユダヤ人の入植地が作られたり、イスラム過激派によるテロや民衆のインティファーダ(対イスラエル蜂起)が頻発したりと、包括的和平への道のりは遠くなっていき、今回のハマスのイスラエル攻撃に至ったのである。
10月24日の国連安全保障理事会で、グテーレス事務総長は、ハマスによるイスラエル襲撃を非難しつつ、「何もない状況から急に起こったわけではない。パレスチナの人々は56年間、息のつまる占領下に置かれてきた」とした。
この発言に、イスラエルのギラド・エルダン国連大使は猛反発し、「テロを正当化している」として辞任を求め、さらにイスラエルは国連関係者にビザの発給を停止した。また、イスラエルのエリ・コーヘン外相は、24日の安保理で、グテーレスを批判し、「ハマスは新たなナチスだ。文明世界は団結してイスラエルを支援し、ナチスを倒さなければならない」と訴えた。
一度に1200人ものイスラエル人が殺害され、しかも、その大半が民間人である。また、200人以上が拉致され人質となった。このような被害は、ユダヤ人の民間人を逮捕し、ガス室などで虐殺したホロコーストに次ぐものである。

----------
国際政治学者、前東京都知事
1948年、福岡県生まれ。71年、東京大学法学部政治学科卒業。パリ、ジュネーブ、ミュンヘンでヨーロッパ外交史を研究。東京大学教養学部政治学助教授を経て政界へ。2001年参議院議員(自民党)に初当選後、厚生労働大臣(安倍内閣、福田内閣、麻生内閣)、都知事を歴任。『ヒトラーの正体』『ムッソリーニの正体』『スターリンの正体』(すべて小学館新書)、『都知事失格』(小学館)など著書多数。
----------
(国際政治学者、前東京都知事 舛添 要一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
イスラエルがハマスと同時にヒズボラにも戦争を仕掛けたがる理由
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月29日 21時18分
-
出口の見えないイスラエルとハマスの戦い。アメリカが長年ユダヤ国家に肩入れし続ける本当の理由とは? 『聖書の同盟 アメリカはなぜユダヤ国家を支援するのか』KAWADE夢新書より6月21日発売!
PR TIMES / 2024年6月20日 10時45分
-
ハマスとの停戦めぐり揺れ動くイスラエル国民 人質の全員解放か、ハマスの壊滅か…割れる意見
東洋経済オンライン / 2024年6月12日 17時0分
-
イスラエルに根付く「被害者意識」は、なぜ国際社会と大きくかけ離れているのか?
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月10日 15時25分
-
バイデン米大統領、イスラエルとハマスの戦闘休止に関する新提案を公表(米国、イスラエル、パレスチナ、カタール)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月3日 11時40分
ランキング
-
1福岡のこども病院でまた…パワハラで職員処分 日常的に「殺すぞ」
毎日新聞 / 2024年6月29日 8時46分
-
2両陛下、英国公式訪問からご帰国 国賓として多くの行事臨まれる
産経ニュース / 2024年6月29日 18時37分
-
3弥彦総合文化会館で配管工事中に爆発事故 1人死亡、5人が重軽傷 新潟・弥彦村
BSN新潟放送 / 2024年6月29日 15時47分
-
4蓮舫氏が激しい雨の中で演説 熱気の聴衆はまるで香港「雨傘運動」のよう
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月29日 9時26分
-
5小学5年生の請願、大和市議会が全員賛成で採択…市の計画に「子どもの意見反映」求める
読売新聞 / 2024年6月29日 8時23分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












