人生50年時代に75歳の徳川家康を超える83歳まで生きた…貝原益軒が食事前に必ずしていた"健康長寿の儀式"
プレジデントオンライン / 2023年12月2日 11時15分
※本稿は、貝原益軒、奥田昌子編訳『病気にならない体をつくる 超訳 養生訓』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。
■『養生訓』は日本人のための健康書
『養生訓(ようじょうくん)』は、江戸時代前期から中期に差しかかる1713(正徳3)年に出版されて以来、日本で最も広く、最も長く読み継がれてきた健康書の古典である。著者の貝原益軒(かいばらえきけん)は医師であり、現在の薬学にあたる本草学をはじめ多くの分野に通じた大学者であるが、『養生訓』に小難しさはない。
バランスよく食べ、腹八分目にとどめ、体を動かし、過不足なく眠り、楽しみを見つけ、心穏やかに健康で過ごすことの大切さと、そのための方法が説得力を持って書かれている。いわば健康になるためのノウハウ書である。
『〔精選版〕日本国語大辞典』(小学館)は、養生を「生命を養うこと。健康を維持し、その増進に努めること」と定義している。養生の概念ならびにその方法は、8~9世紀に中国大陸から伝わり、長らく一部の知識階級のためのものだった。鴨長明(かものちょうめい)が1212年に執筆した『方丈記』には、「つねに歩き、つねに働くは、養性なるべし。なんぞ、いたづらに休み居らん」(よく歩き、よく働くことは養生に役立つ。なぜ、休むなどという無益なことをするのか)という記載がある。「養生」よりも「健康」という言葉が多用されるようになるのは、明治政府が西洋医学を重視する政策を取って以降のことである。
『養生訓』は出版されるやたちまち評判になり、幕末にあたる1864年までの約150年間に12回も重版された。その理由として考えられることは四つある。
一つめは食と健康への関心が高まっていたことである。益軒が生きた元禄時代は産業が発展し、文化が成熟した。豊かになった町人の間で演芸、読書、書画、園芸などの娯楽が広がり、衣食住にこだわる余裕も生まれた。益軒の没後まもなく8代将軍の座についた徳川吉宗が庶民の教育に力を入れたことで、平易な解説書や教訓書の需要が高まったことも追い風となった。
二つめは情報革命の波に乗ったことだ。印刷技術の向上によって、都市部の人々は書物や版画を手軽に入手できるようになっていた。
三つめは平易な言葉で書かれていたことである。日本で最初の医学書とされる平安時代の『医心方(いしんぽう)』も、鎌倉時代に栄西禅師が著した『喫茶養生記(きっさようじょうき)』も、教養ある上流階級を対象に漢文で書かれていた。これに対して『養生訓』は漢字仮名交じりの日本語を用いていたため、あらゆる階層の老若男女が読むことができた。
そして四つめに、外国の借りものではない、日本人のための養生書だったことを挙げたい。『養生訓』以前の医学書、健康書は大部分が中国大陸の書籍の内容をまとめたものだった。益軒は大陸の文献を広く研究しながらも、日本の歴史や文学、文化に造詣が深かった。『養生訓』には儒学や仏教、武士道の考え方、そして自らが生涯を通じて追求し、実践してきた養生体験と、そこから得られた教訓が豊富に盛り込まれている。日本人が取り入れやすい内容だったことから、当時の出版社が、
「本書を読めば著者のように元気で長生きできる」という大判の広告を出したようだ。後述のように、益軒は心身ともに健康で83歳まで生きた。
■『養生訓』に流れる養生哲学
明治時代以降も『養生訓』は解説書を含めて繰り返し出版され、例えば1982年発行の講談社学術文庫『養生訓』(貝原益軒著、伊藤友信訳)は、2022年までの40年間に65回増刷されるロングセラーになっている。
その一方、現代では『養生訓』に対する批判もある。西洋医学が主流になる前に盛んだった中国大陸の伝統的な医学薬学が基礎になっているため、非科学的な記述が多く、時代遅れで役に立たないというのである。
けれども、これは表面的な見方である。『養生訓』は実用的な作りになってはいるが、『養生訓』の『養生訓』たる所以は、健康になり、健康でいるための心がまえを強調していることだ。健康に対する考え方、心の持ち方に関する助言は、時がたっても色褪せることはない。
また、益軒は医薬の専門知識を有しながらも、同時に儒学者であった。冒頭で、「健康こそ人生最高の幸福である」と述べ、「幸福になるために人はどう生きるべきか」を解き明かしていく。体と心の両面から全人的な健康を目指す『養生訓』の思想は養生哲学と呼ぶべきものであり、これこそが『養生訓』の肝である。
■よりよい養生を模索し続けた、益軒の生涯
では、益軒はその生涯を通じて、どのように思想を深め、どのような境地に達したのであろうか。
貝原益軒は1630(寛永7)年、福岡藩に仕える父の5男として生まれた。三代将軍徳川家光の治世である。「益軒」は晩年に用いた号で、本名は篤信という。
母と6歳で、継母とも13歳で死別し、また幼い頃から父の仕事の都合で転居を重ねた経験は、益軒に生と死、人と社会について考えさせただろう。父は薬の調合に通じており、益軒も早くから医薬に触れていたようである。
19歳で福岡藩に仕えたものの、どんな事情からか藩主の勘気に触れて2年で辞めさせられてしまった。自分が正しいと信じることは、誰に何と言われてもやり通す性格が仇(あだ)になったという説もある。
ここから35歳で藩の実務に復帰するまでの歳月が、人生の転機となる。長崎で医学を修め、父のとりなしで藩医として福岡藩に再度取り立てられると、約10年にわたり藩費で京都に派遣され、儒学を学ぶ機会を得た。当時の著名な儒学者をはじめ、各分野の学者、医師らと交流して得た知識と経験は益軒の学問上の素地となった。初期には陽明学の書籍をよく読んでいたが、京都で朱子学に転じたとされる。
朱子学とは、簡単にいうと、宇宙の運動から社会、人の体や精神まで、あらゆる事柄は共通の法則に従っているという思想である。すべてのものに法則があるはずだという思考は、客観的に確かめられた知識こそが本当の知であるとする合理的な考え方に行き着く。これは、学者に欠かせない科学的な態度を育むことになっただろう。例えば益軒は児童教育に関する著作『和俗童子訓(わぞくどうじくん)』で、それまで「いろは」の順で学んでいた仮名を、「あいうえお」順で教えるべきだと提唱している。これも科学的合理性を示すものといえる。
益軒は幼い頃に体が弱く、周囲から「賢い子だが長生きしないだろう」と言われていたらしい。勤勉な益軒は書物や医師、周囲の闘病経験者らから養生の方法を熱心に学び、自らの体調で効果のほどを確かめながら、よりよい養生術を模索した。
福岡藩では藩主や藩士に儒学を講義し、藩主直々の命を受けて重要な記録をまとめるなど重用され、多忙な日々を送っている。その傍ら、没するまでの約50年間に医学、薬学、農学、歴史、地理、教育学、法律、算術、天文学など広範な分野で、一説には98部、247巻とされる膨大な著作を残した。このことから、後年来日したドイツ人医師で博物学者のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、益軒をギリシャの哲学者アリストテレスになぞらえている。

■養生の道がもたらす豊かな人生
益軒は当時の文化の中心地にたびたび滞在し、学識と思索を深めた。藩命によるものだけで京都へ24回、江戸へ12回、長崎へ5回赴き、勉学目的以外にも江戸や京都に再三にわたり足を伸ばしている。39歳のときに当時17歳の女性と結婚して、晩年まで何度も仲良く旅行し、書画を楽しみ、穏やかな日々を過ごしたようだ。
益軒の人となりを表すエピソードとしてよく知られているのが、牡丹の花の逸話である。この逸話は、益軒が亡くなるのと入れ替わるように生まれた歌人で国学者の加藤景範(かとうかげのり)が著した『間思随筆(かんしずいひつ)』に収められている。後に修身の教科書に掲載され、2013年には当時の安倍晋三総理が施政方針演説で言及した。
益軒の自宅に牡丹園があり、その中に、益軒が特に開花を待ちわびている株があった。ようやく咲き始めた頃、下男らがふざけていて枝を折ってしまった。やがて益軒が外出から戻って牡丹園を散策し始めた。はらはらしながら見ていた下男らだったが、叱責(しっせき)されることはなかった。後に話を伝え聞いた人が益軒に、「さぞご不快だったでしょう」と聞いたところ、益軒は微笑んで、「花を育てるのは楽しむためだ。花のことで怒るのはおかしい」と答えたという。
『養生訓』で益軒は、「人として生まれたからには良心に従って生き、幸福になり、長生きして、喜びと楽しみの多い一生を送りたい」と述べている。一例を挙げれば、食事をするときは誰のおかげかを考え、感謝の心を忘れず、農家の人の苦労に思いを馳せ、こんな自分でも食事ができていること、世の中には自分より困窮している人がいること、昔の人は十分に食べられなかったことを思い出せという。武士であり、すでに世に聞こえた大学者であった益軒の謙虚さと、すべての人に向ける優しい眼差しが印象的である。
思想面では、益軒は晩年になって朱子学に批判的な立場を取り、若い時期に親しんだ陽明学の中の知行合一(ちこうごういつ)という概念を重んじるようになる。知行合一とは、煎じ詰めれば、「知っていても実行しなければ知っているとはいえない」という実践重視の考え方である。『養生訓』を出版した翌年の1714(正徳4)年、最晩年に刊行された『慎思録(しんしろく)』には、よく知られる一節、「学ぶだけで人の道を知らなければ学んだとはいえない。人の道を知っていても、実践しなければ知っているとはいえない」がある。
死去する前年においても体力気力ともに充実し、自ら筆を執って『養生訓』8巻を書き上げた益軒は、83歳で見事に天寿をまっとうした。その姿は、生涯をかけて追求した養生の道が正しかったことを雄弁に物語っている。
■現代にこそ読みたい『養生訓』
『養生訓』は我々に何を教えてくれるであろうか。益軒の時代には、食べる目的がそれまでの「生きること」から「楽しむこと」に変化し、栄養不足ではなく栄養過多を原因とする病気に注目が集まっていた。飽食の時代といわれて久しく、生活習慣病やメタボリック症候群が蔓延する現代と重なる。初版から300年を超えたこんにちでも、当時の食材や献立、調理法、摂取法のほとんどが馴染み深いものであるため、実用書として大いに参考になる。
また、誰もがストレスに喘ぐ現代人からみると江戸の暮らしにはのんびりしたイメージがあるが、礼節と忠孝に縛られた社会の中で、人付き合いには細やかな配慮が求められていた。『養生訓』は「心の養生」としてストレス管理の大切さを強調し、その軽減法を具体的に教えてくれている。
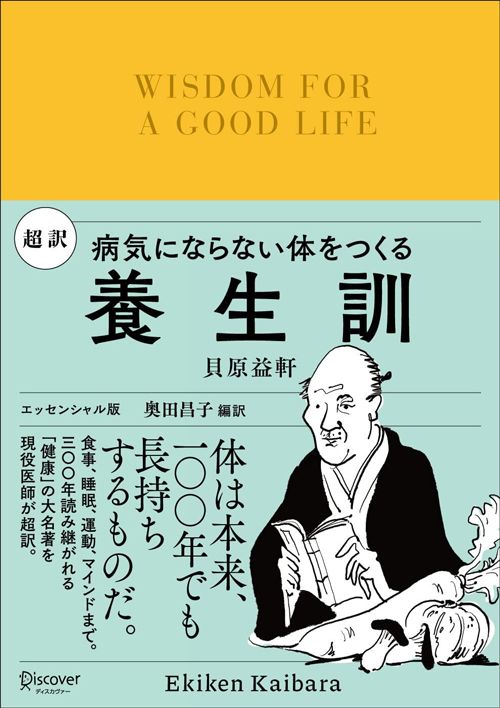
そして益軒の養生哲学は現代の健康思想を先取りするものであった。世界保健機関(WHO)は、1946年にWHO憲章で健康をこう定義している。「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」。はっきりした病気がなければよいわけではなく、ただ長生きすればよいわけでもない。生活の質の向上や健康寿命の延伸に象徴される、質の高さを伴う健康こそが重要ということだ。『養生訓』は健康書があふれる現代にこそ手に取りたい、本物の健康書だといえる。
『養生訓』は健康ノウハウ書であるとともに、益軒が生涯の集大成として書き上げた養生哲学書である。超訳にあたっては、読者がどちらの読み方もできるよう配慮した。できれば異なる視点から二度、三度と読んで、益軒の深く温かい助言に耳を傾けていただきたい。
----------
本草学者、儒学者
江戸時代の本草学者、儒学者。50年間に多くの著述を残し、経学、医学、民俗、歴史、地理、教育などの分野で先駆者的業績を挙げた。
----------
----------
内科医
京都大学大学院医学研究科修了。京都大学博士(医学)。医学部卒業後、博士課程に進み基礎研究に従事。生命とは何か、健康とは何かを考えるなかで予防医学の理念にひかれ、健診ならびに人間ドック実施機関で30万人近くの診察/診療にあたる。海外医学文献と医学書の翻訳もおこなってきた。現在は産業医を兼務し、ストレス対応を含む総合診療を続けている。愛知県出身。著書に『欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」』『日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた』(ともに講談社ブルーバックス)、『内臓脂肪を最速で落とす』(幻冬舎新書)、『日本人の病気と食の歴史』(ベスト新書)など多数。
----------
(本草学者、儒学者 貝原 益軒、内科医 奥田 昌子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「まだボケてないし病気知らず」92歳食の研究家が毎日食べる “最強の長寿ごはん”
週刊女性PRIME / 2024年7月6日 6時0分
-
日本人ならスラスラ説明できて当たり前…20年ぶりに刷新された「新札トリオ」のとんでもない功績
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 10時15分
-
断食ダイエットはむしろ「ポッコリお腹」になる…「スラっとした中高年」になるための最強習慣4つ【2023編集部セレクション】
プレジデントオンライン / 2024年7月1日 17時15分
-
自由で平和で豊かになったはずの日本で「心を病む人」が増えている理由【現役医師が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 8時15分
-
日本初の円硬貨は、なぜ「明治天皇の肖像」ではなく「龍」が刻まれたのか…「お金は卑しい」という日本特有の感覚
プレジデントオンライン / 2024年6月19日 16時15分
ランキング
-
1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”
日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分
-
2イケアのモバイルバッテリーに“発火恐れ” 製造不良で一部自主回収…… 海外では事故も発生
ねとらぼ / 2024年7月17日 20時10分
-
31日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
-
4去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方
東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











