なぜ数十枚のパワポが数千万円になるのか…コンサルという仕事が高い価値を生める"本当の理由"
プレジデントオンライン / 2024年2月3日 6時15分
※本稿は、しゅうマナビジネス『3秒で伝える コンサルが使う「シンプルな言葉で相手を動かす」会話術』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
■「事実やデータ」がない理由は、ただの感想
私たちは仕事を行ううえで、まず結論を導くための仮説を立てます。
例えば、業務が非効率になっている原因を探る案件なら、まずは「部長の社内決裁が滞っているからではないか?」といった仮説を立ててみます。
ここで重要なのは、仮説を立てた段階では、まだ非効率であることを示す根拠は何もいということです。
つまり、「作業が非効率なのは、部長の決裁の遅れが原因」というのは、説得力を持つ論理構成にはなっておらず、「ただの感想」にすぎません。
そこで次に、仮説が本当に正しいのか、事実やデータを見つけて検証します。
いわゆる「仮説検証」というものです。
「部長の決裁が滞っているから作業が非効率なのではないか?」という仮説が正しいかどうかを確かめるには、実際の作業にかかるリードタイムの調査や、部長や担当者にインタビューを行って、実態を明らかにしていきます。
その結果、例えば部長が決裁できる件数が一日に10〜20件なのに対し、決裁依頼が毎日20件以上あるといった事実が判明すれば、仮説は正しかったと言えます。
一方、調査の結果、部長は決裁作業にほとんど時間を費やしていないことがわかれば、仮説は正しくなかったとして、また次の仮説を考えることになります。
■「正しい情報」だから価値が高くなる
コンサルタントは「結論ファースト」であるのと同時に、「ファクトベースで話をする」というスタンスを求められます。
私たちコンサルタントは、サービス内容によっては、パワーポイントで作成した数十枚の資料に数千万円といった料金を頂くこともあります。
だからこそ、そこで伝える意見や考えはただの感想や思いつきではなく、高い価値を持つ「正しい情報」である必要があるのです。

あなたが実際に説明を行う場合にも、相手は無意識のうちに疑問を抱きながら話を聞いています。
そして、その疑問に答えるような説明を続けることで、相手がスムーズに理解できる流れができるのです。
例えば日常の会話でも、このようなやり取りがあるはずです。
〜友人と牛丼チェーン店を訪れた場面で〜
自分「僕、牛丼が大好きなんだよね」主張
友人「そうなんだ(なんで好きなんだろう?)」疑問
自分「ウマいし、料理が出てくるのが早いから」理由
友人「でもたまに遅くなることもあるでしょ?」疑問
自分「ここの牛丼チェーン店は時間管理に厳しくて、遅くとも1分以内に提供するようマニュアル化されているんだ」事実
友人「なるほど、そうなんだ」理解・納得
■相手を納得させるには裏付けが不可欠
このように、主張や結論を伝えると相手はその理由が気になり、理由を伝えると今度はその理由が本当なのかが気になります。
なので、その理由を裏付ける事実やデータを続けて説明することで、相手の納得感が促されるわけです。
仕事上で何か理由を伝える場合でも、
□ 自身の経験や直接見聞きした情報
□ 会議やインタビューでの発言
□ 議事録やメールなどの記録
□ システムなどから出力したデータや数字情報
□ 第三者による客観的な意見や考え
□ 信頼できるメディアや企業からの情報
といった情報や事実、データに基づいて「理由をきちんと裏付けられるか?」と考えてみてください。
それができれば、主張や結論に至ったプロセスを相手も理解しやすくなります。
ただ、ひとつ注意してほしいのが、事実やデータには種類があるということです。
それは「一次情報と二次情報」です。
■「誰からの情報か」が信憑性を左右する
一次情報とは、あなたが直接見聞きした情報です。
例えば、あなたが旅行をしたときに様々なトラブルに巻き込まれたとします。
それらの教訓を踏まえて「あの国には注意したほうがいいよ」と伝える場合、そこでのあなたの体験は紛れもない一次情報です。
一方で、二次情報とは自分自身で直接見聞きした情報ではなく、何かや誰かを通じて得た情報のことです。
特にインターネット上の情報は「誰が」伝えているかが大事で、それによって信憑性は大きく異なります。
以前、私が担当していたプロジェクトで、メンバーの一人にシステム障害の報告書を作成してもらったことがあります。
そのメンバーは障害発生の経緯と原因、そして対策案を資料にまとめる際に、対策案が適切かどうかを裏付けるために専門家の調査結果を引用しました。
報告書のスライドには引用元の記載があったのですが、それを確認してみると、とある個人ブログの記事でした。
■「引用元は個人ブログ」ではかなり厳しい
個人ブログとなると、その人が本当に専門家なのかどうか、その調査結果は本当に正しいのかが疑われて当然です。
さらにお客様から、「その対策案で本当に問題が解決するの?」と聞かれたら、「はい、あるブロガーが自身のブログで解決したという記事を見つけまして……」という回答をしなければいけないことになります。
あなたがお客様の立場で、提案内容の根拠が個人ブログ(だけ)だとすると、どう思いますか?
「そんな提案は信用できるわけがない」と思ってしまいますよね。
たとえその情報が事実だとしても、発言内容の一部が省略されていたり、脚色されていたり、記録した人の個人的解釈が含まれていたり、さらにデータが加工されていたり。
そんなことが起これば、事実と異なる結論になってしまう可能性があります。
特に最近は、フェイクニュースだけでなく、生成AIによる“いかにも”な記事が簡単に作れてしまいます。
だからこそ二次情報を扱う場合には「誰が伝えているか」を正しく理解して使用しなければいけません。
■なぜ「3つのポイント」「3つの理由」なのか
ここでもう一つ、説得力を出すコツをお伝えします。
それが、主張の後の理由を「3つ」述べるというテクニックです。
ロジカルなプレゼンテーションを構築するうえで、コンサルタントが意識しているのが「マジックナンバー3」という考え方です。

「ポイントは3つあります」「次の3つの理由により」といった具合に、「3」という数字は脳が記憶しやすく、量としてもちょうどいいと言われています。
例えば、友人から「今度の旅行、ハワイに行こうよ」という提案をされたとして、その理由として「ハワイは暖かいから」だけだとどう思いますか?
確かにハワイは暖かくて快適ですが、「理由はそれだけ? シンガポールとかバリ島だって暖かいじゃん」と言いたくなります。
こういった感じで、理由が一つだけだと、どうしても不足感が出ます。
商品を買う場合も、「この商品が他社のものよりも安いからです」と伝えると、「え、安いだけで決めちゃったの?」とか、「安けりゃ何でもいいの?」みたいな疑問を抱かれるかもしれません。
■2つでは安定せず、4つ以上は多すぎる
理由は主張や結論を支える土台となるものです。
この土台を1本の脚で支えると不安定ですし、2本でも安定しません。
カメラの三脚もそうですが、物を支える土台には少なくとも3本の脚が必要なのです。
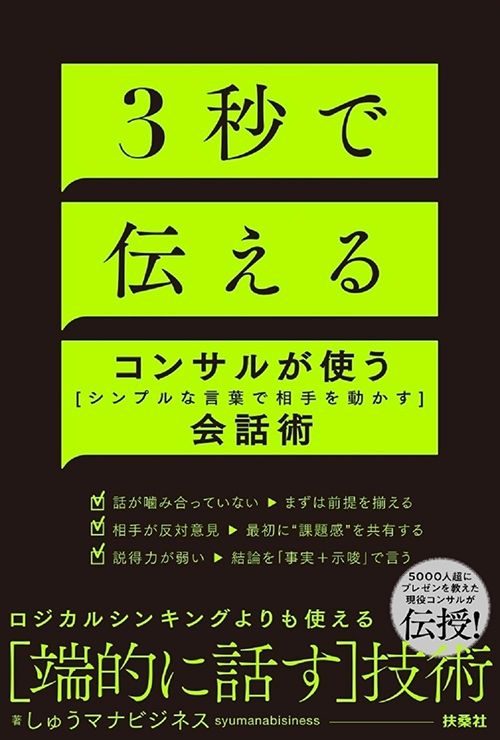
実際に主張や結論を支える理由は4つでも5つでも構わないのですが、あまり多すぎると「もう少しまとめてくれよ」と思われるので、やはり3つがちょうどいい数なのです。
ハワイにした理由は…
「年中暖かいから」
「海や自然がものすごくきれいだから」
「もう一度行きたいとずっと思っていたから」
この商品を選んだ理由は……
「他社のものより安いから」
「デザインがものすごくいいから」
「期間限定で今しか買えないから」
といった具合に、3つの理由を添えることで説得力が高まり、より相手が納得感を生みやすくなります。
■家族を納得させる旅行先の提案方法
例えば、これを本書第2章で解説している「説明の型」のひとつ、TPREP(ティープレップ)法の流れに組み込んでみましょう。
② Point:結論(主張)
③ Reason:理由(根拠)
④ Example:具体例(データ)
⑤ Point:結論(主張)
「年末の家族旅行だけど(テーマ)、今年はハワイに行こうよ(結論)。
日本の冬は寒いけど、あっちはずっと暖かいし(理由①)、
海とかダイヤモンドヘッドとか自然がものすごくきれいだし(理由②)、
ほら、みんなももう一度行きたいって言ってたじゃん(理由③)。
だから今年はハワイにしようよ(結論)」
といった具合に、「テーマ」+「結論」+「理由①」+「理由②」+「理由③」+「結論」という流れもよく使われます。
説得力を出すバリエーションとして、ぜひ実践してみてください。
----------
コンサルタント
大阪府出身。IT ソフトウェア企業を経て、総合系コンサルティングファームに転職。現在は経営管理・IT 領域を中心としたコンサルティング業務に従事。コンサル業と並行してプレゼンや思考法の専門家としてセミナー講師などで活動。YouTube チャンネル『マナビジネス』では「学び」+「ビジネス」をテーマに仕事術についての情報を発信している。Xアカウントは@manabi_business
----------
(コンサルタント しゅうマナビジネス)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「みんなの意見は正しい」はウソである…ダメな会社がやめられない「残念な会議」のシンプルな共通点
プレジデントオンライン / 2024年7月20日 16時15分
-
〈鹿児島県警・情報漏えい〉「さらしすぎとは思わない」性被害訴えた女性のチャットを会見で暴露した医師会は「ハニートラップ」とも発言し身内の性暴力を否定。記者からは「なぜそこまでするのか?」とツッコミも…
集英社オンライン / 2024年7月7日 9時0分
-
石田三成が最高の布陣を敷いた関ヶ原で負けた納得の理由…「自分は正しい」が強すぎて人心掌握に失敗
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分
-
これで「幸せとは何か」にスラスラ答えられる…自分なりの意見を伝えるために必要な"5つの問い"
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 15時15分
-
「時間のムダ」意味ない会議が生まれる根本的原因 議論の前に「良い会議」を定義できていますか?
東洋経済オンライン / 2024年6月27日 16時0分
ランキング
-
1〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」
集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分
-
2土用丑のうなぎで嘔吐=京急百貨店
時事通信 / 2024年7月26日 19時32分
-
3赤字続きのミニストップ、逆転を狙う新業態は「コンビニキラー」? まいばすけっとに続けるか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月26日 6時15分
-
4「ジェネリックにしますか?」と薬局で聞かれましたが、「新薬」にしました。これって損ですか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 8時40分
-
5タワマンで迷子、自分の部屋に帰れない…年金月25万円の69歳父が母と肩を寄せ合い暮らす「子供部屋」に唖然【FPの助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 11時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











