テストは暗記力を問うだけ、成績は紙で管理…インド出身の公募校長が日本の教育現場で感じた「古臭さ」
プレジデントオンライン / 2024年6月18日 7時15分
■日本の教育には「多文化共生」が足りていない
私の出身のインドでは同世代に貧しい人が多く「自分たちを貧乏から救うのは教育しかない」という認識が一般的でした。私は日本のIT企業や銀行で働きましたが、多少成功してお金を稼いだとしても、教育が最も重要だという考え方は体に染みついていて今でも変わりません。
私は大学生のころに、大学で日本語と経済学の先生をした経験があり、教えることに強い興味がありました。人に何かを教える、自分の思いや知識を伝えることへの思いがとても強いのです。人に教える、共有することで自分の理解も深まると理解しました。
私はインドで教育を受け、日本、中国、フランスへの留学経験があります。また、私の息子は日本のインターナショナル校、公立校を経験し、英国の高校を出て英国の大学に在籍中です。よって私は直接、間接的に5カ国の教育に触れる機会を得ました。そこで感じたのは、日本の教育には良い面もあるが、多文化共生の部分が大きく欠如しており、そこを変える必要性を痛感したのです。
■日本国籍を取得し、民間校長に応募
インドの社会では多言語、多文化が当たり前であり、出身地、言語の違いなどは誰も気にしません。教室の中ではカーストを気にすることはありません。私の知る限りインドの学校にはいじめはありません。人それぞれが違うことが当たり前だからです。
日本の学校では、生徒を一つの形にはめ込む教育が中心であり、そこから外れる生徒はいじめに遭うのです。実は私の息子も日本の中学でいじめに遭いました。だから、そこを変えなければならないと強く思うようになったのです。
2012年10月に日本国籍を取得しました。私は外国出身ですが、日本の企業では自分の意見はある程度聞いてもらえ、自分の思いを実現することができました。そして、インド出身の日本人として日本のために何かしたいという思いが強くなったのです。
議員の立場から多文化共生、教育などに携わろうと決め、2019年に東京・江戸川区議選で初当選しました。2021年7月にも多文化共生と教育改革を訴えて東京都議選に出ましたが、僅差で落選しました。さて次はどうしようかと考えていた時に、茨城県での民間校長の公募について知り、これは絶好のチャンスと思いダメ元で応募したのです。
■ルールに縛られない自由な国際学校を目指す
校長になるための県知事との面接試験では、まずは、「自分は最も不登校の生徒が多い学校に行きたい」と話しました。または、自分の言語能力、多文化対応力、さまざまな職歴などの多様性を生かして「国際的なリーダーを育成する学校」を目指し、最終的に「茨城県初の公立国際学校をつくりたい」とも言いました。その結果、2022年から茨城県立土浦第一高校・付属中学校の副校長を、23年からは校長を務めています。
私の夢として目指す公立国際学校とは、単なる国際バカロレア(IB)やケンブリッジ方式などの教育プログラムを導入した欧米式のインターナショナルスクールではなく、日本の文化背景や東洋哲学を生かして、多言語能力育成などとともに、世界に通用する生徒を育てる教育スタイルを持つ学校です。生徒の半分は日本人、半分は外国にルーツのある子どもが理想です。
インドの学校が理想的というつもりはありませんが、インドの学校にはルールに縛り付けるということはなく、自由な発想や行動が可能であり、さらに、社会でのサバイバル能力を養成する要素が多くあると感じています。学校ではインド神話や歴史のラーマーヤナやマハーバーラタなどが、しっかりと教えられており、そこには社会を生き抜くための知恵と道徳がたくさん織り込まれているのです。
■日本の教育現場はアナログまみれ
私が学校に赴任してまず感じたのは、「日本の教育現場はITシステムの導入があまりにも遅れている」ということです。日本の学校は、すべてが紙の記録で管理されており、これまでに蓄積された生徒の情報の分析や整理・共有が全くできていません。
現状では、生徒に関するデータをすぐに閲覧、利用できる仕組みが整備されておらず、校長であってもデータを見るには、別の先生に頼む必要があります。さらに、データそのものも十分にはそろっておらず、データ分析機能もありません。これでは個々の生徒に必要なきめ細かい対応はとてもできません。
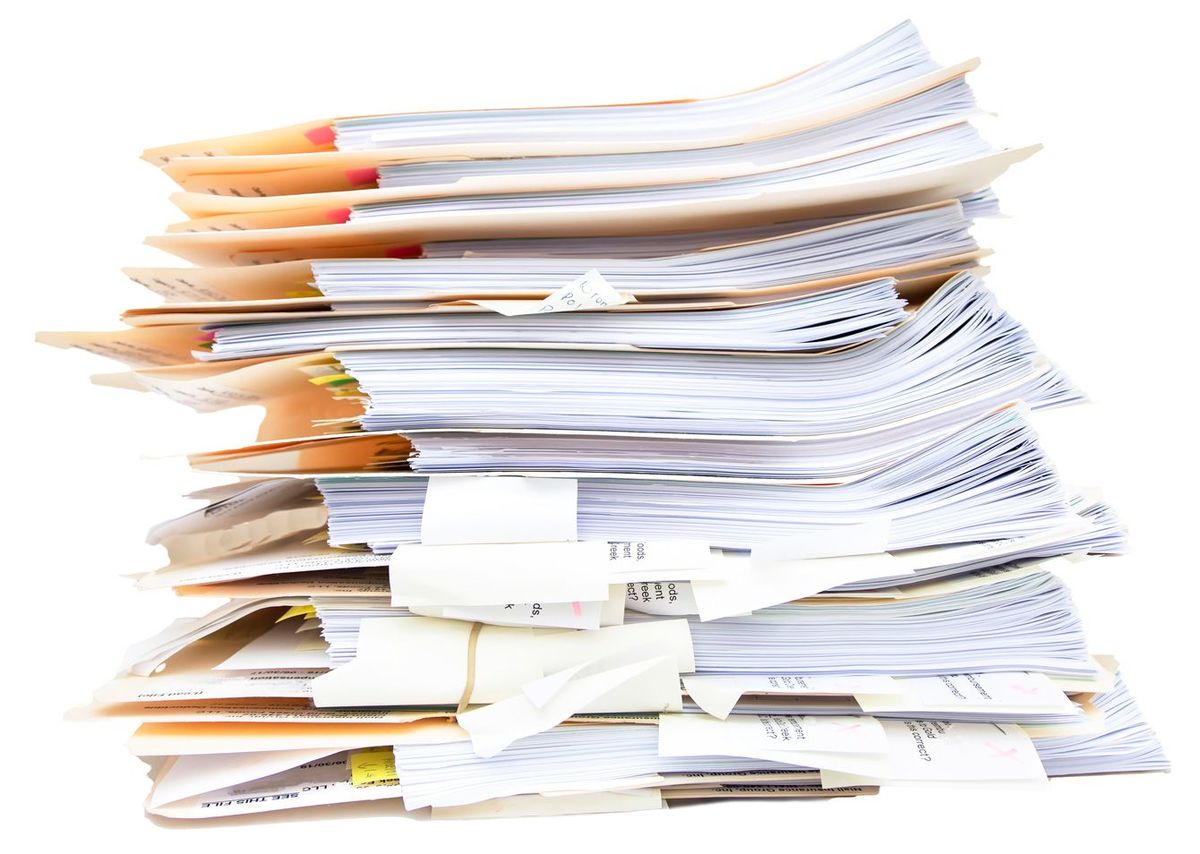
生徒一人ひとりにタブレット端末を持たせるという施策も、持たせるだけで終わっており、それで何かをしようという具体的で有効な活用法がありません。ほとんどの学校で共通して2~3個のアプリを使用しています。形式だけ整えても中身がないと意味がないのです。
私の学校では、これまでは紙ベースで存在したさまざまなデータを、エクセルベースで電子化して、自分のPCで見られるようにしました。将来的にはITシステムを導入して、生徒に目標設定をしてもらい、各生徒の性格や適性、置かれた状況に合わせて、目標に向かって具体的な計画を策定させて、実行してもらいたいです。そして、その進捗(しんちょく)をきめ細かく管理やフォローできるシステムを構築したいと考えています。ITシステム導入後は、その分析も瞬時にできるようにしたいです。
学校の変革には大きな抵抗がありますが、ITシステムを導入することで、さまざまな変革をもたらすことが可能になると考えています。
■「暗記テスト」だけでは思考力は身に付かない
授業やテストも変えていきたいと思っています。
日本の学校の授業では、先生はひたすら黒板に向かって文字を書いて教科を教えていますが、もっと面白い授業の仕方があると思います。例えば、パワーポイントでのまとめや画像、アプリや道具を活用した能動的授業を促進する必要があります。
また、試験の内容も暗記が中心で、本当に重要である考える力や表現する力はほとんど問われていません。教育の世界では、他の業界、社会や分野から学ぶという姿勢が欠けていると感じています。マネジメント力の育成も不十分です。日本の学校教育の世界に改善の余地がいくらでもあると感じました。
私は将来的に、学校の試験を3種類に分けて実施すべきと考えています。
一つ目はオープンノート試験です。自分のノートを見ながら、より良い回答を考えていく。そこでは暗記力は問われませんし、点数もつけません。二つ目はグループテストです。4人でグループを作り、問題解決に取り組むのですが、一つの正解にこだわらず、とにかくさまざまな考え方や回答をグループで考え出すこが大事なのです。
三つ目が暗記型のテストです。大学受験に向けては校外模試を活用することで、教員の作問・採点の負荷もかなり減るはずです。教員の負荷が減ると、改善を考える、導入する余裕が生まれます。
■導き出した答えは本当に現実社会で実現可能なのか
さらに、生徒に関しては次の3つの能力を育成すべきと思っています。一つ目は、生徒たちが自己診断して自分のゴールを設定する能力の育成です。二つ目は、人格形成も含めて、問題解決力、表現力、パブリックスピーキング力を習得させ、かつ、自分の周囲を観察して適切に対応できる能力の育成です。三つ目は、自分の専門分野以外でも一定レベルの専門知識を獲得することです。
他にも現在の教育に足りないものはたくさんあると思います。例えば探求学習ですが、現状では、提示された問題に対して単純に「こうすればいい」という回答を作って終わりです。その対応策や解決策は現実の社会で本当に実行可能なのか、難しければどうすればできるようになるのか、ビジネスチャンスはあるのかなどの検討に発展しません。
現実の行政システム、会社の経営システムがどうなっているか、実行に必要な制度やITシステムは本当に作れるのかなど、実践的な知識が欠けているのです。そのような点を少しでも多く学ぶ必要性を痛感しています。
■大谷翔平のマンダラチャートを活用
生徒の面接試験の練習を実施することがありますが、彼らには、質問に対する回答を考える基本的なフレームワークができておらず、難しい質問を出すと回答に窮して沈黙するのです。どんな質問であっても、さまざまな角度で分析して、自分なりの回答を出して話す力が身に付いていないのです。
現在、専門家を交えて中高の6年間での探求学習の在り方を考えています。これまでも探求学習はありましたが、その有効な実施のためのテンプレートがなく、単に問題や課題を選び、アドバイスを受けたり、人に聞いたりして調査し、最後に感想を書くという流れでした。
探求学習には、課題ベースと目標ベースの探究があります。これまでは、一つの課題を考えて探究していましたが、今後は課題や興味・関心のテーマを10個ずつ書き出して整理し、プライオリティをつけてから一つのテーマで探究を行いたいと思います。
また、大谷翔平選手が使ったことでも有名になった曼荼羅表(マンダラチャート)を導入し、関係者分析やプロセス分析をしながら解決策を考えてみるなどさまざまな手法の導入を進めています。
■海外大学の見学ツアーだけでは不十分
また、海外の大学への進学も増やしたいと考えています。現在でも、ハーバード大を見学し、大学生や教授と交流するプログラムはありますが、それでは不十分です。実際、過去に見学プログラムに参加した生徒でその後ハーバード大に進学しようとする生徒はいません。
まずは、高校1年の夏休みなどを利用して海外の高校に行き、英語を駆使してボランティアするなどして慣れと自信を身に付けるアプローチもあると思います。そのほうが何倍も効果的でしょう。
■インドではタクシー運転手がビジネスの提案をしてくる
生徒には、いろいろな局面でのサバイバル能力を獲得してもらいたいのです。大学入試も、就職してからの仕事においても、人生はサバイバルの連続です。その中で、自分で考えて対応し、強く生き残っていく必要があるのです。学校の中でも、他人からのちょっとしたひとことで心に傷を負ってしまう生徒もいます。
他人から何かを言われたくらいで、自分の人生に何か問題があるのでしょうか。何もありません。そのように考えてほしいです。しかし、サバイバル能力がないと物事をいちいち気にするのです。他人から突っ込まれたら、簡単に凹むのではなく、相手に対して面白く切り返せばいいのです。
インド人のサバイバル能力はとても高いのです。タクシーに乗れば、運転手からさまざまなビジネスや商売の提案が出てきます。路上でホームレスの貧しい子供が、捨てられたガラクタを集めて作った物を売りに来ます。彼らは自分で考えて必死に生きています。日本では社会保障制度で守られ過ぎているのかもしれませんが、もしその制度が機能しなくなると何もできなくなるのではと危惧しています。
■推薦入試をどんどん推進
生徒たちをルールで縛り、違反するたびに罰を与えていては、自己肯定感は決して育ちません。生徒会の中でも、摩擦を避けて自由でフランクな議論は出ないでしょう。それは大人の社会と全く同じことです。生徒会委員の選挙も無投票で決まることが増えていますが、それは地方の市町村議会選挙でも同様な状況です。それでいいのでしょうか。
私が校長に就任してからは、具体的な対策として、弁論大会などの外部での活動への積極的な参加を奨励しています。ボランティア活動をしている生徒には、関連大会への参加を呼び掛け、表彰もされました。インド系の学校や米国の大学との交流も始めました。
大学進学で推薦入学について積極的でない学校もありますが、私は推薦入学をどんどん推奨しています。そうすることで、単なる試験の点数以上のレベルの大学に入学でき、本人の将来にとってより良い影響をもたらす可能性があるからです。生徒自身の基本さえできていれば、推薦入学であっても、入学した大学で必ず上を目指すと確信しています。

(後編に続く)
茨城県立土浦第一高校・付属中学校長
1977年、インド・ムンバイ生まれ。インド・プネ大学で学士号と修士号を取得。グローバスIT企業で約13年勤務後、2010年にみずほ銀行入行、2019年には楽天銀行に企画本部副本部長として入行するも、同年4月の東京都江戸川区議選に出馬し初当選。2021年東京都議選では落選。茨城県の民間人校長公募に応募し、22年4月より同校副校長、23年より現職。
----------
科学技術国際交流センター(JISTEC)上席調査研究員
1951年生まれ。広島大学工学部卒業し、76年日商岩井(現・双日)入社。20年間海外営業を担当し、インドネシア、スリランカに駐在。広報室、人事総務部、日本貿易会出向を経て、12年より日本在外企業協会『月刊グローバル経営』編集長。15~18年 科学技術振興機構(JST)インド代表を経て、22年より現職。23年よりJSTアドバイザ。世界の優秀な若手人材を日本に招聘するJSTの「さくらサイエンスプログラム」の推進に携わる。
----------
(科学技術国際交流センター(JISTEC)上席調査研究員 西川 裕治)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
大学入学共通テスト初実施の「情報Ⅰ」は簡単だった? プロの目から見た試験内容とは
47NEWS / 2025年2月2日 9時30分
-
「早期学力試験の是非」文科省通知がもたらす混乱 「青田買い」に警鐘、関西の大学「なにを今さら」
東洋経済オンライン / 2025年1月27日 12時0分
-
年間の学費は1000万円超え!? それでも日本の富裕層に海外の「全寮制学校」が人気なワケ
マイナビニュース / 2025年1月24日 10時30分
-
開校相次ぐインターナショナルスクール、欧州の首都で人気校の教育を探った 学費は600万円超、広い敷地に充実設備、日本人生徒が感じる光と課題
47NEWS / 2025年1月24日 9時0分
-
ニュージーランド公立小の"自由で刺激的"な日常 移民大国で根付く「ダイバーシティ教育」の実際
東洋経済オンライン / 2025年1月10日 10時0分
ランキング
-
1朝まで起きない「ぐっすりストレッチ」基本の3つ 眠るタイミングに向けて深部体温を下げる方法
東洋経済オンライン / 2025年2月3日 9時0分
-
2凍結した路面で“あおり運転”してきたSUVに天罰。パトカーと救急車、レッカー車が来る事態に…
日刊SPA! / 2025年2月3日 8時53分
-
3こんな所までモザイク処理が…!Googleストリートビュー、意外なプライバシー保護に爆笑「うちもやられた」「面白い」
まいどなニュース / 2025年2月3日 7時20分
-
4トヨタ プリウスPHEV、ジオフェンシング技術で「リッター200km」に燃費向上…欧州2025年モデル
レスポンス / 2025年2月3日 7時0分
-
5空自「最新鋭戦闘機」がまさかの納入遅延 実は世界中で!? 背景にある“根深い問題”とは
乗りものニュース / 2025年2月3日 8時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










