「早く死にたい」とつぶやく高齢者に検査を勧める…現役医師が目撃した「高齢者専門クリニック」の悲惨な現状
プレジデントオンライン / 2024年2月12日 15時15分
※本稿は、久坂部羊『人はどう老いるのか』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。
■「生きとっても仕方ないですよ」
老人デイケアのクリニックでは、余病を持つ利用者さんの健康管理と、売り上げ向上(露骨な言い方ですが)の両目的から、定期的に血液検査と胸部X線撮影を行っていました。血液検査の結果は診察室で説明します。Yさん(88歳・男性)は軽い貧血と肝機能障害があったので、3カ月ごとに検査をしていました。
「前と変わっていませんよ。心配ないです」
そう言うと、Yさんは心底落胆したようなため息をついて、「そうですか。ほんならまだ死ねませんな」とつぶやきました。
血液検査の結果がよければ、喜ぶのがふつうでしょうが、デイケアの利用者さんには逆の反応を示す人が少なくありませんでした。
Yさんの口癖は「早ようお迎えが来ませんかな」で、「先生、ポックリ逝ける薬はありませんか」ともよく聞かれました。冗談や口先だけでないので返答に困ります。「どうしてそんなふうに思うのですか」と聞くと、Yさんは自嘲するようにこう答えました。
「こんな年寄り、生きとっても仕方ないですよ。迷惑をかけるばっかりで」
「迷惑なんかかけていませんよ。Yさんは若いころから頑張ってこられたのだから、今はまわりの人に手伝ってもらったらいいんですよ。みんな順番ですから」
そう宥(なだ)めましたが、Yさんは両膝の上で拳を握ったまま、顔を上げようとしません。Yさんは杖で歩けるし、トイレにもひとりで行けるので、決して要介護度が高いわけではありませんし、同居している息子さん家族も介護に前向きで、決して迷惑がられているわけではなさそうでしたが、家族が親切にすればするほど、Yさんの心の負担は大きくなるようでした。
■「いいことなんか、ありません」
Eさん(89歳・女性)は、送迎バスが到着した直後に胸が苦しいと言って倒れたので、診察室に運んで心電図をとりました。心室性の不整脈発作で、急いで抗不整脈剤を注射すると、なんとか整脈にもどって、意識も回復しました。

「もう大丈夫ですよ。よかったですね」と声をかけると、Eさんはぼんやりと天井を見たまま、「そうですか。死ねませんでしたか」と、心底、落胆したようにもらしたのです。
「そんなことを言わないで。生きていれば、またいいこともあるでしょう」
そう励ますと、Eさんはカッと目を見開き、私をにらみつけて、「いいことなんか、ありません」と、しゃがれた声で断言しました。私は自分の迂闊さ、無責任さを指弾されたようで、言葉を失いました。Eさんは息子さん一家と同居していましたが、嫁と折り合いが悪く、家庭内で苦しい状況にあったのです。
「あんな家に帰るくらいなら、死んだほうがよっぽどましです」
返す言葉がありませんでしたが、だからと言ってもちろんみすみす死なせることはできません。しかし、それは私の保身だったのかもしれません。ほんとうにEさんのことを考えるのなら、発作のまま逝かせてあげるのがよかったのではないかと、一抹の迷いがあったのも事実です。
■「死んでもいい」という患者に検査を勧めるが…
この二人ほど深刻でなくても、死にたい願望を持つ利用者さんは、珍しくありません。
Kさん(78歳・女性)は、杖はついていますが、背中も腰も曲がっていませんでした。パーキンソン病なのでポーカーフェイスで(パーキンソン病には“仮面様顔貌(かめんようがんぼう)”という症状があります)、声も低く、滅多に感情を表に出しません。そのKさんに胸のX線撮影をすると、妙な影が写っていたので、私は肺がんかもしれないと思い、精密検査を勧めました。
不安を取り除くため、「それほど心配ないですから」と言い添えると、「心配はしません。いつ死んでもいいですから」と、Kさんは眉一つ動かさずに応えました。
いつ死んでもいいと言う人に、さらなる検査を勧めることが正しいのかどうか、私は迷い、「精密検査はどうしますか」と聞くと、「先生が受けろとおっしゃるのなら受けます」という答え。まるで検査は私への気遣いのようでした。
結局、しばらくようすを見ることにして、何度かX線撮影を繰り返しましたが、影の増大は見られず、症状も悪化しませんでした。
■「アンタなんか簡単に死ねんの」
昼食後の時間にデイケアルームに行くと、利用者さんがお茶を飲みながら、よくこんな雑談をしています。
「うまいことポックリ逝く方法はないもんかいな」
「朝、目が覚めんとそのまま逝けたら、こんなええことはないな」
「こけて頭打って、そのままあの世に行けたらええのに」
「道でトラックでも突っ込んできて、バーンとはねてくれへんやろか」
デイケアに参加する高齢者にとって、死はある種の憧れ、救いのような側面があるようでした。
高齢者が死を肯定的に捉えていることを、私はあるゲームのプログラムで痛感しました。
利用者さんが二チームに分かれて、風船をとなりの人に順繰りに渡すゲームです。前から受け取った人は、次に背中側に手渡し、背中側で受け取った人はお腹側に渡します。
ついつい焦って風船を受け損ねたり、交互に渡すのを忘れたりして、それが笑いを誘うこともありますが、競争ですから、ときに白熱して利用者さん同士が興奮することもありました。
見ていると、同じ女性が何度か風船を落とし、その度に彼女のチームが負けました。すると、ふだんから意地悪な女性が、風船を落とした女性に、「アンタのせいでまた負けた」ときつい言葉をかけました。
すると言われた女性は取り乱して、「ああ、わたしが悪い。わたしのせいで負けた。もう死んでしまう」と叫んだのです。これに対し、先の女性はさらにきつい口調でこう言いました。
「そんなこと、言うたらいかんの。アンタなんか簡単に死ねんの」

■「すぐ死ねない」ということが悪口になる
ふつう、腹が立ったら「アンタなんか死ね」というのが罵声となるでしょう。ところが、その場では「死ねない」というのが意地悪になっていたのです。私はそのことに妙に感心しました。それだけ死が望ましいものとして捉えられているわけですから。
まだ長生きをしておらず、命が惜しいと思っている人には、理解しがたいかもしれませんが、いつまでも死なないというのは、実際、つらくて苦しいものです。高齢者医療やがんの終末期医療の現場で、過酷で悲惨な延命治療を目の当たりにすると、そのことを実感します。
だったら、適当なところで上手に死ぬことが望ましいはずですが、いつまでも生きていたいと思っている人は、なかなかそちらに気持ちが向かないようです。
死ぬことの準備は不愉快かもしれませんが、それをせずに安穏と暮らし、いざ死が目の前に迫ってから下手な選択をして、悔いの残る死に方をした人を多く目にした私としては、もったいないとしか思えません。
■老いとうつ病には深い関係がある
うつ病には特に理由もないのに気分が沈む“本態性”のうつ病と、つらいこと悲しいことのせいで気分が沈む“反応性”のうつ病があります。
高齢者の場合は、圧倒的に後者が多いです。なぜなら、“老い”にはつらいこと、悲しいことが多いからです。デイケアルームに利用者さんがそろうと、私は各テーブルをまわって挨拶をします。
「おはようございます。今日は身体の調子はどうですか」
この問いにあらゆる不具合と嘆きが返ってきます。腰が痛い、手が震える、口が渇く、咳が止まらない、息が苦しい、もの忘れが激しい、めまい、耳鳴り、便が出ない、便が緩い、この頭痛はなぜ起こるのか、足のしびれはどうやったら治るのか、こんな病気を背負い込むとは思わんかった、歩けんようになるのが怖い、おむつをするくらいなら死んだほうがまし、寝たきりになったらどうしよう、もうこの手の麻痺は治りませんか、年を取ったらロクなことはない、嫁にも孫にも嫌われて、犬にも嫌われて、何もええことはない、苦しいばっかり、もうどうなってもええ、早く死んでしまいたい云々。
聞かされるこちらまで気分が沈みます。

痛みや不如意があっても、心の準備のある人は、ある程度、うつ病にならずに受け止められるようです。心の準備のない人、すなわちいつまでも元気でいられると思っていた人は、「なんでこんなことに」とか「こんなことになるとは」と、よけいな嘆きを抱えるので、反応性のうつ病になる危険が高まります。世にあふれるきれい事情報や、無責任なお気楽情報は、ほんとうに罪深いと思います。
■病気ではないが不具合を訴える男性
高齢になれば、自然な老化現象以外にも、病気という心配と恐怖が襲いかかってきます。年を取ればそれも当たり前と思っている人は、比較的楽に受け止められるようですが、病気が怖くてたまらないという人は、病気以前にその思いに苦しめられます。
韓国人のLさん(80歳・男性)はでっぷりと肥えた大柄な人でしたが、ご家族から“病気のデパート”と呼ばれていました。実際に診断のついた病気はないのですが、不具合の訴えがデパート並みに多かったのです。
デイケアルームに到着しても、頻繁に診察を求めて外来の診察室に下りてきます。食欲がない、吐き気がする、夜が眠れない、オシッコのにおいがおかしい、腰がふらつく、だんだん歩けんようになるのが怖い、寝たきりになったら困る、便所にも行けんようになったら死ぬしかない等々。
■気休めでもいいから“治療”してほしい
検査をしても特段の異常がないので、「大丈夫ですよ」と説明しても納得してくれません。
「先生。注射をお願いします。先生は専門家でしょう。ワシら素人にはわからんから、頼むのです。注射を頼みます。お願いできませんか。注射さえしてもろうたら、楽になると思うんです」
そんなとき、どう応えればいいのでしょう。気休めにブドウ糖かビタミン剤の注射でもするのが親切なのかもしれませんが、一回でもするとまた次もと、やみつきになる可能性が大です。それにまだ若かった私は、そんな医学的に意味のない気休め注射をすることにも抵抗がありました。
「注射といっても、どこが悪いのですか」
そう聞くと、「のどはおかしくないか」と口を大きく開けます。別に異常はありません。
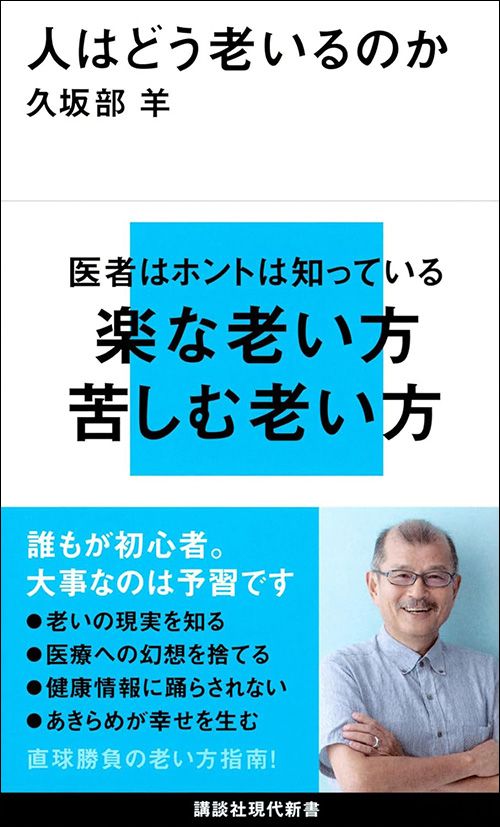
「頭も痛いんです。膝に力も入らんし、なんやお腹が張ってるみたいやし、指の先がしびれとるし、爪も薄くなってフニャフニャしとるし、胸も苦しいし、夜中に息が止まりそうになるんです」
まさに病気のデパートです。
「注射は必要ありませんよ。それにすべてに効く注射もありませんし」
私が首を振ると、Lさんは「そんなことを言わずに、お願いします、頼みます、なんとか注射を打ってください」と食い下がります。私はまるで自分がLさんに意地悪をしているような気分になりました。
----------
小説家、医師
1955年大阪府生まれ。大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部附属病院の外科および麻酔科にて研修。その後、大阪府立成人病センター(現・大阪国際がんセンター)で麻酔科医、神戸掖済会病院一般外科医、在外公館で医務官として勤務。同人誌「VIKING」での活動を経て、『廃用身』(幻冬舎)で2003年に作家デビュー。『祝葬』(講談社)、『MR』(幻冬舎)など著作多数。2014年『悪医』で第3回日本医療小説大賞を受賞。小説以外の作品として『日本人の死に時』、『人間の死に方』(ともに幻冬舎新書)、『医療幻想』(ちくま新書)、『人はどう死ぬのか』『人はどう老いるのか』(ともに講談社現代新書)等がある。
----------
(小説家、医師 久坂部 羊)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
医師「心配いりませんよ」患者「でもテレビで、これは病気だって…」メディアの情報を信じてしまう人々の実態【現役医師が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月2日 7時0分
-
増税が蝕む 日本人のメンタル 追い詰められた高齢者3000人自殺の大問題 諸外国ならデモや暴動が起こる不満や怒り…内にこもる国民性から精神疾患へ
zakzak by夕刊フジ / 2024年5月30日 6時30分
-
健康診断は「健康な人」を「病気」にいざなうシステム? 患者の健康を祈りつつも、いなくなってはお金に困る医療の矛盾【現役医師が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月27日 9時0分
-
人生の一大行事「死」への準備を怠った人は最期に後悔する…「葬式にさだまさしの曲を」以外に計画すべきこと
プレジデントオンライン / 2024年5月15日 15時15分
-
家族3人で「ファストフードは1000円まで」…手取り19万円で小学生2人を育てるシングルマザーが涙を流すワケ
プレジデントオンライン / 2024年5月8日 16時15分
ランキング
-
1診療報酬改定で6月から初診・再診の負担増 医療従事者の賃上げの原資に
産経ニュース / 2024年6月1日 20時15分
-
2兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分
-
3タマネギの皮、納豆のフィルム... 話題の「キッチンでの小さなイライラ撃退法」、実際に試してみました。
東京バーゲンマニア / 2024年6月1日 13時0分
-
4ダンプカーの車体にある「謎の文字と番号」の正体は? 「足立 営 12345」は何を意味しているのか 実は「経済成長」と深い歴史があった!?
くるまのニュース / 2024年6月1日 20時10分
-
5古いテレビを捨てたいです。お金をかけず楽に処分するにはどうすればよいでしょうか?【専門家が解説】
オールアバウト / 2024年6月1日 20時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










