「根拠のない自信」にはすごい効果がある…コーチングのプロは知っている"目標を達成できる人"が持つ能力
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 7時15分
※本稿は、名郷根修『習慣は3週間だけ続けなさい』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■「外発的動機」が脳を働かせる
脳には「ラス機能」と言って、いわば脳の「GPS機能」のようなものが存在します。車や地図アプリの「GPS機能」と同じで、この「ラス機能=GPS機能」を働かせると、あなたはその行動に突き動かされ、習慣化ができるようになります。
それなら、脳の「GPS機能」はどう動かせばいいの? というのがあなたの疑問でしょう。
これには少しばかり工夫がいります。というのも、本来、脳の「GPS機能」は楽しい、嬉しいなどの感情を伴う行動に反応します。
ただ、残念ながら習慣化に向けた行動は取り組み始めた当初はどちらかというとしんどかったり、つらかったりが大半のはずです。語学も筋トレも嬉々として取り組めれば多くの人は習慣化に苦労しません。取り組みそのものは、あまり面白くないはずです。
ですから、「GPS機能」をうまく働かせるには仕掛けが必要になります。脳をだまさなければいけません。まず、あなたは習慣化を身につけるに際して何かしらの理想があるはずです。「あの人みたいになりたい」という漠然とした将来像です。これを「外発的動機」と呼びますが、まず、この動機を持つことが誰でも無理なく「GPS機能」を自然に働かせる第一歩となります。
■「ボーナスのために頑張る」「モテたいから頑張る」
外発的動機は「あの人みたいになりたい」「将来はこうしたい」という憧れのようなイメージ像です。これをもう少し正確に定義しますと、「行為そのものではなく、外部からもたらされるものを目標として、その目標を実現するために行為を行おうとすること」となります。
わかりやすいのがビジネスの現場です。ビジネスにおける外発的動機づけは、上司が部下に何らかの仕事を行ってほしいとき、もしくは、少し背伸びをした仕事を与え成長してほしいときに、提示するケースが多く見受けられます。
「ノルマを達成したら、ボーナスが10万円多く出ます」
「今期の営業成績が前期以上だったら昇進できます」
と言われたら頑張る人も多いはずです。これは「報酬」という外発的動機です。行為そのものではない動機によって行動が促されています。
このように報酬や義務や賞罰、強制などによってもたらされる動機づけが外発的動機に当てはまります。外発的動機は何らかの目的を達成するために用いられることが大半です。
仕事以外でも、
「憧れの大学に行きたいから受験勉強を頑張る」
「モテたいからダイエットを頑張る」
これらも外発的動機づけになります。お金がもらえる、偉くなれる、有名になれる、モテるなどが身近ではわかりやすい例でしょう。
■外発的動機づけの効果は一時的なもの
おそらくあなたも何か新しいことを始める際は外発的動機がきっかけになっているはずです。ただ、気をつけなければいけません。一般的に外発的動機づけの効果は一時的なものといわれているからです。
たとえば、仕事で成果を出したら多額のボーナスをもらえることを動機に頑張っても、「お金はもらえるけれども、面白くないな」と感じる人は少なくないはずです。ですから、きっかけとしては非常に有効ですが、長い期間にわたって仕事をし続ける、成長し続ける際には、必ずしも効果的な動機にはなりえません。

本来は、「行為そのものが楽しい状態(内発的動機)」で取り組めればベストですが、それができていればすでに習慣化は成功しています。あまり楽しくないから苦しんでいるのです。
「報酬のために取り組むのはおかしい」と思う人もいるかもしれませんが、楽しいからやる状態(内発的動機)に到達させるには脳の機能を考えるとステップを踏む必要があります。無意識に行動できるようにするには初期段階では一定の報酬が必要なのです。
気が向かない行動を習慣化するためには、まずなりたい姿、ありたい姿を外発的動機で明確にして「GPS機能」を働かせることが効果的です。この際に可能な限り目標は明確にすべきです。
なぜならば、目標を明確に描くことで脳の「GPS機能」(ラス)がそれを重要な情報として認識しやすくなるからです。ラスは重要な情報に焦点を当てる働きを担っています。目標が視覚化されれば、脳はそれを重要な情報として認識し、集中しやすくなります。ラスが優先的に処理するきっかけとなるのです。
■「行為そのものが楽しい」につなげる必要がある
脳にとって目標を達成することで得られる報酬や充足感は強力な動機づけになります。外発的動機には目標達成によって得られる報酬やポジティブな刺激が関連づいていますので、ラスは反応します。「ノルマを達成したらボーナスがもらえる」という目標があれば刺激になり、習慣化に向けた行動を促します。
脳は変化を嫌います。意識的に新しいことに取り組む処理能力も限られています。ですから、限られたリソースを最適に利用する効率主義の構造です。
外発的動機で特定の明確な目標を持ち、脳の注意を向けさせることで「GPS機能」を優先的に働かせることが可能になります。ただ、外発的動機づけによって「GPS機能」が働くのは意識的につくられた状態です。脳の仕組みをうまく利用して脳をだました状態ともいえます。
持続性に欠けていて、ずっとは続きません。このモチベーションが高まっている状態を維持するためには、最終的には「行為そのものが楽しい」と感じる「内発的動機づけ」での行為につなげる必要があります。そのステップとして、次に必要になるのが「自己効力感」の向上です。
■「実現できる気しかしない!」自己効力感が脳を働かせる
「自己効力感? 自己肯定感じゃないの?」
おそらくそのような思いを抱いたのではないでしょうか。「自己効力感」という言葉を初めて聞いたかもしれません。「自己効力感」はカナダの心理学者アルバート・バンデューラによって提唱された概念です。
これは「人が行動や成果を求められる状況において、自分は必要な行動をとって、結果を出せると考えられる力」のことです。簡単にいいますと、「自分ならばできる」と考えられる状態です。ですから、「自分は達成できる」「自分には能力がある」という確信があれば「自己効力感が高い」といえます。
一方で、「自分には無理だ」「自分には能力がない」と思ってしまえば、「自己効力感が低い」といえます。たとえば、あなたが新入社員の営業職で顧客にプレゼンして自社の商品を売り込む必要があるとします。会社に入りたてなので、まだプレゼンをまともにした経験はありませんが、会社にとっては重要な顧客なので失敗は許されません。
その際にあなたはどう思うでしょうか。「自分ならうまく説明できるし、セールスすることができる!」と思えれば自己効力感が高い人となります。

■「やれる」自信がある人はビジネスでも強い
反対に「自分はうまく説明できる自信がない。セールスできずに失敗するかもしれない」と思ってしまうのは自己効力感の低い人です。「新人だったら、みんな自信がないのでは」と思われたかもしれませんが、自己効力感には周囲の意見や、客観的に実現可能かどうかは関係ありません。
目標を設定した時点で達成までの道のりが全く見えないどころか想像できなくても関係ありません。「自分ができる」と思っているかどうかが全てです。ですから、周りの人が「絶対にできない!」と止めても、自分が「絶対にできる!」と思えれば自己効力感は高いといえます。
反対に、難題に挑む際に自己効力感が高くない状態では、周りに止められることで不安になってやめてしまうでしょう。まとめますと、自己効力感は現状の外側に置いたゴール、つまり、やったことがないこと、想像すらできないこと、今の自分には明らかに難しいことに対して、自分はできる! 絶対にできる! やるぞ! と心から思える気持ちのことです。
一語にしてしまうと、「根拠のない自信」ともいえるでしょう。よくビジネスで成功するのは「賢い人」よりも「行動する人」だといわれます。確かに行動しなければ何も生まれませんが、賢い人は根拠やリスクを考えてしまいがちです。そして、後先考えずにすぐに行動できる人はどういう人かというと「やれる」自信がある自己効力感が高い人なのです。
■自己効力感は「未来」への自信
自己効力感に似た言葉に自己肯定感があります。自己肯定感とは、自己を尊重し、自身の価値を感じることができ、自身の存在を肯定できる力です。
自己肯定感が高い状態だと、「ありのままの自分を受け入れること」ができるので、失敗したときでも、ダメージは小さくて済みます。「今度は頑張ろう」「失敗しても気にするな。それでも自分には価値がある」と捉えられるからです。
つまり、自己肯定感とは「できてもできなくても、ありのままの自分を受け入れられる力」となります。これは自己効力感が「できると自分を信じられる力」であることとはかなり異なります。
何が異なるかというと、この2つには「できない自分をどう捉えるか」という点に大きな違いがあります。自己肯定感が高い人は「失敗してもいい」に行き着くわけですから自分を変える必要がありません。できてもできなくてもいいわけですから、自己効力感が高くなりにくいといえます。
また、「自己効力感」と「自己肯定感」は、自分に対する肯定や自信を表現する言葉としては共通していますが、どの時点での自分を評価しているかが決定的に違います。自己肯定感はあくまで過去や現在の自分を対象としています。
だから、できなくてもいいわけです。それに対して、自己効力感は「達成できるか」どうかで変わるので未来の自分が評価対象になります。つまり、「私はできた!」が自己肯定感であり、「私はできる!」が自己効力感になります。

■自己効力感が目標のイメージを明確にする
では、なぜ習慣化に自己効力感が必要なのでしょうか。なぜ、自己効力感が高いと脳の「GPS機能」(ラス)が働くのでしょうか。これは自己効力感が特定の課題や目標に対する信念であることに関係しています。
そして、「私は絶対にできる」「できないはずがない」という信念が強ければ、目標を明確にイメージできます。視覚化できるのです。たとえば、起業時に「絶対に5年後に年商1億円にする」と自信があればあるほど5年後の自分の姿、事業内容や年収、ライフスタイルなどが鮮やかにイメージできるはずです。
そして、イメージできればできるほど脳のラスはそれを重要な情報と思い込み、目標達成に必要な情報に焦点を当てます。結果的に行動を起こしやすくなり、習慣化につながります。
自己効力感は行動への動機づけにもなります。
■自己効力感が高いとストレスも感じにくくなる
目標に対して「自分は絶対に達成できる」と自信を持って行動すれば何かしらの経験を得られます。たとえば、TOEIC500点の人が「絶対に1年後に990点満点をとる。絶対にできる」と自己効力感が高い状態で勉強を続けたとします。
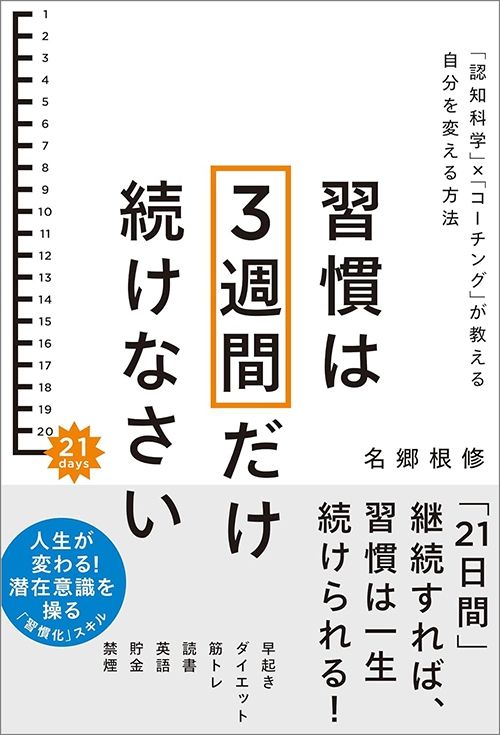
結果的に満点には届かなかったものの、900点までスコアがアップしたとします。悔しいけれども、400点もスコアをアップさせた経験から得られたポジティブな感情がラスに強く影響して、勉強をますます促すことになります。さらに自己効力感は高まります。良いスパイラルが生まれます。
また、当たり前ですが、自己効力感が高いと難題に直面しても前向きな姿勢を保てます。少し雲行きが怪しくなっても「自分はできる」と思い込めているのですから、ストレスも感じにくくなります。
これはラスの働きにおいて非常に意味があります。ストレスの負荷が脳にかかるとラスの注意の焦点が乱れるからです。注意の焦点が乱れないことで目標に向けた行動が継続しやすくなります。
人が新たに挑戦するときは「外発的動機(魅力的な目標)」がまず必要です。目標をいかに明確に立てるかは重要ですが、「ちょっと達成できそうもないな」と感じてしまうと、人は動けません。
■目標の客観的な高さは関係ない
達成できる道筋が見えなければ行動しても無駄になると思ってしまったことはあなたも経験があるはずです。ですから、「達成できる」という感覚が必要になります。
あなたは「それならば最初から達成できそうな目標を設定すればいいのでは」と思うかもしれません。目標のハードルが低ければ、達成できる確率は高まります。ただ、これは自己効力感とは関係ありません。自己効力感を高めてラス機能を働かせるには、目標の客観的な高さは関係ないのです。
繰り返しになりますが、自分が「できると思うかどうか」です。たとえば、あなたが起業するとします。その際に「5年後に会社を株式上場させる」という目標よりも、「5年後に年商1億円にする」という目標の方が達成するのは簡単でしょう。
ただ、あなたが「私は絶対に5年後に上場させる」と強く思い、自分にはできるという信念さえあれば、困難な目標でもラス機能は強化されます。達成の難易度や現実的かどうかは自己効力感に関係ないことは覚えておいてください。
----------
ハイパフォーマンス代表取締役
1978年岩手県生まれ。Rotterdam School of Management, Erasmus University 経営学修士(MBA)。米国戦略コンサルティングファーム、グローバル医療機器メーカー・フィリップスで勤務後、現在はグループ合計年商180億円の医療分野の会社・南部医理科とフィンガルリンクの経営に携わり、世界最先端の医療技術や製品の普及に努めている。「伝説の戦略コーチ」として知られ、Strategic Coach社を創設したダン・サリヴァン氏に師事し、同社が提供している「10x Ambition Program」を卒業した唯一の日本人。
----------
(ハイパフォーマンス代表取締役 名郷根 修)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
習慣化がうまくいく「成長している感覚」とは? 目標に対するモチベーション維持に必須
東洋経済オンライン / 2024年6月14日 15時0分
-
人生がうまくいっている人は絶対に言わない…心理カウンセラーが教える「不幸になっていく人」の残念な口癖
プレジデントオンライン / 2024年6月12日 17時15分
-
新しい挑戦を習慣化させる「1日1分」のすごい効果 あえて大きな目標を設定しないことに意味がある
東洋経済オンライン / 2024年6月9日 19時0分
-
こうすれば不思議と甘い物がいらなくなる…認知科学が解明「ダイエットがうまくいく人」のすごい習慣化力
プレジデントオンライン / 2024年6月8日 7時15分
-
新しいことに挑戦、多くの人が間違える始め方 習慣化しようとする人の4割が最初の7日間で挫折
東洋経済オンライン / 2024年6月4日 18時30分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












