こうすれば不思議と甘い物がいらなくなる…認知科学が解明「ダイエットがうまくいく人」のすごい習慣化力
プレジデントオンライン / 2024年6月8日 7時15分
※本稿は、名郷根修『習慣は3週間だけ続けなさい』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■「それ自体が楽しい!」内発的動機が脳を働かせる
脳には「ラス機能」と言って、いわば脳の「GPS機能」のようなものが存在します。車や地図アプリの「GPS機能」と同じで、この「ラス機能=GPS機能」を働かせると、あなたはその行動に突き動かされ、習慣化ができるようになります。
この脳の「GPS機能」を働かせるために重要なのが「内発的動機」です。「内発的動機」は、文字通り人の内側から湧き上がる動機です。内的で本質的な欲求によって引き起こされるものです。
個人の行動を後押しする内面から湧き上がるモチベーションと考えるとわかりやすいでしょう。この場合のモチベーションは、報酬や称賛などの外部からの動機とは関係ありません。自分自身から発生しています。
つまり、お金や名声、出世、評判などではなく、物事に対する興味や関心、そこから生まれるやりがいや達成感、楽しさなどが当てはまります。
■会社員の草野球や釣りは「内発的動機」による行動
たとえば、「ぽっこりお腹をシックスパックになるまで鍛えてモテたい」という理由で筋トレを始めた人が、いつのまにか筋トレすること自体が楽しくなっていることがよくあります。取り組んでいる間に、モテるかどうかはどうでもよくなって、腹筋することが爽快で楽しい、体がみるみる変わって面白いから毎日やらないと気が済まない。
こうした変化は、まさに行動の動機づけが「外発的動機」から「内発的動機」にうまく切り替わった例といえるでしょう。あなたも内発的動機づけで行動しているはずです。おそらく多くの人にとっては趣味が内発的動機による行為でしょう。
たとえば会社員で休日に草野球をしている人は野球そのものが好きだからプレーしている人がほとんどでしょう。野球選手になってお金を稼ぎたい人は皆無なわけです。同じように休みの日に早起きして釣りに出かける人も、お金のためや仕事のためではなく「釣りが楽しいから」が理由のはずです。
人にどう思われるかは関係なく、損得でもない。自分が心から好きだから没頭する、行為そのものが楽しいから取り組む。これは内発的動機づけによる行動といえます。
■「行為=楽しい」となることが定着には必要
外発的動機で目的地を明確にすることで脳の「GPS機能」(ラス)をうまく働かせられるようになります。習慣化に向けた行動に取り組み行動を脳に意識させ、反復しやすい体制を整えます。
次に日々、行動を繰り返す中で挫折しないように「私ならばできる」という自己効力感を高めます。自己効力感を高めることでラスはさらにその行動の情報を優先して処理するようになり、「GPS機能」は強化されます。
そして第3段階で習慣化に向けて行動指針となってきたラスを定着させ、習慣化のプロセスを万全にします。内発的動機は脳の「GPS機能」を定着させます。それには感情が大きな役割を担っています。
内発的動機は内面から湧き上がるモチベーションですから、個人の情熱や好奇心に深く根ざしています。楽しさや嬉しさや喜びなどですね。この情熱や興味が脳によって認識され、ラスを通じて注意を引くと、感情の中枢が活性化されます。

その行為をすると楽しい、嬉しいなどのように感情と結びつくわけです。そして、感情の結びつきが強いほど、脳はその情報を重要視し、ラスはその情報を長期記憶として定着させる傾向があります。
新しい挑戦は外発的動機で取り組むケースが大半です。「あんなふうになりたい」「お金がほしい」「とにかく痩せたい」という目標をイメージして始めます。
■「ダイエットが楽しい」となれば甘いものは食べなくなる
ただ、内発的動機がなければ続きません。なぜならば、行為自体が楽しくなかったり、嬉しくなかったりしたら、嫌になって飽きてしまうからです。
あなたの周りを見渡しても、長く続くことは感情に結びついているケースがほとんどではないでしょうか。「ダイエットしてモテたい」と目標を立てても誘惑に負けて甘いものを食べてしまうのは、甘いものを食べたいという感情に基づくものだからです。
甘いものに目がない人は外発的動機が小さく、おいしいものを食べると嬉しいという内発的動機に動かされているともいえます。
逆に、ダイエットするのが楽しいとなれば甘いものは食べなくなります。実際、内発的動機による行動が個人にとって意味のあるものになると、脳内でドーパミンと呼ばれる快楽物質が分泌されます。
これが脳の中の報酬系を活性化し、内発的動機が生む満足感や喜びが脳に強く印象づけられます。ラスは報酬に対して貪欲です。報酬が得られる行為に注意を向けてその情報を優先します。もっと報酬をよこせ、もっと報酬をよこせとなるのです。
報酬が「内発的動機」に由来する場合、同様の報酬を得られる行動を後押しします。このプロセスによって内発的動機を継続的に育むことが可能になります。
■苦しいことを楽しいことに変えることもできる
報酬だけでなく成功体験やポジティブな感情を得られる体験を脳は積極的に探しています。ラスはその情報に着目して、同じような成功体験を再現する行動を促します。また、内発的動機が高まると、人は自らのスキルと課題のバランスがとれる「フロー状態」に入りやすくなります。
フロー状態では、時間を忘れるほど集中力が高まります。あなたも仕事や勉強でおそらく一度は体感したことがあるでしょう。あれは内発的動機がもたらすものなのです。
この「フロー状態」が体験されると、脳はその経験を特に重要視するので、ラスを通じて深い学習や行動の定着につながります。行動の動機が内発的動機に基づくようになれば、意識しなくても毎日の行動に組み込めるようになります。

「ああ、嫌だな」という気持ちを抱かずに取り組めるようになっているはずです。歯を磨くのも自転車に乗るのも、筋トレも語学も変わらず向き合っている自分がいるはずです。
習慣化に向けて行動を始めたばかりのときは勉強や筋トレ、ジョギング、食事制限などは苦行以外のなにものでもないかもしれません。ただ、認知科学のプロセスをうまく生かすことで苦しいことを楽しいことに変えることもできるのです。
■脳の「GPS機能」は3週間で定着する
そして、この脳の「GPS機能」は3週間で定着することが分かっています。こう聞いて、「3週間続けるだけで本当に習慣が定着するかどうか」と思うかもしれません。
確かに、これまで何度も習慣化に挫折してきた人の中には「1カ月続けたけど、習慣化できなかった」「2カ月続けたけどしんどくなってやめちゃった」という人もいるかもしれません。
習慣化には一定の継続は必要ですが、必ずしも長く続ければいいというわけではありません。重要なのはプロセスです。
脳の「GPS機能」は、複雑な神経ネットワークの一部であり、情報の仕分け場であることはこれまでにお伝えしてきました。大量の情報の中から人が重要な情報と認識した情報を抽出し、特定の行動を後押しします。
これにより目標を達成したり、習慣化につなげたりすることが可能になります。ですから、どの情報を取り入れるか、どのくらいの注意を向けるかを選択するプロセスをつくることが新しい行動や習慣を獲得する際には欠かせないわけですが、このプロセスは習慣化に向けた行動を始めてからの最初の3週間が特に重要になります。
■3週間さえ続ければ「一生続ける脳」に変わる
なぜ、1週間でも半年でもなく3週間かというと、脳の仕組みが変わるのに必要な期間がちょうど3週間だからです。新しい行動や習慣を始めると、脳内のシナプス結合が変化し、それに伴って神経回路が強化されます。このプロセスを神経可塑性と呼びます。初めての行動や情報に対して神経回路が新しく形成されることで、脳の「GPS機能」はそれを重要な情報として認識しやすくなります。
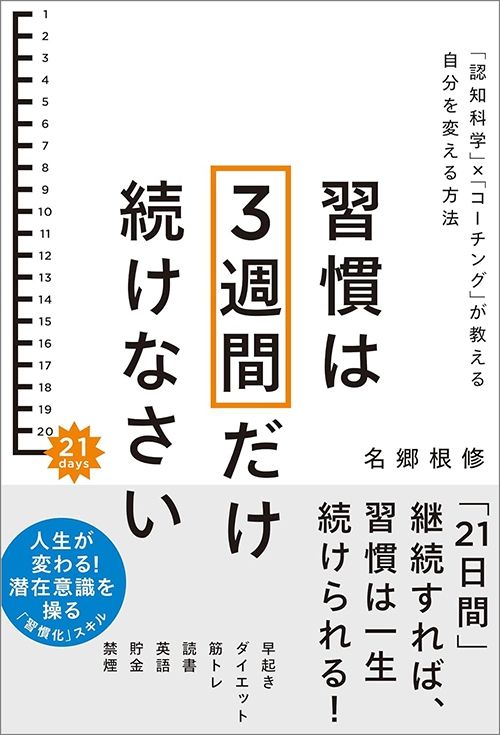
また、習慣の定着には反復が必要です。3週間あれば、行動や習慣を十分な回数繰り返すことで神経回路が十分に安定化し、ラスがその情報を無意識に認識できるようになります。
この過程において、行動が無意識的かつ自動的に行われるようになり、それが習慣の定着につながります。つまり、3週間続けることで、神経可塑性と反復の相互作用によって神経回路が変わります。脳が変わるのです。
ですから、3週間さえ続ければあなたの脳はその習慣を一生続ける脳に変わるといってもいいでしょう。
もちろん、3週間続けるのも難しく感じているかもしれません。私も新しい挑戦に挫折したことは少なくありませんが、今、振り返れば、正しい取り組み方を知らなかっただけです。
正しい手順を踏めば、誰もが無理なく続けられて、一生ものの「習慣化」メソッドを手に入れられます。
----------
ハイパフォーマンス代表取締役
1978年岩手県生まれ。Rotterdam School of Management, Erasmus University 経営学修士(MBA)。米国戦略コンサルティングファーム、グローバル医療機器メーカー・フィリップスで勤務後、現在はグループ合計年商180億円の医療分野の会社・南部医理科とフィンガルリンクの経営に携わり、世界最先端の医療技術や製品の普及に努めている。「伝説の戦略コーチ」として知られ、Strategic Coach社を創設したダン・サリヴァン氏に師事し、同社が提供している「10x Ambition Program」を卒業した唯一の日本人。
----------
(ハイパフォーマンス代表取締役 名郷根 修)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
人付き合いの不安・怒り…そのストレス「脳科学」でスッキリ解決できます!【医師解説】
ハルメク365 / 2024年6月17日 11時50分
-
習慣化がうまくいく「成長している感覚」とは? 目標に対するモチベーション維持に必須
東洋経済オンライン / 2024年6月14日 15時0分
-
新しい挑戦を習慣化させる「1日1分」のすごい効果 あえて大きな目標を設定しないことに意味がある
東洋経済オンライン / 2024年6月9日 19時0分
-
「根拠のない自信」にはすごい効果がある…コーチングのプロは知っている"目標を達成できる人"が持つ能力
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 7時15分
-
新しいことに挑戦、多くの人が間違える始め方 習慣化しようとする人の4割が最初の7日間で挫折
東洋経済オンライン / 2024年6月4日 18時30分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた
東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分
-
4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
5「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












