事情通の間で常識「世田谷、横浜で家を買ってはいけない」…業界の息かかった「住みたい街ランキング」の罪深さ
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 9時15分
※本稿は、山下努『2030年不動産の未来と最高の選び方・買い方を全部1冊にまとめてみた』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。
■バス便エリアはもう新築がほとんど建たなくなる
少子化や人口減少は進み放題で、東京圏も人口の減少が始まる。
仕事を東京に求める若者が多い郊外や地方でバス便のエリアではもう、新築マンションはほとんど建たなくなるだろう。
郊外や地方の人口減少を受けて、駅前の買い物需要を奪って発展してきた郊外のローサイドの店舗も都心回帰を始め、都心方向に立地を移している。
ロードサイドの大型店の閉店や撤退が増えているが、マンションなどに土地を再利用できそうな物件はほとんどない。
そうなると、郊外のロードサイド店の周りにできた住宅やマンションの価値も落ちて、若い層もますます出て行くために住人の高齢化に拍車がかかる。
■世田谷と横浜は買ってはいけない
高齢者の車の運転による買い物が困難になり、ロードサイドの住宅街はさらに買い手がつかないまま暴落し、新たな空き家地帯になってしまう。
これは、最悪のケースを想定した場合、中途半端な立地の横浜市や世田谷区の未来でもある。
バス便が一日1往復に減った住宅街もあるが、バス事業は儲からないので会社ごと消える可能性すらある。タクシーも同じだ。郊外は駅徒歩圏の選択は必須だ。
だから、不動産業界も郊外での新規供給は抑える。私鉄沿線では駅前のタワマン建設を競い合っている。
世田谷区は23区の南西端で現在も23区最大の人口を擁するが、ベッドタウンとしての本質的な役割は経済と人口が増えたバブル期に終焉している。区市町村としては全国最多の空き家を抱えるのがその証拠といえる。
マイホームを買う場所として、なぜ「世田谷区はダメでなぜ大田区はOK」「横浜が売りでなぜ川崎は買い」なのか。
「ヨコハマ崩壊、世田谷心配」を知らない人々に、以下、解説していこう。
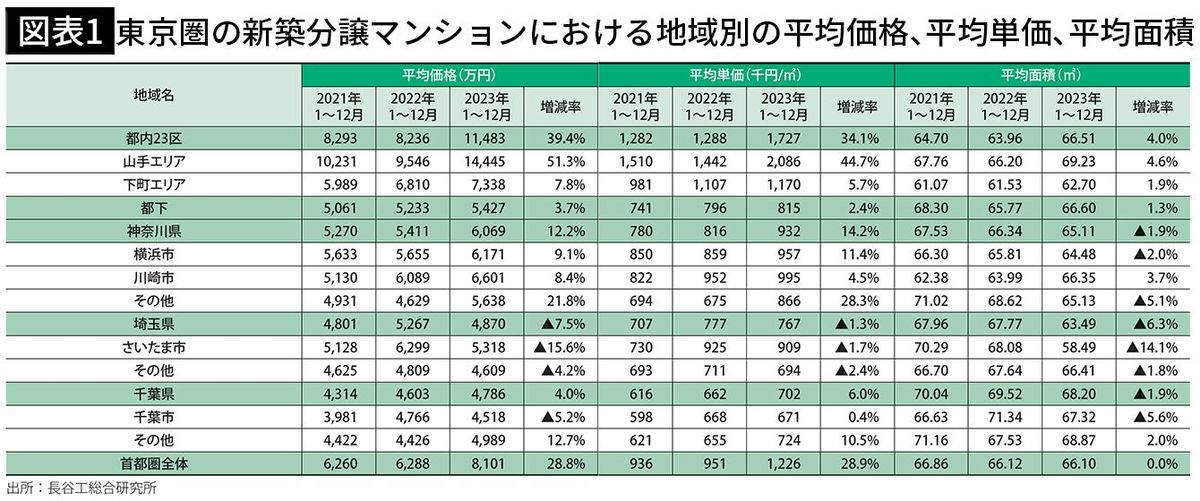
■事情通は10年以上前から知っていた事実
現在は「世田谷心配、横浜大変」という状況である。これは事情通には10年以上前からわかっていたことだが、まだまだ割高の世田谷区や横浜市の住宅を求める人も少なくなく、これからも多くの悲鳴が聞こえるはずだ。
都心や湾岸にタワマンがない時代に、「最もよい選択」として世田谷や横浜を選んだのだ。
だが、人気住宅地は地殻変動し、不動産業界の息のかかった「住みたい街ランキング」が虚構色を帯びてしまった。

■役割を終え、空き家だらけとなった世田谷区
23区で最多の世田谷区(94万人)の人口は、隣県の山梨県(79万人)より15万人近く多い。
山梨といえば空き家率が全国トップクラスだが、自治体のなかで最も空き家が多いのが世田谷区である。
しかも、世田谷区は23区の南西の端に位置する。
地価などが高いまま、膨張する人口を抱えていたバブル時代までのあだ花の地だ。
その衛星都市(ベッドタウン)としての機能は、じつは40年前にはピークアウトしたばかりか、役割はほぼ終わっていたわけである。
それなのに、圧倒的な人口を誇る団塊の世代があこがれた世田谷の地は、十分に価格が下方修正できないまま、いまを迎えた。
空き家の数が多いのは、じつは大都市だ。
だから空き家問題は、半分は都市問題といえる。
総務省の2018年の住宅・土地統計調査によると、下記のように続く。
第1位 東京都世田谷区(49070戸)
第2位 東京都大田区(48080戸)
第3位 鹿児島市(47100戸)
第4位 東大阪市(44180戸)
第5位 宇都宮市(44050戸)
■「横浜は売りで、川崎が買い」はすでに常識
同様に、コロナ後の東京都心再集中の時代では、「横浜って素敵」という素人判断も大間違いである。
「おしゃれ」「港」「都会的」などのイメージで横浜を選んでしまう間違いは、10年かけても訂正があまり進んでいない。
住宅購入期の30~40代が、真似をしてはいけない親世代の住宅観をなかなか修正できず、損失を出し続けていることも意味している。
横浜市の人口規模は、静岡県、四国4県、モンゴルと比べても、3者のそれぞれの人口より多い370万人超を誇るが、2年連続で人口が減り、2024年も人口減は食い止めないだろう。
■横浜市の多くは空き家を抱える住宅エリア
横浜市は、みなとみらい(MM)を有する西区と中区の一部にだけ集中的に開発資金が投下され、立派な街のように見えるが、多くの地域は空き家を抱える住宅エリアだ。
横浜市は日本最大の自治体である点、つまり図体が大きすぎることから機能不全となっている。
市議会はほぼオール与党で、市の遅れた開発政策を修正できないでいる。
みなとみらいや関内の開発コストが高いうえ、オフィスビルや賃貸住宅の賃料水準も東京並みに高く、諸税の減免をしてみても、横浜に進出検討する企業は多くはない。
東京から進出してくる企業の開発負担を減らすためか、昔の中心地である関内の趣ある市庁舎は数千万円で叩き売られた。
こうした企業誘致における初期段階の出血大サービスは、横浜市が得意とするデベロッパーへの「必殺技」だ。
その周辺に東京資本(財閥系の不動産最大手3社)が超高層ビルを建て、地元資本の関内らしい年季の入ったビル群のオーナーは本当に迷惑している。
ハザードマップでも、液状化などのリスクを抱える関内の一部は危険エリアを示し、外資系企業の投資対象になりにくい。
至れり尽くせりの関内駅前再開発で、関内全体で起きているオフィス建物の二極化はさらに進みそうだ。
■横浜は「訪日客通過都市」となっている
さらには山下ふ頭で大規模な再開発を行い、大自然が残る瀬谷(米軍返還地)で道路工事、区画整理や伐採などの土木工事を大規模に行い、花の万博を行い、その後はテーマパークにする。
万博とテーマパークの事業採算も不透明だ。横浜に観光に来て泊まる訪日客は少なく、素通りして箱根や富士方面に行く。
横浜は「訪日客通過都市」なのだ。
横浜市は市民一人当たりの債務残で見ても全国有数の財政難都市なのに、このような再開発事業が目白押しだ。

しかし、そうしたツケで子どもの医療費補助や、高校の授業料減免は、東京都と比べて大幅に後れをとってきた。
そのうえ、横浜市は台地や丘陵地など、「崖の上の住宅」に近いところも大量にある。
移住先に選ばれない街の横浜が若い層(車は持ちたがらない)を呼び込みたいなら、市バス便も生命線だ。
横浜の郊外ではバス便が大きく減った住宅街もあり、バス会社の9割は赤字なので会社ごと消える可能性もある。タクシーも同じ状況だ。
坂や崖が多い横浜の郊外は駅徒歩圏が必須だが、まだ住宅価格が調整できず、買い控えられる。そして24年も3年連続の人口減となるだろう。
このため、三浦市、横須賀市に続いて、横浜市南部の人口減少は著しい。横浜の人口は北東に向かってシフトしている。
つまり、東京方面に回帰し、川崎市に向かっているのだ。
プライドの高い横浜市民は、川崎と比べられること自体嫌がるが、川崎の工業都市のイメージはすでに薄れ、住宅都市に変貌している。
もちろん、横浜の中区には山手や中華街など観光地もあるが、ただそれだけである。
■なぜ横浜はダメで川崎が買いなのか
「横浜は売りで、川崎が買い」
「東京を選ぶなら世田谷は外す」
というのは、個人的にはもう一般常識の範疇だと思う。
読者は、「ダメな横浜に隣接する川崎(人口154万人)がなぜよいのか」といぶかるかもしれない。
東京からの移住先としてほとんどメリットはないのが、横浜の実情なのだ。
東京の下町エリアより家賃の高い横浜は、本当は企業にも勤労者にも人気はないが、最近は人気(ひとけ)も少ない。
横浜市は、「住みたい・住み続けたいまち」「選ばれるまち」としての都市ブランド確立に向けたプロモーションを展開。吉本興業と制作したYouTube動画で、「横浜の魅力を満喫します」(政策局広報戦略)と言うのだが。
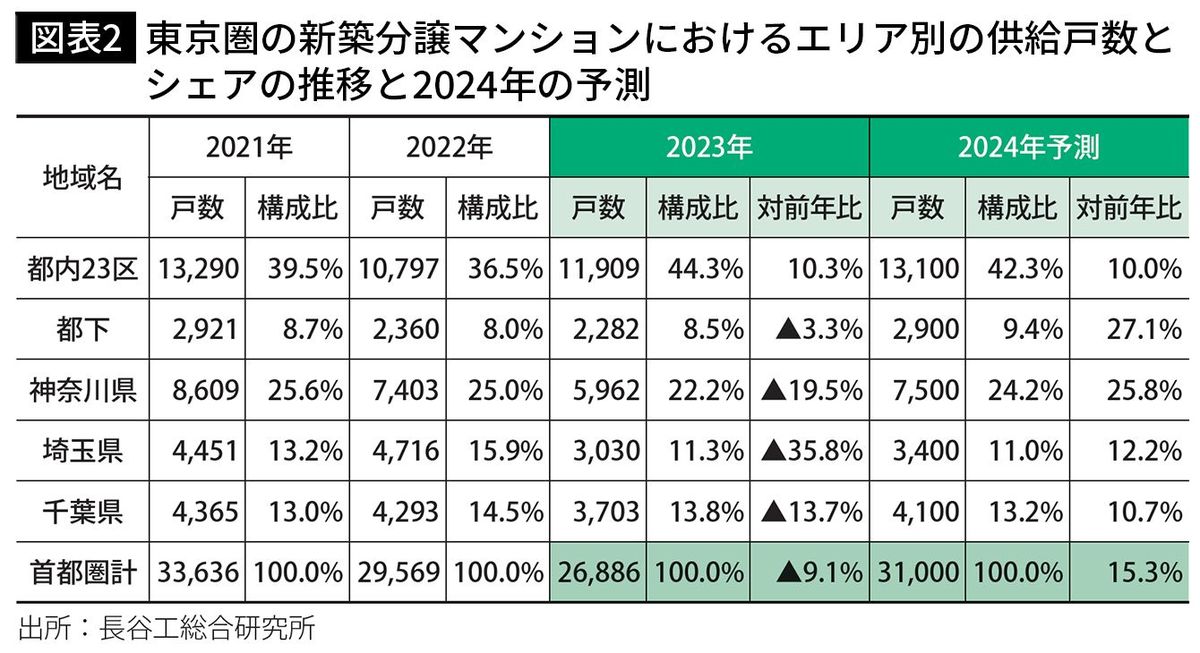
■月島の狙い目は「もんじゃ焼きタワー」
ここで、湾岸エリアの月島の状況を見てみよう。
月島のもんじゃ焼き商店街は、アーケードの下にあるが、アーケードの裏手に回るとタワマンだらけで、お好み焼きのお店までタワマンに入っていることがわかる。
もんじゃ焼き店のアーケード街を見上げて、「月島は古い街で風情がありますね」なんて言っていると、頭隠して尻隠さずの世界だ。
「もんじゃ焼き店が入るタワマン」はこれから人気が出るかもしれない。風情があるのかないのか、謎の立地なこともむしろプラスだ。
月島においては、住友不動産、東京建物、大和ハウス工業などが分譲する「グランドシティタワー月島」という建設中の超大型物件が注目されている。
58階建て、総戸数1285戸ともなる巨大タワマンだ。
その対抗馬は、三井不動産レジデンシャル、野村不動産、大成建設が2028年に竣工予定の48階建て総戸数744戸のタワマンである。なお、佃も月島エリアだ。
■豊洲にまだまだ掘り出し物あり
地下鉄有楽町線の延伸が決まった江東区でも「豊洲」を冠したマンションが増殖する動きに拍車がかかりそうだ。
2001年から数年間は、「豊洲なんて変なところの地名をマンション名につければ売れ行きが悪くなる」ということで、「東京」などの名を冠した地名のない格安マンションが増殖した。
豊洲駅徒歩5分でも新築で坪単価は150万円、広さは100m2弱で5000万円弱の物件も豊富だった。我が家も似たようなものだ。
造船関連産業の匂いも残り、海外からの住民もいた。
かつての小学校のPTA通信は日本語、韓国語、中国語、タガログ語で書かれ、「多様性があって英語がないところが最高だ」と購入候補地に決めた。
当時は市場評価も低かったが、現在は外資系企業の関係者の住む街からオフィス街に変貌した。
私が道路の目の前の部屋を選んだのは、道路には新たな建物が建たないと判断したからだ。
豊洲においても「少しでも閑静な場所を」と公営住宅や公園に近いところを選ぶ人もいた。
しかし、高層化された公営団地や新しいタワマンの日陰になってしまった建物が続出している町である。

■かつては「豊洲隠し」のマンションが多かった
こうした背景があって、20年近く前は、あえて名前に豊洲を冠しない「豊洲隠し」のマンションは普通にあった。
駅前の中古物件でも意外に値上がりせず、発売価格の2倍には届いておらず、タワマンでないためか掘り出し物が、じつに多い。
いまの豊洲の新築価格は、豊洲隠しの時代の2~3倍の価格だ。
「豊洲」の名を外したマンションは、資産価値を上げるため、「豊洲」に名を冠した名前に変えれば、もっと中古価格が上がるはずだ。
オフィスビルは、所有者が変われば名前も変わり、管理体制や賃料も変わる。
レジデンス(住宅)でもそうした時代がくるので、筆者自身が自宅マンションの理事を務めた際には、マンション名の改名という提案も軽くしてみた。
名前も「豊洲」を冠した「豊洲駅レジデンス」などとしたほうが、価値が上がるだろう。
リッチな中華系の客をとるには、漢字を入れたほうがいい。
■「将来の建替え」も視野に入れて物件を見る
資金繰りが厳しくなるばかりのマンション管理は、「名称の大規模修繕」が今後の課題になる。
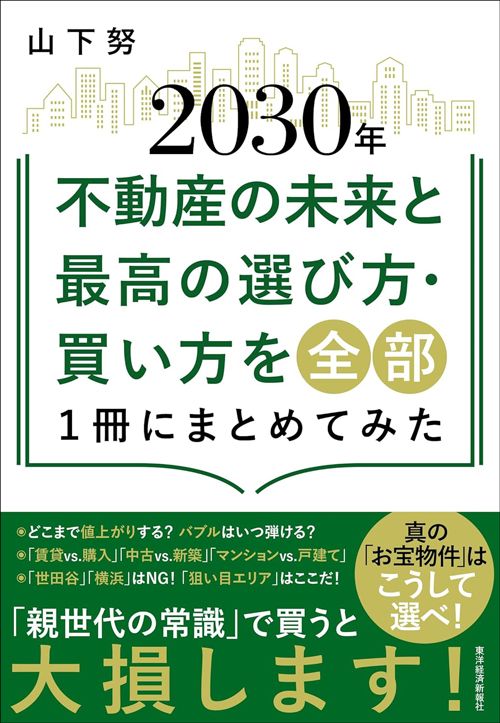
このように、タワマン以外なら、湾岸でも「驚きの格安物件」が意外にも残っている。
不動産価格は急には修正されないからだ。
20階建てくらいでも、「タワー」を冠したほうが売れ行きにプラスになるかもしれない(これはうわべのタワーブームに乗る前のジョークだが)。
たとえば、豊洲4丁目9の大規模物件は、主力の棟が14階からの中低層の集合体で中庭がかなり広く、一戸当たりの土地面積も広い。豊洲駅から徒歩5分ほどだ。
25階以上でないため、一部の住戸は億ション扱いになったものの、富裕層や外国人の投資対象にはなっていない。だが、将来は青空駐車場や中庭の広い敷地にツインタワーが十分に建ちそうだ。
建替え検討時には、一戸当たりの家族数は新築時の半分以下になっているだろう。
よって住民分の建替え住戸の面積はコンパクトでよく、建替え面積の半分以上を外販してそれを建替え資金とすれば、建替え費ゼロも不可能ではない。
おまけにインフレとコロナ禍の前に決めた全戸のペアガラス(断熱)の導入決議も、大規模修繕のあとに導入反対運動が起きて、ペアガラス導入の撤退決議が通った。結果的に、修繕積立金を数億円も節約している。
「脱炭素で環境に優しい」と聞けば、無条件にEV施設の導入も許容される時代だが、マンション管理の財政は悪化するうえ、「環境に優しい」効果も疑わしい。
もうかるのは、納品や工事を請け負う業者筋だ。
----------
元朝日新聞経済部記者、経済ジャーナリスト
1986年朝日新聞社入社、大阪経済部、東京経済部、『ヘラルド朝日』、『朝日ウイークリー』、「朝日新聞オピニオン」、『AERA』編集部、不動産業務室などに在籍。2023年朝日新聞社退社。不動産業(ゼネコン、土地、住宅)については旧建設省記者クラブ、国土交通省記者クラブ、朝日新聞不動産業務室などで30年以上の取材・調査経験を誇る。不動産をはじめとする資本市場の分析と世代会計、文化財保護への造詣が深く、執筆した不動産関連の記事・調査レポートは1000本以上に及ぶ。『不動産絶望未来』(東洋経済新報社)、『「老人優先経済」で日本が破綻』(ブックマン社)、『世代間最終戦争』(立木信名義、東洋経済新報社)、『若者を喰い物にし続ける社会』(立木信名義、洋泉社)、『2030年不動産の未来と最高の選び方・買い方を全部1冊にまとめてみた』(東洋経済新報社)など多くの著書がある。
----------
(元朝日新聞経済部記者、経済ジャーナリスト 山下 努)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
家を買うなら「谷・丘・山・台」つく地名は要注意だ 「地価暴落・空き家増・店舗閉鎖…」リスクあり?
東洋経済オンライン / 2024年7月10日 12時0分
-
「名商店街は壊され分断される」タワマン建設を都知事候補小池百合子氏や首長がスイスイ認める恐るべき目論見
プレジデントオンライン / 2024年7月4日 10時15分
-
都知事選で「都内の"不動産価格"」今後どうなる? 「住宅や再開発政策」はもっと争点になるべきだ
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 13時0分
-
都内「タワマン乱立」で"下町消滅"は問題ないのか 「商店街をなくす再開発」で"下町情緒"は消え…
東洋経済オンライン / 2024年6月25日 11時30分
-
東京「どの駅」「どの区」が今後、価値が上がるのか 「昼間人口比率」に見る「住むべきエリア」正解は
東洋経済オンライン / 2024年6月21日 13時40分
ランキング
-
1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分
-
2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収
ロイター / 2024年7月18日 8時34分
-
3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り
共同通信 / 2024年7月18日 11時58分
-
4マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」
J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分
-
5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵
プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











