「泣きすぎて顔が紫色に」朝ドラのモデル三淵嘉子は戦争で夫を亡くした…終戦前後に出した「4つの葬式」
プレジデントオンライン / 2024年5月29日 8時30分
※本稿は、佐賀千惠美『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』(日本評論社)の一部を再編集したものです。
■嘉子は28歳のとき結婚し、苗字が武藤から和田になった
弁護士になった翌年の、昭和16年(1941年)11月5日。嘉子(よしこ)は和田芳夫と結婚した。
彼女の弟である武藤輝彦はこう書いている。
(和田は)父の中学時代の親友の従弟で、父の関係した会社に勤めながら明大夜学部を卒業した努力家でした」(『追想のひと三淵嘉子』)
筆者は武藤輝彦に会い、さらに詳しく尋ねた。
輝彦「お茶の水(編集部註:東京女子高等師範学校附属高等女学校)の同級生の皆さんは、いわゆる立派な大学を出て、一流会社に入ったような人のお嫁さんになっておられます。姉は法律を選びました。『お茶の水出』という、花嫁切符を捨てたわけです。母が心配したとおり、世間でいう『いい縁談』は、来ませんでした。
一人、嘉子と結婚したいと熱心に言った男性はありましたが。性格がもうひとつでした。
和田芳夫は我が家にいた、書生さんの一人です。当時、ちょっとした家には、女中さんと共に、書生さんがいたものです。武藤家にも、郷里の香川県から次々と若者が上京して、書生をしてくれました。彼らは勉強しながら働いたのです。和田は明治大学を卒業しました。
和田も、郷里から出て来て、我が家から、学校と仕事に通いました。古なじみな一人なわけです。彼は、周りにいた中で、最も気立てのやさしい、いい男でした」■夫の和田芳夫は優しい人、病弱なのに兵役について病死する
「結婚は、相手の性格がいいことが一番だ」と、筆者は思う。芳夫と結婚して、嘉子はよかっただろう。
しかし、一方、法律を勉強したというだけで、結婚の話が来なくなるなんて。何と不当なことか――。
輝彦は言う。
「当時の世間は、女性が勉強することを望まなかったのでしょう」
結婚して1年2カ月後。昭和18年(1943年)1月1日、ひとつぶ種の芳武が生まれた。嘉子の両親にとって、芳武は初孫である。目に入れても痛くないほど、かわいがった。
子供が生まれて1年半後。昭和19年(1944年)6月、夫の芳夫は兵隊にとられた。しかし、以前に肋膜炎をした傷あとがあって、召集が解除された。
しかし、翌20年(1945年)1月。彼はまた召集された。もう戦争の末期である。弟の輝彦はこう書いている。
芳夫は戦地に行き、病気で亡くなってしまう。
■お嬢様育ちの嘉子が福島の農家に疎開して田植えを手伝う
戦争が激しくなるにつれ、生活が苦しくなった。長男の芳武が生まれて約1年後の昭和19年2月。住んでいた麻布笄町(こうがいちょう)の借家は、軍の命令で引き倒された。空襲による火事を防ぐためであろう。嘉子らは高樹町に移った。しかし、翌20年5月。この家も空襲で焼けた。弟の一郎の妻である嘉根と一緒に、嘉子は疎開した。嘉根は生まれたばかりの娘を連れていた。芳武は、2歳半だった。
4人は6カ月間、福島県の坂下の農家で暮らした。輝彦は疎開先の様子をこう語る。
豊かな家で育てられた彼女である。大変な苦労であったろう。
■終戦前後の3年間で家族を次々と失い、4つの葬式を出す
終戦をはさんで3年の間に、嘉子は4つの葬式を出した。
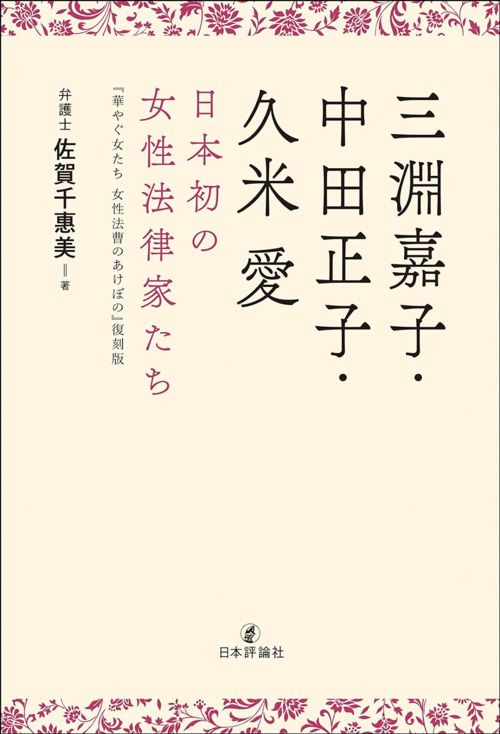
まず、彼女のすぐ下の弟、一郎が戦死(昭和19年〔1944年〕6月)。彼は、2度目の応召で沖縄に向かっていた。船が鹿児島湾の沖で、沈没した。
武藤家の長男が亡くなったわけである。しかも、遺骨は帰らなかった。遺品だけが父のもとに返された。
次に、嘉子の夫が軍隊で病死した(昭和21年〔1946年〕5月)。和田芳夫は病気をするために兵隊に行ったようなものだった。中国に渡るとすぐ発病。上海で入院した。そして、長崎の陸軍病院までは帰って来ていた。
芳夫と嘉子夫婦の一人息子である和田芳武は、筆者にこう語った。
電報が家に着いたときのことは、今でも覚えています。家中、驚きましたから」
筆者「まだ3歳でいらしたでしょう。よく、記憶にありますね」
芳武「ええ。強い印象でした」
嘉子は当時、明治大学の女子部で、民法を教えていた。ちょうど女子部で勉強していた、佐賀小里は言う。筆者の義母である。
涙で顔が紫色になった人を見るのは、私は初めて。『夫が死ぬと、こんなにつらいめにあうのか。それなら、私は結婚はするまい』と思ったほどでした」

■嘉子の母ノブも脳いつ血で急逝、その9カ月後も葬式を出す
さらに、嘉子の母、ノブも脳いつ血で突然、世を去った(昭和22年〔1947年〕1月)。心労が重なったのだろう。
芳武は4歳。祖母の死去の日も、彼は覚えていた。
筆者「どんなおばあさまでしたか」
芳武「行儀にうるさく、怒ると怖かったです。しかし、いつもはとても優しかった。祖母が四角いかごを背負ってぼくを中に入れ、新潟の瀬波温泉まで連れて行ってくれたこともありました」
嘉子の父、貞雄も9カ月後に亡くなった(昭和22年10月)。
芳武「ぼくが覚えているのは、祖父がよく酒を飲んでいたことです。肝硬変になり、足がむくんで亡くなりました」
■生活のため働かなくてはならなくなり、弁護士より裁判官を目指す
嘉子は相次いで、弟、夫、母と父に死なれた。幼い芳武をかかえて、生活していかなければならない。彼女はこう書いている。
昭和13年に受験した司法科試験の受験者控室に掲示してあった司法官試補採用の告示に『日本帝国男子に限る。』とあったのが私には忘れられなかったのである。(中略)同じ試験に合格しながらなぜ女性が除外されるのかという怒りが猛然と湧き上がって来た。(中略)そのときの怒りがおそらく男女差別に対する怒りの開眼であったろう。当時は司法官のみならず女性は官吏には採用されなかった。(中略)
ともかく、私は男女平等が宣言された以上、女性を裁判官に採用しないはずはないと考えて裁判官採用願を司法省に提出した。当時司法省の人事課長であられた石田和外氏(後の最高裁判所長官)が、私を坂野千里東京控訴院長に面接させた。
院長は、はじめて女性裁判官が任命されるのは、新しい最高裁判所発足後がふさわしかろう、弁護士の仕事と裁判官の仕事は違うからしばらくの間、司法省の民事部で勉強していなさいといわれ、裁判官としての採用を許されなかった。間もなく新憲法が施行され、最高裁判所が発足するという昭和22年3月のことであった」(『追想のひと三淵嘉子』)
■女性はまだ裁判官になれなかったが、司法省でのキャリアを開始
嘉子は昭和22年(1947年)6月30日、司法省の民事部に勤め始める。「司法調査室」で仕事をした。彼女は次のように書いている。
当時、民法調査室は(中略)、民法の改正法案についてGHQと審議を続ける一方、家事審判法案作成作業中だったと思います。
すでにでき上がっていた民法の改正案を読んだときは、女性が家の鎖から解き放され自由な人間として、スックと立ち上がったような思いがして、息を呑(の)んだものです。始めて民法の講義を聴いたとき、法律上の女性の地位のあまりにも惨めなのを知って、地駄んだ踏んで口惜しがっただけに、何の努力もしないでこんなすばらしい民法ができることが夢のようでもあり、また一方、余りにも男女が平等であるために、女性にとって厳しい自覚と責任が要求されるであろうに、果たして、現実の日本の女性がそれに応えられるだろうかと、おそれにも似た気持ちを持ったものです」(「婦人法律家協会会報」17号)
----------
弁護士
1952年、熊本県生まれ。1977年、司法試験に合格。1978年、東京大学法学部卒業。最高裁判所司法修習所入所。1980年、東京地方検察庁の検事に任官。1981年、同退官。1986年、京都弁護士会に登録。2001年、京都府地方労働委員会会長に就任、佐賀千惠美法律事務所を開設。著書に著書に『刑事訴訟法 暗記する意義・要件・効果』(早稲田経営出版)、『三淵嘉子・中田正子・久米愛 日本初の女性法律家たち』(日本評論社、2023年)、『三淵嘉子の生涯~人生を羽ばたいた“トラママ”』(内外出版社、2024年)
----------
(弁護士 佐賀 千惠美)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
朝ドラのモデル三淵嘉子が語らなかった傷害未遂…裁判所内で当事者の老女にカミソリを向けられた最大の危機
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 7時15分
-
朝ドラ「虎に翼」“発芽玄米”小橋(名村辰)株急上昇! 刃物向けられた寅子(伊藤沙莉)を気遣う姿に「見直した!」「君にキュンするとは」
iza(イザ!) / 2024年7月10日 11時14分
-
「女だから家庭裁判所というのはおかしい」朝ドラのモデル三淵嘉子は上官の最高裁判所長官に秒で反論した
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 7時15分
-
朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分
-
朝ドラの梅子は新民法のおかげでサバイブしたが…旧民法下で最愛の娘を取り上げられ命絶った女性詩人の悲劇
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 7時15分
ランキング
-
1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
21日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
-
3「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”
日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分
-
4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃
乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分
-
5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方
東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











