なぜ日本の医療現場でこれができないのか…人手不足のフランスの病院が"5週間の休暇"を完全消化できるワケ
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 8時15分
■難航する「医師の働き方改革」
長時間労働による心身の健康被害が問題視され、適正な労働時間を守るために進められている「働き方改革」。2019年に関連法が成立・施行され、残業の上限時間の設定や有給休暇の一部取得義務化などの対策が行われている(参考:厚生労働省愛知労働局「働き方改革関連法」の概要)。
医療機関に勤める医師の40%が月80時間以上の残業をしているなど、過労死ラインを超える過重労働が一般化してしまっている医療現場でも、2024年4月より「医師の働き方改革」が始まった。国からの掛け声は大きいが、運用には医療機関によってばらつきがあり、業務の一部を「自己研鑽」と呼び替えて無償残業の悪習を継続する例も見られている。
現場の医師たちの反応は複雑だ。医療専門メディアm3.comの勤務医1000人アンケート(4月16日〜17日実施)では、回答者の21.1%が「働き方改革はよかった」としたが、若い世代の反応は他の世代よりも「よくない」という回答が多かった。
また、医療従事者にヒアリングしてみると「医師は“体力おばけ”が生き残る生存バイアスで作られた世界で、そもそも『休む』という概念がない」「運用は何も変わらず、休めと号令だけかけられている」との声も依然として聞かれる。
■医師が夏のバカンスを取得できるフランス
「バカンス大国」として知られるフランスでは、労働法で義務取得とされる年5週間の有給休暇が医師にも適用され、勤務医も開業医も、主に夏の7、8月にまとまった休暇を取得している。看護師や保育士、介護士など、医療福祉をめぐる別業種も同様だ。
同じ業種でも、国によってここまで休暇の取得状況が変わるのはなぜなのだろう? 在仏日本人ライターの筆者は、フランスで多業種の人々に取材し、「休める働き方」の実現に欠かせない制度やノウハウを書籍『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)にまとめた。
本稿ではこの『休暇のマネジメント』から、医師・看護師に関する箇所を、要約抜粋してご紹介しよう。両者とも、日本で国家資格を取得し働いた後、フランスの総合病院に勤務している日本人だ。
■同僚や上司もみな「5週間の年次休暇」を取得している
医師でインタビューに答えてくれたのは、パリ首都圏の公立総合病院で働く脳神経外科医アツシさん。日仏の大学病院間の協定で研修医(レジデント)として派遣されて3年間、実質的には専門医(チーフレジデント)として働いている。大学病院の常勤教授のもとに配置され、当直はなし。週の勤務時間は残業込みで平均55時間ほどで、日本で勤務していた大学病院よりもかなり短い。年次休暇は法定通りの5週間で、同僚や上司もみな、消化しているそうだ。
そのような働き方は、どうやって可能になっているのだろうか。
「まずフランスの勤務医は、とにかく雑務が少ないんです。医師・看護師以外のスタッフとの分業が徹底しています。常勤医になると基本的に、仕事は手術・外来・病棟診察・カンファだけで、それ以外の事務仕事、紹介状や書類関係の書類もすべて秘書が担います」(アツシさん)
■院内業務の分業が徹底されている
外来と手術のスケジューリングも、カレンダーアプリを使って秘書が管理し、検査オーダーや結果の受け取りも秘書が行う。常勤教授には1人につき1人、専門医には2人につき1人、秘書がつくという。
「専門業務以外の分業は、看護師でも同じです。手術室の清掃や手術道具の消毒を行うのは看護師ではなく、他に専門の人員がいます。手術室から病室に患者を移送するのも、力自慢の専用人員が2、3人いる。院内業務の分業が、医師と看護師以外の多くの人員に担われているのです。そうして雑務を少なくした上で、フランスは外来も手術も入院中の診察も、完全当番制で行います」
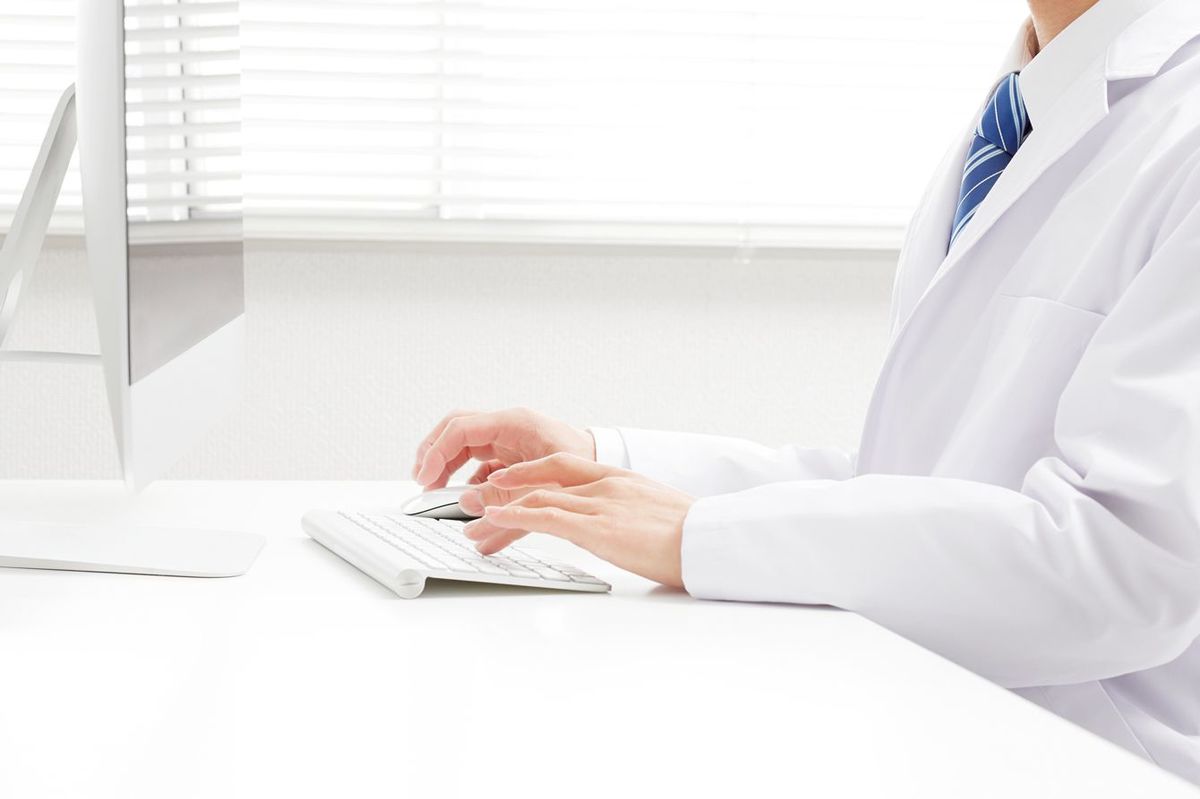
いわゆる「チーム医療」と呼ばれるものだ。フランスでも執刀担当医はもちろんいるが、同じ医師が術後にも主治医として病棟を回診するとは限らない。回診は主に研修医が担い、「今週は君が3階病棟、来週は5階病棟の担当ね」と週替わり・入れ替わりで当番を割り振られる。患者側もそれを分かっているので、特定の執刀医を求める人はあまりいない。
「教授クラスの外科医になると『この先生に執刀してもらうために』と病院を選ぶ方も多く、回診中に『教授と話したい』との要望を受けることもあります。ですがそれも『教授は今多忙なので伝言しますよ』と言えば、深追いされることはほぼないです」
■治療のゴールについては当番制でも大きな違いを感じない
土日の当直も完全当番制で、専門医と研修医がコンビで担当。まず研修医が診察し、手術が必要であれば専門医が執刀、難しいケースは教授に連絡が行くが、それも電話の指示程度で、教授が当直に来ることは珍しい。
「日本は主治医が診察から執刀、手術後の回診も担う担当医制ですね。私もその中で学び経験を積んでいるので、治療の継続性やカルテの引き継ぎなどで担当医制の良さは実感しています。が、治療のゴールという点では、当番制もそこまで大きな違いは感じません」
もう一つの大きな違いとして、アツシさんは集約化を挙げる。
「たとえばパリ圏では、重篤なケースの救急対応を6つの大学病院で日替わり輪番する連携体制『グランド・ギャルド(大当直)』があり、救急対応も集約化しています。各病院は6日に一度の担当日の当直日に人員を多く配置し、時間体制で救急車を受け入れる一方、残りの5日間の当直はより少ない人員配置で回せる。集約化は医療アクセスの距離が伸びる面もあるので、良いことばかりではありませんが、医療側としては余力を作れる方法です」
■医師であっても休暇を楽しむのが当たり前
このような仕組みやスタンスで回っているので、フランスの病院では「誰かの不在が、残った誰かに負担をかける」ということが起こりにくくなっていると、アツシさんは感じている。また患者の側にも、医師であってもちゃんと休暇を楽しむのが当たり前、との理解がある。9月に病院に戻ると、患者さん達も「きれいに日焼けしたね。バカンスをしっかり楽しめて良かったね」と明るく会話をしてくれるそうだ。
「私自身もフランスで働くうち、バカンスが仕事に必要なメリハリと考えるようになりました。今では春先あたりから、夏を楽しみに働くようになっています。日本で働いていた経験を振り返ると、担当医制は、医師個人への負担がどうしても大きくなってしまうと感じます。業務量的にも、患者さんとの精神的な関係や責任面でも。担当医制は患者さんと医師の信頼関係が密に築けますが、その関係が深くなりすぎる危険もあります」

■「日勤専門」と「夜勤専門」がある病院も
フランスの看護師の働き方について話してくれたのは、私立の総合病院で循環器疾患の集中治療室を担当するサトミさんだ。日本で看護師資格を取り、公立病院に6年勤めたのちに渡仏。フランスで働いて8年になる。新型コロナ禍の2020年は看護師招集があり休みなしだったが、今はコロナ禍前と同じリズムで働けるようになった。無期限正規雇用で役職はなく、年間で労働時間を調整する契約のもと、週35時間労働で働いている。
「私の勤務先では看護師に『日勤専門』と『夜勤専門』の2種類の働き方があり、私は前者。勤務時間は朝8時から20時までで、シフトは2週間単位で組まれます。1週目は月・火・金・土・日曜日の週5日勤務、水木休みの週60時間労働。2週目は水木連勤の週2日勤務・24時間労働です。年次休暇は法定の5週間、加えて1カ月に2日半の「労働時間調整のための休暇」と、年3日の追加有休があります。休みが多いですよね」
1年間の勤務日数を数えてみたら、120日もなかったそうだ。が、それで良いとサトミさんは考えている。看護師は長時間連続の肉体労働で、命を預かる仕事をしているから。この休みの長さは、特殊な仕事の対価であると。
■職務と責任の範囲が明確に定められている
「そのように考えて仕事ができるのは、この国では看護師の職務と責任の範囲が明確に定められているからだと思います。フランスの医療体制は分業制で、看護師の仕事は『看護』です。患者さんを一番近くで継続して見ていますが、診察や治療、検査は医師や技師の担当ですから、手を出しません。そこは分業ですし、契約の際の『職務表』にもそう書かれています」
その表には、「これ以外はしない」という、看護師の仕事の範囲が定められている。範囲外の業務は看護師の知識や職能では責任が持てないので、してはならないのだ。これは日本の看護師の働き方と、大きく異なる点だとサトミさんは指摘する。
「私の日本の看護師時代は仕事の範囲がここまで明確ではなく、看護師の業務ではないと感じる仕事も、ボランティア精神でやることが多くありました」
フランスでは、看護師と患者の配置基準も厳格だ。「これ以上の数を担当しては患者を危険に晒すもの」として、絶対厳守される。サトミさんの部署では、看護師1人につき患者4名が最大数。病床自体は最大18床設置できるが、今は看護師が3人なので、12床しか稼働していない。
■バックアップの看護師を送り込む「プール部門」
「私立の医療機関なので黒字化は重要ですが、医師も師長も、配置基準を破ることはしません。危険ですから! もし急な病欠などで看護師が休んだ場合は、院内の人員管理部の『プール』部門から、バックアップの看護師が送られてきます」
このプール部門とは、幅広い診療科を担当できる職能豊かな看護師集団で、バックアップのためにある。いわば院内の看護師派遣部署だ。人員不足の管理職がヘルプを出すと翌日には心強い助っ人を送ってくれるシステムで、日本に是非知られてほしいとサトミさんは考えている。
職務範囲を明確に定めて遵守する環境で、フランスの看護師たちは年間5週間の有給休暇を完全に消化している。その調整はかなり前倒して進め、9月の段階で翌年3月の休暇調整をするそうだ。

「長期休暇は同僚達とすり合わせて師長に希望を出し、休暇開始の2カ月前には師長から決定の連絡が来ます。学校の休みの期間は子持ち世帯の休暇が優先になりますが、私の周囲はそれで問題なくいっていますね。私は旅行が生きがいで、旅費の高い学校休みの期間は避けて計画したい。なので子持ちの同僚がいると、お互い様でちょうど良いです」
■休暇取得のための調整は「肩代わりしてはいけない業務」
同僚全員が同じ時期に休暇希望を出して誰も譲らない場合、師長は誰かの予定を変えさせることはなく、代理要員を外部の派遣会社に手配する。その気持ちをありがたく受け取っても、「悪いな」とは感じないのがフランスの看護師たちだ。
「休みは私達の権利ですし、それを行使させるのは管理職の仕事。休暇取得のための調整は、非管理職の私達が肩代わりしてはいけない業務です。私達には代替要員を手配する権限もありませんから」
看護師がバカンスを取ることを悪く思う患者さんには、フランスでは会ったことがない、とサトミさん。むしろ、「しっかり休んできてね」と送り出してくれる。看護師が休養できないと、その余波は自分達に返ってくると知っているからだろう。

「フランスの非管理職の看護師は、決してお給料は良くないです。ですが年間の勤務日数がこれだけ少ないですから、総合的に見たらこんなものかと思います。医療従事者には休みが必要ですし、日勤と夜勤でワークシェアをしていると理解しています」
■医療従事者の健康に配慮しないことは「患者を危険に晒す」
以上見てきたように、フランスでは日本と異なる職業観や働き方で、医師・看護師の「休める働き方」を確保している。しかしこの国でも、医療福祉分野では常に人手不足が懸念されている。それでも休暇の取得が損なわれないのは、「休暇を取らせるのは雇用主の義務」と労働法で定められ、不履行には罰則が設定されているためだ。
「人が足りないから休めない」ではなく、「人が足りなくても休まねばならない」。そしてそのために、仕事のオーガナイズを変えるのが、フランスのやり方と言える。
その背景には、医療従事者に関して「フランスにあって、日本にはない」社会通念が存在する。医療従事者の労務管理を怠りその健康に配慮しないことは、医療の受益者である患者を「危険に晒す行為」に繫がる、との認識だ。
この「危険に晒す行為」は刑法でも定められていて、雇用主には労働法に加え、この点での違反もあり得る。これは保育士や介護士など、社会福祉職にも共通している。保育園のように利用者の生活拠点が家庭にある施設では、8月の1カ月間など決まった期間に施設全体を閉めてしまい、従業員全員に同時に休みを取得させている。
■「年休取得日数」と「離職率」には相関関係がある
医療従事者の働き方を、その健康や社会的な影響を含めて考えることは、日本社会でも当然、重要だ。医療機関の働き方改革を手掛けてきた特定社会保険労務士・河北隆氏は言う。
「計画的・協力的・必要的に休むことは、日本の医療現場で働く人々のメンタルヘルスの維持向上や一人当たりの生産性の向上に欠かせません。また厚労省などの各種調査からは、『年休の取得日数』と『離職率』との間に強い相関関係があることが分かっています。『休める働き方』の導入と定着は、人材の確保・定着にも効能があるのです」
現在では日本各地で、フランスの形に近い複数主治医制やチーム診療制を実践している医療機関が増えつつあるという。また新たな日勤・夜勤の分業法を導入して、医師の勤務時間の短縮に成功している病院もある。
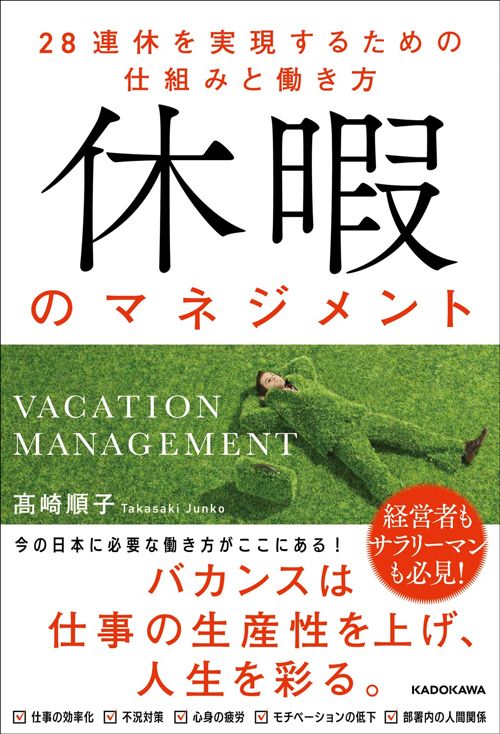
実践方法がなんであっても、働き方改革に欠かせないのは、「やる」という固い決意だ。その決意が形になるには、「医療従事者も、休みの必要な人間のひとり」と認めることが不可欠である。そしてその認識は医療業界だけではなく、その技術と知見を享受する患者側・一般社会の側にも、同様に求められる。
これからの日本は、少子高齢化で医療のリソースがますます限られていくと見込まれている。医師の不足や偏在により、これまで受けられた診察や治療が受けにくくなる現実は、すぐそこだ。
今こそ社会全体で意識改革に取り組み、医療の高度人材が健康に働きつづけられる、持続性の高い環境を作っていかねばならない。「医師の働き方改革」は、私たち一般市民の生活に直結する課題なのだから。
*本稿は『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』より要約抜粋しました。本書では医療従事者やサラリーマンの他、個人商店や中小企業メーカー、町工場、農業従事者など、多業種の「休める働き方」を紹介しています。
----------
ライター
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)などがある。
----------
(ライター 髙崎 順子)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
TOPPAN、医療従事者の説明業務支援サービス「DICTOR(R)」提供開始
PR TIMES / 2024年7月18日 13時40分
-
マイナビ看護師、「看護師白書2023年度版」を発表
PR TIMES / 2024年7月8日 14時45分
-
「ブラックペアン2」キャスト・役柄一覧【2024年夏クール・TBS系日曜劇場】
モデルプレス / 2024年7月7日 10時0分
-
「女帝・小池百合子知事はまた公約不履行」突っ込まれそうな"無痛分娩の助成"…病院の受け入れが無理筋なワケ
プレジデントオンライン / 2024年7月5日 10時15分
-
麻酔科医の働き方改革 ~特定行為研修修了看護師を麻酔科医が直接マネジメント~
PR TIMES / 2024年7月2日 1時40分
ランキング
-
1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分
-
2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収
ロイター / 2024年7月18日 8時34分
-
3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り
共同通信 / 2024年7月18日 11時58分
-
4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵
プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分
-
5電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で
共同通信 / 2024年7月18日 21時35分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











