日本企業が「80年代の栄光」を取り戻すにはなにが必要か…露骨な「日本叩き」の欧州や中国に対抗するべきこと
プレジデントオンライン / 2024年5月28日 8時15分
※本稿は、長内厚『半導体逆転戦略』(日本経済新聞出版)の一部を再編集したものです。
■過去の成功体験と残念な歴史
日本企業あるいは日本社会が、これまでなぜ技術でトップを取ることにこだわり続けてきたのか。半導体やエレクトロニクス産業をなぜビジネスとして捉えきれなかったのか。そこには、エレクトロニクス全般に言える過去の成功体験と、日本の半導体が歩んできた残念な歴史が関係していると考えます。
さらに元をたどると、学校教育の課程、カリキュラムもしくはシステムに原因が求められるかもしれません。日本では、高校の段階ですでに理系と文系に分けたカリキュラムが取られることが多くあります。そしてそのまま理系と文系に分かれて大学の学部に進み、特別な事情がなければそのまま卒業します。
理系と文系に分けられることを問題視しているわけではなく、理系学部では経営や経済を学ぶこともないだろうし、文系学部で技術などを学ぶことも一切ない、ということを言いたいのです。いわば、ガチガチの理系頭、文系頭を持って今度は会社に入ることになり、会社でも技術系と事務系とに分けられます。
■日本のメーカーが抱える「最大の問題」
こう見てくると、10代後半に選択したならば、理系頭と文系頭のままで交わらずに進んでいくのです。もちろん、個人で研鑽を積む人もいるでしょうが、そのような人は例外の部類に入ると考えられます。
そうした教育を受けてきた果てには、技術は得意だがビジネスがさっぱりわからないエンジニアや、技術には疎いがビジネスのコツはつかんでいる営業社員など、社内は二極化と言えるほどの分化が起きてしまうのではないかと思われるのです。
したがって製造業では、技術戦略とビジネスの戦略が分断されたまま事業が行われるケースが増えるのではないかと考えるのです。
前述したイノベーションのフレームワークである、価値創造と価値獲得を思い出してください。価値創造は、新たな技術や製品をつくるプロセスです。これは日本企業では理系のエンジニアが担います。一方で、価値獲得のプロセスは、マーケティングや営業など文系のスタッフが担当します。社内で理系と文系が二分しているなかで、価値創造と価値獲得が統合的にマネジメントできない、これが日本のメーカーが抱える最大の問題と言えます。
■技術で勝ってビジネスで負ける
話を元に戻して、成功体験と残念な歴史について述べます。
通信産業において、iモードが最初に出た頃の第2世代の携帯電話に、NTTドコモではmova(ムーバ)と言っていた時代ですが、搭載されていたのはPDCという技術でした。このPDCという技術は非常に優れたものでしたが、世界的にはGSMという同じ第2世代の技術に負けて採用してもらえませんでした。
電話は、相手とつながって初めて役に立つ機器ですから、いかに性能が良くてもつながらなければ商品価値はありません。これは「ネットワーク効果」あるいは「ネットワーク外部性の便益」というもので、単体の商品自体がどれほど優秀でもネットワークの規模が小さければ商品価値がない、ということです。その意味では、GSMはPDCと比べて技術的には劣るけれども世界中で使えるからこちらを選ぶという話になります。
これは、かつて日本で起きたベータ対VHSのビデオ戦争で、ソニーのベータ方式が技術的にはVHSより優ると言われても、VHSを持つ人が多いという理由で勝負の軍配はVHSに上がったのと同じ現象なのです。技術的に優れているだけでは、ビジネスとして成立しないということです。
■国際会議で議論に入り込めなかった理由
第2世代で負けた日本は、次の第3世代携帯では世界が認める技術を握れば世界のビジネスで主導権を取れるのではないかと思ったわけです。そして、第3世代携帯の国際標準をつくるための国際会議に乗り込んだのですが、日本企業は、技術の標準をつくる場だからとエンジニアばかりをメンバーに選びました。しかし会議に出席した日本の出席者は、欧米メーカーの出席者を見て、エンジニアだけではなくマーケティングや経営戦略の担当者も同席させていることに気がついたのです。
標準規格を話し合う場でも、日本の参加者はエンジニアばかりですので、技術的な妥当性についての議論では発言しますが、欧米の参加者は、エンジニアよりもむしろマーケティングや経営戦略担当のメンバーの発言のほうが強く、論点となっている規格が決まった場合、自分たちにどのようなメリット・デメリットがあるのか、といったビジネス面での議論で盛り上がっているのです。日本は純粋な技術論以外の知識には乏しいメンバーですから、そうした議論に入り込むことができなかったと言います。

この場面を見ても、「技術さえよければ顧客はついてきてくれる」という日本の製造業の純粋さ、と言うよりも甘えが見て取れます。
■日本が米国に勝った半導体製造技術
経営学では有名なレベッカ・ヘンダーソンとキム・クラークという学者が1990年に発表した「アーキテクチュラル・イノベーション(Architectural Innovation)」という論文に出てくる半導体露光装置メーカーの話を紹介しましょう。
半導体製造では、1970年代頃までは米国がトップを走っており、半導体露光装置に関しても米国企業のキャスパーがトップを走っていました。そのキャスパーに挑むように、日本のキヤノンが新しい露光装置をつくって提供するようになるのです。
露光装置とは、半導体のウエハーと呼ばれるシリコンの基板の上に、密接して回路のパターンを描く装置のことです。レンズを通して光を当て、基板に回路パターンを焼き付けるわけですから基本的には写真と同様の技術となり、登場する企業は、日本ではキヤノンやニコンといったカメラメーカーになります。
米国のキャスパーの露光方法は、直接基板に露光機械を押し当ててパターンを描く密着型露光というものでした。それに対してキヤノンは、非接触型露光という機械と基板を直接接しないよう、わずかに浮かせて回路パターンを焼き付ける方法を取りました。
機械と基板が接するか接しないか以外、部品レベルでの相違はまったくありません。使われている要素部品はまったく一緒ですが、この、機械を基板からわずかに浮かせて、それでいてズレないようにパターンを転写する技術には、大変な位置決め調整のノウハウが必要となるのです。個々の技術ではなく、部品と部品を組み合わせるアーキテクチャの知識と呼ばれる調整技術が必要な領域のものです。それをキヤノンが成し遂げ、非接触型露光による新しい半導体露光装置をつくったのです。

■1980年代は「日本の時代」になったが…
基板に接しないようにすると何がよいか。密着させてしまえば、機械と基板の間に埃などが入ってしまった場合、基板に傷がついて不良品になってしまうわけです。非接触型露光では、ウエハーに傷をつけるリスクが少なく不良率も下がって歩留まりも上がる、ということになってキヤノンの露光装置のほうが性能が良いとなりました。
これを機に、急速に日本メーカーは半導体の露光装置の分野で存在感を増し、これに合わせて日本のNEC、三菱電機、日立といった会社の半導体製造も増えていくのです。
この時期は、半導体が強い=半導体メーカーが強い+半導体製造装置メーカーも強いという垂直統合の時代でした。これは日本も米国も変わらず言えることでした。半導体の製造装置でキヤノンやニコンが存在感を増していった結果、米国のキャスパーは結果的につぶれてしまい、1980年代は日本の時代になりました。しかしその日本も、日米半導体協定を境に下降線をたどり、各国に後れを取る状態になっています。
現在マクロ的に見て、日本がトップでいる市場は、シリコンウエハーや一部の部材しか残っていません。エレクトロニクス産業では「完成品がだめなら部材や設備で生き残る」と部材や設備のビジネスに活路を求める風潮がありますが、こうした中間材メーカーも最終消費財メーカーとのつながりや近接性が重要かもしれません。
■欧州のEV対トヨタ自動車の全方位戦略
地球温暖化防止の風を受けて、欧州、中国を中心に自動車業界はいまEVが主流になろうとしています。トヨタ自動車は、もちろんEVも生産していますが、ハイブリッド車や燃料電池車、水素エンジン車などの開発も行う全方位戦略を取っています。トヨタ自動車の市場の見方を推察すると、以下のようだと筆者は考えます。
「グローバルという言葉どおりに世界を見渡した時、ヨーロッパのような脱石油が進んでいる国々にはEVが受け入られやすい環境が整っているが、日本や米国の中西部もそうだが他にも火力に頼っている新興国もあって、これらの国・地域では脱炭素という意味ではEVである必要がないし、そもそもEVに必要な電力供給のインフラが整っていない地域も多くある。特に世界でもっとも自動車を販売するトヨタは国内だけでなく、北米、中南米、欧州、アジアなどさまざまな地域でまんべんなく自動車を販売している。2位のフォルクスワーゲンは、売り上げの50%余りが中国で、EVを積極的に推進する中国やヨーロッパの地域のビジネスがほとんどなのでEVに特化する戦略を考えることもできるが、電力インフラ事情の悪い市場も多く抱えるトヨタは同じようなわけにはいかない――」

■今日のEVは必ずしも環境に良くない
また、ヨーロッパの国々は、標準や規格などのルールをつくる際、技術的な妥当性を主眼にするのではなく、自国のメーカーや企業にいかに有利に働くかという観点で発言をします。EVに関する議論でも、EVは欧州メーカーにとってメリットがあるのでEV寄りの発言をし、流れをつくってきました。
中国も同じです。中国は国産の自動車産業を世界レベルに引き上げたいと産業育成に注力をしてきました。しかし、従来の内燃機関の技術では日米欧に対抗できません。そのため、EVという根本的に異なる新技術を用いることでゲームチェンジを図りたいのです。ですからヨーロッパにしても中国にしても、EVを環境適応技術として推しているのは自国の産業育成や保護のためと言っても過言ではありません。
しかし、今日のEVは必ずしも環境に良いとは言えません。発電がクリーンエネルギーでなければ意味がありませんから、現在のところ、消耗品であるバッテリーの回収、リサイクル、処分などのめどが立っておらず、将来大量の廃棄バッテリーが生じた時の環境負荷を考えると、一概にEVが環境に良いとは言えないのです。
トヨタが全方位戦略を取る理由もここにあります。EVだけがカーボンニュートラルの最適解ではない、という技術的に正しい主張をしているだけなのです。
■なぜトヨタの正論が受け入れられないのか
にもかかわらず、日本は菅政権の頃からEVだけがあたかもカーボンニュートラルに資する技術であるかのように、EV推しをし始めています。トヨタ自動車の戦略も、次第にその流れの圧力に押されてきて、全方位を全面的には打ち出しにくくなってきた、というのが現状です。
自国政府も味方をしてくれないのであれば、トヨタがいくら正論を唱えていてもそれがなかなか社会に受け入れられないのはやむを得ないでしょう。
技術者が技術的に正しいことを言うだけではビジネスにならない、というのはメーカーの宿命ではあります。日本の技術者の多くは理系で技術論だけを学んできているので、ビジネス的見地・感覚を身につける訓練は疎かになってきた、という歴史があります。これが1つの大きな問題点なのです。
■自動車産業と半導体産業の「互恵的成長」
また、先ほども述べたように、今日の自動車には多数のECU(車載コンピュータ)が搭載され、かつてとは比較にならないほど、自動車開発に半導体が欠かせなくなりました。半導体産業にとっても自動車はかつて以上に重要な市場になってきています。
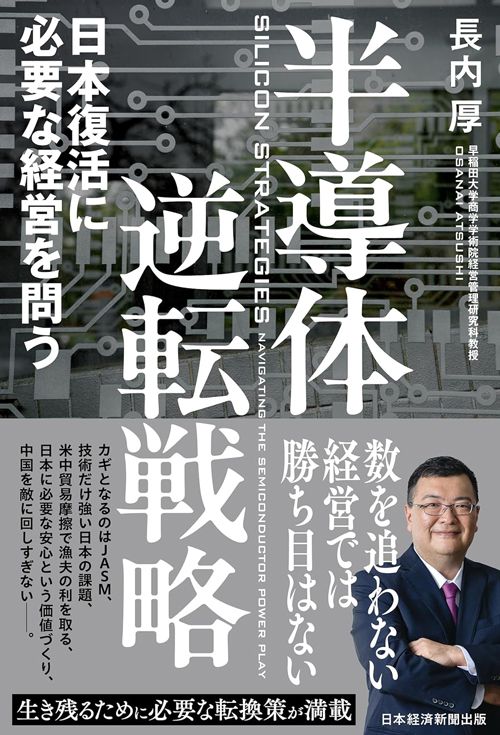
一方、日本の自動車産業のライバルであるヨーロッパの自動車産業は、伝統的に日本製の自動車部品をできるだけ使わないという風潮があります。敵に塩を送りたくないからです。ヨーロッパ内で調達できるものはヨーロッパ内で、それがかなわない電装部品は日本ではなく韓国から、といった具合です。
おそらく半導体製品についても同様な動きになるでしょう。トヨタやホンダなど日本の自動車メーカー各社は、日本で先端半導体の研究開発を行うための共同研究組織、自動車用先端SoC技術研究組合を設立しました(※1)。日本国内に半導体の製造企業が増えれば、必然的にこうした自動車産業との協業が増えるでしょうし、日本の自動車産業と半導体産業が互恵的に成長することも可能です。日本国内の半導体産業を育てることは、おのずと日本の自動車産業など他産業を育てることにもつながるのです。
(※1)https://www.yomiuri.co.jp/economy/20231226-OYT1T50291/
----------
早稲田大学大学院 教授
1972年東京都生まれ。京都大学経済学部経済学科卒業後、ソニー入社。映像関連の商品企画、技術企画、新規事業部門の商品戦略担当などを務めた。2007年京都大学で博士(経済学)取得後、研究者に転身。同年、神戸大学経済経営研究所准教授着任。早稲田大学商学学術院准教授などを経て、2016年より現職。2016年から17年までハーバード大学客員研究員。ベトナム外国貿易大学ハノイ校客員教授、総務省情報通信審議会専門委員などを務める。主な著書に『読まずにわかる! 「経営学」イラスト講義』(宝島社)、『イノベーション・マネジメント』(中央経済社・共著)など。YouTubeチャンネル「長内の部屋」でニュースやビジネスに関する動画を配信している。
----------
(早稲田大学大学院 教授 長内 厚)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「10年落ちの半導体を作る」というJASM熊本工場は素晴らしい…日本企業の「最新技術なら勝てる」という勘違い【2024上半期BEST5】
プレジデントオンライン / 2024年8月18日 17時15分
-
韓国企業が注視…日本の「コスパEUV」装備、ASMLの独占構図を崩せるか
KOREA WAVE / 2024年8月14日 11時0分
-
「日産・ホンダ」陣営に三菱も参画、ホンダ社長は資本提携「別に否定せず」[新聞ウォッチ]
レスポンス / 2024年8月2日 8時17分
-
トヨタとホンダ「遅れたEV挽回策」の決定的な違い テスラ失速でも、EVシフトの大波は止まらない
東洋経済オンライン / 2024年7月31日 9時0分
-
フロスト&サリバン、世界の機械試験・計測業界の現状を調査、モジュール式試験装置の変革課題と対応を公表
@Press / 2024年7月30日 9時0分
ランキング
-
1JT、米たばこ4位のベクターを買収 総額約3780億円
ロイター / 2024年8月21日 19時35分
-
2タンス預金が違法になるのはどんな時? 金額が大きいだけなら問題ないの?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月21日 2時0分
-
3ふるさと納税・初の1兆円突破も…“ポイント付与禁止”の波紋 専門家「どう考えても愚策」【Bizスクエア】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年8月21日 6時0分
-
4為替相場 22日(日本時間 8時)
共同通信 / 2024年8月22日 8時0分
-
5スシロー、北京に1号店 原発処理水の逆風も長蛇の列
共同通信 / 2024年8月21日 18時9分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











