「タワマンバブル崩壊」はまもなくやってくる?…資産価値が下がり、管理費は上がる「売れないタワマン」の特徴
プレジデントオンライン / 2024年6月3日 16時15分
※本稿は、長嶋修『マンションバブル41の落とし穴』(小学館新書)の一部を再編集したものです。
■そもそも「いいマンション」とはなにか?
マンションの管理力を測るうえで、さくら事務所が重視しているのは次の4つのポイントです。
①組合運営力
②メンテナンス&資金力
③コミュニティ&住み心地力
④防災力
さくら事務所が管理力の高いマンションをセレクトしているマンション取引サイト「BORDER5」でも、これらの指標でマンションの管理力を数値化しています。
「組合運営力」とは管理組合がきちんと組織・運営されているかを測る指標です。管理組合総会の出席率が8割以上などと高く、理事会の議事録が管理組合員に速やかに情報共有されており、管理費の滞納が少ない、などの条件を満たしていれば、組合運営力は高いと言えるでしょう。
「メンテナンス&資金力」とは、長期的な目線で管理組合の会計が健全化されており、必要な修繕とその資金について適切な計画が立てられているかをチェックする指標です。
妥当性の高い長期修繕計画が定められており、計画的に積立金が徴収されていることや、必要な法定点検が漏れなく実施されていること、相見積もりを取って修繕工事を発注しているなどの取り組みができているマンションは、メンテナンス&資金力がハイレベルです。
■実は「住民同士のつながり」が重要である理由
「コミュニティ&住み心地力」の高さも大切です。賑わいを生むコミュニティの形成は、マンションの管理力を高めるうえでの基盤となります。というと餅つきやクリスマス会などイベントの開催を連想するかもしれませんが、管理力につながるのはイベントの有無ではなく、住民同士がコミュニティ意識を持ち、横のつながりを持っているかどうかです。
競争力が高く、高値で売れていくマンションと、そうでないマンションとを比べると、前者のほうが住民同士の横のつながりが強い傾向にあります。ほかの住民とのつながりができやすいのは管理組合の役員が回って来たときですが、そこで管理の重要性に目覚めて、「みんなでマンションを良くしていこう」と考える住民が増えていくと、そのマンションの競争力はおのずと上がっていきます。
このようなマンションでは、管理組合の役員の任期が終わった人たちも、大規模修繕委員会や防災委員会、イベント委員などにオブザーバーとして加わり、役員任せにせず、大勢で積極的にマンション管理にかかわっていくような体制がとられています。
■「人付き合いが必要ない」という認識は誤り
役員の任期が一巡し、ほとんどすべての住民に役員経験があり、マンション管理に前向きなマンションは、管理力が非常に高まっている状態です。それは、新築にはない中古マンションならではの価値と言えるでしょう。
一方で、横のつながりを持って他人とかかわることに抵抗感を持つ人もいるかもしれません。よく「人付き合いが苦手だからマンションを選んだ」と言う人がいますが、そもそもこの認識が誤りです。
マンションは購入した途端、強制的に管理組合のメンバーに加えられ、一定の頻度で管理組合の理事会役員も務めなければならず、戸建住宅で生活するよりも断然人との関わりが多くなります。賃貸なら役員を務める必要もないので、無関心を貫けますが、マンションを買って区分所有者になったなら、人付き合いを避けては通れません。
■管理費がドンドン上がる“売れないマンション”に
仕方なく理事会の役員を務め、任期が終わると「後はもう関係ない」とばかりに、管理組合総会や防災訓練などのイベントにも参加しなくなるような住民ばかりだと、そのマンションは横のつながりが希薄になります。
一見、気楽で良さそうに見えるかもしれませんが、こうした状況だと、管理費の値上げや長期修繕計画の見直しなど、今多くのマンションで問題になっている重要なテーマに関しても、活発な議論が望めないでしょう。
結果として、管理はすべて管理会社にお任せ状態になりがち。となると、頻繁に管理費が値上げされたり、本来不要な修繕工事が行われたりするかもしれず、異常に高コスト体質の住み心地の悪いマンションになってしまうリスクがあります。この状態ではもちろん管理力は高いとは言えず、市場における競争力は低下します。
中古マンションを買うのであれば、賑わいのあるコミュニティかどうかに注目すべきでしょう。イベントが盛況だったり、管理組合総会の出席率が高かったりすれば、ある程度横のつながりが保たれたマンションだと判断することができそうです。
■災害リスクの高いエリアは資産価値が下がる?
冒頭でマンションの管理力を測るポイントとして「組合運営力」「メンテナンス&資金力」「コミュニティ&住み心地力」について解説しましたが、ここからは4つ目の「防災力」について詳しく掘り下げていきましょう。
2024年の元日に発生した能登半島地震の大きな被害は記憶に新しいところですが、災害大国・日本では地震や津波、高潮、台風・暴風雨、洪水、土砂災害といった自然災害が後を絶ちません。

近年は気候変動の影響で、災害の規模は激甚化しており、これから住まいを選ぶのであれば、被害を最小限にとどめられそうなエリアを探したり、マンションであれば防災対策を入念に行っているところを選ぶ視点が不可欠となります。
近い将来には、災害リスクの高いエリアにある不動産の鑑定評価が下がる可能性もあります。これまでの日本では、災害リスクの高低が不動産鑑定評価に反映されてきませんでした。しかし、実際に災害で被害を受ければ確実に資産価値は下がるため、あらかじめリスクを反映して評価をしておかなければ合理的とは言えません。
■災害リスクの高低に応じて火災保険料も変動する
ちなみに2024年、これまで全国一律だった火災保険の水災部分の保険料が、エリアごとの災害リスクの高低に応じて変動する予定です。たとえば、低地で河川の氾濫の影響を受けやすいエリアは保険料が高く、そうでないエリアでは安くなり、もっとも高いところでは低いところの1.5倍程度の保険料になるとされています。
今後は、不動産鑑定評価も保険と同じように、災害リスクの高低で評価を変動させる動きが出てくるでしょう。すでに国土交通省も「実際に災害が起こったとき、その不動産にどの程度の損失が見込まれるか」などを計算し、不動産鑑定評価に適切に反映すべきとの見解を示しています。
資産価値が目減りするかもしれず、さらに保険料まで高くつくケースがあることを思えば、災害リスクの高いエリアの不動産をわざわざ選ぶのは得策ではありません。
エリアごとの災害リスクを知るためには「ハザードマップ」が役に立ちます。ハザードマップは各自治体が作成するもので、洪水ハザードマップのほか、都市の排水能力を超える水量が下水道に流れ込み、下水が逆流して起こる内水氾濫や、高潮、津波、土砂災害の危険エリアを表示するもの、火山の噴火による影響が及ぶエリアや、ため池の決壊時の浸水エリアを表示するものなど、さまざまな種類があります。
■川崎市で起きた「タワマン浸水」は今後も起こりえる
自治体によって提供しているハザードマップの種類には差がありますが、最近は内水氾濫による被害が非常に増えているため、内水ハザードマップがある場合はよく見ておいたほうがいいでしょう。
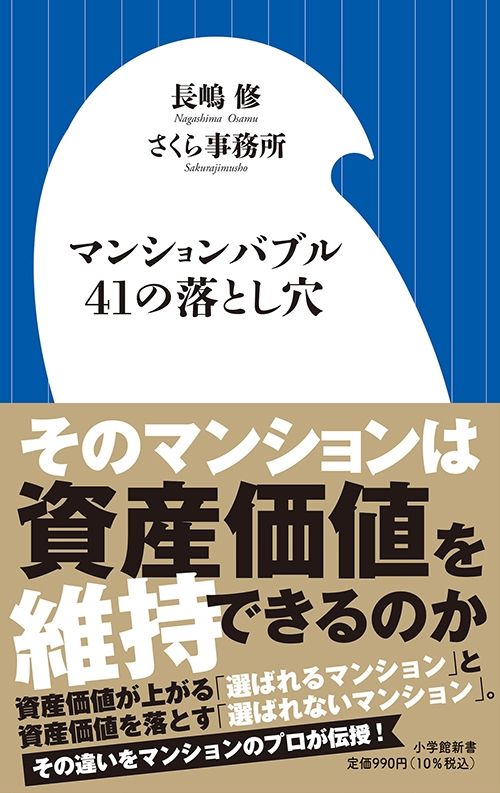
近年、内水氾濫でもっとも話題になったのは、2019年の令和元年東日本台風で、神奈川県川崎市にあるオール電化のタワマンが2週間以上も停電した事例です。このタワマンでは地下にあった電気室(電気設備が格納された部屋)が内水氾濫によって浸水したため、停電が起こってしまいました。
内水氾濫の際は真っ先に地下から浸水しますが、タワマンに限らず電気室はマンションの地下に設けられている場合が多いため、停電したり、地下の駐車場が浸水して車が故障したりする被害は、実は少なからず起きています。
そのため、中古のマンションを買う際には、そうした被害の履歴がないかどうかも必ずチェックしましょう。買う前に近所の人に話を聞いたり、地元の不動産会社に尋ねてみたりするのもおすすめです。
ちなみに先ほど例に挙げたタワマンは、地下から地上へと電気室を移す工事を行ったそうです。一度は被害を受けたものの、それで防災意識を高めて、適切な対策を済ませているマンションに注目するのも手でしょう。
■買う前だけでなく、買った後も年1回の確認を
なお、ハザードマップはこまめに更新されるものです。昨今の気候変動により各種災害の危険エリアは徐々に広がっているので、物件を買う前だけでなく、買った後も年に1回くらいは最新のハザードマップを確認してください。
買った物件が数年後にハザードマップで危険エリアにかかってしまうケースはよくあります。いざというときにどうやって逃げるかなど、心づもりをしておくべきでしょう。
もちろんマンションを選ぶときにも、ハザードマップでリスクを警告されている災害に対し、どのように備えているかを知る必要があるでしょう。管理組合として何一つ防災対策をしていないマンションも多いですが、これから住むなら防災意識の高い物件を選びたいものです。
----------
不動産コンサルタント
さくら事務所会長。1967年生まれ。業界初の個人向け不動産コンサルティング会社「さくら事務所」を設立し、現在に至る。著書・メディア出演多数。YouTubeでも情報発信中。
----------
(不動産コンサルタント 長嶋 修)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
金沢市に、日頃の備えや災害時の迅速・効率的な避難行動を一体的に支援する「水害ハザードマップアプリ」を納入
PR TIMES / 2024年6月27日 16時15分
-
マンション組合総会「モンスター住民」の対処法 円滑なマンション・コミュニティのあり方とは
東洋経済オンライン / 2024年6月21日 11時30分
-
【ソナエル】ハザードマップの浸水想定は「ベランダにいても溺れる」毎年のように浸水 玄関にブルーシートと土のうを置く家 それぞれの場所に合った避難を 福岡
FBS福岡放送ニュース / 2024年6月20日 19時41分
-
記録的大雨から間もなく11か月 治水対策の取り組みを紹介 災害への備え呼びかけ
ABS秋田放送 / 2024年6月10日 19時19分
-
内水氾濫の被害を防げ 3年前の住宅浸水被害を教訓に 佐賀県
RKB毎日放送 / 2024年6月10日 18時50分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












