「夢のマイホーム契約」が最悪の体験に…住宅メーカーから「支離滅裂な240万円の違約金」を請求された結果
プレジデントオンライン / 2024年6月4日 9時15分
■「ネットの情報」を鵜呑みにしてはいけない
住宅購入は一生に一度の大きな買い物と言われています。中でも一戸建てに住みたいという希望は強く、建売住宅ではなく、間取りや設備を自由に選択できる注文住宅を建てたいという人が多いものです。
注文住宅で理想のマイホームをと思いきや、大きなトラブルになるケースも散見されます。特に多いのが解約をめぐるトラブルです。工事が完成するまでの間、注文者はいつでも解約できる立ち位置にいますが、解約までに要した実費費用を負担することが条件となります。この解約に関してインターネットで検索すると誤った情報が掲載されていたり、素人の顧客に対して明らかに不当な金額を請求する担当者もいたりするので、注意が必要です。
今回は、私がサポートを担当した事例を紹介しながら、注文住宅の“思わぬ落とし穴”について解説します。
■優秀な営業担当者かどうかは運次第
注文住宅を建てる際には住宅メーカーや工務店に相談をするわけですが、個々の顧客に営業担当者が専属でついて間取りや見積もり、住宅ローンの手続きまで併走することになります。
そのため、いかに優秀な営業担当者に出会えるかが、理想の住まいづくりに近づく第一歩なのですが、現実は優秀な営業担当者に出会える可能性は低く、いわゆる「営業ガチャ」に左右されてしまうのです。
近年の建築価格高騰により、大手の住宅メーカーに依頼すると、延床面積にもよりますが請負契約金額が5000万円を上回る場合が多く、担当営業の対応が悪いと金額的には割に合わない現実が待っています。
特に、注文住宅を受注する営業担当者は、間取りや各仕様などの建築に関する知識、契約ごとや登記、将来の相続などの法律に関する知識、そして住宅ローンや保険、税金などのファイナンスの知識を兼ね備えていないといけないものです。
しかし、現状ではトータルの専門知識を豊富に持つ営業担当者は減っています。例えば、契約までの間の商談は担当Aさん、契約後の詳細打ち合わせの担当はBさんというような流れになっている場合が多く、質問をしても答えが返ってくるまでに相当な時間がかかり、下手すると何の返答もないという事例もあります。
■「営業ガチャ」に失敗し、別の会社に変更
まずはこんな事例を紹介しましょう。
各住宅メーカーの良し悪しもよくわからないのでサポートしてほしいというご夫婦のFさんが相談に来ました。数社の話を聞いて最終的に2社に絞り込みをしました。2社とも誰もが知る有名住宅メーカーですが、A社のほうが設計やインテリアのセンスが上でした。
しかし、このA社の営業担当者はご夫婦の意見や希望に対して否定的で、自分が勧めるものを押し付けるという、常に上から目線の商談でした。設計変更や新たな提案をお願いしても「弊社とご契約いただけますか?」という発言が頻繫に出て、結局は設計変更を受けないなど、対応の悪さが目立ったのです。
Fさん夫婦は、営業担当者の変更も検討した上で、結果的にもう1社のB社にお願いすることにしました。B社の営業担当者はご夫婦の話を良く聞いてくれて、ご夫婦にとって話しやすい人でした。私もA社・B社との商談には必ず同席していましたが、請負契約金額が1億円を超える住まいをお願いするには、A社はふさわしくないという印象でした。
昨今では、「優秀な住宅メーカーの営業マンを紹介する」というようなビジネス広告も見かけますが、本当に優秀かどうかは何とも言えません。例えば、「優秀な営業マンです!」と紹介されても、顧客にとってはそうでない場合もあります。最終的には、相性の良い人が、その顧客にとって「優秀な営業担当者」となるのでしょう。
■「解約すると違約金がかかる」?
この事例は住宅メーカーと請負契約をしていなかったのですが、請負契約を締結した後に金銭のトラブルになるケースも多いものです。
今年4月初めにこんな相談がありました。
「住宅メーカーで注文住宅の契約をしましたが、解約をしたいと担当者に言ったら違約金がかかるので解約はやめたほうがいいと言われました。違約金は払わないといけないのでしょうか?
インターネットでも調べたのですが、違約金は契約金額の1割程度はかかるとかあって不安です」
相談者によれば、「注文住宅の契約解約にかかる違約金は、契約金額に対して約1割が目安で、契約金額が4000万円ならば違約金は400万円です」とあり、しかも「宅建業法で違約金と損害金の合計は契約金額の2割までと決められていますが、その金額よりも安価ですから安心です」という記述があったとのこと。
たしかに、そのように解説するウェブ記事もあるのですが、これは不正確です。
■注文住宅の契約と不動産の売買契約は違う
注文住宅の契約はいわゆる工事請負契約にあたるわけですが、不動産の売買契約と同じように捉えている人が多いのです。
例えば、不動産の売買契約では契約時に払ったお金を「手付金」と称し、この手付金を放棄すれば契約は解約できるという解約手付となっています。
ところが、工事請負契約では手付金という表現は少なく、単なる「契約金」と称しており、注文者から契約を解約する場合には、解約の時点でそれまでにかかった費用を請負者に賠償することで解約はできます。
また、不動産の売買契約では宅地建物取引業法の縛りが厳しく、違約の場合は売買代金の2割を上限に「違約金」として請求できます。しかし、請負契約の場合では違約金の上限が定められておらず、あくまでも損害を賠償することで契約を解約できるものとしています。
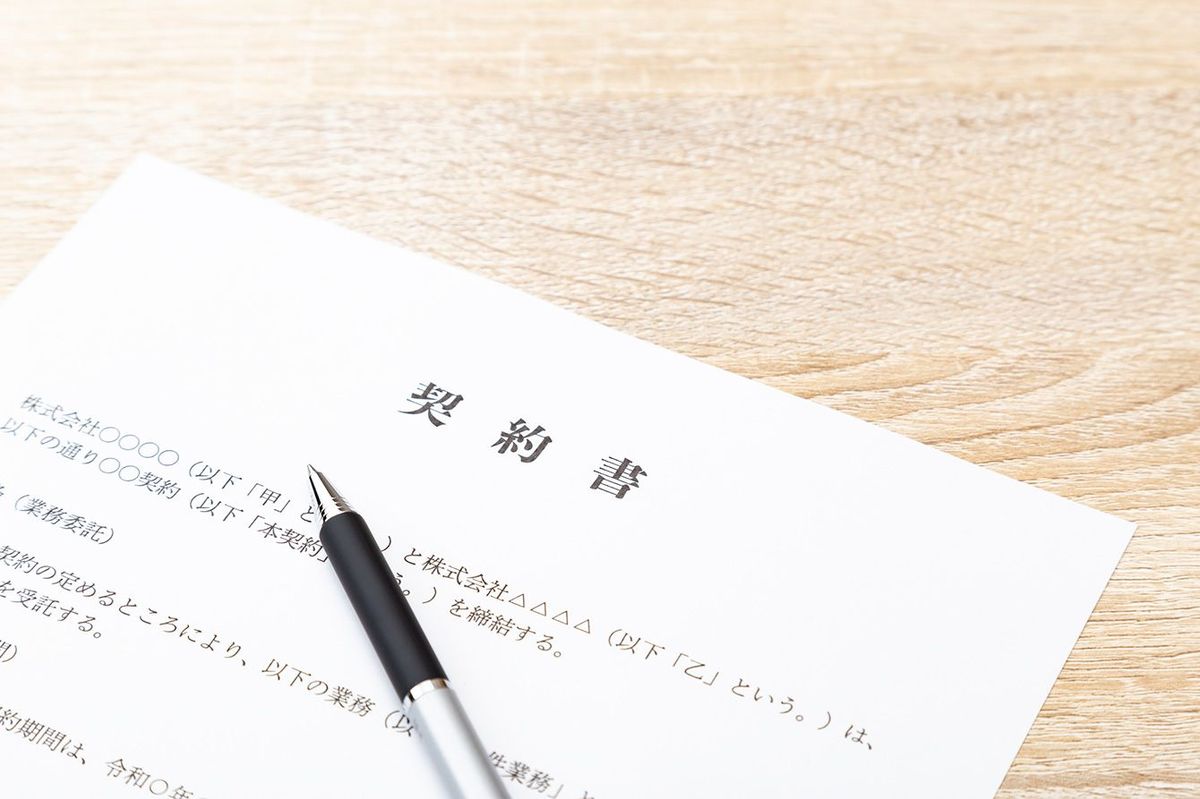
■「違約金は契約金の1割程度」はおかしい
ある住宅メーカーの工事請負契約の約款には、注文者が請負契約を解約する場合には次のように書かれています。
この約款内容は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と明記している、民法第641条(注文者による契約の解除)に準じたものです。
したがって、「契約金額の1割ぐらいが違約金としてかかる」というのはおかしいのです。
例えば、上記の契約金額が4000万円の請負契約を解約する場合、工事着手前であれば、それまでにかかった費用を実質精算して解約となります。注文者は、敷地調査や地盤調査、詳細設計、確認申請などにかかった費用を請負者に払って解約することが可能なわけです。
また、工事着手後に解約をする場合は、基礎工事や上棟にかかった材料費用と工賃を支払うことになります。当然、このタイミングで解約とあれば、契約金額の2割以上が請求されてもおかしくないわけで、先ほどの「2割上限」という縛りでは請負者側には割が合わないのです。
■住宅メーカーは解約金240万円を請求
ここからは私が注文住宅の解約をサポートしたAさんの事例をお話しましょう。
Aさんは大阪に本社がある住宅メーカーと2023年7月末付けで工事請負契約を結び、仮契約金1万円、手付金と称して100万円を支払いました。
しかし、担当者の杜撰な対応に不信感を抱き、同年11月に直接解約を申し出ました。担当者も非を認めていたのですんなり解約できるのかと思っていましたが、約款に記載された請負金額およそ2400万円の10%に当たる240万円を請求されました。
たしかに今回の事案では、契約書の約款に「解約の場合には違約金として請負代金の1割を支払う」旨の文言がありました。しかし、工事請負契約では、解約までに要した実費費用を負担すると法律で定められているので、この約款の文言には問題があり、効力はないと言えます。
「なぜこちら側がさらに請求されなければならないのか」と担当者へ返信したところ、翌12月に今度は担当者の上司から「信頼回復のため本契約の履行を続けたい」と回答がありました。話がかみ合わない上に、信頼回復のための具体的な案の記載がないため、再度、請求理由を求めました。
年が明けても返信は来ず、2024年1月初めに本社宛にメールを送り、ようやく社長が対応してくれることになりました。事情を話すと「契約時に入金した101万円の放棄で契約を白紙撤回する」とのことです。
■内容が分からない、支離滅裂な経費内訳
しかし、このメーカーと本契約を結ぶ前に仮測量を1回行い、本契約を結んでから打合せ2回、図面を1枚描いてもらっただけです。消費者契約法第9条1項の平均的損害額を超えているのではないかと問い合わせると、経費内訳のデータが社長から送られてきました。
現地調査費 50,000円
役所調査費 20,000円
プラン作成費(建築家の先生含む) 300,000円
移動費 30,000円
銀行事前審査代理費 100,000円
打合せ図面製作費 250,000円
確認申請費 500,000円
地盤調査 100,000円
合計 1,420,000円
行っていない確認申請費50万円、詳細の分からないプラン作成費30万円(建築家の先生とは誰なのか……)、誰がどこまで移動したか分からない移動費3万円など、金額も莫大で支離滅裂です。
私としては仮測量、打合せ2回、図面1回の料金以外は払うつもりはないと考えましたが社長がこのような態度なので、埒が明きません。
■結局、10万5000円の支払いで決着
疑問のある内訳について、以下のように理由を添えて「私(Aさん)は支払う必要はありません」と請負者に通知してもらいました。
・プラン作成費
「そもそもプラン作成は貴社の営業経費に該当し、注文者に請求するものではありませんし、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎて費用としての信頼度がありません」
・打ち合わせ図面製作費
「そもそも図面製作は請負者の営業経費に該当し、注文者に請求するものではありません。また、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎ費用としての信頼度がありません」
・確認申請手数料
「担当者より確認申請を行ったという報告を受けておりませんし、今般の請負者からの電子メールでは確認申請がなされたという申請書等の控えの成果物すらなく架空請求としか言えません。また、当初の請求金額と今回の提示金額の差がありすぎ費用としての信頼度がありません」
結局、これらの費用請求は却下され、10万5000円を賠償金として支払うことになりました。Aさんはすでに101万円を入金していたので、賠償金を差し引いた90万5000円を返金してもらいました。
■業者に問題があれば、逆に損害を請求できる
このように、請負者は往々にして多額の費用請求をしてきますが、その費用が妥当なものか、あるいは実際に行われた作業なのかなどを吟味する必要があるのです。
さきほども説明したように、民法第641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」とありますが、注文者が解約したい理由の大半は請負者側のミスや理不尽な対応に起因しています。
例えば、営業担当者が約束を守らない、依頼事項を忘れる、設計者が的外れな間取りや好みではないインテリアコーディネートばかり提案していつまで経っても設計が決まらない、初めから決められた予算内でお願いしているのに大幅な予算オーバーばかりの提案でとても建築はできない、など、さまざまな理由で注文者は解約を希望することになります。
当然ながら工事着手もできず、時間ばかり経過して機会損失の損害を被ったのは注文者側にあるとなれば、請負者側にそうした損害を求めることも可能になります。
■打ち合わせの記録は残しておくべき
例えば、建て替えで仮住まいの期間が長期化すれば、その賃料も注文者が負担することになりかねません。こうした事由であれば、請負者側に既に支払済みのお金を全額返金してほしいと主張することは可能でしょう。
注文住宅の解約は時間や労力がかかってめんどうくさいと思いがちですが、請負契約時に支払ったお金は100万円を超える場合が大半です。請負者側に非があれば、その非を証明して支払ったお金は返金してもらうべきでしょう。
そのためには、請負契約を締結する前から住宅メーカーなどの請負者との打ち合わせ記録は残しておくことです。いつ、どこで、だれと、何の打ち合わせをしたのかなどを記録しておけば、「言った、言わない」のトラブルも防ぐことになります。

■トラブルを回避するための5つのポイント
今回紹介した2つの事例からもわかるように、各住宅メーカーの営業担当者やそこに関わる設計者など、顧客との信頼関係を構築できずに契約に至らなかった、もしくは契約後の解約というケースは多いものです。
注文住宅を建築するという行為は顧客自身、頻繫に経験する行為ではないため、すべてが初めてのこと。ところが、住宅メーカーや工務店は注文住宅を受注、建築することを生業としていますので、顧客よりははるかに優位な立ち位置になるわけです。したがって、「情報弱者」の顧客を時として上から目線になってみたりするのでしょう。
こういった背景から顧客としてはいかにトラブルに巻き込まれないようにするかが重要です。そのポイントは以下の通りです。
・営業担当者や設計者との相性はどうか、を見極める。気に入らない場合には担当者の変更を申し出する
・設計や予算など、希望通りになるまでは契約を急がない
・打ち合わせ時には必ず打ち合わせ記録をお客様自身で作成しておく
・専門家にセカンドオピニオンとしての意見を聞く、もしくはサポートしてもらう
上記のポイントを踏まえ、理想のマイホームを実現したいものです。
----------
住宅コンサルタント
1960年東京都生まれ。アネシスプランニング株式会社代表取締役。住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務した後、2006年にアネシスプランニング株式会社を設立。住宅の建築や不動産購入・売却などのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行っている。これまでに2000件以上の相談を受けている。NHK名古屋「ほっとイブニング」「おはよう東海」などTV出演。東洋経済オンライン、ZUU online、スマイスター、楽待などのWEBメディアに住宅、ローンや不動産投資についてのコラム等を多数寄稿。著書に『不動産投資は出口戦略が9割』『学校では教えてくれない! 一生役立つ「お金と住まい」の話』『不動産投資の曲がり角で、どうする?』(いずれもクロスメディア・パブリッシング)がある。
----------
(住宅コンサルタント 寺岡 孝)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
“電気”と“太陽光発電設備のリース”をパッケージにした「はぴeセット ソラレジ※1」の取り扱いメーカー拡大
PR TIMES / 2024年7月1日 12時15分
-
外壁塗装をしている隣家の「ペンキ」がうちの車についた…!もめたくはないのですが、どう対処すればいいですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 6時30分
-
認知症になると「認知症保険」は請求できない…「老後の備え」をうたう人気商品のとんでもない落とし穴
プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分
-
気になる物件がいくつもあって決められません。全部「仮押さえ」したら後でキャンセル料がかかりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月10日 10時0分
-
疾病が原因の事故では自動車保険金が払われない? 補償の対象外となるケースとは
MONEYPLUS / 2024年6月9日 11時30分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた
東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分
-
4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
5カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












