なぜオウム真理教は殺人テロ集団になったのか…ヨガ道場が「カルト教団」に変質した根本原因
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 17時15分
※本稿は、島田裕巳『日本の10大カルト』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
■ヨーガの道場としてはじまったオウム真理教
オウム真理教は、サリンを使った無差別大量殺人を敢行し、多くの死傷者を出した。その結果、教祖や多くの幹部、信者が逮捕され、宗教法人は解散になった。
しかし、オウム真理教の教祖、麻原彰晃の教えに従う人間たちは、その後も活動を続けている。後継教団となったのが、アレフ、ひかりの輪、そして、公安調査庁が「山田らの集団」と呼ぶグループである。
いずれも宗教法人にはなっていない任意団体で、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)」のもと、観察処分の対象になってきた。アレフについては、2023年9月に、観察処分よりも重い再発防止処分が下されている。
その点で、オウム真理教はカルトの典型であり、後継教団は依然としてカルト性を強く持っていると考えられる。
しかし、オウム真理教が発足当初の段階からカルトであったわけではない。そもそもオウム真理教はヨーガの道場としてはじまったのであって、宗教でさえなかったからである。
■なぜテロ集団に変貌したのか
麻原彰晃が東京の渋谷にヨーガの道場を「オウムの会」として開いたのは1984年2月のことだった。この時期、日本はバブル経済の時代に突入しようとしていたが、それと併行するように、オウム真理教は勢力を拡大し、1995年には地下鉄サリン事件を引き起こすに至る。
その時点で、オウム真理教の在家信者は1万4000人ほどで、出家者は1400人に達していた。富士山麓には「サティアン」と呼ばれる拠点が築かれ、ロシアでは日本よりも多い3万人の信者を抱えていた。オウム真理教の誕生から破滅までの期間は10年をわずかに超える程度であり、その拡大スピードはあまりに速かった。
なぜオウム真理教は急速にその勢力を拡大したのだろうか。もちろん、その勢いは、高度経済成長時代に巨大教団へと発展した創価学会などとは比べ物にならない。だが、オウム真理教には、一流の大学を卒業したエリート層が多かった。それは、創価学会などには見られなかったことである。
それ以上の謎は、なぜヨーガの道場が、最終的に無差別大量殺人を敢行するテロ集団に変貌したかである。サリンは「貧者の核兵器」とも言われる。そのことばに示されているように核兵器に比べれば製造費用は安価なわけだが、民間の宗教団体がサリンを製造し、それを使用するなどということはそれまでないことだった。
■「解脱」からわずか2年で道場開設
オウム真理教がさまざまな事件を引き起こすまでの過程について、私は、2001年に刊行した『オウム なぜ宗教はテロリズムを生んだのか』(トランスビュー、現在は『オウム真理教事件I・II』として同じトランスビューから出ている)で分析を行った。
私は、この本を書くにあたって、オウム真理教が事件後に刊行した『尊師ファイナルスピーチ』という麻原の著作物や説法などを収録した大部の4巻本すべてに目を通した。それによって、オウム真理教がどういう経緯を経て危険な行為に及び、殺人を肯定する教義を形成していったのかを明らかにすることができた。
ヨーガ道場の時代に会員から「先生」と呼ばれていた麻原は、1986年7月に2カ月にわたってインドに滞在して修行を行い、その間にヒマラヤの山中で解脱を体験したと称するようになる。麻原は、『生死を超える』という自身2冊目の著書のなかで、その際の解脱体験について語っていた。

その時期にはすでにオウムの会は「オウム神仙の会」に発展していたが、『生死を超える』を刊行した直後の1987年6月には「オウム真理教」に改称されている。宗教教団としての性格を強く打ち出すことになったのである。
会員のなかには、宗教教団になることに反対する者もいて、離脱者も出たが、教団には多くの若者たちが集うようになり、麻原は精力的にセミナーを開催し、説法をくり返した。その結果、1988年8月には、静岡県富士宮市に「富士山総本部道場」を開設するまでに至る。
■多くの若者がオウムに入信したワケ
麻原自身は、ヨーガの道場をはじめる以前に結婚しており、子どももいた。したがって、在家の立場にあったわけだが、集まってきた若者のなかには道場に泊まり込んで修行を行う者も出てきた。そのため、出家の制度が誕生する。出家した信者は「サマナ(沙門)」と呼ばれるようになる。
宗教教団としての性格を帯びるようになったオウム真理教において、修行の中心はヨーガであり、そこにチベット密教の要素が加えられた。新宗教のなかには、修行を実践させるようなところもあるが、オウム真理教ほどそれに力を入れた教団はなかった。
そこが魅力となり、多くの若者たちが集まってきたわけだが、もう一つ、バブル経済の膨張による金余りの風潮についていくことができない人間たちに、それとは大きく異なる精神性を深めてくれる生き方を提示したことが信者を引きつける要因になっていた。
■殺人集団に変貌するきっかけになった事件
若者たちは、長い年月をかけてじっくりと修行に取り組むのではなく、即効性を求めた。オウム真理教の修行は、それに応じるように激しさを特徴としていた。セミナーでは、朝から深夜までそうした修行が続けられた。
禅の道場である永平寺などでも、そこで修行する雲水たちは早朝から深夜まで修行を続けるわけだが、オウム真理教の修行は、坐禅のような瞑想だけではなく、立位礼拝や呼吸法を含めた激しいものだった。しかも、これは永平寺とも共通するが、食事の量や睡眠時間もかなり制限されていた。
それが結果的に、一つの重大な事件を引き起こすことになる。
富士山総本部道場が開設されて1カ月半ほど経った1988年9月下旬のことだった。在家の信者として修行に参加していた男性が、突然、道場のなかを走り回り、大声を上げて叫び出すという出来事が起こる。
それに対して出家信者が水をかけたり、顔面を浴槽の水につけたりした。もちろんそれは、在家信者を正気に戻すための試みだったわけだが、結果的に信者は死亡してしまった。
■秘密を隠すために新たな秘密を抱える
これは、信者が死亡しているわけだから、重大な事件である。ただ、意図的な殺人ではない。したがって、事件が起こった当初の段階で教団がこの事実を公にしていたとしたら、責任を問われたにしても、殺人罪が適用されることはなかったはずだ。
他の宗教団体でも修行中に亡くなる信者はいる。それによって教団は大きなダメージを被り、教団の発展にブレーキがかかっただろうが、最終的に無差別大量殺人に行き着くことはなかったのではないだろうか。
ところが、その時期は、宗教法人としての認証を受けるために東京都と事前準備の折衝を行っていた最中だった。事件が明るみに出ると、認証されなくなるのではないか。それを恐れた麻原は、亡くなった信者の遺体をドラム缶を使って焼却させ、遺骨は近くの精進湖に捨てさせた。
この死亡事故の隠蔽が、すべてのはじまりだった。
企業による組織犯罪の場合にも、やはり隠蔽からはじまる。秘密を抱えるようになった集団は、なんとかそれが外部に漏れないよう策を弄するようになり、さらに秘密を抱えることになっていくからだ。
■決して凶暴な人間たちではなかった
事故と隠蔽工作について知る者は、教祖と数人の幹部に留まっていた。ところが、たまたま信者が死亡した現場に居合わせた出家信者が一人いた。その人物は、教団の修行のあり方に疑問を抱くようになり、脱会を申し出てきた。
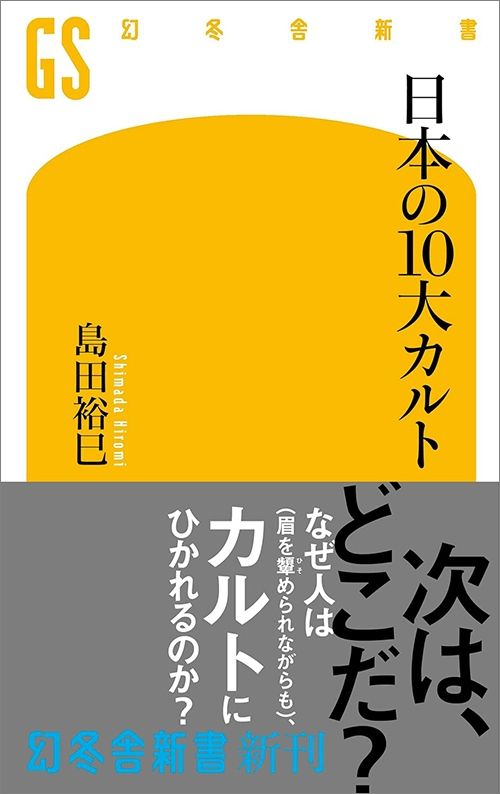
麻原は幹部に指示して、翻意させようとしたが、拒まれた。そこで、秘密の漏洩を恐れて、その出家信者を殺害してしまったのだ。
殺害のやり方は、出家信者の首にロープを巻き、それを4人の幹部が2組に分かれて引っ張るというものだった。犯行にかかわったのは、早川紀代秀、新實智光、岡崎一明、村井秀夫で、いずれも事故死した在家信者の遺体遺棄に関与していた。ロープで巻かれた出家信者が抵抗したため、新實が頭と顎の部分を押さえ、首を捻じった。これで出家信者は亡くなる。教団は最初の殺人を犯したのである。
犯行に関与した幹部たちは、事故死が明るみに出ることを恐れたわけだが、彼らは、ヨーガの修行をするためにオウム真理教に入信したわけで、自分たちが殺人を犯すとは考えてもいなかった。彼らはもともとは決して凶暴な人間たちではなかった。したがって、殺人を犯したことに激しいショックを受けたに違いない。
そこで麻原は、殺人の直後、それを正当化する教義を説くようになる。
----------
宗教学者、作家
放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)、『教養としての世界宗教史』(宝島社)、『宗教別おもてなしマニュアル』(中公新書ラクレ)、『新宗教 戦後政争史』(朝日新書)など著書多数。
----------
(宗教学者、作家 島田 裕巳)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
突然やってきた初の戦場取材 駅前の戦車に恐る恐るカメラを向けて… 話の肖像画 報道カメラマン・宮嶋茂樹<21>
産経ニュース / 2024年7月22日 10時0分
-
「妻が宗教に引っかかって娘まで入れようとしている」と相談にきた男性に禅僧がピシャリと言ったひと言
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 7時15分
-
未曽有の化学テロから30年、今も続く特定人物のつるし上げ 松本サリン事件「犯人視報道」の教訓
47NEWS / 2024年7月14日 10時30分
-
「宗教2世」メディア狂騒 オウムから四半世紀、テロ発の問題提起 新テロ時代 二律背反⑤
産経ニュース / 2024年7月12日 7時0分
-
オウム遺骨返還訴訟、二審開始 元死刑囚の次女「父返して」
共同通信 / 2024年7月2日 12時40分
ランキング
-
1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…
日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分
-
2「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て
東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分
-
3日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?
オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分
-
4まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】
イエモネ / 2021年5月8日 12時30分
-
5扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











