「幼少期の悲惨な境遇」は減刑の理由にはならない…パパ活詐欺に「懲役9年」という冷徹な判決が下った理由
プレジデントオンライン / 2024年5月31日 10時15分
■「約1億5000万円の詐欺で懲役9年」は重すぎる?
先日、「頂き女子りりちゃん」と呼ばれる25歳の女性が、詐欺罪、詐欺幇助罪、所得税法違反の罪で懲役9年、罰金800万円の判決を受けました。
判決が認定した事実によると、その女性が3人の男性から騙し取ったお金は総額約1億5000万円、そのお金を申告せずに脱税した金額は約4000万円にも上ります。また、詐欺の手口をマニュアル化したものを販売し、他の人が同様の詐欺をすることの手助けをしたことも認定されています。
報道や、公表されている女性の手記などから、女性がこのような犯罪に手を染めたきっかけは、推しのホストをナンバーワンにすべく大金をつぎ込むためだったようです。そのホストも、女性が詐欺で得たお金と知りながら、そのお金を店で支払わせたという組織犯罪処罰法違反の罪で逮捕され、現在裁判が行われています。
世間では、女性に対する刑が重すぎるのではないか? いや、これだけのことをして軽いのでは? などとさまざまな声が上がっているようです。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と刑法で定められています。被害総額が大きくなければ執行猶予判決か、実刑でもそれほど長期間の懲役刑になることはありません。ただし、複数の詐欺があったり、他の罪名もあったりする場合は、長期間の懲役刑になったり、詐欺罪の法定刑上限を上回る懲役刑になる場合もあります。
■父親からは虐待を受け、母親は裁判に出てくれなかった
この事件の場合、女性の手口の巧妙さ、悪質さ、被害金額の大きさ、騙した行為の数、被害者の受けたダメージ等からすると、重い処罰になるのはある意味当然と言えます。
判決は「言葉巧みに好意があるように装って自身への恋愛感情を抱かせる」「時には一人二役を演じる等して数々の金銭的な問題を抱えているようにほのめかす」「男性心理を手玉に取り、好意に付け込む狡猾な犯行」と断じています。詐欺に加え、脱税額もかなり高額です。
しかし、犯罪の背景には、父親から虐待を受け、家庭にも学校にも居場所がなかったなどの事情があったようです。女性の手記には、「父からライターで火をつけられる」「何度か殴られた」「殺すと言われた」などの少女時代の過酷な体験が書かれており、勇気を出して110番通報したのに警察にまともに取り合ってくれなかったとのことです。
周囲に信頼できる人がおらず、自己肯定感が著しく低下した中で、自分を褒めてくれるホストにのめり込んでいったのかもしれません。弁護側もそういった背景を考慮すべきであると主張していました。母親が情状証人として裁判に出てくれなかったことも、女性にとってはかなりショックだったのではないでしょうか。
■弁護士が意外に感じた今回の判決
判決前にメディアから取材を受けた際、記者から「確かに生い立ちはかなり気の毒で、なぜ彼女に救いの手が差し伸べられる機会がなかったのだろうか、とは思う」という話を聞き、女性のそのような境遇がどのくらい判決に考慮されるのか、個人的に注目していました。
しかし、判決では、そういった事情は一切考慮されなかったようです。確かに、いかに生い立ちが不幸であっても、それとはまったく無関係の人に対する犯罪で、刑を軽くするのは筋違いでしょう。ただ、「被告人の生い立ちに不幸な面があることは否定できないが、それを被告人の情状として重視すべきではない」など、何らかの言及はあるのではないかと思っていたので、何も触れられなかったことは意外でした。
詐欺は、立件が最も難しい犯罪類型のひとつです。「必ず返すからお金貸して、と言われて貸したのに、後から返せないと言われた。これは詐欺だ」という相談はよくあります。しかし、最初から返すつもりがなければ「騙した」ことになりますが、その時は本当に返すつもりだった、というのであれば騙したことにはなりません。
刑法の詐欺罪は、次の点を満たすかどうかによって判断されます。
●だました被害者に勘違いをさせる
●被害者が勘違いのために財産を渡す
●加害者が被害者の財産を受け取る
■金品を騙し取られれば刑法上の「結婚詐欺」が成立する
刑法の詐欺罪が認められるには、加害者の行為が上記4つをすべて満たし、それらに因果関係があることを証明する必要があります。
たとえば「だますつもりはなかったが、被害者が勘違いをして代金を支払った」という場合は詐欺とはみなされません。
詐欺は証明することが難しい犯罪です。加害者側が「だますつもりはなかった」「被害者が勘違いしただけ」と主張した場合、そうでないことを証明するのがどうしても難しいためです。しかし、被害者が複数いるのであれば、証明がしやすくなる場合があります。
民事訴訟の場合、相手にお金を渡した経緯や金額などのさまざまな要素に問題がなかったかどうかを検証し、契約の無効や取り消し、慰謝料の支払いなどを主張していくことになります。
また、刑法の詐欺罪は、騙し取る対象が金品であることが必要です。「結婚すると言っていたのに、他に彼女がいた。騙された、結婚詐欺だ」「結婚したとたんに人が変わったように態度が冷たくなった。資産目当ての詐欺だ」など、一般的に「詐欺」という言葉は広く使われていますが、「結婚詐欺」が刑法の詐欺になるには、「結婚するつもりがないのに、結婚をエサに金品を騙し取った」ことが必要です。
■「パパ活」が行きすぎると詐欺や脱税に問われる場合も
刑法の詐欺罪は経済犯なので、金品をだまし取る行為がなければ、刑法上の詐欺にはなりません。そのため、仕事や学歴、年収などについて嘘をつかれても詐欺にはなりません。また、結婚できると一方的に信じて肉体関係を結んでも、犯罪にはなりません。
しかし、民法の不法行為にあたる可能性はあります。貸したお金を返してもらう、だまされて傷ついたことに対する慰謝料を請求することはできます。
ただ、これも証拠が必要となるので、必ずしも請求が通るとはかぎりません。まずは直接、または第三者を介して交渉してみましょう。
いわゆる「パパ活」は、女性が年上の男性と食事やデートをして、そのお礼にお小遣いをもらうことです。これは詐欺ではないの? とよく聞かれますが、お互いがそれに納得しているのであれば、犯罪にはなりません。
ただ、そのお金が多額であったり、お小遣いをもらう過程で女性側に騙す行為があったりした場合は、詐欺や脱税になることもあります。また、男性側に何らかの下心があり、繰り返しお小遣いやプレゼントをもらっていると、ストーカー等の思わぬトラブルに発展することもあるので、注意が必要です。

■女性の犯罪者は暴力被害を受けていることが多い
「頂き女子りりちゃん」の今後に関して言えば、弁護人が高裁に控訴したとの報道があり、控訴審でこの判決が維持されるのか、刑が軽くなるのかが注目されます。
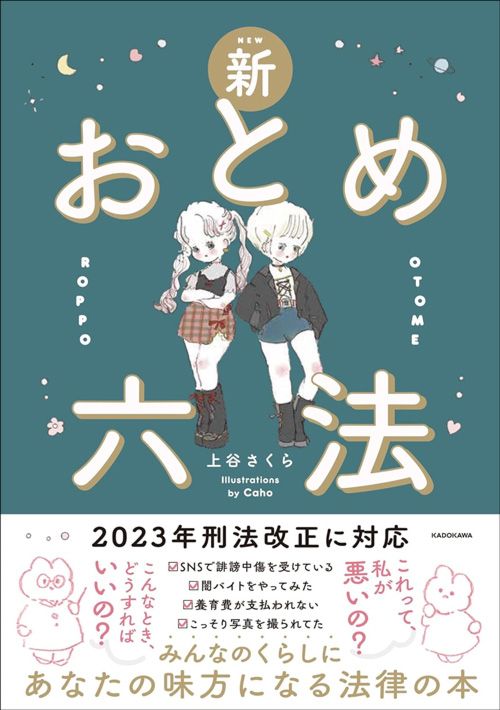
女性の手記を読むと文章もしっかりしていますし、頭のいい人なんだろうと感じます。今後、自らが犯した罪に向き合い、被害者の方にしっかり謝罪をしたうえで、更生してその能力を良い方向に活かしてほしいと願っています。
この事件は、別の角度からみると、未成年者が激しい虐待を受けていたのに、社会や大人たちが救えなかった、という側面を有しています。特に女性の犯罪者は、幼少期に性暴力や虐待を受けている人が多いですから、どのようにしてそのような子どもたちを守っていくのか、ということはもっと真剣に実現可能な方法を考えていくべきです。
----------
弁護士 第一東京弁護士会所属
福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。保護司。
----------
(弁護士 第一東京弁護士会所属 上谷 さくら)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
性犯罪の刑法改正で「不同意」の相談増加 支援センター「抱え込まないで」
産経ニュース / 2024年7月7日 19時49分
-
不同意性交罪認知件数1488件 今年1~5月、前年の2倍 処罰対象明確化が背景に
産経ニュース / 2024年7月7日 19時44分
-
〈6月28日初公判〉「JCの“初めて”売ります。1万円」殺人未遂で逮捕の元“パパ活女子”が綴った苦難に満ちた28年。「中学生というだけで自分に価値があると思った」売春との出会いが彼女の人生を変えた
集英社オンライン / 2024年6月27日 17時0分
-
飲み会で幹事に「4000円」払ったのですが、後日「1000円」余分に徴収していたことが発覚! これって「詐欺」? 飲み会費用の“注意点”を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 4時40分
-
彼氏がコンビニで「他人の傘」を勝手に使っていた! これって「窃盗」になるの?「置いておくほうが悪い」と言っていたのですが、そんなことありませんよね? 実際どんな罪になるんでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 4時30分
ランキング
-
1一番売れている「軽自動車の“王様”」はどれ?「23ヵ月連続ナンバーワン」も! 2024年「“軽”販売ランキング」トップ3
くるまのニュース / 2024年7月8日 12時50分
-
2〈公約達成に疑問もなぜ圧勝?〉小池百合子が都知事選3選で「日本終了」「東京終了」がトレンド入り「政策目標9割達成」強調も「絶望しかない」
集英社オンライン / 2024年7月8日 11時23分
-
3空腹時の“炭水化物ドカ食い”は幸せだけど…話題の「血糖値スパイク」がもたらす“怖いリスク”<医師監修>
日刊SPA! / 2024年7月8日 15時52分
-
4医師が考案「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープ 中性脂肪と悪玉コレステロールをためこまない
東洋経済オンライン / 2024年7月7日 18時0分
-
5裏金自民に衝撃!東京都議補選「2勝6敗」の大惨敗…ステルス支援の都知事選勝利ふっ飛ぶ
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月8日 10時52分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











