"長寿サプリ"に飛びついちゃダメ…アンチエイジング研究第一人者推奨の心身健やかな「健康寿命」の延ばし方
プレジデントオンライン / 2024年6月3日 16時16分
■シワが多い人は体内も老化している
ここからは、老化の仕組みを詳しく解説していきます。
ヒトの体は約200種・60兆個の細胞によって構成されています。それらの細胞は常に一定数死んでいて、それと同じくらいの数の細胞が新しく生まれています。ヒトの体のなかでは毎日1~2%、約6000億~1兆2000億個もの細胞が入れ替わっています。
このようなメカニズムによって保たれているヒトの体ですが、年齢を重ねていくにつれて「老化」していきます。
老化には、「テロメア」という細胞内の「染色体」の末端にある構造が深く関わっています。
本来、染色体はとても不安定な存在で、テロメアがないと何かの拍子に他の染色体とくっつく可能性があります。そうなると「DNA」の損傷が起こりやすくなり、遺伝子自体がダメージを受け、細胞が機能しなくなったり、がん化したりします。そのような事態を引き起こさないように、染色体の末端を保護しているのがテロメアです。
テロメアには、もう一つ重要な役割があります。細胞分裂の際、DNAの一部は複製されないため、そのままだと分裂のたびに短くなってしまいます。そこでテロメアは自分の一部を差し出すことで、DNAが短くなるのを防いでいます。その結果、新しい細胞も正確に複製された遺伝子を受け取れるようになるのです。
しかし、テロメアは細胞分裂のたびに短くなります。テロメアがある程度まで短くなると、細胞は「これ以上は分裂できない」と判断して分裂をストップします。そうやって分裂の寿命を迎えた細胞が「老化細胞」になるのです。つまり、テロメアを節約することが老化の予防につながります。
■血流が滞ると体が錆びついていく
ここで、全体的なヒトの老化の仕組みにおいて、どのようにテロメアが関わっているかを見てみましょう。
生命を維持するにあたって、細胞は内部にある「ミトコンドリア」が細胞呼吸で産生した「ATP(アデノシン三リン酸)」をエネルギー源にして活動を続けています。そのATPを産生するのに酸素と栄養素が必要で、毛細血管を流れる血液から摂取しています。
しかし、仕事などでストレスがかかって自律神経の一つである「交感神経」が優位の状態になると、毛細血管が収縮して血流が低下します。すると、酸素や栄養素を十分に摂取できず、細胞呼吸の機能が低下して、ATPの産生効率も落ちます。そして、「酸化」の作用を及ぼすフリーラジカルが多く発生し、DNAや他の細胞の構成成分を傷つけるようになるのです。
そこで、体を構成している大多数の体細胞は、分裂することで、機能の維持を図ります。しかし先述の通り、分裂のたびにテロメアが短くなり、やがて限界に達して老化細胞に変化します。一方、新しい細胞を補充する役割を担っている「幹細胞」も、分裂の繰り返しで疲弊していきます。そして、細胞の補充が追いつかなくなり、組織や器官、臓器そのものが老化し、全身のあちこちで老化現象が起こるのです。
通常、老化細胞は「マクロファージ」をはじめとする「免疫細胞」で取り除かれます。ところが、加齢などが原因で免疫細胞の働きが低下すると、老化細胞は居座り続けます。厄介なことに、その老化細胞からは「炎症性サイトカイン」という炎症作用のある物質や、発がん促進作用のある物質が分泌され、ヒトの寿命を脅かすようになるのです。
■テロメアを節約すれば健康寿命が延びる
老化の進行と密接な関係にあるテロメアは、「命の回数券」とも呼ばれています。イギリスのニューカッスル大学と慶應義塾大学の共同研究チームが、100歳以上の長寿者とその直系子孫ら約1500人を対象に調査したところ、「100歳以上の長寿者はテロメアが長い」「長寿者やその家族では、実際の年齢が80歳代でも、テロメアは60歳代の平均値に匹敵する長さを保っている」ということがわかりました。
また、細胞分裂のたびに短くなるテロメアですが、テロメアを合成する「テロメラーゼ」と呼ばれる酵素に、短くなったテロメアを修復する働きがあることが突き止められています。その修復の働きの強いことを、「テロメラーゼ活性が高い」と表現します。
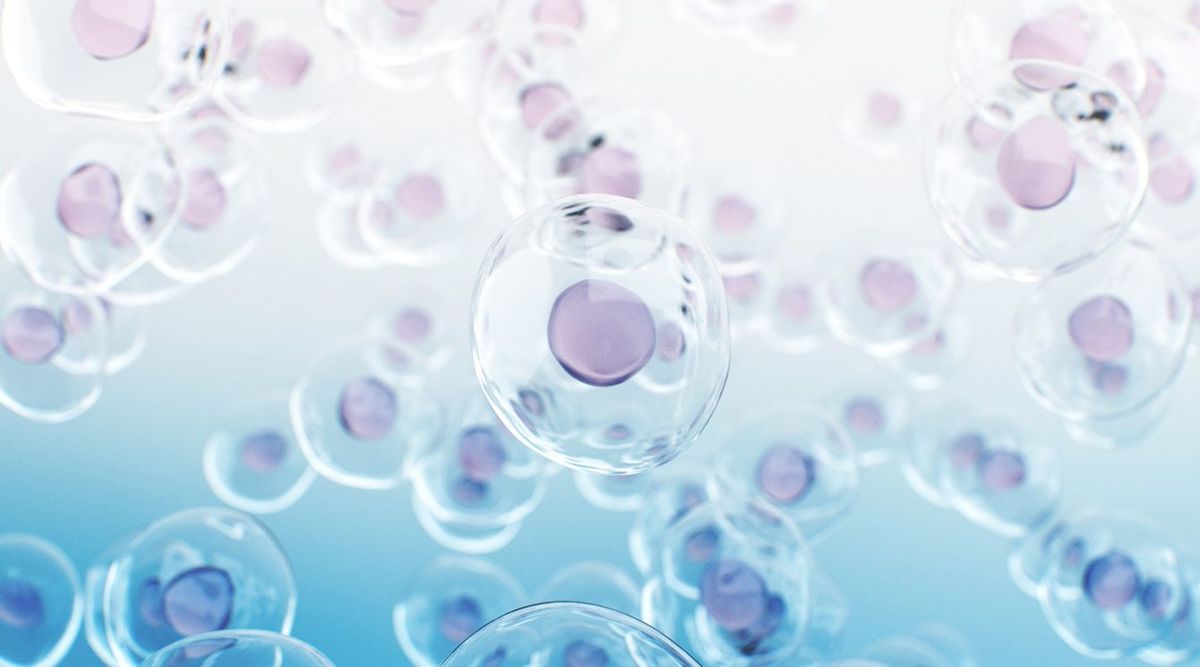
ただし、基本的にヒトの細胞の大半を占める体細胞は、テロメラーゼの活性がありません。一方、幹細胞はテロメラーゼ活性が比較的高く、周囲の体細胞が老化細胞になっていくなかで、自身のテロメアを修復・維持しながら、新しい細胞を供給してくれます。たとえば皮膚の線維芽細胞(せんいがさいぼう)は体細胞、真皮幹細胞は幹細胞の一種です。
そのことを知ると、「人為的に体内でのテロメラーゼ活性を高めてやれば、老化が防げるようになるのでは」と考える人が出てくるでしょう。すでに世の中には「テロメラーゼの活性」を謳(うた)ったサプリメントが出回っています。しかし、事はそう簡単ではありません。
テロメアが短くなる速度は細胞によってバラツキがあり、すべての細胞でテロメラーゼが働くようにしても、テロメアの修復が一律に行われるのか疑わしいのです。たとえ一律に修復されても、何か不具合が起きないとも限りません。また、特定の部位の細胞だけテロメラーゼを活性化する技術は、まだ確立されていません。さらに、がん化のリスクもあり、安易にサプリメントに飛びつかないほうが賢明でしょう。
一方、老化細胞を取り除けば、老化細胞が引き起こすトラブルを防げるかもしれないという考えも成り立ちます。2021年に東京大学の研究グループが、老化細胞の生存には「GLS1」という遺伝子が必須であることを突き止め、GLS1を阻害する薬剤「GLS1阻害剤」を開発しました。
実際にマウスに投与すると、正常な細胞には影響を与えず、さまざまな組織や臓器における老化細胞が除去されました。その結果、肥満性糖尿病や動脈硬化が改善したり、筋力が維持されたりと、加齢に伴う現象が改善され、老化の治療の道筋が見えてきました。
しかし、老化細胞が除去されると、組織や臓器を構成している細胞の総数が減り、組織や臓器の本来の働きに支障が生じる恐れが出ます。それを防ごうと、体細胞は分裂して数を増やし、幹細胞も新しい細胞を補充するため分裂を繰り返して、除去された老化細胞の穴埋めを図るはず。分裂の回数が増えれば体細胞のテロメアは短くなり、幹細胞には強い負担がかかります。
つまり、老化細胞を除去することは、テロメアを激しく消耗する可能性があるわけです。ヒトに対する治療に実際に活用できるのか、判断を下すまでには、もう少し時間を要しそうです。
テロメアに関しては未知な領域が大きく、テロメラーゼが活性化していても細胞が老化することはあります。「テロメアの長さ=細胞の寿命の長さ」とは言い切れないのが現状なのです。
では、テロメアと老化、そしてヒトの寿命について、どう考えればいいのでしょうか。「テロメアは健康寿命の指標」と、私は捉えています。健康寿命とは、介護を必要とせずに、心身ともに健やかで自立して生活できる期間のことです。テロメアを適切に節約する生活を心がけて、継続することによって老化の進行を防ぐことができ、健康寿命を延ばせます。40代、50代で始めても遅くはありません。
※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。
----------
医師・医学博士
東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程修了。ハーバード大学医学部客員教授、ソルボンヌ大学医学部客員教授、フランス国立保健医学研究機構客員教授、東京大学客員上級研究員、奈良県立医科大学医学部客員教授。アンチエイジング研究の第一人者。『ハーバード&ソルボンヌ大学ドクターが教える! 超休息法』(徳間書店)、『老化は予防できる、治療できる』(ワニプラス)、『ハーバード&ソルボンヌ大学の最先端研究から考案! 肩甲骨リセット』(文響社)など著書多数。
----------
(医師・医学博士 根来 秀行 構成=伊藤博之)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
東北大、死細胞が老化を抑制する物質を分泌していることを動物実験で確認
マイナビニュース / 2024年7月3日 7時2分
-
「高齢でもヨボヨボにならない人」は明らかにその"数値"が低い…最新研究でわかった人間の寿命差を生む要因
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時16分
-
性染色体の「Y」が男性からなくなると心不全死のリスクが1.8倍増加に…生物学の最新研究からわかった疾患リスクとは
集英社オンライン / 2024年6月17日 11時30分
-
阪大、脊椎動物では卵子が寿命を延ばし精子が寿命を縮める可能性を発見
マイナビニュース / 2024年6月14日 23時7分
-
糖尿病の薬が、アルツハイマー病など加齢疾患の治療薬として期待 順天堂大
財経新聞 / 2024年6月13日 16時3分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
-
418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












