「がんばれ」と「がんばってるね」は全然違う…「孫氏の兵法」に学ぶ"子供のすごい知能"を育てる親の声かけ
プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分
※本稿は、小島宏毅『孫子の兵法から読み解くAIに負けない「すごい知能」の育て方』(日刊現代)の一部を再編集したものです。
■子どもたちに身につけてほしい「やり抜く力」
一見まわり道のようでも自分で試行錯誤しながらいろいろ試してみて、どうすれば良い結果が得られるかを自分で工夫する機会が子どもには必要です。そうすれば、人より遅れをとっているように見えても、長い目で見れば自分で困難を乗り越えられるようになります。これがレジリエンスと言われるもので自己管理力、自制心という自立に必要な力になります。まわり道は、自立への一本道なのです。
以前、『やり抜く力――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』(アンジェラ・ダックワース著、ダイヤモンド社)という本が話題になりました。自分のやりたいことや興味関心のあることに取り組み、最後までやり抜くということはとても大切なことです。うまくいかなかったら、どうすればうまくできるようになるか、それを自分で考えて工夫してみる試行錯誤する力、自分が思ったとおりの結果でなくても、めげずに何度でも挑戦する力――すなわちやり抜く力は、ぜひ子どもたちに身につけてほしい力です。
■「がんばれ」という声かけは正しいのか
そのために、どんな言葉で声かけをすれば、効果的でしょうか。誰もがぱっと頭に思い浮かぶのは、「がんばれ」でしょう。「がんばれ」と応援すれば、子どもはやり抜くことができる、そう考える方もいるかもしれません。たしかに、「がんばれ」は相手の気持ちを強くすることもあり、わかりやすい励ましの言葉です。たとえば、なにかの競技に取り組む子どもに対し「がんばれ、がんばれ」と応援する光景はよく見られますし、子ども自身も後押しされ、「がんばってみよう」という気にもなるかもしれません。
しかし、いつも「がんばれ」と言っていればやり抜く力を育むことができるかといえば、そうでもありません。場面を考えないで使えば、逆効果となります。それは、「がんばれ」とは「困難にくじけず、最後までやり遂げよ」というメッセージだからです。つまり、この言葉は子どもに大きなプレッシャーを与えることにもなるのです。
■場面を考えないで使えば、逆効果となる
競技中の選手には、「がんばれ! がんばれ!」でいいと思います。途中であきらめてしまったら、結果は出ないからです。大勢の人から応援されれば、苦しさを乗り越え、ふだん出ないような力が発揮されることだってあるでしょう。

ただし、ふだんの生活のなかで「がんばれ! がんばれ!」と言われつづけるのは、「自分に負けるな」「あきらめないで、最後までやり抜け」とずっと強要されているのと同じことです。これでは子どもは疲れ果ててしまい、生きる希望を見失ってしまうかもしれません。この場合の「がんばれ」は、子どもからすれば「おまえはいま、がんばってない、だからがんばらなければならない。がんばらなければ、生きている価値もない」というメッセージを受け取ることになります。
明確な目標があるのなら、「がんばれ」も効果があるでしょう。「なにに対してがんばるのか」がわからないまま「がんばれ」と言われたところで、それは空疎な言葉となります。「人の気持ちも知らないでがんばれるか」、あるいは「勝手なことを言うな」という気持ちになるだけです。試行錯誤にしても、自分でやってみる前から「がんばれ」と言ったのでは、やる気を育むことはできません。やり抜く力に必要な意欲がわいてこないのです。
■試行錯誤が見られたら、「がんばれ」ではなく「がんばってるね」
「言葉がけとは、行動に対する同時性と随伴性である」と指摘したのは、ある有名な心理学者――ではなく、かくいうこの私なのですが、これは「子どもをほめる言葉がけは、子どもが何かをしているときにその行動を言葉にすることと、行動を終えたときにそれを追随して承認したときにこそ期待する効果が伴う」という意味を指します。
つまり、子どもが試行錯誤する姿が見られたら、そのときは「がんばれ」ではなく「がんばってるね」と声をかけること。試行錯誤している最中に「こうしたらどう?」「こうしたほうが、うまくいくわよ」などという余計な口出しは一切禁物で、子どもの考えにまかせること。そこは「待つ」「見守る」「まかせる」の姿勢を維持し、やり終えたら「がんばったね」「がんばってたね」「一生懸命やったね」「よく考えたね」と、子どもの行動を認める言葉をかけること――そうすれば、子どもはほめられたことで自信がつき、意欲がわき、やり抜く力が身につき、たくましい姿に育ちます。
■2000人以上を調査してわかった「成長思考」と「固定思考」
心理学者のアンジェラ・ダックワースとキャロル・ドゥエックは、2000名以上の高校生を対象に、「成長思考」についてのアンケートを実施しました。すると、「成長思考」の生徒は「固定思考」の生徒よりも、はるかにやり抜く力が強いことがわかりました。その後、低学年の子どもたちや、年上の成人を対象に調査したところ、「成長思考」と「やり抜く力」は比例することがわかりました。

やり抜く力とは、「困難に直面してもめげずに立ち向かう力」ですので、「成長思考」「前向き」「ポジティブ」「心が強い」という姿勢がその原動力になることは、よくわかると思います。成長マインドセットは、困難や逆境を楽天的に受け止められるので、粘り強く立ち向かうことができるのです。
ドゥエックは、「マインドセットは、人が過去にどのような成功や失敗を経験してきたか、そして周囲の人々、とくに親や教師などの権威をもつ立場の大人が、どのような反応を示したかによって決まる」と述べています。また、ダックワースも「(成長思考になるか固定思考になるかは)子どものころのほめられ方によって決まる確率が高い」と述べています。ほめ方については、すでにお話ししてきたとおり、「結果(正解や一番であったこと、100点満点)をほめない、プロセスをほめる」「能力や才能をほめない、努力をほめる」ということが重要です。
マインドセット、心の持ち方は経験したことのある成功と失敗で決まる、ということを示す、動物を使った実験があります。成功と失敗の体験内容が、人の心を強くするか弱くするか、その違いになって現れてくるようです。
■幼いころの成功体験が、子どもをたくましく育む
セリグマンと犬の無力感についての実験をしたスティーブ・マイヤーは、その40年後にラットを使い、ほぼ同じ実験をしました。回転ホイールを回せば電気ショックが止まるグループと、電気ショックを制御できないグループとにラットを分けたのですが、犬の実験と違うところは、ラットが生後5週間だったこと。これは人間の青年期に当たります。ラットを使った2回目の実験では、5週間後にラットが成体になったとき、両グループを回転ホイールがない状態(=電気ショックが制御できない状態)に置き、ラットの行動を観察しました。
この結果、最初の実験で制御可能なストレスを経験したラットは冒険心が旺盛で、成体になったときに「学習性無力感」に免疫力を持っているように見えました。レジリエンス(耐性と回復力)を身につけて成長したので、無力感に陥ることはなかったといえます。一方で、若いときに制御できないストレスを経験したラットは、成体になって再度制御できないストレスを経験したときに、臆病な行動をとることがわかりました。つまり、若いころにつらいことを経験しても、「自分でストレスを制御できる」という成功経験をした場合、冒険心が旺盛になり、目に見えてたくましくなり、強くなったということです。
■逆境を経験して、乗り越えたときに脳が成長する
この実験結果について、マイヤーは次のように述べています。
「若いときに大きな逆境を経験して、それを乗り越えた場合、それ以降にまた逆境が訪れると、対処のしかたが変わってくる。ただし、それは非常に大きな逆境を経験した場合に限られる。ちょっと困った程度のことでは、脳に変化はおこらない」
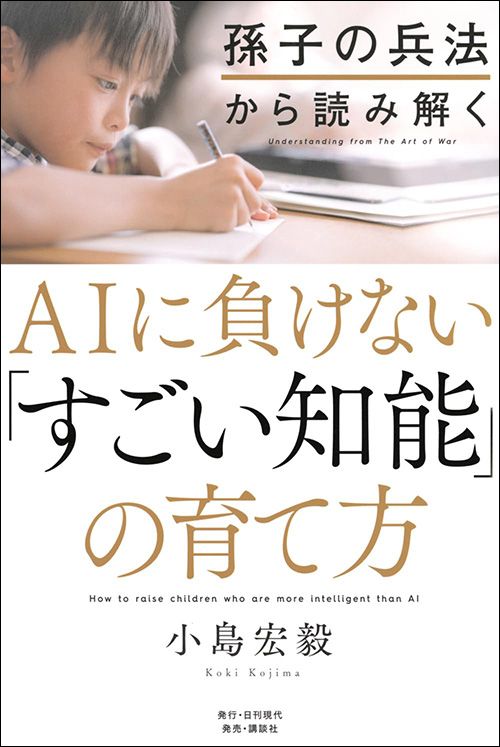
「あなたなら逆境を乗り越えられる、と言われるだけじゃダメなんだ。(「がんばれ」ではダメなのですね。/筆者注)脳の神経回路の再配線が起こるには、下位の抑制領域(辺縁系=ストレスを感じるところ/筆者注)と同時に、制御回路(前頭前野/筆者注)が活性化する必要がある。それは実際に逆境を経験して、それを乗り越えたときに起こることなんだ」
「困難なことに出会っても、必ず克服できる」「自分で自分をコントロールできる」という自信を持つこと、「こうすればこうなるはずだ」と自信を持って思えることが、困難を乗り越える力となります。若いときの制御可能なストレス体験がレジリエンスを生み、その後の大きな逆境にも立ち向かうことができるようになる、ということです。そのとき脳は、神経回路の再配線がなされて「すごい知能」に育っているのです。
■子育ての「迂直の計」(軍争篇)
【書下し文】
軍争の難(かた)きは、迂(う)を以って直となし、患を以って利となす。故に其の途(みち)を迂にしてこれを誘うに利を以ってし、人に後(おく)れて発し人に先立ちて至る。此れ迂直の計を知る者なり。(軍争篇)
【現代語訳】
戦闘が難しいのは、遠まわりが逆に近道となるように不利を有利にする知恵が必要だからだ。したがって、わざわざ遠まわりをして遅れているように見せかけて相手に優勢であると思わせておき、敵に遅れて出発しながら敵に先んじて戦地に到着する謀議をし、自陣が有利な態勢をとること、これを迂直の計を知るという。
【育児対訳】
子育てが難しいのは、試行錯誤することが目標に到達する近道であると考える智恵が必要だからです。
----------
ひよし幼稚園理事長・園長、児童文学作家
1961年生まれ。岐阜県出身。幼稚園園長として保育制度や子育てに関する著作、児童文学作家として絵本を発表している。著書に『ママはすっきり、パパはしっかり、園長びっくり! 認定じいさんに聞きました 認定こども園がみるみるわかる本』(ギャラクシーブックス)、『「ママ、うれしいわ」が子どもを育てる 孫子の兵法を知れば子育てがわかる、変わる』(幻冬舎)。児童文学作家として『しましま』(ひかりのくに)、『たこやきくんとおこのみくん』『飲茶むちゃむちゃ』『100歳になったチンチン電車 モ510のはなし』『う、のはなし』(以上4作品とも幻冬舎)がある。
----------
(ひよし幼稚園理事長・園長、児童文学作家 小島 宏毅)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「根拠のない自信」持つ人に共通する"すごい特徴" 思考停止に陥る「3つのワナ」にはまらないコツ
東洋経済オンライン / 2024年7月17日 19時0分
-
「ベストやなと」巨人・坂本が打撃に試行錯誤 若手の早出練習に2日連続で参加
スポーツ報知 / 2024年7月15日 5時45分
-
「やりたくない仕事」は脳細胞をどんどん破壊する…脳科学者が説く"簡単に転職できない人"のための労働のススメ
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 8時15分
-
従業員の“恐怖心”がイノベーションの妨げに 経営層が参考にしたい思考法
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月5日 7時5分
-
2024年7月18日(木)「建築&不動産ビジョン2030~少子高齢化&労働力不足を乗り越える次世代への成長戦略」開催のお知らせ
PR TIMES / 2024年7月4日 12時15分
ランキング
-
1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」
日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分
-
3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分
-
4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃
乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分
-
51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











