なぜ「高学歴な人」は就活で優遇されるのか…大人が「良い大学→大企業」ルートをお勧めする残酷な理由
プレジデントオンライン / 2024年6月3日 9時15分
■誰でもやれる仕事の給料は低くなる
仕事をすればお金がもらえる。これを当然のことと考える人は多い。君もきっと、アルバイトをすれば1時間千円とか、お金がもらえると思っているだろうし、事実その通りではある。
東京都の最低賃金は1113円(令和6年3月現在)だから、どんな仕事であれ働きさえすれば、最低でも1時間1113円はもらえるわけだ。これはあくまで最低賃金であって、仕事の内容によっては高い給料をもらえることもある。
では質問だ。給料が高いか低いかは、どうやって決まると思う? 給料の高い仕事は、低い仕事と何が違うのだろうか。
労働力が商品だとしたら、給料はどうやって決まるのか。実はこれも、需要と供給で決まる。お金さえ払えば何でもさせられるというわけではない。仕事の内容に応じて、給料が決まる。やりたい人やできる人が少ない仕事の給料は高めになるし、誰でもやれるか人気がある仕事の給料は低くなる。
■高学歴な人が「仕事でも優秀」とは限らないが…
これは考えたらわかるだろう。君がやりたい仕事があったとしても、同じ仕事を安くてもやりたいという人が他にたくさんいたら、会社はわざわざ高い給料を払って君を雇うことはないだろう。
誰もやりたがらない、あるいは他の人にできないが必要な仕事なら、君にいくら高い給料を払ってでも雇いたいと思うだろう。給料もマーケットで決まるんだ。
だからできるだけ、他の人にはできない仕事をしたほうが給料は高くなる。君が今、必死に勉強して手に入れようとしている学歴もそこに価値がある。高い教育を受けた人の価値は高くなる。難しい試験問題で高得点を取れたのだから、きっと複雑な仕事もミスなくやってくれるのではないかと期待されるからだ。
実際には、よい大学に行っているからといって、仕事の面で優秀な人とは限らない。でも複雑な問題にあきらめずに挑んでくれて、うまくやろうと努力することを知っている人なのではないかということを期待して、会社は学歴の高い人を雇って高い給料を払っているんだ。勉強以外の強みがある人もたくさんいるけれど、それは長い時間をかけて付き合ってみないとわからないからね。
■企業が「頭のよい」人を選ぶのは合理的
だから会社が高学歴の「頭のよい」人を雇いたがるのは、合理的だといえる。学歴や偏差値を重視する傾向はだんだん減ってきているとはいわれているけど、未だに高学歴を歓迎する会社がたくさんあるのは事実。

従って、勉強が苦手ではないならしっかり勉強しておいて、高学歴を手に入れることは学生にとっても合理的だということになる。残酷な話をしているようだけど、これが世の中の仕組みだ。
これからAIがさらに発達し、普及してくると「頭のよさ」の定義が変わる可能性はある。記憶力だとかミスをしないことの価値は下がり、創造性やリーダシップ、コミュニケーション能力といったことの価値が上がるかもしれない。
そういう変化を予想してもなお、君自身の頭脳に投資をしておくことは有益だと思う。勉強だけでなく、人間として幅を広げるような、よい経験をたくさんしておくとよいだろう。体を鍛えて、全力で遊んで、笑って泣いて、信頼できる人間関係を築きなさい。それが全部、頭脳への投資になる。
■雇う側から見た「高給にしたい人」
給料は需要と供給で決まると書いたけれど、これを今度は雇う側から見てみよう。はっきり言うと、僕は自分の会社を儲けさせてくれる人になら、いくらでも高い給料を払っても構わないと考えている。1億円の利益を出してくれる人には、5千万円払っても高すぎるとは思わない。逆に、利益を出してくれない人には1円も払いたくはない。
でも仕事にはいろいろあるから、商品をたくさん売る人だけが利益を出しているというわけではない。その営業の人を支える事務をしたり、宣伝をしたり会計をしたりと、チームで役割分担をしていろんなことをやっている。そういう、間接的なことも含めて「役に立ってくれている」人には喜んでお金を払いたい。
「会社の利益を出すためにすごく役に立ってくれていて、かつ代わりの人を雇おうと思ってもなかなか見つからない」となると、そういう人の給料は高くなる。
日本の会社ではまだ年功序列制といって、会社に属する年数が長い人の給料が高くなるところがある。僕も社員の年齢が高くなって家族を養っているなら、少しは給料を高くしてあげないと大変だろうなとは思う。でも、ただ長くいるだけのことが給料を上げる理由にはならないと考えている。基本的にはその人の経験に価値があると思えば、高い給料を払うということだ。
■フリーターはお勧めできない理由
雇われる側の目線に戻ろう。人に雇われて働くというのは、自分の時間を切り売りするということだ。同じ時間を売るなら、できるだけ高く売ったほうがよい。
君は自分の時間を、いくらで売るだろうか。会社員として長く過ごすつもりなら、生涯を通じていくら稼ぐかという長期的な視点が一つのポイントになってくる。最初は給料が低くても、後半で高くなることが期待できる業界もあるからだ。
その意味では、学生時代のアルバイトのような仕事を、社会人になっても続けることは、基本は勧められない。最低賃金に近い金額で、誰にでもできる仕事を続けても、キャリアを積んで高い給料がもらえるようになるとは思えないからだ。キャリアという言葉は聞いたことがあるだろうけど、簡単にいえば仕事で得た経験で、それも今後に役立ちそうなものとなる。
最終的には、給料も含めて納得できる、自分に合った仕事を見つけるとよいだろう。給料は少し低くても、職場の人間関係がよいとか、大きなストレスを感じずに働けるということに価値を見出すのであれば、そこに注目するのも悪くない。給料はもっとほしいけど成長できると感じる仕事なら、それも魅力的だろう。
■学生時代に起業に挑戦してみる価値
どんな仕事で、いくらで自分の時間を売るか。これは、その次のキャリアを見据えながら、常に考え続けるだけの価値があるテーマとなる。
学生時代はキャリアがあるわけではないから、アルバイトもいろんな職業が選べるようにはならないだろうけど、なるべくなら今後の自分に役立ちそうなものを選ぶといい。
給料も得られるものもそんなに期待できないのなら、学生時代であっても何か他のことに没頭するのが得策だと僕は考える。スポーツに打ち込んだり、難関資格の一つでも取ったりするほうがいいかもしれない。
起業はもっとも有効な経験だろう。起業というと、ハードルが高いように感じてしまうかもしれない。でも今は、学生でも起業はそんなに珍しいことではない。小学生や中学生でも、起業している子がいるくらいだ。若いうちの失敗は、ダメージが少ないどころか人生の糧となるから、挑戦してみる価値は大いにある。
■「ベストな就職先」は自分で探すしかない
「なぜ大人はどの会社に入ったらよいのかを、教えてくれないのか」
これは僕が学生のときに感じていた不満だ。
この世界はゲームみたいなものだと感じていたし(これは今でもそうだけど)、どこかに攻略法があるのではないかと思ってそれを探していた。
だが、ついに見つからなかった。そこかしこにヒントは散りばめられているものの、人生というゲームは、自分で試行錯誤しながら攻略するしかないんだ。
僕はサラリーマン時代、金融機関で財務分析を仕事にしていたこともある。会社にお金を貸すにあたって、返す能力があるかどうかを、その会社の過去の決算書などを調べて判断する仕事だ。お金を返してもらうのは何年も先だから、過去の実績だけではなくて、将来性も判断する必要がある。この会社はよい、こっちの会社は悪い、なんて偉そうに判断していたものだ。でも今、白状する。あの頃の僕は、何にもわかっていなかった。

■就職できるのは結局、1社だけ
この先、君が就職をするなら、将来性のある会社がよいだろうとは思う。ここ最近の売上や利益よりも、向こう何十年伸びる業界で、勝ち続ける会社がよい。その会社が小さいうちに入社しておいて、大きくなる頃には部下がたくさんいる、それが理想だろう。
だがこの戦略には、一つ問題がある。将来のことは誰にも予想できないんだ。さっきも書いたけど、どの業界が伸びるか、どの会社が勝ち残るか、そんなことは実のところ全くわからない。予想をしても、ちょっと外す程度で済むこともあるけど、そんなレベルじゃないことばかり。全くわからないんだ。
これが投資だったら、よさそうないくつかの業界の、いくつもの会社に分散して投資をしておけば、その中のどれかが大当たりになる可能性はかなり高い。
しかし就職できるのは1社しかないので、これを確実に当てるなんてことは誰にもできない。僕が今、どこか特定の会社のあらゆる情報を入手して判断しても、予想はまず当たらないだろう。
■勢いのあるスタートアップより大企業がいい
だから、これから成長するであろう会社に入るというのはよさそうな戦略に見えるが、実現の可能性に期待しないほうがいい。
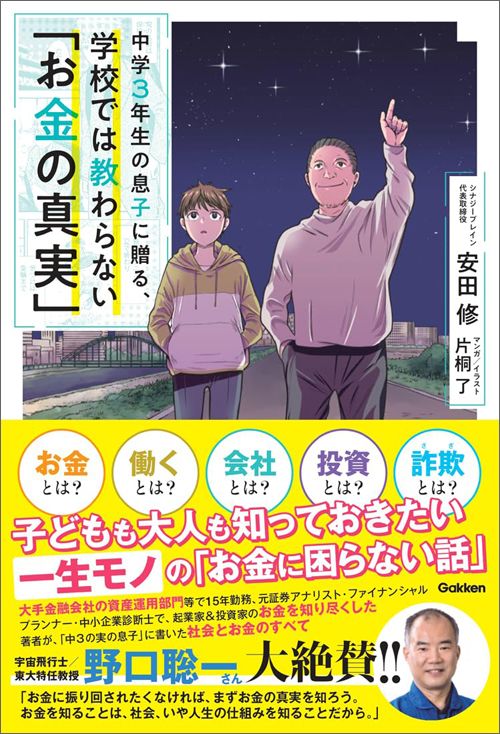
若いうちは、会社を判断する自分の観察力や分析力に自信があるので、「この会社は絶対伸びる!」と考えてしまいがちだが、その感覚はほぼ確実に、間違いだ。
実際にその会社が伸びたとしても、それはとても運がよかったというだけのことで、正しい予想ができているわけではない。
若いうちは特に、スタートアップ企業への就職は魅力的に感じるかもしれない。ただ、大学を卒業して最初(新卒)の就職先としては、意外に聞こえるかもしれないけど、大企業をお勧めする。理由は以下の通りだ。
・特定のスタートアップ企業が成功するかは、予想できない
・スタートアップから大企業への転職はなかなかできない
・大企業からスタートアップに転職すると重宝される
・スタートアップでは早くから仕事を任されるが、得られる経験は実は誰でもできることが多い
・大企業では重要な仕事を任されるまでに時間がかかるが、仕事の規模は大きく、得られる経験が実は大きい
あくまで新卒で入る1社目としてはという話で、正解だと言い切るほど強い根拠はない。一般的にはこういう感覚の大人が多いという程度のことで、参考までに知っておいてほしい。
----------
起業コンサルタント
1976年北海道生まれ、北海道大学経済学部卒。大学卒業後、日本生命入社。15年勤務を経て、株式会社シナジーブレインを設立、代表取締役。会員3000人超のコミュニティ・プラットフォーム「信用の器フラスコ」代表。フラスコノート会を主催、「フラスコビジネスアカデミー」「ダーウィン」など多数のコミュニティの立ち上げ、運営に関与。中小企業診断士・証券アナリストなど難関資格にも多数合格。著書に『書けば理想は実現できる 自分を変えるノート術』(明日香出版社)、『仕事と勉強にすぐに役立つ「ノート術」大全』(日本実業出版社)、『お金が増えるノート術』(幻冬舎)、『新しい副業のかたち』『新しい起業のかたち』(以上、MdN)などがある。
----------
(起業コンサルタント 安田 修)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「本気で言うてんの? みんな働いてんねんで」5浪目に突入した息子(33)に年収180万家庭の母親が言い放った一言《地方×底辺校×貧困家庭の三重苦》
文春オンライン / 2024年7月14日 11時0分
-
インフレでお金の価値が下がってもどこ吹く風…お金持ちがダメージを受けない理由<br /><br />
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月13日 10時15分
-
新卒の時に知っておきたかった…「それってやる意味あるんですか?」が口癖の人が「最終的には損をする」これだけの理由<br /><br />
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月9日 11時15分
-
給与だけではない!外国人社員が離職しない秘訣 公私問わない関係づくりで安定した就労環境を
東洋経済オンライン / 2024年7月6日 9時0分
-
「奨学金500万円」それでも母が大学進学させた結果 「うちは中流よりは下」と思ってた子どものその後
東洋経済オンライン / 2024年7月4日 11時30分
ランキング
-
1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分
-
2電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で
共同通信 / 2024年7月18日 21時35分
-
3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り
共同通信 / 2024年7月18日 11時58分
-
4「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収
ロイター / 2024年7月18日 8時34分
-
5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵
プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











