わが子に「むち打ち」をためらう人は愛が足りない…信者を虐待に駆り立てる「エホバの証人」のおそろしい教え
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 17時15分
※本稿は、島田裕巳『日本の10大カルト』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
■「エホバの証人」の信者だった親が子どもの輸血を拒否
この集団のことが社会的に大きな話題になったのは、1985年に起こった、「輸血拒否事件」を通してだった。
1985年6月、川崎市で交通事故にあった小学校5年生の男児に対して、エホバの証人の信者だった両親が輸血を拒否し、男児が死亡する事件が起こった。これによって、輸血拒否の是非が問われたのだった。
この事件については、ノンフィクション・ライターの大泉実成が『説得 エホバの証人と輸血拒否事件』(現代書館、後に講談社文庫)という本を書いている。
これをもとに1993年にはビートたけし主演でテレビドラマ『説得』が作られている。このドラマは平成5年度文化庁芸術祭芸術作品賞を受賞しており、事件の複雑さを世間に印象づけることとなった。実際、この事件以降、医学界は輸血拒否に直面したときの問題に苦慮するようになる。
2000年には、輸血をしないで不測の事態が起こったとき病院側の責任は免責するという同意書に患者が署名していたにもかかわらず、患者の生命に危険が生じたときには輸血をするという方針で手術に臨んだ医師が、その方針を患者に説明しないまま輸血を行ったとして損害賠償を請求され、それが最高裁で認められるという出来事も起こった。信教の自由が優先されたのだ。
■なぜ輸血を拒否するのか
その理由は聖書に求められる。旧約聖書の「創世記」9章4節には、「生きている動く生き物はすべてあなた方の食物としてよい。……ただし、その魂つまりその血を伴う肉を食べてはならない」(『新世界訳聖書』)とある。
新約聖書の「使徒の活動」(一般には「使徒行伝」あるいは「使徒言行録」)15章20節にも、「偶像によって汚された物と性的不道徳と絞め殺された動物と血を避けるよう書き送ることです」とある。
旧約聖書は、もともとはユダヤ教の聖典で、そこでは、信者が守るべきさまざまな律法が示されている。そのなかには食物規定があり、豚などの動物を食べてはならないとされている。これをユダヤ教徒やイスラム教徒が守ってきたことはよく知られている。血を食べてはならないという神のことばも、こうした食物規定に含まれるわけだが、通常は動物の血を飲むことを戒めたものと解釈されている。
ところが、エホバの証人では、それを、世間の目から見れば拡大解釈し、他人の血を体内に取り込む輸血についても血を食べる行為としてとらえている。しかし、手術を行うには輸血は不可欠である。輸血を拒否することで、エホバの信者は亡くなる可能性がある。それは、エホバの信者の子どもについても言える。
■武道、国家、選挙も拒否
親が輸血を拒否したことで、実際に子どもが亡くなった事例があるわけだが、なぜ親は、信仰に従うことで子どもの命を犠牲にしてしまうのだろうか。信者ではない一般の人間からすれば、そこに疑問を感じる。
ただ、そこには信教の自由の問題がかかわってくる。最高裁での判決もあり、苦慮した医学界は、それ以降、輸血拒否に対するガイドラインを設定せざるを得なくなる。18歳以上の場合には、本人の意思が優先され、拒否する場合には輸血は行わず、無輸血治療などに努力する。
18歳以下でも15歳以上であり、患者本人が輸血拒否をしている場合には、18歳以上と同じに扱う。ただし、15歳未満の場合には、信者の親が輸血を拒否しても、輸血を行うといったものである(医師会や病院では、これについて細かな規定を定めており、詳しくはそうしたものを参照)。
注目されるのは、エホバの証人が拒否するのは輸血だけではないことである。戦前の灯台社で実行に移された兵役拒否もその一つになるが、格闘技を行わない、国旗への敬礼や国歌斉唱はしない、選挙への立候補や投票など政治に参加しないといったことも定められている。学校に通う生徒が生徒会の役員に立候補することも禁じられている。
■信仰を貫き通すことが達成感につながる
格闘技については、高等専門学校で問題が起きた。
1990年に神戸市立工業高等専門学校に入学した学生のなかにエホバの証人の信者が5人いて、彼らは剣道の授業の受講を拒否した。
イザヤ書2章4節に「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いを学ばない」とあるからである。
そのなかに進級できず、退学になった学生がいて、彼らは学校側の進級拒否、退学処分は不当であると裁判に訴えた。一審では、原告となった元学生の訴えは棄却されたが、高裁と最高裁では訴えが認められた。他の学校では代替措置が講じられており、それを認めないのは、学校の側の裁量権の範囲を超えた違法なものだというのである。
こうして、憲法で保障された信教の自由により、輸血拒否にしても武道の授業の拒否についても、エホバの証人の側の主張が認められた。社会が求めてくることについて、信仰にもとづいて拒否することは、信者にとっては試練である。輸血の場面に遭遇すれば、命がかかわっているわけで、相当に厳しい決断を必要とする。
しかし、状況が厳しいものであればあるほど、信仰を貫き通すことが、信者にとっては大きな達成感になる。そして、そうした経験を経ることで、よりいっそう信仰は強化されていくことになる。逆に言えば、教団の側は、信者の信仰を強化するために、さまざまな禁制を用意していることになる。そこに、エホバの証人の大きな特徴がある。
■子どもの尻に鞭打ちを行う
最近、エホバの証人をめぐる重大な問題として取り上げられるようになってきた鞭打ちによる体罰については、ここまで取り上げたこととは性格が違う面がある。
エホバの証人のあいだで子どもに対する鞭打ちが頻繁に行われてきたことについては、膨大な証言がある。たとえば、2022年に国会で野党が行ったヒアリングでは、元信者の女性が次のように訴えた。
「下着を取られて、お尻を出した状態で叩かれますので、皮膚も裂けて、ミミズ腫れになり、座ることやお風呂に入ることが地獄だった。同じ組織の信者同士の間で、何を使えば子どもに効率的なダメージを与えられるかの話し合いが日常的になされていた。一家庭の問題ではなく、組織的に体罰が奨励されていた。性的な羞恥心も覚えるようになり、私は毎日、いつ自殺しようかと本気で悩んでいた」(大泉実成「【エホバの証人】『パパぁ、むちしないでぇ』元信者のジャーナリストが語る『むち打ち』の衝撃実態『信者間で“子供に効率的にダメージを与える方法”が日常的に話し合われていた』」集英社オンライン、2023年3月9日)
この記事で、大泉は、『説得』を書くために取材をしていた37年前と変わらないことがくり返されていると述べている。鞭打ちについての根拠も聖書に求められている。旧約聖書の「格言の書(箴言)」13章24節には、「むちを控える人は子供を憎んでいる。子供を愛する人は懲らしめを怠らない」と述べられている。

■エホバの証人と福音派の違い
他にも、旧約聖書には随所で、同様のことが述べられている。子どもに対する「愛の鞭」は是非とも必要だというのである。エホバの証人は、聖書に述べられたことに忠実であろうとしてきた。
こうした姿勢をとるキリスト教徒は「キリスト教原理主義」と呼ばれ、アメリカの福音派に多い。福音派では、広く知られているように、進化論を学校で教えることや人工妊娠中絶に反対してきた。エホバの証人も同様の主張を持っているが、それを強く主張しない点で福音派と異なる。
それというのも、福音派は自分たちの主張を実現するために政治に積極的にかかわろうとしてきたが、エホバの証人は政治とのかかわりそのものを拒否するからである。
■一般の宗教団体とカルトをわけるもの
元信者の証言にもあったように、エホバの証人の鞭打ちは相当に激しいもので、しかも、親たちは、子どもたちにより大きなダメージを与えるための工夫さえ施している。
エホバの証人の親たちも、最初は鞭打ちをためらうであろう。ためらいがあっても、子どもに鞭を当てることで、一つの困難な課題を克服したという達成感を得ることができる。
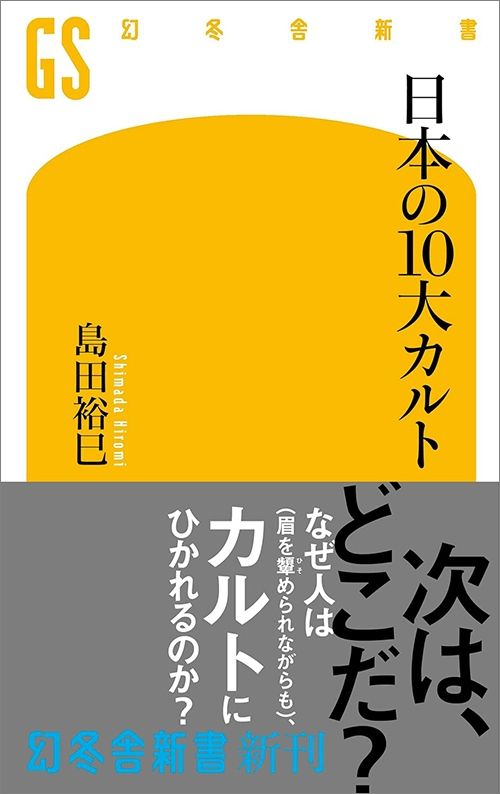
人間は達成感を求める動物でもあるが、一度それを得ると、さらに大きな達成感を得ようとして、より過激な方向に進んでいくことがある。博打にのめり込んでいくのも、そうした心理のなせるわざである。
鞭打ちは身体的な行為であり、その分、困難なことをやり遂げたという感覚をはっきりと味わうことができる。そこから親は鞭打ちにのめり込み、子どもにより打撃を与える方法を模索するようになるのだ。
カルトと言われるような集団では、こうした達成感を得られる仕組みが備えられている。そこが、カルト性を弱め、社会に定着してきた一般の宗教団体との違いであると言える。
布教活動によって仲間を増やすことも達成感につながる。問題は、達成感が、本人にとっては満足できるものであっても、その結果が他者にとって好ましいとは言えないことである。
鞭打ちでは、子どもは犠牲者になる。だが、親の側は、達成感の虜になり、子どもに鞭を打ち続ける。そして、達成感を得たことで、本人の信仰は強化されるのだ。
----------
宗教学者、作家
放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、同客員研究員を歴任。『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)、『教養としての世界宗教史』(宝島社)、『宗教別おもてなしマニュアル』(中公新書ラクレ)、『新宗教 戦後政争史』(朝日新書)など著書多数。
----------
(宗教学者、作家 島田 裕巳)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
聖書の授業、義務化通達 米オクラホマ州の教育長
共同通信 / 2024年6月28日 6時43分
-
出口の見えないイスラエルとハマスの戦い。アメリカが長年ユダヤ国家に肩入れし続ける本当の理由とは? 『聖書の同盟 アメリカはなぜユダヤ国家を支援するのか』KAWADE夢新書より6月21日発売!
PR TIMES / 2024年6月20日 10時45分
-
旧統一教会、エホバ…なぜ世間にこれだけ叩かれてもなお、惹かれる信者がいるのか……そのヒントは“カレーライス”にあった
集英社オンライン / 2024年6月6日 19時0分
-
フランスにおける「セクト」(カルト)の捉え方とは? セクト的行動を規制する法律の背景にあるフランス社会の特殊性
集英社オンライン / 2024年6月5日 19時0分
-
918人が集団自殺…「カルト」の文字が初めて新聞に踊った1978年人民寺院事件…日本では“金余り”90年代に「オウム、統一教会、幸福の科学」らが躍進
集英社オンライン / 2024年6月4日 19時0分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












