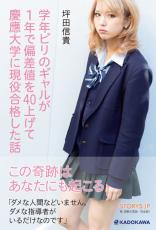「少子化で日本が滅びる」は絵空事ではない…「ビリギャル」の2回目の離婚がネット民の関心を集めた理由
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 8時15分
■芸能人でもスポーツ選手でもないのに…
ベストセラーとして知られ、映画化もされた『学年ビリのギャルが1 年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(KADOKAWA、通称ビリギャル)のモデル・小林さやか氏が離婚を発表した。
小林氏は5月12日、自身のXとnoteで離婚について綴(つづ)っている。それを報じたオリコンニュースの記事(Yahoo!ニュース配信)には、29日時点で1420ものコメントがつき、芸能人でもスポーツ選手でもない人物の動向に関する記事としては異例の盛り上がりを見せた。なぜ、ここまで多くの人の関心を集めるのだろうか。
私は小林氏の離婚そのものについて論じたいわけではない。理由がどうあれ、他人には窺い知れないからであり、離婚にまつわる経緯や反応のほうが興味深いからである。そして、彼女自身を含めた離婚に関する語り口が面白いからである。
小林氏は、noteへの約4000字にのぼる長文の投稿で、詳細に離婚に至る心情と事情を明らかにしている。あくまでも前向きにとらえようとする姿勢を見習いたい、と思う人も多いのだろう。あっという間に3000を超える「いいね!」がついている。彼女自身が何をどう考えようと自由であるし、それを支持する人たちがいるから、ここまで注目を集めたとみられる。
■「手を繋いで、離婚届を出しました」
注目したいのは、小林氏が離婚をこと細かに語る姿勢である。彼女は、2018年にも離婚しており、その顛末についても、ブログをはじめとして、著書『キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語』(マガジンハウス)のなかで記している。彼女にとってだけではなく、離婚は大きな人生の転機であるし、思うところや伝えたい内容はあふれるほどあろう。
何をどう語ろうと、第三者には立ち入る筋合いはないものの、彼女が元夫たちに向けた言葉づかいに、引っかかる。
たとえば、2018年の離婚では、ブログのなかで「桜満開のなか、手を繋いで、離婚届を出しました」とした上で、「いまでも良き友人としてわたしを支えてくれている」し、「彼のことは今も大好きです。ずっと死ぬまで大切な人です」と書いている。
また、『marie claire』のインタビューでは、結婚後に講演依頼が増えるなど生活が変化していく中で、「妻にはこうあってほしいという彼の思いとは違う結婚生活になっていくことに、かなり戸惑っていたと思います」と話している。
■「男性の軽視」が感じられる表現
どちらも、一見すると、別れた後も元夫をおもんぱかっている。大事な存在であり、別離は夫婦のすれ違いの結果に過ぎない。どちらが悪いわけではなく、ありがちなものなのだ、と。そうした見解ととらえられるのかもしれない。
「手を繋いで、離婚届を出」すのは、ブログでの彼女の表現によれば「こういう離婚もあるんだよ」のひとつなのだろう。夫婦生活を長く続けていても、あるいは、続けているからこそ、「手を繋いで」歩く機会がめったにない(私のような)夫婦もいる。それに対して、離婚する際も、いや、そういう場面だからこそ、あえて「手を繋いで」いくのは、麗しいと評せよう。

それでも、「手を繋いで」と(わざわざ)書く必要は、どこにあるのだろうか。円満さを強調したいのだとしても、その直後に「いつも誰よりもわたしの気持ちを理解して、支えてくれた彼に、いっぱい感謝しています」と褒めるのなら、なぜ別れるのだろう。そこまでの感情があるのなら、一緒にいれば良いのではないか。
いや、そう難癖をつけたいわけではない。
彼女のこうした表現は、今回の離婚の報告にも通じており、そこに元夫たちへの視線、ひいては、男性の軽視を感じてしまうのである。
■配慮しているようで、ばっさりと切り捨てている
今回の離婚報告で、私が最も違和感を覚えたのは、次のくだりである。
この文章での彼=元夫が、本当にどう思っていたか、は、他人にはわからない。それよりも、「住み慣れた環境」や「憧れだったニューヨーク生活」といったところからは、思いやりよりも、憐れみが感じられるのではないか。自分(小林氏)は、「住み慣れ」ていないにもかかわらず、ニューヨークに慣れて、世界のトップ大学=コロンビア大学で修士課程を終え、当地での生活を続ける。その傍らで、16年勤めた会社を辞めて同行してきた元夫は、2年で日本に戻る。
「ニューヨークにいる彼」は、「彼の能力を生かした仕事」はできなかったし、これからもできない。その判断は、「彼」に配慮しているようで、その実、ばっさりと切り捨てているのではないか。
■noteに書かれた、元夫とのニューヨーク生活
2年前の移住直後には、「現在、ニューヨークは金曜日の夕方である。夫が、夕飯の支度をしてくれている」「毎週末ニューヨークを夫と探検するのが楽しみ」とnoteに書いていた。元夫が夕食づくりの当番だったのかもしれない。また、2023年元日の投稿では、次のように報告している。
ただし、小林氏のnoteには、これ以降、元夫についての近況はほとんど見られない。2023年の夏に日本に一時帰国したらしいとは伝わってくるものの、離婚報告で推測していた「彼の気持ちもいろいろ変わった部分もあったようだ」の根拠となるような痕跡は、まったくない。

小林氏は、みるみるうちに人脈を広げ、英語力を上げている、とnoteに書く。そのかたわらで、元夫は、何をして、どんな「変わった部分もあった」のだろうか。こうした言葉づかいの端々から上から目線が滲み出ている。
■「上昇婚」を望む日本人女性
乱暴に言えば、夫は刺身のツマ、というか、自分の人生に彩を添える脇役であり、さらには夕ご飯を作ってくれる家政婦と見ているのではないか。
私自身、自宅で家族の夕ご飯を用意しているから、被害妄想を膨らませているだけなのかもしれない。けれども、小林氏が2回離婚をし、そのいずれについても、多くの関心を集めている背景には、個人の感想では済まない、日本社会全体に通じる何かがあるのではないか。
そのひとつは、社会学者の赤川学氏がつとに指摘してきた「上昇婚」である。赤川氏は「現代ビジネス」の記事で「女性が自分より社会的地位の高い男性と結婚することを女性上昇婚」と呼び、かつての日本社会では、これが一般的だったと解説している。これに対して、「女性が自分よりも学歴や収入など社会的地位の低い男性と結婚する傾向」を「格差婚」とりわけ、「女性下降婚」という。赤川氏の示すデータによると、日本は、この「下降婚」が少ないため、「上昇婚」を望む人が多いと考えられる。
他方で、社会学者の三輪哲氏によれば、日本での「階層同類婚」、つまり、学歴と職業、それぞれが同じぐらいの人と結婚する率は減っている。女性は、自分より社会的地位が低いだけではなく、同じだとしても結婚しなくなっている。裏を返せば、「上昇婚」でないかぎりは、結婚そのものに踏み出していないのではないか。この傾向に照らすと、小林氏のケースは、どう考えれば良いのか。
■「下降婚が少ない社会では出生率が低い」という現実
「上昇婚」でなかったから、やはり満足できずに離婚した、と言いたいのではない。それよりも、彼女の離婚が耳目を集める要因と、日本社会における「下降婚の少なさ」が「同類婚の減少」に通じているところが重要なのである。
2011年時点で教育社会学者の福田亘孝氏は、「日本の少子化の要因は婚姻年齢上昇にある」という命題は実証分析では支持されない、と述べている。結婚する年齢が上がるために少子化になっている、わけではない、という。であればなおさら、そもそも結婚しなくなっているところにこそ、少子化の原因のひとつがあり、結婚しない理由として、上に挙げた「上昇婚」へのこだわりがあるのではないか。
実際、赤川氏が論じる通り、「下降婚が少ない社会では出生率が低い」という知見が得られる。日本社会は、まさしくこれに当てはまる。「下降婚」だけではなく「同類婚」も避けられており、独身時代の生活水準を保ちたい、あるいは、学歴の低い男性とは結婚したくない、と考える女性が多いと見られる。だからこそ、小林氏の離婚は、この私の記事を含めて大勢が論じたくなる話題なのではないか。
■「少子化で日本が滅びる」は絵空事ではない
ここで、「上昇婚」をあきらめるべきだ、と説教したとしても、百害あって一利なしである。「おひとりさま」が流行語になった時代は遠くなり、今や「子持ちさま」と子育て世代が揶揄される。結婚も子育ても、特権階級にみなされるほどに、生涯未婚率は高まり、少子化が進んでいる。小林氏の離婚は、そんな流れに棹(さお)さす出来事だった。
合計特殊出生率が1.0を切っている韓国や台湾ほどではないものの、このままのペースで少子化が進めば、やがて日本が滅びる、そんな懸念も絵空事ではない。いまさら「産めよ、増やせよ、国のため」などというスローガンは掲げられないし、少子化=国の消滅とストレートには結びつかないものの、それでも、「上昇婚」を好むこの国のムードを、止められない以上、すぐに歯止めはかからない。

小林氏が「上昇婚」をあきらめられないのかどうかはわからないが、少なくとも、過去2回の結婚は(小林氏の視点からは)「同類婚」か「下降婚」だったと見られる以上、現代日本の典型例ではない。そんな彼女が紡いだ言葉は、「上昇婚」をあきらめられない私たちに刺さったのである。
----------
神戸学院大学現代社会学部 准教授
1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(社会情報学)。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』(青土社)、『「平成」論』(青弓社)、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』(青弓社)など。共著(分担執筆)として、『運動としての大衆文化:協働・ファン・文化工作』(大塚英志編、水声社)、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』(楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房)などがある。
----------
(神戸学院大学現代社会学部 准教授 鈴木 洋仁)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
お母さん、やめてくれ!箱入り娘の60代母「息子に代わり結婚相手を探す」大暴走に、年収800万円の息子本人が悲痛の訴え【令和の結婚事情】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月31日 17時15分
-
「結婚した夫婦から生まれる子どもが少数派になっている国も…」日本の少子化を考える、意外なヒントは“婚外子”にあった
文春オンライン / 2024年7月31日 17時0分
-
《円満離婚なんてない》田中美佐子、格差婚から“仮面夫婦”と言われて29年「生じていた3年前の異変」「突然消えた結婚指輪」元夫は女性ファンとラブホデート
NEWSポストセブン / 2024年7月22日 16時15分
-
「本当は何もない人では」京大の先輩・ジョーカー議員が “一夫多妻” 発言の石丸伸二氏を分析
週刊女性PRIME / 2024年7月19日 6時0分
-
「育休はなくす、その代わり……」 子なし社員への「不公平対策」が生んだ、予想外の結果
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月4日 6時35分
ランキング
-
1「モテすぎて坊主にした」SNSで話題の女性。「無駄に性愛を向けられることは9割減りました」
日刊SPA! / 2024年8月2日 15時53分
-
2免許を取ったばかりなのですが、「初心者マーク」をつけるのが恥ずかしいです。 貼らなくてもいいのでしょうか?
くるまのニュース / 2024年8月2日 19時10分
-
3東京株式市場の大幅続落に投資家が悲鳴! SNS上で名指し《植田ショックを招いた3悪人》の名前
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年8月2日 16時58分
-
4旅行に行くなら持っておきたい100円ショップの便利グッズ6選
MONEYPLUS / 2024年8月2日 18時0分
-
5女性から自然と「好かれる/嫌われる男性」に共通している“6つの特徴”
日刊SPA! / 2024年7月28日 8時52分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください