寝ていた父親の顔面めがけて木製踏み台を投げ、鼻は折れ血が噴出…貧乏家庭が直面した"死の病と憎悪と絶望"
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 10時16分
■父親の強制送還
現在関東地方在住の知多翔平さん(仮名・30代)が中学生になった頃、高校生の兄は、40代後半の飲んだくれの父親に暴力を振るうようになっていた。関係もすっかり冷え込み、険悪化した両親もしょっちゅう取っ組み合いのケンカをしていた。
そうした場に居合わせた知多さんは、非力な母親(43)の味方をする。酔っ払って暴れている父親から母親を引きはがすために、しかたなく殴って黙らせることもあった。
「『酒を飲まないでくれ』『学校だってあるんだ。寝させてくれ』と言葉で伝えても、父は何も変わってくれない。暴力で父をおとなしくさせるのは、早く楽で、確実な方法でした。でも僕が暴力を振るったのは、『効率化』だけが目的ではありません。うちが貧乏なのも、母が大変なのも、夜に静かに眠れないのも、全部『身勝手でやりたい放題な父』のせいだと思い、父のことが憎くて堪らなかったんです」
しかし知多さんは、父親を憎めば憎むほど、かつて父親を好きだった自分が思い返され、罪悪感に苦しんだ。その罪悪感を打ち消すように、「父は僕にもっとひどいことをしているんだ! だから殴られて当然だ!」と暴力を正当化しようとする自分がいた。
そんなある日、知多さんにとっては特に手応えのない一撃に、父親が崩れ落ちた。
「人っていうのは、こんなに簡単に壊れてしまうのかと思い、暴力を振るうことが怖くなりました……」
それ以降、知多さんが父親に暴力を振るうことはなくなったが、3つ上の高校生の兄の暴力は勢いを増していた。
最初は兄も知多さんと同じ、夫婦喧嘩の仲裁をしようとしていた。しかし気付けば兄は、「殺してしまうのではないか?」というほどの激しい暴力を振るうようになっていたのだ。
ある晩、事件は起こった。珍しく父親は静かに布団で寝ていた。その無防備な父親の顔面めがけて、兄は木製の踏み台を投げつけたのだ。父の鼻は折れ、鼻血が吹き出した。寝ていた父親は何が起こったかわからない様子でうめいていた。知多さんは絶句したが、兄は無表情で自室に去っていった。
それでも父親は、病院へ行かなかった。それまでことあるごとに母親に離婚を勧めてきた知多さんと兄だったが、ここでようやく母親が動いた。
「『このままでは兄は父を殺しかねない』『息子を人殺しにしたくない』と思ったのでしょう。母はようやく父と離婚し、父は実家へ“強制送還”されました」
知多さんが中学2年の夏だった。
■歪な家族
離婚したものの、自身の母親(知多さんにとって父方の祖母)と折り合いが悪かった父親は、たびたび「遊びに来た」という“てい”で知多さんの家にやって来て、勝手に居続ける。当然のことながら、兄は父親に暴行を加え、それが激化すると、数週間か数カ月後には父親は実家へ帰る。この繰り返しだった。
同じ頃、兄のターゲットは母親に移行した。暴力ではなく、お金を無心するようになったのだ。
兄は名前が書ければ入れるような高校を卒業し、大学に進学。一人暮らしを始めたが、すぐに中退。新聞配達員として働き始める。だが兄は、自分が稼いだお金は使わなかった。服やゲームを買っていたが、その費用はすべて母親に出させた。
「兄は高校入学時に母から携帯電話を買い与えられましたが、兄が自分で携帯電話料金を払ったことはありません。でも僕は、携帯電話を自分のお金で購入し、携帯電話料金も自分で払っていましたし、高校のお昼代も僕は自分で払っていました。そのことに不平等を感じ、不満を持っていました」
兄と同じ高校に入学した知多さんは、入学前から興味があった器械体操部に入部。「部活を頑張ろう」と思っていたが、入部した器械体操部には先輩部員がおらず、1年のみ。しかもやる気がある部員はいない。部活に失望した知多さんは、アルバイトにのめり込んでいった。
やがて高校2年生になると、母親からは「高校くらいは卒業して」と言われたが、兄からは「中途半端はやめろ」と言われ、知多さんはコンビニバイトを優先し、中退。
18歳になる頃、母親から「一人暮らしをしない?」と持ちかけられる。
何がきっかけかはわからないが、当時兄は心療内科か精神科に通院していた。知多さんが知る限りで、強迫性障害、睡眠障害、統合失調症の診断がおり、障害者手帳を申請し、障害年金を受給していたようだ。
もともと兄の一人暮らしの部屋の家賃、光熱費、携帯電話料金は母親が持ち、その他の兄の生活費は兄が持つという約束での一人暮らしだった。だが、徐々に全て母親持ちということになっていったうえ、兄の病状が悪化し、一人暮らしができる状態ではなくなってきていたのだ。
少ない母親の収入はほとんど兄に使われ、母親と知多さんが暮らす賃貸アパートの家賃や光熱費も滞り始める。そうなると知多さんが払うより他なく、今度は母親が知多さんにお金の無心をするようになっていく。

結局、兄が実家に戻り、兄が一人暮らししていたアパートに知多さんが住むこととなった。それでも、母親から知多さんへの金の無心は続いた。
■知多家のタブー
筆者は家庭にタブーが生まれるとき、「短絡的思考」「断絶・孤立」「羞恥心」の3つが揃うと考えている。
母親は自分の兄に「優しくて堅実な男だ」と勧められたからといって、よく知りもしない父親との結婚を選んだ。一方父親は、結婚直後に無計画に退職。その後も、家族に相談も報告もなく仕事を辞めてしまい、働きに行こうとしなかった。
知多さんの両親はどちらも場当たり的で極めて短絡的志向の持ち主だったといえる。そして、北海道出身で関東に出てきた両親は、社会から孤立していた。実際、母親は兄を出産した頃、孤独さに苛(さいな)まれるあまり「我が子を愛せなかった」と話している。コミュニケーション下手な父親も社会から孤立し、酒に溺れていった。
知多家の悲劇にはルーツがある。
父方の祖父は、知多さんが中学生の頃に亡くなった。その知らせを聞いた父親は、泣きながらお酒をあおっていたという。
父親は自分の父親が好きだったのだろう。だが、父方の祖母は支配的で過干渉な人だったらしく、父親は幼い頃からプレッシャーを感じながら育ったため、大人になってからも折り合いが悪かったようだ。
父方の祖父は、支配的で過干渉な妻(父方の祖母)を静止できなかった。知多さんの父親は、幼い頃からそんな母親(父方の祖母)から与えられるプレッシャーで萎縮し、自分に自身が持てず、コミュニケーションが上手くとれない大人に成長したのかもしれない。
一方、母方の祖父は大の酒好きで、酒癖が悪かった。漁師だったが、他界するずいぶん前から働いていなかったため、母方の祖母が家計を支えた。母親の兄は、早くに亡くなった父親に代わり家の中で威張り、次兄や母親、弟はみな、支配的で独善的な長兄を良く思っていなかったらしい。母方の祖母も次兄も母親も弟も、長兄の顔色を伺い、言いなりになっていたようだ。
母方の祖父母の家庭は、知多さんが育った家庭そのものだ。知多さんの母親は、酒好きで酒癖の悪い自分の父親と、懸命に家計を支える母親の姿を見て育ったため、我が家が同じ状態になっても“普通”だと思っていたのだろう。
さらに、母親の長兄は、知多さんの兄に似ている部分も多い。知多さんは「母方の祖母はおっとりした優しい人」という印象だと語るが、それはバイアスがかかっている可能性もある。もしかしたら母方の祖母は、酒癖の悪い父親を持った子どもたちへの罪悪感から、子どもたちを甘やかし、その罪から目を背けるために「家計を支える」ことに没頭してきた人なのかもしれない。
こうしてみると、知多さんの両親は、2人とも共依存体質だった可能性が高い。父親は自分の父親に。母親は自分の長兄に依存していたが、結婚し、慣れない土地で暮らすうち、体質も影響し、お互いに依存するようになった。それは知多さんの兄にも受け継がれているように感じる。
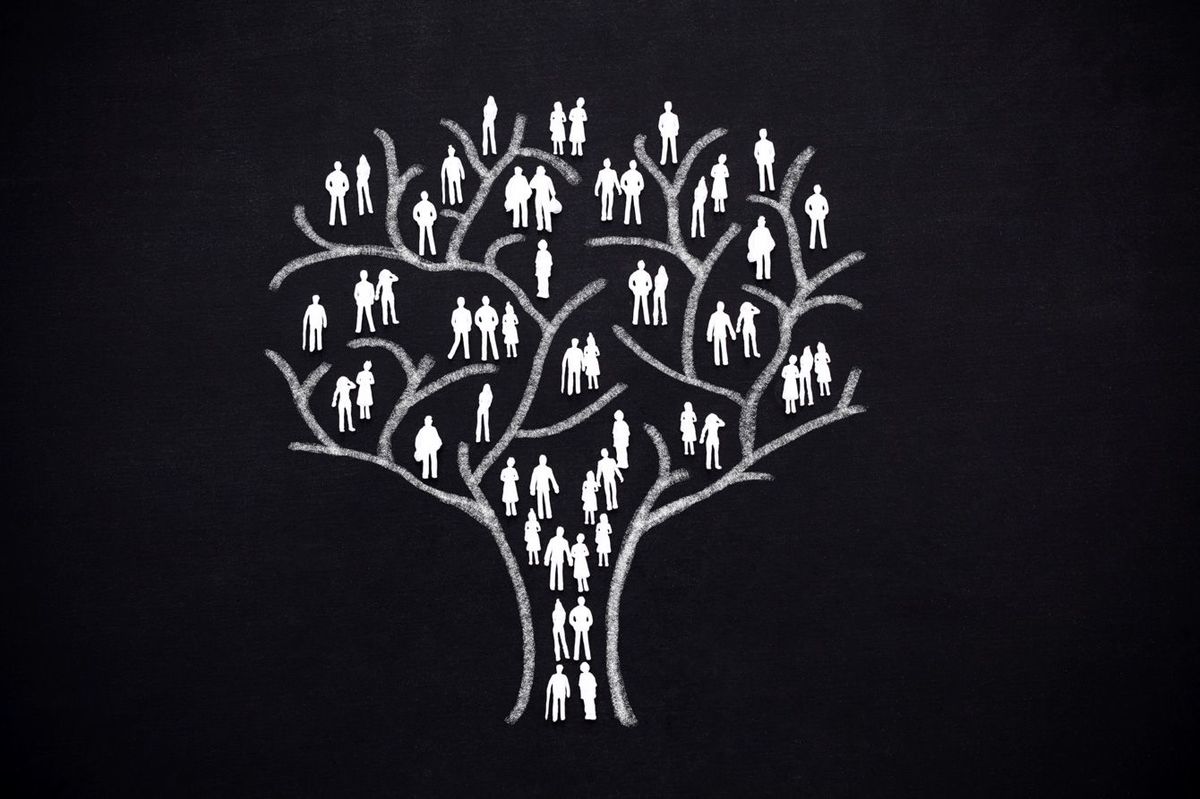
知多さんは、そうした「家族」を心の底から嫌悪した。
■呪いの言葉
現在知多さんは、両親とも兄とも絶縁し、10年以上会っていない。
「10年ほど前に母方の祖母の法事があり、家族の顔を見たのはその時が最後です。父は7年前に咽頭がんで亡くなったと母から聞き、『やっと楽になれて良かったね』とは思いましたが、葬儀には行きませんでした。現在の母は生きているのか他界しているのかすら知りません。兄はたぶん生きています」
知多さんは6年前、住民票閲覧制限の手続きをした。自分の所在地を知られたくなかった。
「父はアルコール依存症と鬱だったのだと思います。兄は子どもの頃は暴君で、現在はガッツリと心を病み、ひきこもっています。我が家で“好き放題できる権利”を賭けた“イス取りゲーム”に負けた僕は、良い子になるしかなかった。何より、母からの“呪いの言葉”によって良い子になるよう支配されていました。母は幼少期に兄を愛せなかった自分の罪悪感から兄の言いなりになり、兄と僕がケンカをすると、『あなたは優しいから』『あなたは我慢できる子だから』と言って譲ることを僕に強制し続けてきました。“呪いの言葉”というと攻撃的なものを想像する人が多いかもしれませんが、優しい“呪いの言葉”も使い方次第では、とても強力な呪いになると思います」
高校を中退後に一人暮らしを始め、コンビニで働き始めて以降、10年近く母親からの金の無心は続き、知多さんは母親のために自分が稼いだお金を渡し続けた。そして、そのお金が兄のために使われることに心は蝕まれ続けた。

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
「母にお金を渡さなければ母が苦しむ。しかし僕が稼いだ金は、僕が憎んでいる兄に渡される。『どっちに転んでも痛い目しか見ない選択を迫られる状況』を、心理用語で『ダブルバインド』『二重拘束』というらしいのですが、何より僕が苦しかったのは、母は僕が兄に暴力を振るわれてきたことを知っていたのに、僕ではなく兄を守り続けたことでした」
知多さんが25歳、母親が55歳の頃、兄からのお金の無心に耐えられなくなった母親は、知多さんに助けを求めてきた。知多さんは母親を信頼できる知人の家に匿(かくま)い、「絶対に兄さんに連絡をしないで」と言い聞かせ、自ら兄と対峙。母親に依存し、全く生活力のない兄に家事を教え始めた。
ところが1週間ほど経ち、兄が家事を覚え始めた頃、母親は突然兄のもとに戻っていた。知多さんは絶望した。
■「家庭のタブー」から逃れられる社会
「僕視点で母を単体で見れば、そう悪い母親ではなかったんじゃないかと思っています。母にも原因はあるけれど、父や兄が強過ぎた。あの家庭の中で、一番苦労したのは母だということを分かっていました。だから苦しんだ。でも、母がどれだけ大変であっても、僕だって『助けて!』『守って!』という気持ちがありました。もちろん今さら、『助けろ!』『守れ!』などと言うつもりはありません。『頑張ったよね。助けてほしかったよね』と、自分の気持ちを受け入れることが大切だと気付いてから、少しずつ心の傷が癒えてきました」
知多さんは20代後半の頃、睡眠障害に悩まされてコンビニを辞めた。病院にはかからず、代わりに自分と向き合う作業に取り掛かった。「その日の感情が上下した出来事」をメモ書きし始めると、自分自身に興味が湧いてきて、過去の記憶の書き起こしも始めた。

兄にされた酷いことを思い出すのは嘔気がするほどつらかったが、自分なりに掘り下げ、過去の自分と現在の自分と対話していくうちに、いつしか認知行動療法のような形になり、問題を解決する力に育っていた。
「今はもう、家族への憎しみはかなり薄れています。ですが、仮に会う機会があっても会いたくはないです。聞いてみたい話はあるのですが、今の平穏を崩すくらいなら接触は避けたいです。それでも、母のことだけは嫌いになれません」
筆者はこれまで夫婦や親子間のDVが絶えない多くの家庭を取材してきた。その経験から言うならば、知多さんの母親は、兄に対する自分の罪悪感と子どもたちの教育とは切り離して考えるべきだった。それができれば、兄にも知多さんにも、もっと違った人生があったのではないか。
アルコール依存症で鬱の父親はその兆候があった段階で、本人が拒否しても家族がただちに医療機関につなげ、早急に手を打つ必要があった。
一方、兄が暴力に訴えたことは決して許されることではないが、彼も苦しんでいたことは明白。兄のみならず、知多さんも被害者だ。
では父親と母親が加害者なのかと言えば、それも違う。夫の仕事の都合で故郷から遠く離れた土地で暮らすことになり、1人で子育てに追われたうえ、夫が働かなくなるなど、困難に直面し続けた母親には、同情すべき点は多大にある。もしもそばに相談できる先、頼れる先があったら、知多家は崩壊せずにすんだかもしれない。
親とて完璧な人間などいない。2004年のイラク人質事件以降に広まり、最近では大リーガーの通訳による事件でも度々目にした「自己責任論」だが、もっと「助けて」と言いやすい社会に、また、「助けて」を言う先が見つけやすい社会にならなければ、日本はむしろ自分たちで自分たちの首を絞める“生きにくい社会”になっていく一方なのではないだろうか。
----------
ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー
愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。2023年12月に『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱い」する母親たち〜』(光文社新書)刊行。
----------
(ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「父も母も鬱病」担任教員に容姿や成績の悪さを揶揄され不登校の小3女子…40年後に"ワンオペ両親介護"の不遇
プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分
-
「母さんといることが限界だ」と涙の訴え…定年退職した父が“夫婦別居”を望んだ「切実な理由」
Finasee / 2024年7月12日 13時0分
-
月22万円の年金では足りず老後破綻の危機…お金でしか問題を解決できない両親の自業自得な末路
Finasee / 2024年7月12日 13時0分
-
「とどめ刺したのは社労士の兄」脳と心臓がやられた親4人、不登校の息子、自分も大借金…40代女性の壮絶戦記
プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時16分
-
「確実に嫌な予感」30代嫁が直面した"絶望ワンオペ"…難あり老親4人と愛息2人を"私一人で"という無謀
プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分
ランキング
-
1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」
日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分
-
3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分
-
4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃
乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分
-
51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











