伝説の投資家バフェットもこれで大金持ちになった…誰でも実践できる"バリュー投資"の基本の「き」
プレジデントオンライン / 2024年6月7日 8時15分
※本稿は、しん『電子版 謎のトレーダー「しん」の>〈株〉バリュー投資法』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
■グレアムとバフェットが心の師匠
ベンジャミン・グレアムという人の名前は聞いたことはなくても、株式投資に興味を持っている人であれば、アメリカの投資家であるウォーレン・バフェットの名前は聞いたり、みたりしたことがありますよね。
実は、バリュー投資はベンジャミン・グレアムが始めた投資方法で、ウォーレン・バフェットはグレアムを師匠として勉強し、バークシャー・ハサウェイ社を買収し、その会社をベースにしていろんな会社の株式を買い、日本円で4兆円を超す個人資産を築き上げました。株の世界では立志伝中の人物です。
グレアムはバリュー投資のバイブルといわれる『賢明な投資家』『賢明な投資家・財務諸表編』『証券分析』などの本を出しています。一方、バフェットは自分で書いた本こそありませんが、多くの人がバフェットの人となり、投資手法について書いていて、あまたの本が出版されています。この2人の本の影響を受けてバリュー投資をはじめたので、先方は私のことを知りませんが、私は勝手におふたりを「師匠」と思っています。
■本当の価値より安い株をみつけて投資する
バリュー投資というのは、ある会社の本当の価値よりも低い株価の銘柄をみつけてそれに投資をするという投資方法です。
もしも、私があなたに「私の1万円とあなたの2万円を交換してくれませんか」といったら、交換してくれますか。自分が明らかに1万円損すると知っていて、交換するはずはありませんよね。しかし、株式市場では2万円の価値のある株式を1万円で売ってくれるというような、信じられないことが起こるのです。
■会社の「解散価値」に着目する
『電子版 謎のトレーダー「しん」の>〈株〉バリュー投資法』では第3章から詳しく説明していますが、会社は現金とか預金、土地、建物などの資産を持っています。資産のなかで現金や預金、有価証券のように、現金化しやすいものを流動資産といいます。会社はこうした資産がある一方で負債(借金)もあります。負債のなかでも支払手形とか買掛金、1年以内に返さなければならない借金などを流動負債、1年以内に返さなくてもよい借金を固定負債といいます。
そして、流動資産から流動負債を差し引いたものを純流動資産といって、運転資金がどれくらいあるのかがわかります。後ほど詳しく話しますが、流動資産から流動負債と固定負債を差し引いたものが会社の大まかな「解散価値」をあらわします。これを「正味流動資産」ということもあります。前節で話した会社が解散したときの「価値」がこれです。
解散価値は1株あたり2万円の価値があるのに、株式市場では株価は1万円という会社があります。これが株式市場では2万円の価値のある株式を1万円で売ってくれるという意味です。こうした会社の株式をみつけて、それを買うのがバリュー投資の1つのやり方です。

■正味流動資産と株価が3分の2以上離れていること
これは私が考えついたものではなくて、グレアムがいっていることです。師匠はまた、会社の解散価値が300万円だとしたら、その会社を丸ごと買うのに200万円くらいしかかからないような会社の株式を買いなさいといっています。
具体的にいうと、1株あたりの正味流動資産と株価が少なくとも3分の2以上離れているような銘柄に分散投資をすれば、平均年利回り20%くらいの利益は得られるというのです。
私もこの考えに沿うような割安株をみつけて投資してきました。
2002年のことです。生化学工業という製薬会社があり、これが当時1株800円ほどで売られていました。このときに、生化学工業はいくらの正味流動資産を持っていたか調べると、おおよそ1株1200円の現金と現金に近い資産を持っていたのです。グレアムのいう正味流動資産(解散価値)と株価が3分の2ほど離れていたわけです。
■よい経営をしているのに過小評価されている会社
これはバリュー投資にぴったりの銘柄だと判断して1000株を購入しました。投資金額は82万円ですが、買った時点で120万円の現金を手に入れたことと同じです。しかも、生化学工業は赤字になったこともなく、利益もきちんと出し、配当金も払っていました。あとは投資家がきちんと評価してくれるのを待つばかりでした。
生化学工業の株価は思ったよりも早く動きました。買ってから2週間くらいたって、すぐに1株1200円くらいに上昇しました。やっと1株の評価が1株あたりの正味流動資産と同じ評価になったのです。これからは収益性なども評価されることになるはずなので、保有をし続けました。そして、買ってから1年以上たち1680円で売ったので、2倍以上の利益を得ることができました。
買ったのちに少し上がったからといって売っていたら、これだけの利益を上げていたかどうかわかりません。割安株をじっくりと持っていたため、買値の2倍で売り抜けることができたことには満足しています。
この話にはもう1つのポイントがありました。この間、市場は20%近く下げていたのです。それにもかかわらず、明らかに割安だという銘柄を買って2倍以上の利益を上げたわけで、投資したらじっくりと値上がりを待つバリュー投資に自信を持ちました。
■バリュー投資における「安全域」という考え方
バリュー投資では安全域という考え方があります。『電子版 謎のトレーダー「しん」の>〈株〉バリュー投資法』第4章で詳しく説明していますが、次のように理解してください。

大事な商談があって東京駅を朝9時にでる新幹線に乗らなければならないとき、あなたは何分前に駅に着くように家を出ますか。9時だから9時1分前に着けばいいという人もいるでしょうけど、商談に間に合わなくなって大損をするリスクを考えたら、少なくとも10分とか15分前には着くようにしようと思いますよね。
要するに、ギリギリではなくて余裕を持って新幹線に確実に乗れるように努力をするはずです。その時間が「安全域」になるのです。
割安株に投資するときも同じです。生化学工業の場合は、1株あたり最低1200円の価値がある株式が800円で売られていたわけです。この場合、1200円と800円との差が安全域にあたるわけです。
この安全域が大きい銘柄をみつけることができれば、利益を得られる可能性もまた、大きいということができます。
■収益面から「割安」な銘柄を見つける方法
これまでは資産の面から安全域を見てきましたが、収益面からも安全域という考えは、当然あります。
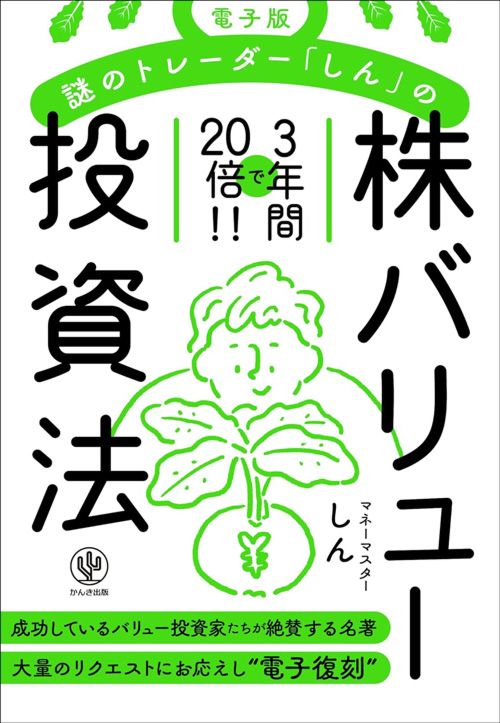
収益面から割安かどうかをみるときには、PER(株価収益率)という指標が使われます。PERは株価がその企業の1株あたり利益(以下、「1株利益」)の何倍の水準にあるのかということを示すものです。
たとえば、1株利益が100円の銘柄の株価が1000円だとすると、PERは1000円÷100円と計算するので10倍ということになります。株価は1000円のままで1株利益が200円になると、PERは倍となります。PERは低い方が割安なので、5倍と10倍では5倍のほうが割安というわけです。
PERは株価が1株利益の何倍なのかという観点からみているのですが、株価に対して1株あたりどれだけの利益を上げているのかという見方もあります。これを株式益回りといい、株価が1000円で1株利益は100円というときは、100円÷1000円×100で10%が株式益回りとなります。
■預金よりはるかにいい利回り
もうわかりますよね。株式益回りはPERの逆数をとって百分率(%)であらわしたものです。銀行預金などは1000円預けて100円の利息がつくと、利率は10%といいますよね。これと同じで株式では「益回り」と言い換えて、預金の金利みたいに考えるのです。
今のところは、メガバンクの預金金利は有利なもので0.025%くらいですが、株式では10%くらいの益回りの銘柄は少なくありません。こういった株式を見つければ、預金よりもずいぶんといい利回りが得られるということになります。
それでは、収益に対する安全域はどう見ていけばいいのでしょうか。師匠のグレアムは、国債の2倍の安全域をみておけといっています。私自身は、国債の利回りと比べると、かなり大きな「安全域」をとっています。
2024年5月末現在、日本の10年国債の利回りは預金よりもよくて年およそ1%です。仮に株価が1000円で1株利益が100円の銘柄をみつけたとします。すると株式益回りは100÷1000×100=9%となり、国債よりも10倍の差があります。この10倍の差が安全域となるわけです。
■PER10倍以下の銘柄を買っていくのが基本
グレアムの安全域が2倍なのは、アメリカの国債の利回りを基準としているからです。たとえば、1971年のアメリカの5年もの国債の利回りは約6%でしたから、2倍というと12%の利回りを銘柄選びの基準とすることになります。
ところが、今の日本はすごく低金利で、単純に国債の利回りの2倍を適用することがいいとは思いません。これから金利が上がってくる可能性もあるはずです。とすると、1%を基準にして2倍という安全域は、私は少しも安全とは思いません。
私はその意味からも、10%以上の益回りものをみつけて、投資したいと考えています。
株式益回りが10%ということは、株価が1000円で1株あたり100円の利益を上げているということです。PERに直すと、1000円÷100円=10倍ということです。したがって、PER10以下のものをみつけて買うということになります。
----------
愛知県在住。サラリーマンとして大手自動車系子会社に勤務するかたわら、年収アップを目指し、株式投資を始める。ウォーレン・バフェットの株式投資方を研究。バフェットの師匠であるベンジャミン・グレアムとウォーレン・バフェットの両方の手法をとりいれた投資(バリュー投資)を実践する。
----------
(バリュー投資家 しん)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
専門家や評論家のオススメはうまく行かない?株式投資の銘柄選びはシンプルでよい理由
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月27日 11時0分
-
株式投資で1億円の資産を築き上げるのは不可能じゃない!「億り人」になる4つの方法
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 11時0分
-
今の株式市場は「高い?」それとも「安い?」…買い時・売り時を判断する方法をプロが解説【投資の基本】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 10時15分
-
「日経平均4万円台」はまぐれではない…「金利のある世界」が日本株にとって追い風になるこれだけの理由
プレジデントオンライン / 2024年6月17日 10時15分
-
個人投資家は「目標株価」を決めない方がいい?「モメンタム投資」の考え方
トウシル / 2024年6月6日 11時0分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
-
5医薬品の販売規制案にドラッグストア反発の事情 市販薬のオーバードーズ問題に有効な規制とは
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 12時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












