怒りがこみ上げた時には「決断」も「行動」もしてはいけない…世界の偉人でも後悔した「怒りへの対処法」
プレジデントオンライン / 2024年6月11日 8時15分
※本稿は、キム・ヘナム著、渡辺麻土香訳『「大人」を開放する30歳からの心理学』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。
■古代ローマの哲学者「セネカ」も怒りについて語っていた
古代ローマのストア派哲学の大家セネカは、著書『怒りについて』(兼利琢也訳、岩波書店)で「この情念のもたらす結果と害悪に目を向けると、人類にとってどんな悪疫も、これほど高くついたためしはない」と断言し、次のように語っている。
「激情のなすがまま、苦痛、武器、血、拷問を求め、一片の人間性もない欲望に哮(たけ)り狂い、他者を害するまで己を忘れ果て、矢玉の注ぐ中へ突進する。復讐に燃え、復讐者自身、もろともに引き倒さずにはおかない。(中略)狂気も同様に、己を抑えられず、体面を忘れ、係累(けいるい)に思いを馳せず、着手したことに意固地に固執し、理性にも助言にも耳を閉ざし、些細な理由に激しては正義も真理も見分けず、瓦礫(がれき)の崩壊にさも似て、砕け落ちては押しつぶしたものの上に飛散する」
■「怒る」と「怒りをあらわにする」は別物
セネカはそういう理由から、日常生活の中で怒りの解消法を習得することの重要性を主張した。幸い大抵の人たちは、怒りを放出したばかりに相手のみならず自分まで壊れてしまうという最悪の結末を望まないため、できるかぎり怒らないように努める。
なお、「怒る」ことと「怒りをあらわにする」ことは別物だ。怒りは極めて自然なもので、制御不能な感情である。反面、怒りを抑えるか相手にぶつけるかの選択は、100%私たちに委ねられている。とはいえ、その選択は決して容易ではない。なぜなら、ある人は怒りを抑えこみ過ぎて、またある人は怒りをぶちまけ過ぎて問題を起こしてしまうからだ。そのため古代の哲学者アリストテレスは、「誰でも怒ることはできる。それはたやすい。だが、適切な相手に、適切な度合いで、適切な時に、適切な目的のため、適切な怒り方をすることは、たやすいことではない」と言っている。
■怒りが湧いた時は「すぐに反応しない」
1.怒りが湧いた時は数をかぞえるべし
怒りが湧いた時は、その感情を認める一方ですぐに反応しないことが重要だ。怒りが制御不能になると、興奮して理性を失ってしまう。すると余計なことを口走り、振り返った時に必ず後悔する。なぜなら怒りの表出は、相手の最も痛いところを突くことを目的としているからだ。ゆえに怒りがこみ上げた時は、ひとまず心の中で1から10まで数えよう。数をかぞえているうちに多少は興奮が静まって、湧き上がる怒りで失いかけていた理性も戻ってくるはずだから。そうなれば後悔するような言動は未然に防ぐことができる。
それでも腹が立ってどうにもならない時は、アメリカの第3代大統領トーマス・ジェファーソンの言葉を思い出すことだ。「腹が立ったら10まで数えろ。べらぼうに腹が立ったら100まで数えろ」
■人は誰でも「自分の基準」で行動している
2.他者に対する最低限のマナーは守るべし
周りを見渡せば腹の立つことばかりだ。なぜなら世の中は理解不能な人間であふれているからである。通勤中の人混みでは今日も誰かに肩をぶつけられた。それにしても、ああいう連中はどうして「ごめんなさい」のひとことが言えないのだろう? 人波をかき分けてようやくたどり着いた会社では、自分のために淹れたコーヒーをチーム長にかすめ取られた。煮えくり返る気持ちを抑えて仕事に集中しようとしてみるが、今日にかぎってなぜこうもクレームが多いのか。
後輩の手柄を横取りすることで有名なソ課長に、仕事そっちのけで株ばかり気にしているキム代理、今月の売り上げ目標は何としてでも達成しろとチーム員をせっつくチョンチーム長らに囲まれて1日仕事をしていたら、げんなりしてくる。周りを気にせず自分の仕事に集中しようと思っても、不意に怒りがこみ上げてくるのだ。どいつもこいつも、どうしてこんなに身勝手で厚かましいのだろう? なぜあんな生き方ができるのか、全くもって理解に苦しむ。

人は誰でも自分の基準で行動し、それを正しいと考えるものだ。そのため一方では他者を理解しようと努めても、もう一方では自分の基準から大きく外れる相手に不満を持ち、腹を立ててしまうものである。そういう時は、誰にでもそれぞれ自分だけの基準があることを改めて思い出すことだ。自分が気に入らないからといって、相手が間違っているわけではない。ただ自分とは人生の基準が違うというだけである。
それに、どんな人も100%正しい基準を持って生きているわけではない。つまり、自分だって間違える可能性は常にあるわけだ。したがってどんなに理解できなくても、一方的に自分の基準を押しつけ、怒りをぶつけたり相手を侮辱したりしてはいけない。それが他者に対する最低限のマナーだ。
3.あなたの怒りは恐怖の裏返し
人は自分の弱みを隠したがるものだ。それゆえ劣等感や羞恥心がかき立てられた時も、「キレる」ことによってその感情を隠そうとすることがある。こうした現象は、幼い頃に「男は絶対に泣くな」と言われて育った男性たちに多く見られる。彼らは自分の感情を正しく把握できていないことが多い。深く傷ついた時も、拒絶されそうで怖い時も、恥をかいてしまった時も、何やら負の状態に置かれたことに恐怖を覚えるだけなのだ。そのため恐怖心を隠そうとして烈火のごとく怒りをぶちまけ、他者を攻撃するのである。
だから腹が立った時は、自分の抱く感情が本当に怒りなのか、その裏に何か別の感情が潜んでいないか、真っ先に探る必要がある。怒りをぶつけることと、何かへの恐怖を伝えることは全く違うことだからだ。
■チンギス・ハーンの「失敗」
4.腹が立った時は、いかなる決断も行動もしないこと
モンゴル帝国を率いたチンギス・ハーン。ある日1人で狩りに出かけた彼は、途中で喉の渇きを覚えた。小川を求めて歩き回ると、岩地の間を流れる細い湧き水が目に入る。彼は腕に乗せていた鷹を下ろし、取り出した銀の器に水を注いだ。岩を伝う水流は糸のように細く、器が満たされるまでには、じれったいほど時間がかかった。ついに満たされた器を口に運ぼうとした矢先、鷹が器を跳ね飛ばし、水を地面にこぼしてしまった。

彼は腹が立ったものの、相手はお気に入りの鷹だ。鷹も喉が渇いていたのだろうと考え、改めて水をため始めた。しかし器に半分ほど水がたまったところで再び鷹が飛びかかってきた。とてつもなく喉が渇いていた彼は激怒し、引き抜いた剣を片手に再度水をため始めた。やがて器がいっぱいになり、それを口に運んだ瞬間、またしても鷹が飛びかかってきた。彼はとうとう堪忍袋の緒が切れて鷹をひと思いに斬ってしまった。
ところが、しばらくして水源を探しに岩の上に立った彼は、驚くべき光景を目撃する。猛毒を持つ蛇の死体が小池のような水源に落ちていたのだ。もし彼がその水を飲んでいたら、確実に命を落としていただろう。彼は死んだ鷹を胸に抱いて野営地へ戻ると、その鷹の置物を金で作るよう家来に命じ、片方の羽に次のような言葉を刻ませた。
「怒りに任せ行動すれば、失敗を招く」
■腹立ち紛れに離婚する人、怒りに任せて人を殺す人…
これはパウロ・コエーリョの『賢人の視点』(飯島英治訳、サンマーク出版)に出てくる物語だ。鷹は主人の命を守るべく器に飛びかかっていたのだが、その事実を知らないチンギス・ハーンは腹を立てて鷹を殺してしまった。このように何かが起きた時、そこには避けられない事情やそれに相当する理由が隠れている場合がある。だが怒りは理性を麻痺させ、判断力を奪ってしまうものだ。そのため、ある人は腹立ち紛れに離婚して、怒りに任せて人を殺す。
したがって腹が立った時は、いかなる決断も行動もしないことだ。どんなに腹が立ったとしても、避けられない事情がなかったか確認するのが先決である。重要な決断は怒りが収まり、理性が回復したあとで下しても遅くない。哲学者バルタサル・グラシアンも言っている。「腹が立った時は何もするな。何をしても裏目に出るだろう」と。
■怒りがこみ上げたときは「口を閉じる」のが得策
5.怒るのは明日に持ち越せ
チェコには「明日に持ち越すべき唯一のものは怒りである」ということわざがある。セネカも怒りに対する最善の対策は、怒りを持ち越すことだとして次のように語った。
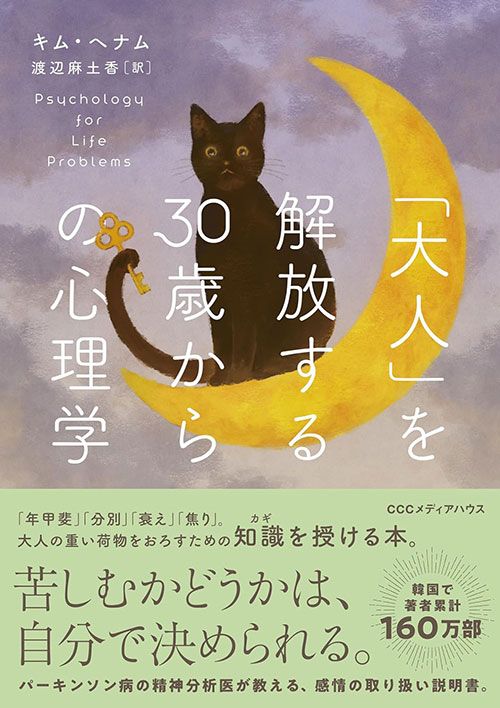
「しばしば哀れみが怒りを引き戻す。そこにあるのは、しっかりした堅固さを欠いた虚ろな膨張でしかなく、最初の激しい勢いに乗っているだけである。ちょうど、大地から立ち上がり、川や湖から発生した風は、吹き荒れても持続しないのと何も変わらない。激しい突進とともに始まりはするが、その後、本来の時が来る前に疲れて熄(や)んでしまう」
だから本当に脳天まで怒りがこみ上げた時は、いっそ口を閉じたほうが得策だ。お互いの怒りが静まったあとで、何がいけなかったのかゆっくり考えてみればいい。そしてできるかぎり怒るのは先延ばししよう。怒るのを明日に持ち越せば、その瞬間に気づくはずだ。あなたの怒りは、もうすでに収まりつつあるということに……。
■腹が立つのは、相手がある程度大切な存在だから
6.人生において人より大切なものはない
腹が立っている時は、相手の言動に強い悪意を見いだしやすい。だが本当に悪意のある言動というのは、思うほど多くないものだ。相手はただ少し身勝手だったり、考えが浅かったりしただけである。それに相手が赤の他人なら、あなたはそもそも腹を立てることなどなかっただろう。腹が立つということは、その相手があなたにとってある程度大切な存在だということだ。
したがってどんなに腹が立っても、関係を壊すような言動は控えたほうがいい。例えば相手の致命的な弱点や恥部には決して触れないこと。親や家族に言及して相手のプライドを傷つけるのもご法度だ。相手の言動になぜ自分が腹を立てたのか、その理由を伝えて相手を納得させるだけで十分である。すなわちどんなに腹が立っても、人生において人より大切なものはないことを肝に銘じておくべきだ。最後にセネカの言葉を伝えよう。
「すべてを目にし、すべてを耳にするのは当を得たことではない。(中略)だから、あるものは延期し、あるものは笑い飛ばし、あるものは大目に見てやるべきである」
----------
1959年ソウル出身。高麗大学校医科大学を卒業し、国立精神病院(現国立精神健康センター)において12年にわたり精神分析の専門家として勤務。ソウル大学校医科大学招聘教授として教鞭を執り、キム・ヘナム神経精神科医院の院長として患者を診た。五人兄妹の三番目として生まれ、常に両親の愛情に飢えていた経験を持つ。愛情を独占していたのは仲のよかったすぐ上の姉で、羨望と嫉妬の感情を抱きながら育ったが、高三の時、この姉が突然の死を迎え、衝撃を受ける。医科大学に入学したのは、このときの体験がもとになっている。42歳でパーキンソン病を患う。
----------
(精神分析医 キム・ヘナム)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「人生終わった…」恋愛で失敗しがちなこじらせ女性の「NG行動と対処法」
ananweb / 2024年6月20日 20時30分
-
老後の知恵...「断れない人」「すぐ謝る人」が「雑に扱われない人」になるために絶対すべきこと
ニューズウィーク日本版 / 2024年6月19日 10時55分
-
「70歳でヨボヨボの人」と「70歳で快活な人」は何が違うのか…米国の実験が証明した"若々しさ"の源
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 8時15分
-
"何もしない時間"に耐えられない人が多すぎる…寝ても疲れが取れない人が今すぐ取るべき「休息」の種類
プレジデントオンライン / 2024年6月13日 8時15分
-
自立できない大人の特徴5つと対処法3つ
KOIGAKU / 2024年6月3日 18時23分
ランキング
-
1ローソン「富士山」騒動現状報告 “バスツアー”4社に取り下げ要請も「掲載が継続」、警備配備も【対応一覧】
ORICON NEWS / 2024年6月20日 22時46分
-
2「ジャンプ式折り畳み傘」の取り扱いに注意 手元が飛び出し大けがの事例も
オトナンサー / 2024年6月20日 23時10分
-
3“優先席で席を譲らない40代女性”にブチ切れた女子高生「非常識じゃないですか?」その後女性は…
日刊SPA! / 2024年6月21日 8時53分
-
4「芸名ですか?と聞かれますが、本名です」あまりにも長いお名前に「貴族っぽい」「綺麗すぎますね」
まいどなニュース / 2024年6月18日 12時10分
-
5あなたが考える「信頼できない女性政治家」ランキング。元おニャン子・元SPEED議員も当然のワースト入り
女子SPA! / 2024年6月21日 8時45分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












