「70歳でヨボヨボの人」と「70歳で快活な人」は何が違うのか…米国の実験が証明した"若々しさ"の源
プレジデントオンライン / 2024年6月15日 8時15分
※本稿は、キム・ヘナム著、渡辺麻土香訳『「大人」を開放する30歳からの心理学』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。
■かつては年長者たちの知恵が下の世代の指針だった
私たちは加齢によって失うものと得るもの、どちらのほうが多いのだろう? まずは加齢によって失われていくものを考えてみよう。
若さ、ハリ、黒髪、体力、健康、情熱、性機能、記憶力、(死別に伴って)友人や配偶者、人生に残された時間……。
では逆に加齢によって増えるものには何があるだろう?
年齢、子孫、シワ、腹回りの肉、シミ、頑固さ、小言、激情、悔恨、捨てるべき家具や衣服、孤独感……。
加齢によって増えるものもたくさんあるが、その中でポジティブなものを挙げようとすると、ほとんどないように思う。
かつては年輪を重ねた年長者たちの知恵が、下の世代の人生において重要な指針になった。そのため若者は困難に直面すると必ず集落の長老を訪ねてアドバイスを求めたし、長老は日頃から敬われていた。
私たちが死の存在を認知してもなおこの世で生きていられるのは、自分たちが死んでも後世の人々をとおして自分たちの人生も続いていくという確信があるからだ。自分が蓄えた知恵は後世に受け継がれるだろうという確信は、個人の人生に一層の責任感を与える。過去から未来へと続く連続した時間の中に自分も属しているという感覚は、それだけ重要なものなのだ。
■年長者は「若者たちの世界へ移り住んだ移民」なのか
とはいえ現代のように急速に変化する時代では、過去の知識はすぐに意味を成さなくなる。科学技術の飛躍的な発展が、前世代の知識を使いものにならなくしてしまうからだ。そのせいで年長者の考えは古くさいものとされ、誰からも耳を傾けられなくなる。
このように歴史的な連続感を失ってしまった人々にとって老いることは、若さや美しさ、名声のほか魅力を失って、役立たずに成り下がることを意味する。そのため人類学者マーガレット・ミードは30代以上の人々に対し、よくこう言っていたそうだ。
「私たちは皆、若者たちの世界へと移り住んだ移民だ」
移民たちが現地の人たちに交じって生き残るためには、かなりの労力が必要だ。だが悲しいことに年を取れば取るほど、新たなスキルを習得し、ついていくのは難しくなる。するとある瞬間にすっかり置いていかれて、ついていくことを諦めるようになる。その結果、いつしか老いることは死よりも恐ろしいものになるのだ。すると世間から向けられる否定的な視線に抗うエネルギーも楽天性も失ったまま、良い時期はとうに過ぎ去り、もはや悪いことしか待っていないような気がしてくる。それゆえ人は長生きしたがる一方で、老いることを望まないのだ。
■私たちは老いてもなお、成長や発展を遂げられる
しかし、果たして本当にそうだろうか? 老年期の人生は私たちにとってオプションとして余った時間、文字どおり「余生」にすぎないのだろうか? そうした理由のせいで徹底的に目をそらしたくなる恐ろしい現実でしかないのだろうか?
ある日、詩人ロングフェローは熱心なファンからこう言われた。
「おおっ、久しぶりじゃないか! それにしても君は変わらないな。何か秘訣(ひけつ)でもあるのかい?」
ロングフェローは庭にある大きな木を指して答えた。
「あの木を見てみろ! もはや老木だというのに、ああやって花を咲かせ実までつけているだろ。それができるのはあの木が毎日多少なりとも成長しているからさ。私だって同じだよ。年を取っても毎日成長しようと思って生きているんだ!」

このように老人は決して「終わった存在」ではない。人は生きているかぎり、常に成長のための新たな課題を与えられているのだ。よって人は死ぬまで絶えず鍛えられ、再編成され矯正される。つまり私たちは老いてもなお、成長や発展を遂げられるのだ。人生の各段階が新たな変化の機会を提供してくれるからである。人格も同様だ。70、80、90歳を過ぎても変化し続けていく。その際、老いを捉える姿勢次第では、人生を「惨めで悔いばかり残るもの」ではなく「いつまでも希望と変化がある能動的なもの」にすることもできる。
■70代後半~80代初めの男性たちが「若返った」
アメリカのハーバード大学心理学部教授エレン・ランガーは、1979年のある日、地元の新聞に70代後半から80代初めの男性たちを募集する広告を出した。心の時計を20年前に戻した場合、人の体にどのような変化があるかを調べるためだ。エレン・ランガー教授はある修道院を20年前の1959年と同じ環境にして、被験者に1週間、1959年当時に戻った気分で暮らしてもらった。被験者は『ベン・ハー』や『お熱いのがお好き』といった映画を鑑賞し、ラジオでナット・キング・コールの歌を聞き、当時の時事問題について討論した。その際、彼らは家族やヘルパーの介助なしに自分で食事のメニューを決め、調理や皿洗いなど身の回りのことを自分1人で行わなければならなかった。
すると1週間後、驚くことが起きた。被験者全員が実験前より若返ったのだ。視力や聴力、記憶力も向上し、知能が高まって歩く姿勢も良くなった。誰かの支えなしでは歩くのも難しかったある老人は、杖なしで背筋を伸ばして歩き始め、また別の老人は、フットボールの試合にまで参加できるようになった。
■私たちの限界を決めているのは「頭の中身」
「心の時計の針を巻き戻す実験」と呼ばれるこの研究は、物理的な時間を戻すことはできなくても、心の持ちようでいくらでも若々しく生きられるという事実を立証したことで、世界中の心理学者と行動経済学者から、老化と肉体の限界に挑戦する革新的な心理実験として絶賛された。これについてエレン・ランガー教授は次のように述べている。
「私たちの限界を決めているのは、肉体そのものではなく、むしろ頭の中身のほうだ」
つまり同じ70歳でも、その年齢をどう捉えるかによって若々しく生きることは十分に可能というわけだ。例えば何をするにも年齢を考え、年齢を意識している人は、身体的な状態とは関係なく70歳を「老いて何もできない年齢」と考えているため、受動的で依存的な生活を送ってしまう。反対に同じ70歳でも、年齢を聞いて驚いてしまうほど若々しい人たちは想像以上に多いものだ。彼らは自分の年齢を大して意識していない。ただ一生懸命体を動かし、新しいものを学び、趣味を楽しんで活気ある毎日を送っているだけだ。

■健康に年を取る秘訣は「身体年齢に固執しないこと」
したがって健康に年を取りたいのなら、自分の身体年齢にあまり固執しないことだ。70歳になろうが80歳になろうが、年齢とは関係なく「昨日より今日、今日より明日と少しずつ成長する自分」を念頭に置いて生きるのである。実際、延世(ヨンセ)大学哲学科の名誉教授キム・ヒョンソクは、「100歳まで生きてみたら60歳までの自分は未熟だったし、自分の人生における黄金期は、65歳から75歳だった」と語っている。
また、エレン・ランガー教授の実験からもわかるように、年を取っても可能なかぎり自力で日常生活を送ったほうがいい。心の時計の針を巻き戻す実験に参加した老人たちは、そのほとんどが子どもと同居していた。彼らにとっては自宅も自室も完全には自分のものではなく、いつからか身の回りのことも家族に頼りきりになっていた。自分で決断したり実行したりすることがほとんどなかったのだ。そうした受動的で依存的な人生では、どうしたって無気力になる。
実際にアーノルドという被験者は、実験に参加するまで何もやる気が起こらないし、体を動かすことは何もしていないと答えていた。ところが彼は1週間、身の回りのことを自分でしなければならない環境に置かれると、食事の準備や後片づけを進んでやるようになった。心の時計を20年前まで巻き戻し決定権を手にしたら、無気力な人生から脱して自発的で能動的な生活を送れるようになったのだ。このように人生の舵を自ら切っているという感覚、すなわち自らの人生の主導権を握り、それを行使しているという感覚は、人間にとって大変重要な人生の原動力になる。
■老人ホームの入居者を2つのグループに分けた実験
これについてエレン・ランガー教授は『ハーバード大学教授が語る「老い」に負けない生き方』(桜田直美訳、アスペクト)で次のように述べている。
「私は同僚のジューディス・ロディンと共同で、老人ホームの入居者を対象にしたある実験を行った。老人たちを二つのグループに分け、一つのグループには、いろいろなことを自分で決めてもらうようにする。たとえば、訪問客と面会する場所や、ホームで上映される映画を観るかどうか、観るとしたらいつ観るか、といったようなことだ。また、このグループの老人たちは、自分で世話をする植木を選ぶことができる。植木を置く場所や、水やりの時間、水の量も、自分で決めることになる。
もう一つのグループの老人たちには、いつも通りの老人ホームの生活を送ってもらった。自分で何かを決めるような指示はしていない。彼らの部屋にも植物はあるが、水やりはいつも通りスタッフの仕事だ。(中略)実験を始めてから一年半がたち、自分で決めるグループと、いつも通りのグループの間には、大きな違いが見られるようになった。自分で決めるグループのメンバーのほうが、より元気があり、活動的で、頭の働きもしっかりしている。(中略)自分で決めるグループから出た死亡者は、いつも通りのグループの死亡者の半分にも満たなかった」

■自ら決定するほど人生の幸福感は高まる
このように自分の人生を自分で決めて選択していれば、幸せになれるだけでなく健康にまでなれる。だからどんなに老いて体が弱っても、人生の舵はできるかぎり自分で切ったほうがいい。自ら選択し決定することが増えるほど、人生の幸福感や達成感、自尊感情は高まるからだ。
私はまだ64歳だけれど、パーキンソン病によって体が少しずつ固まりつつある。前へ進むには、ひとまず両足でまっすぐ立つことが必要なのに、病気のせいでそれさえおぼつかない状態だ。1歩足を踏み出したはいいが、次の1歩を出す前にバランスを崩して倒れてしまうことも多い。最後に両足で颯爽と走ったのは、いつのことだろう。また腕や指も思うように動かないため、時が経つにつれできないことが1つ2つと増えてきた。最近は他に方法がないのでヘルパーの手もかなり借りている。人に頼らざるを得ない身の上は決して愉快ではないけれど、そうするしかないのが現実だ。
■今日は誰と会おうか、お昼に何を食べようか…
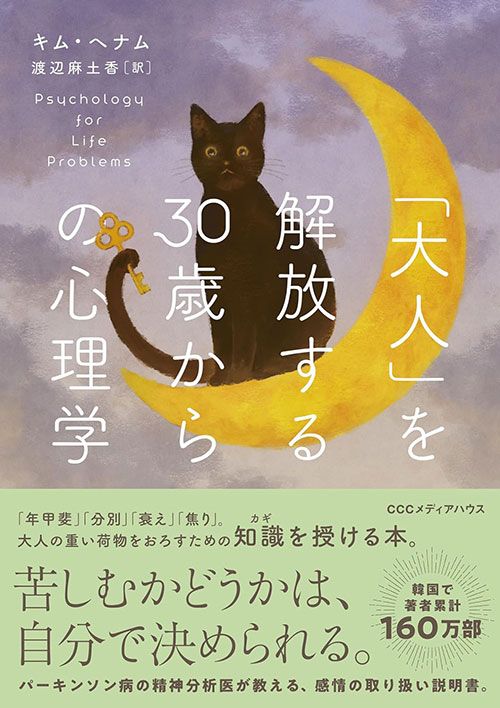
だが、そういう状況になればなるほど、この瞬間に何をしようか慎重に考えて決めるようになるものだ。今日は誰と会おうか、90歳の母とはお昼に何を食べようか、髪を染めようか、どの映画を見ようか、どんな本を読み、友達にはどんなメールを送ろうか、悩み抜いて決めるようになる。体調が悪くてベッドから起きられない時は、体調が良くなったら何をしようか考える。そうすると自分はまだたくさんのことを決めて選ぶことができるのだとわかり、それができて本当によかったと思えるようになる。
この世はまだ私の知らないことだらけで、学べることであふれているというのもうれしい。
せっかく今日も目覚めて起きられたのだから、楽しく過ごしてステキな思い出をいっぱい作らなきゃ!
それが私の1日の過ごし方であり、老いに向き合う姿勢である。
----------
1959年ソウル出身。高麗大学校医科大学を卒業し、国立精神病院(現国立精神健康センター)において12年にわたり精神分析の専門家として勤務。ソウル大学校医科大学招聘教授として教鞭を執り、キム・ヘナム神経精神科医院の院長として患者を診た。五人兄妹の三番目として生まれ、常に両親の愛情に飢えていた経験を持つ。愛情を独占していたのは仲のよかったすぐ上の姉で、羨望と嫉妬の感情を抱きながら育ったが、高三の時、この姉が突然の死を迎え、衝撃を受ける。医科大学に入学したのは、このときの体験がもとになっている。42歳でパーキンソン病を患う。
----------
(精神分析医 キム・ヘナム)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
老齢医療の現場で医師は見た…「元気なうちにやっておけばよかった」と多くの人が死に際に思う"後悔の内容"
プレジデントオンライン / 2024年7月11日 15時15分
-
酒もタバコも嗜む94歳"自撮りおばあちゃん"は元気ピンピン…和田秀樹「後悔しない人生後半のお手本」
プレジデントオンライン / 2024年7月10日 15時15分
-
見た目年齢の差はあっという間に開く…和田秀樹「若く見える人、老け込む人」を分ける"たった1つ"の要素
プレジデントオンライン / 2024年7月9日 15時15分
-
注意されても、酒もタバコもやめなくていい…和田秀樹が「医者の言いなりでは人生を損する」と説く理由
プレジデントオンライン / 2024年6月29日 10時15分
-
熟年離婚に踏み切れない日本人は変だ…和田秀樹「欧米の高齢者に学ぶ"人生後半の楽しみ方"の最終結論」
プレジデントオンライン / 2024年6月27日 15時15分
ランキング
-
1「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?
くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分
-
2【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」
東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分
-
3大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?
南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分
-
4まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】
イエモネ / 2021年5月8日 12時30分
-
5終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…
日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











