「行列に並んだラーメンは美味い」と「雨の日にズブ濡れで営業に行く」は同じ…結果を出す人の「あざとい」やり方
プレジデントオンライン / 2024年6月8日 18時15分
※本稿は、柿内尚文『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。
■食事を最高においしくする簡単な方法
問題です。
食事を最高においしくする簡単な方法とは、なんでしょうか?
あなたなら、どう答えますか?
僕の回答はこうです。
「とにかくお腹をすかせること」
いくら素晴らしい料理だったとしても、お腹がすいていない状態では、そこまでおいしく食べられません(一部食通の人はそんなことはないかもしれませんが)。
おいしく食べるために大切なのは、料理の味だけでなく、そこまでのプロローグです。人生の節目というストーリーもプロローグになりますし、なによりお腹がすいていることは最高のプロローグです。
「おいしいものを食べたい!」と思った時、通常は「おいしい料理」のほうに意識が行きます。でも、実はおいしく食べたければ、食べるまでの「プロローグ」も重要なのです。
「プロローグ」とは序章とか序幕のことですが、時間のプロローグは「ゴール(目的)を盛り立てるためのプロセスストーリー」を指します。
「行列に長時間並んで」食べるラーメン。
「創業から継ぎ足した秘伝のタレ」のうなぎ。
上記の「」の部分がプロローグになって、おいしさを引き立ててくれます。食べることだけではありません。
おいしいビールを飲むためにサウナで汗をかき、のどの渇きをガマンする。
休みの日を最大限楽しむために日々の仕事をがんばる。
■凄腕営業マンが大切にしていること
大切なのは、ゴール(目的)までの「プロローグ」。
この「プロローグ」をつくると、記憶に残るゴールが生まれます。
「プロローグ化」が時間の価値を高めてくれるのです。
営業の仕事ですごい売上を出している知人がいます。
彼に、なぜ営業成績がそんなにいいのか聞いたことがあります。
「自分は話が特別うまいわけでもなく、その場で営業先の人を盛り上げたり、その気にさせたりは苦手なんです。その代わりに自分が大切にしているのが『プロローグ』です。
営業で大切なのは、商品を売る瞬間よりも、売るまでのストーリーだと思ってます。商品を相手が買いたくなるまでのストーリーを描いて、そのストーリーを実行に移します。愚直にそれをしていたら営業成績につながったんです」
彼は、風の強い大雨の日にズブ濡れになりながら、営業先を訪ねたそうです。
その姿が営業先に響き、取引につながったことがあるそうです。
このストーリーづくりも、「プロローグ化」のひとつです。
ちょっとあざとい感じもしますが、そんな彼の姿が相手の心を動かしたのです。
プロローグ化は、ゴール(目的)を最大限に盛り上げてくれる存在です。
喜びを大きくして、記憶に残る時間をもたらしてくれる方法なのです。
■プロローグをつくる「4つの方法」
では具体的にどうやって「プロローグ」をつくればいいのでしょうか。その方法を4つ紹介します。
ガマンをプロローグ化する
「夜、ネットフリックスで好きな映画を楽しむために昼間の仕事をがんばる」
「おいしいビールを飲むためにトレーニングして汗をかく」
イヤなことやつらいことを、その先にある「目的のためのプロローグ時間」にして、主従を逆転させる方法です。
マイナスの絶対値が大きいほど、目的を手にした時の喜びは大きくなります。

ストーリーをプロローグにする
ゴール(目的)を達成するまでのストーリーを自分でつくっていくことも、プロローグ化の方法のひとつです。
脳は事実の羅列だけだと印象に残りにくくできています。味気ない事実よりも、ストーリーのほうが感情に響き、モチベーションが上がったり記憶に刻まれやすくなります。
先ほど紹介した営業の話も、ストーリーをプロローグ化した一例です。
ビジネスの世界で「ストーリー戦略」という手法がありますが、これは時間の蓄積をストーリーに仕上げてプロローグ化するやり方といえます。
リサーチをプロローグ化する
たとえば、初めての人と会う前に、SNSなどでその人に関する情報を調べておく。「準備」というプロローグをつくっておくと、会った時にコミュニケーションがうまくいき、その時間の価値がより高くなります。そのためにも事前にリサーチ、準備が必要です。
観光に行った時に、その場所の歴史や地理などを知っているとより楽しめますが、それもプロローグ化です。
時間の蓄積をプロローグ化する
これは商品やサービスを提供する際の考え方です。
「まる3日煮込んでつくったデミグラスソース」「18カ月熟成させた生ハム」というように、時間の蓄積をプロローグ化して伝える方法です。
3日煮込んだものが味がいいとは限りませんが、プロローグ効果で、3日煮込んだソースにはお客さんにとって価値が生まれています。
■刑事ドラマの「謎解きシーン」をヒントにする
どう締めるかで時間の価値が変わるそれは、犯人がなぜそんな犯罪をしたかを、主役の刑事がドラマの後半で説明(謎解き)をするシーンです。
刑事ドラマのエンディングで欠かせないシーンがあります。たとえば、ドラマ『相棒』(テレビ朝日)では、よく主役の杉下右京(すぎしたうきょう)がラストに謎解きをしています。多くの刑事ドラマにあるこのシーン。最後に犯行の謎解きという「意味付け」をしてくれることで、納得感を得ることができ、ドラマが締まります。
過ごした時間に対してこの「意味付け」を行うことを、僕は「時間のエピローグ化」と呼んでいます。
自分がしたことを振り返り、そこに意味付けして、自己納得をするための行為です。エピローグ化は時間磨きのひとつです。
エピローグ化のイメージは「振り返り・復習」です。
あとでその時間を振り返り、復習することで、時間価値を高めます。
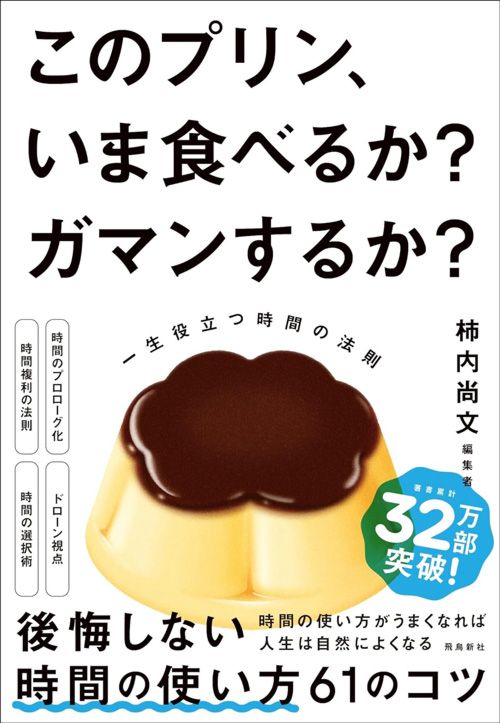
「勉強したことを、記憶に定着させるには復習です」
学生時代、教師から口酸っぱくいわれた復習の大切さ。
僕は復習が苦手で、次にどんどん行きたくなるタイプだったので、記憶の定着はあまりよくありませんでした。
仕事をはじめてからは、復習の大切さに気づき、仕事が終わるとその仕事の総括をしながら、復習&ひとり反省会をするようになりました。
仕事でうまくいったポイントはどこか、うまくいかなかった原因はどこかなどを検証していたら、だんだんと仕事で成果が出るようになりました。
----------
編集者
1968年生まれ。東京都出身。聖光学院高等学校、慶應義塾大学文学部卒業。読売広告社を経て出版業界に転職。ぶんか社、アスキーを経て現在、アスコム取締役。長年、雑誌と書籍の編集に携わり、これまで企画した本やムックの累計発行部数は1300万部以上、10万部を超えるベストセラーは50冊以上に及ぶ。現在は本の編集だけでなく、編集という手法を活用した企業のマーケティングや事業構築、商品開発のサポート、セミナーや講演など多岐にわたり活動。著書に『パン屋ではおにぎりを売れ』『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(共にかんき出版)がある。
----------
(編集者 柿内 尚文)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ミラノ風ドリア「480円→290円」で売上数3倍…創業者が「サイゼリヤの料理は、まずくて高い」と語る深い理由
プレジデントオンライン / 2024年7月4日 8時15分
-
「なぜか読書ができない」社会人必読の一冊 ― 20代~30代が今読んでいるビジネス書ベスト3【2024/6】
マイナビニュース / 2024年7月1日 17時0分
-
電車内の音漏れにイライラするのはもったいない…「不快な時間」を「有意義な時間」に変換させる"考え方のコツ"
プレジデントオンライン / 2024年6月7日 18時15分
-
「病院はガマンして長時間待つもの」は大間違い…時間を「有効活用できる人」と「できない人」の決定的な差
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 18時15分
-
偏差値70超の子はやっている…カリスマ塾長が激推しする最短で最高の結果を生むたった一つの学習習慣
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 10時15分
ランキング
-
1バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分
-
2ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分
-
3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた
東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分
-
4auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針
読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分
-
5「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












