日テレと小学館の「ふんわり合意」に原因あり…「セクシー田中さん」ドラマ化が悲劇を招いた2つの根本問題
プレジデントオンライン / 2024年6月6日 9時15分
■これ以上「被害者」を生んではいけない
日本テレビの連続ドラマ「セクシー田中さん」(2023年10月期放送)の原作者が急死した問題をめぐり、5月31日に、日本テレビが「『セクシー田中さん』 調査報告書」を公表した。週が明けて6月3日には小学館も「調査報告書」を発表した。
すでにさまざまなニュースになり、またX上でも話題になっているが、現在のドラマ制作現場の問題点を自ら告白する非常に興味深い内容だ。
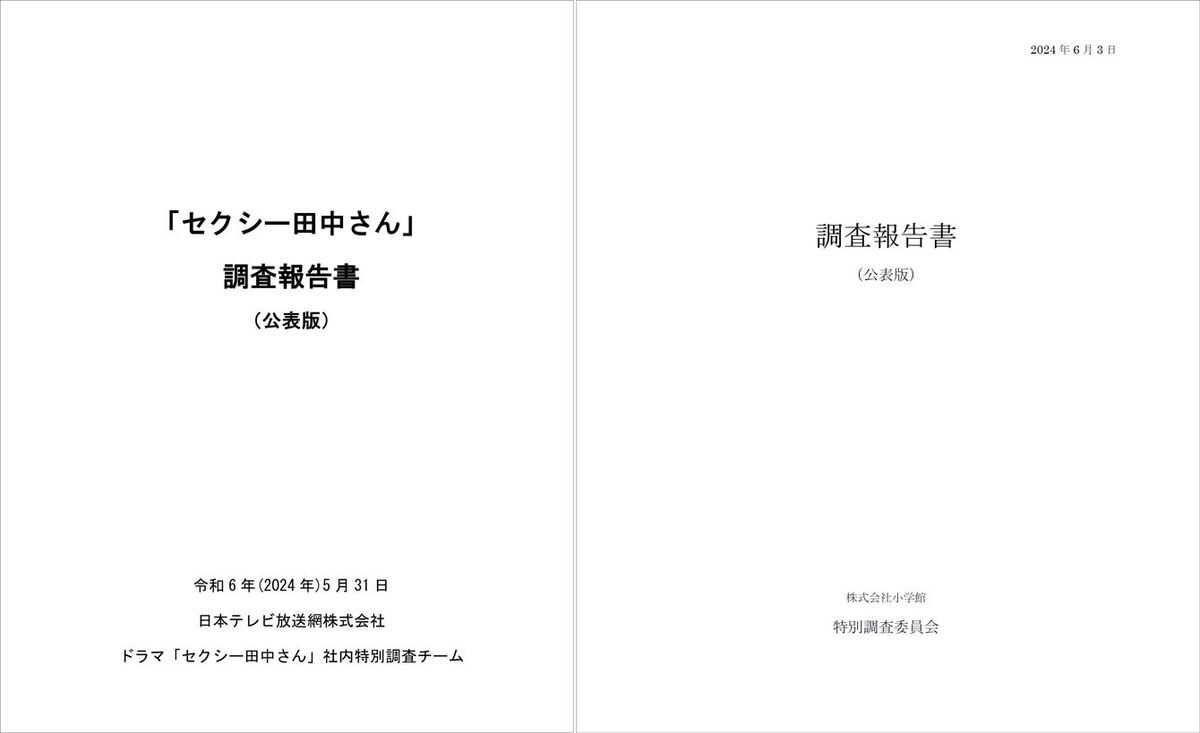
最初に書いておくと、報告書の登場人物を挙げてこいつが悪い、あいつのせいだというような犯人探しは絶対にやめるべきだ。このドラマのトラブルについてSNSが騒然となった結果、何が起こったかを思い出してほしい。ここでまた誰かを個人攻撃をしては、私たちは何も学べなかったことになる。みなさん、そういう投稿は慎もう。
■原作者の「条件」は共有されていなかった
さて、2つの報告書にはいたく感心した。ドラマや映画の制作上のトラブルについて、これほど詳細に調べ上げた文書は初めて読んだ。こういう話は公式に公開されることはないものだった。当事者である日本テレビ、小学館それぞれがここまで赤裸々に文書にしたことはまず評価したい。
私は、ドラマ「セクシー田中さん」をたまたま見始めたらハマった熱烈なファンだ。あれほど素晴らしい作品制作の裏で、ここまで壮絶なやりとりがあったことにあらためて驚いた。
そして2社が同時に公表した文書により、今回のトラブルの原因が明確になったと私は受け止めた。この件に関心があった人なら、原作者が2024年1月24日に公開したブログに、「必ず漫画に忠実に」「原作で未完の部分は原作者があらすじからセリフまで用意する」ことを条件にドラマ化を許諾したと書かれていたのはご存じだろう。
だが、この条件が共有されないままドラマ制作が進んでいたのだ。
■「羅生門」のような2社の報告書
原作を尊重してドラマ制作を進めることはふんわり合意していたが、具体的にどうドラマ化するかは結局曖昧なまま進んだことがよくわかる。
2つの報告書を照らし合わせると、それぞれ自社の立場を守る書き方が目につく。報告書同士が「言った言わない」の水かけ論をやらかしているとも言える。同じ出来事をそれぞれが全く別の物語として語っていて、映画『羅生門』のようだ。読み比べてどちらが「正しい」かは、裁判でもやって決着しない限りどうとも言えるだろう。ここではその「判定」はできない。
問題だったのは、そのふんわりした合意が原作者と脚本家を「対立」させてしまったことだ。原作者は、ドラマ化は原作に忠実に進めてもらう条件で許諾をしたつもりでいた。それは脚本家にも伝わっていると思っていた。脚本家はそんな条件があったことは知らなかったし、知っていたら引き受けなかった。ここに大きな齟齬があり、二人が対立する形になった。
■原作者と脚本家の対立を生んだ責任
原作者は「条件」に納得したはずの脚本家がなぜいちいち原作を変えてくるのかと感じたようだ。脚本家は、「条件」を知らないのでなぜドラマ化のための改変に事細かにダメ出しするのかと受け止めた。ついに最後の9話と10話では、原作者が自ら脚本を書くことになった。
原作者からすると、脚本家が原作を変えようとするので「条件」に従って自分が書くべきと考えたし、脚本家からすると突然原作者が自分で書くと言い出したと理不尽に映っただろう。
「条件の共有」がなされていなかったのは会社間の問題だ。不幸なのは、それが原作者と脚本家の個人同士の対立に集約されてしまったことだ。
最初に、個人を責めるべきではないと書いたが、日本テレビと小学館という二つのメディア企業にはやはり責任があると思う。
そして最大の責任は、条件共有の曖昧さより、二人のSNS投稿を止められなかったことにある。脚本家は2023年12月下旬に、原作者はそれから約1カ月後の24年1月下旬にドラマ制作の経緯についてそれぞれ投稿を行っていた。
■SNS投稿は本人のためにならない
Twitterはイーロン・マスク氏が買収してXになって以来、同氏の新たな施策が裏目に出てこれまでにないほど殺伐とした空間になっている。特に、昨年末から年始にかけては最悪で、そこに松本人志氏の性暴力疑惑も重なって暴露大会と罵詈雑言の坩堝と化していた。長年、Twitterの時代から使ってきた私も、うかつに投稿できないと恐ろしく思っていたほどだ。
そんな中でブログやインスタグラムであってもネットで投稿してしまうと、Xで吊し上げられ、何より投稿した個人にマイナスにしか働かない。当時、日本テレビは脚本家との関係が決裂していたようだが、それでも「投稿は脚本家のためにならない」ということをなんとしても伝えるべきだった。

一方、小学館の報告書からは、原作者がどうしても世間に主張したいとの意向をむしろ尊重して、小学館側が投稿をサポートしたように読み取れる。何より「あなたのために、何一ついいことはありません」と全エネルギーをもってして説得に回るべきだった。
あるいは、「小学館として日本テレビに公式に抗議します」と伝え、実際に抗議するべきだったと思う。会社同士のトラブルを、最終的に個人同士の諍いにしてしまった。
■二度と同じ悲劇を起こさないために
そして実際、脚本家は猛攻撃に遭い、原作者は自分の主張を遂げたはずなのに、脚本家への恐ろしい攻撃を目の当たりにして驚愕した。原作者はXアカウントをこの時のために作ったので、どんな場かよく知らなかったに違いない。だから「攻撃したかったわけじゃなくて。ごめんなさい」という投稿をXに残している。
実際、いいことがなかったどころか傷ましい悲劇を生んだ。コンテンツ制作でのトラブルをSNSで訴えかけても悪いことしか起こらないことを業界で認識すべきだと思う。弁護士を立てて交渉するなど、冷静な対処をするほうがずっといい。
さて2社の報告書を読んで、今後どう改善すべきか、私なりに総括したい。俯瞰的に見ると、今回のトラブルの大きな原因として、メディア業界が契約書を後回しにしてきたことがある。
映像制作には細かい話、微妙なニュアンスがつきまとうため、その共有がものすごく重要なのに、ふんわりした言葉で曖昧に物事を進めることが多い。この件でいうと「原作をたいせつにするドラマ化」とはどういうことか、明文化されないまま制作に至ってしまった。
この業界が契約書をないがしろにする、つまり条件を明確な言葉にすることをなおざりにしてきたために、今回の悲劇が起こった。そのことをこそ、この報告書から読み取るべきだと私は思う。
■契約書を軽視してきたメディア業界
実際、それぞれの報告書では後半に書かれた「提言」の中で「契約書の早期締結」(日本テレビ報告書)、「契約の見える化」(小学館報告書)という項目がある。
メディア業界は契約書を軽視してきた。私は2000年代まで広告制作に従事してきたが、関わった仕事で制作会社が広告代理店と制作契約書を結ぶのを見たことがなかった。その割に制作費や修正費用について揉めることが多々あり、揉めたら制作会社が負担をかぶるのが普通だった。いまは変わったかもしれないが。
さすがに映画制作では契約書が交わされるが、それも撮影が始まってようやく、というケースがよくあった。メディア業界には「契約書のような面倒はやめとこうぜ」という不思議な気風が漂っていた。
「セクシー田中さん」の原作利用許諾契約も、なんと放送までに締結されていなかったと日テレ報告書にある。文書で契約を交わそうと早い段階で進めていれば、何が原作者の許諾条件かもはっきり示され、関係者に共有できたのではないか。
なお、同年6月15日以降、日本テレビと小学館が本件ドラマ化についての契約書締結交渉を始める。同年6月15日にA氏が小学館にドラフト作成を依頼。同年7月28日に小学館から契約書ドラフトが日本テレビに届き、契約書内容が過去作品から大幅な変更があり、検討に時間を要したため、日本テレビの回答は同年9月27日であった。結果的に、放送前には締結に至らなかった。
日本テレビの「調査報告書」P20より
■「ふんわりした合意」では揉めるだけ
契約書でなくても、メディア業界は打合せの場に文書を持ち寄ることが少ない。打合せの後に議事録を作成する習慣もない。だから「ふんわりした合意」になりがちなのだ。
日テレ報告書の提案にある「相談書」でもいいと思う。原作側は「こう作ってほしい。これを絶対守ってください」とはっきり伝える。制作側は「われわれはこう作りたい。だからこうさせてほしい」と文書で明示する。

面倒でもはっきり伝えるほうが後で揉めるよりずっといい。その上で互いに合意した条件を契約書に盛り込めばいい。
日本テレビ報告書の「提言」にはもう一つ、私がかねがね絶対大事だと思っていたことが出てくる。それは「放送開始の1年半前の企画決定」だ。
■放送開始まで余裕がないドラマ制作現場
企画に時間をかけないことこそが、日本のドラマ制作の大問題だ。タレントありきですべてが決まってきたからだと思う。企画は後回しで出演者が先に決まる。そんなことを何十年もやってきたので、半年前の企画決定が常態化してきた。
日テレ報告書によると、今回の「セクシー田中さん」も、放送枠が正式決定したのは約4カ月半前だったとある。
10月期日曜ドラマとして初回放送日や話数等の正式決定 日本テレビ内部で、本件ドラマが「10月期日曜ドラマ枠」ということで初回放送日と放送話数が正式決定し、2023年6月8日、A氏はC氏に「日テレ内で『10月ドラマ枠』で正式決定いたしました。」とメールした。A氏の認識では、ドラマ化自体と放送枠は決まっていたが、初回放送日がこのタイミングで決まった。
日本テレビの「調査報告書」P17より
ハリウッドでは、ドラマの企画は脚本家が立ち上げ、スタジオにプレゼンしてうまくいけば第1話の脚本が発注される。それも評価されればパイロット版が制作される。映画も完成された脚本が、億単位の金額で映画化権を買われたりする。その脚本をさらに改良するために別の脚本家が雇われることもある。
脚本にはお金をかけ、いい脚本ができたら企画にGOを出す業界文化がある。準備段階にお金も時間もかけるのだ。それができるのは、製作費が日本とは桁違いであり、巨額な費用を回収できるグローバルな市場が形成できているからだ。
■制作準備のプロセスを大きく見直すべき
日本のエンタメは、国内市場がほどほどの大きさだったから海外展開に本腰を入れなかったとよく言われる。そのため市場が大きくならず、ハリウッドのように脚本制作に時間もお金もかけられないままここまで来た。制作準備期間が短いのも契約書をないがしろにするのも、その原因を突き詰めると市場の小ささに行き着く。
しかし最近は「国内市場だけではもたない」と、世界へ向かう空気が出てきた。だったら、制作準備のプロセスを大きく見直すべきだ。日テレ報告書にある通り、放送の1年半前に企画を決定すること、契約書締結を早期化すること。せっかく作った報告書にこうした提言があるのだから、日本テレビはそれをどうしたら具現化できるかに取り組んでほしい。
いま、配信サービス「TVer」で人気だからとドラマ制作の本数がどんどん増えている。粗製濫造に陥りかけていないだろうか。そして個々の現場で小さなトラブルが起こり、原作者や脚本家に限らず疲弊する人たちが生まれていないか心配だ。
業界全体でこの2つの報告書を読み込んで、仲間たちと議論し、業界の明日に繋げてほしい。間違っても「机上の空論」と切り捨ててはいけない。そんな姿勢では、日本のコンテンツは世界市場へ羽ばたけないだろう。
----------
メディアコンサルタント
1962年福岡市生まれ。東京大学文学部卒。I&S、フリーランス、ロボット、ビデオプロモーションなどを経て、2013年から再びフリーランス。有料マガジン「MediaBorder」発行人。著書に『拡張するテレビ』(宣伝会議)、『爆発的ヒットは“想い”から生まれる』(大和書房)など。
----------
(メディアコンサルタント 境 治)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
フジ 日テレ「セクシー田中さん」調査報告書受け「映像化させていただくという立場を肝に銘じ」
スポニチアネックス / 2024年7月5日 17時44分
-
日テレ系番組「どうなの課」は、なぜTBSに"移籍"したのか…テレビ局と制作会社の「上下関係」に起きている大異変
プレジデントオンライン / 2024年6月24日 10時15分
-
「改変ありきに問題」「作るうちに想定外の展開も」 BPO、日テレ『セクシー田中さん』調査報告書を議論
マイナビニュース / 2024年6月21日 17時23分
-
第2の「セクシー田中さん」が生まれるだけ…「芦原さんの死は日テレのせい」という安易な決めつけが危険な理由
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 16時15分
-
「どの面下げて」24時間テレビ強行、水卜アナ謝罪で日テレ炎上…「出禁」「原作改変」多すぎる不祥事
週刊女性PRIME / 2024年6月21日 6時0分
ランキング
-
1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分
-
2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」
日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分
-
3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分
-
4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃
乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分
-
51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO
ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











