三流は周囲から蔑まれる、二流は敬われる…2500年前から変わらない「最高のリーダー」のたった一つの特徴
プレジデントオンライン / 2024年6月20日 16時15分
一流のリーダーにはどんな特徴があるのか。コンサルタントの山口周さんは「真に優秀なリーダーとは、問題が発生しても自らの手で解決したりしない。大した成果が得られないことをよく知っているからだ」という――。
※本稿は、山口周『クリティカル・ビジネス・パラダイム 社会運動とビジネスの交わるところ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■論理的に正しいのに、なぜ失敗してしまうのか
社会運動、社会批判という側面を強く持つビジネス、クリティカル・ビジネスを実践するにあたって、そのアクティヴィストには「問題をシステムとして捉える」、いわゆるシステム思考の素養が必要になります。
システム思考とは、問題の発生する原因を局所的なものではなく、自分も含めたシステム全体にあると考え、システム全体を改変することを志向するアプローチです。
どうにもイメージが湧きにくいですね。ではシステム思考と対照的な思考方法である要素還元主義の論理思考がもたらした実例について考えてみましょう。以下は実際に起きた問題です。
●ホームレス保護施設を増やしたら、ホームレスが増加した
●麻薬の取り締まりを強化したら、麻薬犯罪が増加した
●食糧援助を展開したら、飢餓が増加した
●厳しい実刑判決の実施によって、凶悪犯罪が増加した
●職業訓練プログラムの導入によって、失業率が悪化した
これらはなぜ起きるのでしょうか。間違いなく一つ一つの政策や取り組みは論理的に正しく、善意に基づいています。しかし、それらの論理的に正しく、また善意に基づいている施策によってかえって悪い結果がもたらされているのです。
■システムへの洞察がなく、症状しか見ていない
クリティカル・ビジネスの実践にあたって、アクティヴィストはもちろん、社会的な問題の解決を目指してイニシアチブを起こすわけですが、ここで注意しなければならないのは、複雑なシステムに関する洞察のないままに、問題の症状への対処を行うと、問題は解決されないばかりか、かえって悪い状況を招きかねないということです。
善意から行われたものであるにもかかわらず、結果的により悪い方向へ状況を変化させてしまうイニシアチブには、三つの共通項があります。
●根本的な問題ではなく、症状へ対処している
●誰の目にも文句なしの策に映る
●短期的には効果がある場合も多い
このようなイニシアチブの発動に対して、当初の成果に多くの関係者は喜びます。しかし、長期的かつ広範囲の因果関係によって短期的な効果が徐々に損なわれていくことになり、やがて意図せざる、大きなマイナスの結果が生み出されます。このような現象の典型例として挙げられるのがDDTです。
■マラリアを撲滅したら、次はペストが蔓延した
20世紀の前半まで、マラリアは文字通り「人類の敵」でした。マラリアのせいで毎年何万人、何十万人という人が亡くなっていたのです。このマラリアを撲滅するために開発されたのが殺虫剤DDTでした。
DDTは、本当の意味で虫を殺す歴史上最初の殺虫剤で、第二次世界大戦中には発疹チフスやマラリアの発生を抑制するために莫大な量が散布されました。
この散布は劇的な効果を上げ、たとえばスリランカでは1948年から1962年までDDTの定期散布により、それまで年間250万人いたマラリア患者の数を30人にまで激減させることに成功しています。そして、その絶大な効果を確認した世界保健機関=WHOは1955年、DDTによって地球上からマラリアを撲滅すると高らかに宣言したのです。
ところが、ほどなくしてWHOのもとに、DDTの散布地域であったボルネオで、奇妙な現象が観測されているという報告が届くようになります。DDTを散布した地域だけでペストが異常に蔓延しているというのです。
調査によってわかったのは、次のようなメカニズムでした。
DDTは極めて安定性の高い化学物質で土中でも分解されません。残留したDDTは、マラリアを媒介する蚊を撲滅したわけですが、DDTの毒性に対して耐性を持つゴキブリは体内にDDTを蓄積していきました。
■解決策が新たな問題の原因にならないために
そしてこのゴキブリを捕食したトカゲはDDTにより神経を冒されて酒に酔ったようになり、簡単にネコに捕食されるようになります。ところがDDTに耐性のないネコはバタバタと死んでしまい、結果、天敵であるネズミが大量に発生し、ペストが蔓延したのです。
マラリアを媒介する蚊の根絶という側面については、DDTは文字通り絶大な威力を発揮したわけですが、別の側面ではとても大きな問題を生み出すことになってしまったのです。つまり「解決策が新たな問題の原因になっている」ということです。
では、どうすれば、このような状況が発生することを防げるのでしょうか? システムリーダーに必要な三つのコンピテンシーを用いることによって、というのがその回答になります。
システムリーダーが用いる一つ目のコンピテンシーは「より大きなシステムを捉える」能力です。複雑な状況では、人は大抵、自分に都合の良い視点から問題を捉えます。問題に関わっている人々が、それぞれの立場から問題の枠組みを捉えることで、常に「誰の視点が正しいか」という不毛な議論を引き起こすことになります。
複雑なシステム問題について関係者の共通理解を形成するために、各人が描く局所的な枠組みを包括する「より大きなシステム」を捉えるコンピテンシーがシステムリーダーには欠かせません。
■自己内省し、組織で共有できる力が必要
システムリーダーが用いる二つ目のコンピテンシーが「生成的な対話を促す能力」です。カギになるのは内省の能力です。内省は、自分の思考について考察し、自分ですら囚われていることに気づいていなかった呪いについて意識的になることを可能にします。
その内省の結果を各人が他者と共有することで、組織や個人からなる集団がそれぞれの異なる意見を本当の意味で聞き、互いの見ている現実を認知的だけではなく、感情的にも理解し合うことが欠かせないステップとなります。
システムリーダーが用いる三つ目のコンピテンシーが「リアクティブからアクティブへとフォーカスを移す能力」です。
クリティカル・ビジネスのアクティヴィストは、常に望ましくない状況を起点にしてイニシアチブを立ち上げます。多くの場合、このようなイニシアチブは、目の前の問題に局所的、かつ反応的に対処することになりがちですが、システムリーダーは、集団が、問題への対処に終始するのではなく、前向きな未来のビジョンを作り出すことができるようにファシリテートします。

■一流のリーダーは、他者に達成させる
言葉を変えて表現すれば、システムリーダーは「自らの手でアジェンダを解決すること」を志向しないということです。なぜなら、このようなアプローチでは大した成果が得られないということをよく知っているからです。システムリーダーは、変化が生まれ、変化が自律的に継続するような場を生み出すこと、に注力します。
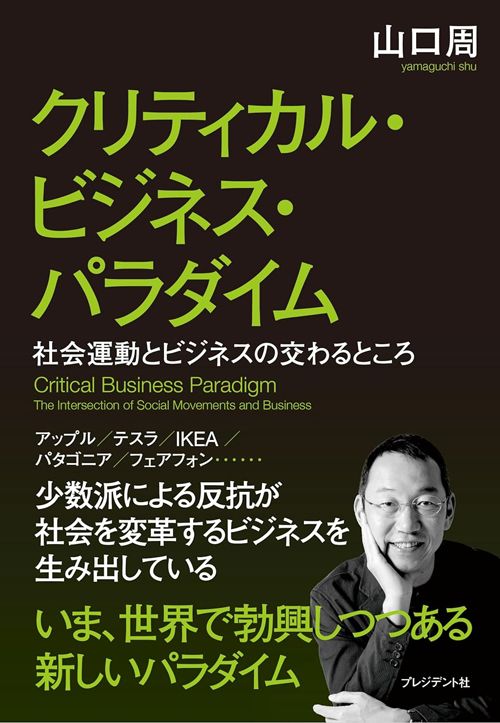
いまからおよそ2500年前、システムリーダーの理想について述べた賢者がいます。
悪いリーダーは、人々から蔑まれる。
良いリーダーは、人々から敬われる。
最高のリーダーは、人々に「私たちがやった」と言わせる。
老子のこの言葉は、クリティカル・ビジネスのイニシアチブをとるリーダーにとっても、非常に示唆に富んだものだと思います。
クリティカル・ビジネスが、その定義上、これまで解決されることのなかった社会的問題にアドレスする以上、その問題は複雑なシステム問題であることが少なくありません。
クリティカル・ビジネスのアクティヴィストはすべからく、システムリーダーとしてのコンピテンシーを果たさなければならないのです。
----------
独立研究者・著述家/パブリックスピーカー
1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て現在は独立研究者・著述家・パブリックスピーカーとして活動。神奈川県葉山町在住。著書に『ニュータイプの時代』など多数。
----------
(独立研究者・著述家/パブリックスピーカー 山口 周)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
A-STEP実装支援(返済型)におけるSORA Technology株式会社への開発支援の決定
PR TIMES / 2024年7月1日 18時15分
-
モンタビスタ、CentOS 7に対するMVShieldの対応を延長 最短でも2034年までの10年間サポートを継続へ
@Press / 2024年7月1日 10時30分
-
山口周氏 ご登壇!日立がオンラインセミナー「生成AI×ヒューマニティ~ビジネスの未来を創る鍵~」を7月12日(金)に開催
PR TIMES / 2024年6月24日 12時45分
-
PagerDuty、Snowflake Trailとの統合によりオブザーバビリティワークフローを強化
Digital PR Platform / 2024年6月17日 11時4分
-
グーグルやフェイスブック創業者は、なぜ趣味を仕事にできたのか…山口周が考える「仕事で大成する人」の特徴
プレジデントオンライン / 2024年6月14日 16時15分
ランキング
-
1最高値を更新した日本株の上昇は今後も続く ただし短期では強弱感対立による激しい攻防も
東洋経済オンライン / 2024年7月8日 10時30分
-
2なぜSuicaのペンギンは愛されるのか ペンギンの顔をした「ベレー帽」が“激アツ”の理由
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月7日 7時30分
-
3苦しんでいる人の「死にたい」という発言に「そんなこと言わないで」と返すのがNGな理由【医師・和田秀樹氏が解説】<br />
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月8日 10時0分
-
4「成田空港駅」が廃止!? 空港の旅客ターミナル再編で鉄道も大変革か 「新駅」も想定
乗りものニュース / 2024年7月8日 14時42分
-
5ボーイング、司法取引で詐欺共謀罪認める方針 2度の墜落事故巡り
ロイター / 2024年7月8日 15時12分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











