なぜ心臓手術の名医は「ガラス張りの手術室」を作ったのか…日本は手術を隠したがるダメ医者が多すぎる
プレジデントオンライン / 2024年6月12日 8時15分
※本稿は、渡邊剛『心を安定させる方法』(アスコム)の一部を再編集したものです。
■絶対にミスが許されない心臓外科医の習慣
心得 「メンタルフラット」で生きよう
時間が止まったかのような、研ぎ澄まされた感覚を得ることを「ゾーンに入った」と言うそうです。
世界的なハードル選手だった為末大さんは、認知心理学者の下条信輔さんとの共著『自分を超える心とからだの使い方』(朝日新聞出版)のなかで、「ゾーンに入った」経験は人生でたった3度だけとおっしゃっています。
ゾーンに関する話題は、漫画やアニメの世界でも描かれることが多く、周りの人たちの動きが止まって見えるなか、主人公だけ動けているシーンや、周囲の音が一切消えて、自分の世界だけが描かれている場面を目にしたことがある方もいると思います。
心臓外科医である私にも、「手術をしているときの感覚も同じですか」と、取材をしてくださる記者の方から聞かれることがよくあります。
そんなわけがありません。
もし、あなたが患者として、私に心臓手術の執刀を託してくださったとしましょう。
日によって驚くほどの実力を発揮することもあれば、そうでもない手術をすることもある心臓外科医。こんなパフォーマンスに波のある外科医に、自分の命運を賭けたいと思いますか? 少なくとも、私が患者なら嫌です。
■「いつもと同じ」が理想的
心臓外科医にとって、何よりも大切なのは「メンタルフラット」であること。緊張しすぎず、いつもどおり、練習でやってきたことを本番でも再現することに意識を向けます。
そして、もし何か最初の想定とは違うことが起きたとしても対応できるように、スタッフからの声が聞こえるくらいの深さの集中をもって、患者さんと向き合います。
毎回ゾーンに入れるのであればいざ知らず、為末さんでさえ、生涯において経験されたのはわずか3回だけです。そんな奇跡のような状態を引き出そうとするよりも、実力をしっかり発揮できる力を身につけるほうが、価値があると思います。
では、仕事においてパフォーマンスにムラがある人と、パフォーマンスの波が少ない人で比べた場合、どちらに仕事を任せたいと思うでしょうか。
多くの方が、後者に仕事を任せると思います。なぜなら、仕事を任せるときは「期待どおりの働き」を相手に求めているからです。はじめから「期待以上の働き」を求めている人はいないでしょう。
大事なのは「いつもと違う力を発揮する」ことよりも、「いつもと同じ力をどんなときでも発揮できるようになる」ことです。「メンタルフラット」を強く意識してください。
■手術直前に患者の手を握る
心得 違和感を「気のせい」にしない
朝起きて、なんか今日はいつもとちょっと違う感じがするとか、今週は嫌なことが立て続けに起こるなどと思うことはありませんか?
「気のせい」かもしれませんが、そういった「自分を取り巻く“気”の違い」を感じた場合、その違和感はスルーしないほうが賢明です。
私は手術当日、患者さんのもとを訪ね、最後に手をギュッと握ることを習慣にしています。手術前に患者さんの手を握るのは、単なる挨拶ではありません。お互いの気持ちの確認です。

これは滅多にあることではないのですが、手を握った直後に私のほうから「今日、手術をするのはやめましょう」と言うこともあります。
それは、患者さんのエネルギーを感じ取れないときです。
今日、病気と闘って絶対に元気になる! そう強く意志を固めている患者さんからは、エネルギーが伝わってきます。でもときに、そうでないこともあります。手が冷たいだけでなく、「エネルギーの交流ができていない」と感じるのです。
■迷ったまま行動を起こしてもいい結果は得られない
たとえば、こんなことがありました。
患者さん自身が、じつは手術を受けることに積極的ではないのです。それでも親族から「手術を受けたほうがいい」と言われ入院したものの、本当は手術を受けたくないという気持ちが強い。事前にお会いして話したときは「手術を受けます」と口にしながらも、本当は迷い続けている。
そんなとき、私は言います。
「今日は、お帰りください」と。
緊急を要する場合を除けば、気持ちが定まっていないときに手術を受けることはよくありません。自分の体の行方は、自分の意志で決めるものです。互いの心が通じ合っていないと、最善の手術はできません。
それでも、見放すつもりはもちろんありません。迷っているなら延期しましょう、ということです。人間誰しも迷いはあります。
そして、迷ったまま行動を起こしても、自らが願う結果にはたどり着けません。
自分が感じた違和感を、大切にしてください。そして、相手から感じた違和感にも敏感になりましょう。心の揺れは、ほうっておくといずれ大きな問題となって、あなたにかならず降りかかります。
「あのときこうしていればよかった」と思うのは、うすうす違和感に気づいていながら放置した結果なのです。
■流行や評判を過度に気にしない
心得 流れに執着してはいけない
何事にも流行りすたりがあります。ファッション、フード、生活スタイル、テレビタレントの人気、受験勉強のやり方など、さまざまな分野に「流行」はあります。そしてこれは、医療の世界にも存在します。
治療法、術式、投薬などでも一時は盛んに用いられていたことが、いまでは行われていないものが多々あります。
もちろんこれは医療の進歩によるところも大きいのですが、一種の流行と捉えることもできるでしょう。さらに専門医がよいか、総合的に診られる医者がよいかなどの評判にも流行があります。
さて、この流行ですが、どのようにしてできるのでしょうか。
個人個人の趣向が同じ方向を向くことで生じると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
最初は小さな波なのです。それを見たり感じたりした周囲の人たちが「これが今年のトレンドなんだ」とそれに合わせていくなかで流行はできあがっていきます。たとえば複数のファッション誌がいっせいに「今年の冬コーデはこれで決まり!」といった特集を組むと、それに倣っていく感じです。
(自分だけ違ったことをしていたらカッコ悪いから)そんな気持ちを持つ人が多いように思います。逆から見れば、だから流行が生まれるのでしょう。
■「本当にやりたいことは自分の心の声に従いなさい」
流行を追うことを楽しめて、有意義ならそれはいいと思います。でも、流行を追い続けていてはいけません。なぜならば、周囲に流され続けていると、独自の思いや考えを明確にできなくなってしまうからです。
なぜこれが流行っているのかを考え、その本質を見抜くことは大切ですが、追う必要はないのです。人の意見を聞かなくてもいいとは思いません。でも、周囲の声に過敏になりすぎてもいけないでしょう。
映画監督の小津安二郎さんは、かつて「なんでもないことは流行に従う。重大なことは道徳に従う。芸術のことは自分に従う」と『キネマ旬報』の取材で語られていました。
これは、「本当にやりたいことは自分の心の声に従いなさい」と言い換えることができるのかもしれません。自身の軸をしっかりと持ち、自分を信じ邁進したときに初めて、動じない心を手に入れることができるのです。

心得 心を丸裸にすれば不安は消える
みなさんはドラマや映画での場面以外に、実際の手術の現場を見たことがありますか? おそらく、医療関係者でもない限り、ほとんどの人が「ない」と答えることでしょう。
「手術室は閉ざされたもの」というのが、かつては常識でした。でもご家族は、心配で「手術の様子を見ていたい」と思われるのではないでしょうか。密室のなかで何が行われているかわからないのでは、不安が募るのも当然です。
■手術室をガラス張りにした理由
見てもらえばよいのではないか、と私は思いました。
「手術は医療側の秘事であって、他者に見せるものではない」
そのあり方には、ある種の権威主義的意識を感じます。医師が自信を持って適切な手術をしているのであれば、ご家族に見ていただいてもなんの不都合もないはずでしょう。
そこで私は、「ニューハート・ワタナベ国際病院」の手術室をガラス張りにしました。希望されるご家族には手術の様子を見守ってもらっています。
スタッフがどのように関わり、手術がいかに進行しているかを実際に見て納得していただきたいからです。
これは私がタイの病院を視察した際に初めてガラス張りのオペ室を見て、「導入しよう」と思ったことがきっかけでした。私が知る限り、日本にはガラス張りでご家族に見てもらえる手術室は当院にしかありません。今後、開かれた手術室が全国に広がることを望んでいます。

もう少し言えば、手術は医師が一方的に行うものでもありません。手術は、医師と患者さんの共同作業です。患者さんと医師の信頼関係が築けてこそ、その後のみなさんの人生を有意義にする手術が行えます。絶対に病気を治す、手術を成功させるーー。そのために私は、つねに最善を尽くします。と同時に、患者さんにも強い気持ちを持っていてほしいと思っています。
さらには手術室や医療の現場を開かれたものにすることで、お互いの不安をなくし、物事が前向きに進むことを願っています。都合の悪いことは隠したくなるのが人情ですが、じつは隠さないことこそ、心の乱れをなくす第一歩なのです。
■「ダメな病院」を見分けるためのポイント
「先生から見て、どういう病院がいい病院と言えるでしょうか?」
私がこれまで受けてきた取材のなかで、もっとも多い質問のひとつです。それだけ多くの方が、病院選びに悩んでいらっしゃるのでしょう。
私が考える「いい病院」にたどりつく方法は、次の4つです。
② 病院の名声ではなく命を預けるにふさわしい医者かどうかで考える
③ 医療と関係ないところで判断をしない
④ 他院へのセカンドオピニオンを快諾しているかを確認する
ひとつ目ですが、病院のホームページを見ていったときに、去年や一昨年の成績がきちっと載っていて、手術数も実績として載っているような病院でしたら、まずはひと安心でしょう。
ここで気をつけなければいけないのは症例数。年間の症例数が少ないために、過去数年間の合算で「何百件」と出している病院があります。
こういう掲載の仕方をしている病院は、避けたほうがいいでしょう。嘘はついていないでしょうが、数年分を合算することで、かさを増しているだけです。
■「実績のかさ増し」には要注意
たとえば「手術実績100件以上」と書かれているものの、よく見たら小さく(過去5年)と書かれているケース。1年間あたりで割るとたった20件です。参考に、私の病院の2023年の年間心臓手術件数は、639件でした。
海外に目を移すと、心臓手術年間500件はスタンダードなライン。ですので、5年で100件がどれだけ少ないか、そこに自分の命を預けることがどんなに危ないことかがわかっていただけるかと思います。
あなたの命は、手術手技で決まります。“手術”は飲んで効く“薬”ではありません。名医は必ずいますから、必ず手術実績が掲載されている病院で、スーパードクターを選ぶようにしてください。
■病院の名前・ブランドよりも実績のある医師を選ぶ
ふたつ目は、病院の大きさや名声だけで安易に命を託してはいけないということです。事前に実績を調べて目星をつけた病院に行ってみても、対応に違和感を覚えたら迷わず次の病院を探すことを考えてください。
本来であれば患者さん側が医者の情報にアクセスしやすい環境がもっと整っているべきなのですが、残念ながら日本はまだまだそのあたりが遅れています。
ちなみに私が考える理想は米国ニューヨーク州のアクセス方法です。たとえば「○○先生が執刀した年間執刀件数は何例、死亡が何例」といったことが、調べればすべて出てきます。
非常にフェアな方法なので日本でもぜひ取り入れてほしいところですが、現状はそうなっていないので、「この医者は私の命を託すに値する医師かどうか」という視点で選ぶようにするといいでしょう。
3つ目ですが、これは日本の患者さん特有の感覚でしょう。ひとつ目で避けたほうがいいといった病院に万が一入院した場合。普通であれば転院しようという気持ちになるはずですが、実際はなかなかなりません。
とても不思議なことに、日本の患者さんは、自分がかかっている病院のことを「いい病院だ」と思い込もうとする傾向があります。
■セカンドオピニオンを拒否する医者は絶対NG
「先生が親切」とか「若いけれどよく見てくれる」とか、医療以外の面を重視してしまい、結果としてわざわざ患者さんが高いリスクを負ってしまう。あるいは、地方ほど「この病院に見捨てられたらほかの選択肢がない」という考えを持ってしまう人もいるでしょう。
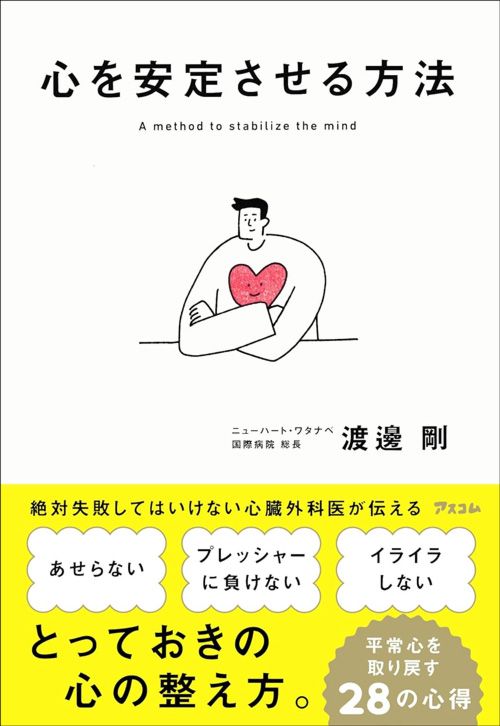
心臓外科は、最終的には腕がすべてです。
そして最後の4つ目ですが、患者さんが他院へのセカンドオピニオンについて尋ねた途端、「もう今後は診ない」とか「あそこに行ってもよくないよ」などと言い出す医者ならば、すぐに病院を変えてください。その医者はおそらく、自らの医療が劣っていると考えているか、プライドを傷つけられたと感じていると思います。
生死に関わるような事態に、医者のプライドをくみ取る必要などまったくありません。ベストな環境での治療を選ぶことが大切です。
もし、みなさんの周りで病院探しをしている方がいたら、この4つのポイントをぜひ伝えてみてください。
----------
心臓血管外科医
1958年、東京都生まれ。心臓血管外科医、ロボット外科医(da Vinci Pilot)、医学博士。日本ロボット外科学会理事長、日伯研究者協会副会長。麻布学園高等学校卒業後、医師を志す。金沢大学医学部卒業後、金沢大学第一外科に入局する。海外で活躍する心臓外科医になりたいという夢を叶えるためドイツ学術交流会(DAAD)奨学生としてドイツHannover医科大学に留学。金沢大学心肺・総合外科教授、国際医療福祉大学三田病院客員教授などを経て、2014年にニューハート・ワタナベ国際病院を開院。著書に『医者になる人に知っておいてほしいこと』(PHP新書)などがある。
----------
(心臓血管外科医 渡邊 剛)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
心臓外科医が説く「手術に向き合う」心の整え方 「ゾーンに入る」ことを期待してはいけない
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 19時0分
-
国内では「猟奇的」と非難された…「世界初の内視鏡心臓手術」を実現した医師が日本の医療界に言いたいこと
プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分
-
ダメな医師ほど患者の話を聞かない…心臓手術の名医が「勉強熱心な患者を迷惑がる医師は三流」というワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月13日 8時15分
-
「良い手術を受けるために患者さんがすべきこと」と「日本の医療制度の問題点」/渡邊剛(ニューハート・ワタナベ国際病院総長)
マイナビニュース / 2024年6月12日 7時30分
-
増加する心臓病─。知っておきたい病院選びのポイント /渡邊剛(ニューハート・ワタナベ国際病院総長)
マイナビニュース / 2024年6月11日 7時30分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












