ダメな医師ほど患者の話を聞かない…心臓手術の名医が「勉強熱心な患者を迷惑がる医師は三流」というワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月13日 8時15分
※本稿は、渡邊剛『心を安定させる方法』(アスコム)の一部を再編集したものです。
■医師は常に患者を見ているとは限らない
心得 白衣を着たらやることはひとつ
「懈慢界(けまんがい)」という仏教用語があります。無数の快楽によって、極楽浄土に生まれようとする本来の目的を見失わせる世界のことを言うそうですが、まさにこの世の中はその世界に近づいてきているような気がします。
私が初めて「オフポンプ手術」を成功させたころの医学界の反応は、決して好意的ではなく、それどころか、激しい批判を浴びました。
1994年の日本外科学会で、私は手術の成果を発表しました。より安全な手術を多くの医師に行ってもらい、患者さんのリスクをできる限り取り除きたいと思ったからです。
理解を得られると思っていたのですが、そうではありませんでした。この学会で司会を務めた医学界の重鎮である国立系専門センターの総長は、みんなにこう呼びかけたのです。
「こんなトリッキーで危険な手術をやりたいという人がいたら、手を上げてください」
会場は静まり返り、誰も手を上げませんでした。露骨な嫌がらせだと私は感じました。
なかには、私の発表に興味を持った方もいらっしゃったことでしょう。でも、重鎮である総長に忖度し、手を上げなかったのだと思います。もしくは、新しいやり方を提示されるのが嫌な方もいたのかもしれません。
■目を向けるべきは学会の反応ではなく患者
自分たちのこれまでのやり方を否定された気持ちになったのか、それとも新たな手術のやり方に対応する自信がなかったのか……。
このときに私は、改めて思いました。目を向けるべきは学会の反応ではなく、患者さんのためにさらに手術を進化させることだと。“白衣を着たら、やることはひとつ”です。
何か新しいことを始めようとしたとき、それを邪魔するのは「一般的ではない」という固定観念。また、新機軸への共鳴を拒むのは「周囲から何を言われるかわからない」という自己保身意識です。
本当に大切なことは、「なんのために、誰のためにやるのか」という本来の目的を忘れないことです。
とはいっても、長い人生においてさまざまな人の影響を受けて、自分も気づかないうちに、それを見失ってしまうこともあるでしょう。
だからこそ、白衣を着たら何をすべきか思い出すことが医者に必要なように、みなさんも、たとえばスーツを着たとき、仕事着を着たとき、「なんのためにやるのか、誰のためにやるのか」を思い出す習慣をつけてください。
それだけで、心が本来の目的に立ち戻るきっかけをつかむことができるはずです。
■医師は病状や治療法、手術の内容を丁寧に説明すべき
心得 言葉に「血が通っているか」を見極める
医師である私が言うのも変ですが、病院は嫌なところです。用事がなければ近づきたくないでしょうし、できれば病院に行かないといけない事態は極力避けたいと思っているはずです。
ですが、もし体調を崩してしまったら、自分が患った病状について、あるいは手術が必要な場合はどのようなことが行われ、術後にどのようになるかについて、医師から説明を受けることになります。
これはどの科においても同じかもしれませんが、医師が悪い意味で「患者に慣れてしまっている」傾向があるように感じます。
診察する医師にとっては見慣れた病気で、その患者さんは大勢の患者の一人にすぎないのかもしれません。しかし、その患者さんにとっては、自分の身に突如としておきた異変ですから、不安になって当たり前です。
「自分の病状、治療法、手術の内容をとことん知りたい」
そう患者さんが思うのは、当然のこと。しっかりと説明を受け、治療、手術を受けるべきです。また逆に患者さんの意向も、医師はしっかり聞くべきでしょう。

■「セカンドオピニオンを聞きたい」と聞けば分かる
医者の言うことを黙って聞いていればいい――それは違います。医療は、患者さんと医師の信頼関係をなくして成り立たないのです。
もし納得がいかなければ、「セカンドオピニオン」「サードオピニオン」を患者さんは求めることができます。これは近年、一般化してきているのですが、こんな悲しい話をしょっちゅう耳にします。
「セカンドオピニオンを聞きたい」。
そう申し出た患者さんに対して「じゃあ、もううちでは診ない!」と医師が怒り出したというのです。でも、そんな狭量な医師の言うことなんて、聞く必要はありません。
医者は星の数ほどいますが、世界にひとつだけの、大切なあなたの体のことなのですから、多様な診断や治療法を求めることも当然の権利です。医師に限らず、決意して打ち明けた不安に理解する姿勢を示さない人とは、距離を置くことをおすすめします。
「人はいつかわかりあえる」という考えがあります。たしかに、多くの時間をかけて丁寧にコミュニケーションを続けていけば、いつかそうなれると私も信じたい。でも、いつまでたっても平行線の人間関係も、実際に存在します。
とりわけ病気に限っては、時間との勝負です。みなさんの抱えている不安を取り除かずに、淡々と流れ作業のように体を診る医師に割いている時間など、一秒たりともないのです。
■医師と患者に上下関係は存在しない
心得 心を曇らせてはいけない
人と信頼関係を築くときに、私が大事にしていることとは何か。それは、「真摯であれ」ということです。まず、しっかりと患者さんの話を聞く。この基本ができていない医師が、とても多いと感じます。
「先生」と呼ばれることで、勘違いしてしまっているのかもしれません。
ときには、患者さんは自分の言うことを聞くものだと思い込み、横柄な態度で接している医師もいます。医師と患者の間に、上下関係などありません。
私は、決して人付き合いのいいタイプではないと思います。必要以上に相手に気を遣って馴れ合うことはしませんし、お酒を飲むこともほとんどありません。時間があるなら、自分が没頭できることに割きたいと考えます。
それでも、人に対しては誠実に接したいと思っていますし、いままでもそうしてきたつもりです。群れて生きる必要性を感じたことはありませんが、出会った人に対しては、誠実に謙虚に、まっすぐに向き合いたい。
これは、「医師として」というよりも、「人として」至極当然のことだと思います。
相手の立場によって態度を変える人がいます。手術室でも、そういう外科医はたくさんいます。自分よりも立場が上の人にはペコペコし、下の者には威張り散らす。そんな人に、私は嫌悪感を抱きます。人を見下すような人は、自分より立場が上にあっても、尊敬する気にはなれません。
■横柄なのは「心の曇り」「自信の無さ」の表れ
横柄な態度は、人の気持ちがわからない「心の曇り」であり、同時に「自信のなさ」から生じるものです。立場に見合う実力を備えていないから、自分を大きく見せようと尊大に振る舞っているにすぎません。
ただ、ポジションが人を狂わせてしまうこともあるので、その可能性も頭の片隅に置いておいてください。
課長や部長など、役職で呼ばれるようになると、どうしてもその役割のイメージを演じようと、自分でも気づかぬうちに悪い方向に変わってしまいます。だからでしょうか。最近はどの役職であろうと、肩書ではなく「○○さん」と名前で呼ぶことをルール化している企業が増えてきたと聞きます。
いちばん大事なのは、誰に対してもつねに真摯な姿勢でいること。心を曇らせず、年上・年下、役職にとらわれず、人と真摯に向き合うことを忘れないでください。

■いい治療を受けるためにするべきこと
私は金沢大学附属病院時代の2005年から、患者さんが私に直接相談をできるようにするため、心臓手術に関する相談フォームをホームページに設けています。
「メール外来」と呼んでいただくこともあるこの相談フォームですが、これまで心臓に不安を抱える多くの方々とやり取りをしてきました。
いただいたメールはすべてに目を通し、よほどの事情がない限りはすぐに返信するようにしていますが、ときに深刻な場合は相談相手から検査結果や経過を聞き、必要な場合には当院で手術を行っていただくことも幾度となくありました。
たくさんの方とやり取りをしてみて思うのは、私のところに相談をしてくださる方は、自分の病状や治療法を本当によく調べている、ということです。
それは決して悪いことではなく、むしろ非常にプラスです。
こういった心配をされる患者さんがよくいらっしゃると聞きます。
「先生にあまりあれこれ聞きすぎると嫌な顔をされないだろうか」
「医者でもない自分が、治療法について疑問を投げかけるのはおこがましいのではないか」
これらは私から言わせていただくと、気にする必要はまったくありません。
■「お医者さんにすべて任せましょう」はもう古い
私のもとに相談に来られる方のなかには、論文まで読み込んで、「だから先生の手術を受けたいんです」と言って来られる方もいらっしゃいます。
もちろんみなさん全員がそうする必要はありませんが、診断を下した医者から言われた治療法だけがすべてではありません。
インターネットの検索画面にキーワードを打ち込めば、関連する項目が無数に出てくる時代において、ひとりの医者の言葉を妄信することなく、自ら治療法の選択肢を広げていくことが大切です。
そのときに、情報の波に飲まれそうになったら、心臓に関しては私にメール相談をしてくださったらいいと思います。
治療法だけでなく、予後に関しても調べておくことを勧めます。どんな手術を受けたかによって、回復や退院するまでの日数は大きく変わります。とくに、早く復帰しなければいけない状況にある方にとって、どれくらいで歩けるようになり、退院できるのかは、これまでの生活を維持していくうえでも大切なことでしょう。
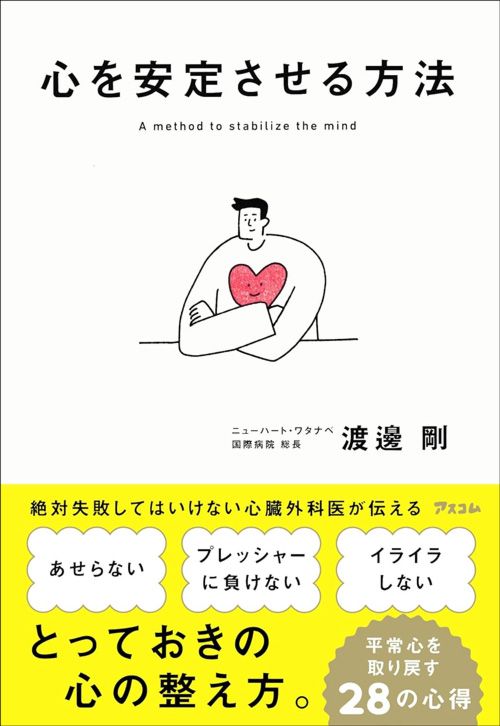
私の友人で肺がんの手術を行っている外科医がいます。彼の手術を受けた患者さんは、手術終了1時間半後には歩けて、水を飲んで吐き戻しがなければ昼ご飯が出ます。しかも、80歳の高齢者であろうと関係ありません。そして、翌日には退院できるそうです。
このような患者さんの予後にまで気を配れるすばらしい医者は、調べることで出会える可能性が広がります。はじめから「お医者さんにすべて任せましょう」という考えは、もう古いと言えるでしょう。
誰に自分の命を託すのか。まずご自身の手で調べることがQOL(生活の質)の向上にもつながるのです。
----------
心臓血管外科医
1958年、東京都生まれ。心臓血管外科医、ロボット外科医(da Vinci Pilot)、医学博士。日本ロボット外科学会理事長、日伯研究者協会副会長。麻布学園高等学校卒業後、医師を志す。金沢大学医学部卒業後、金沢大学第一外科に入局する。海外で活躍する心臓外科医になりたいという夢を叶えるためドイツ学術交流会(DAAD)奨学生としてドイツHannover医科大学に留学。金沢大学心肺・総合外科教授、国際医療福祉大学三田病院客員教授などを経て、2014年にニューハート・ワタナベ国際病院を開院。著書に『医者になる人に知っておいてほしいこと』(PHP新書)などがある。
----------
(心臓血管外科医 渡邊 剛)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
心臓外科医が説く「手術に向き合う」心の整え方 「ゾーンに入る」ことを期待してはいけない
東洋経済オンライン / 2024年6月16日 19時0分
-
国内では「猟奇的」と非難された…「世界初の内視鏡心臓手術」を実現した医師が日本の医療界に言いたいこと
プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分
-
なぜ心臓手術の名医は「ガラス張りの手術室」を作ったのか…日本は手術を隠したがるダメ医者が多すぎる
プレジデントオンライン / 2024年6月12日 8時15分
-
「良い手術を受けるために患者さんがすべきこと」と「日本の医療制度の問題点」/渡邊剛(ニューハート・ワタナベ国際病院総長)
マイナビニュース / 2024年6月12日 7時30分
-
増加する心臓病─。知っておきたい病院選びのポイント /渡邊剛(ニューハート・ワタナベ国際病院総長)
マイナビニュース / 2024年6月11日 7時30分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












