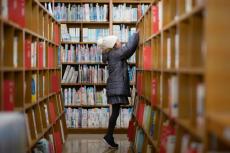本当の原因は「日本人の活字離れ」ではない…「街の本屋」がどんどん消えているビジネスモデル上の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月18日 16時15分
※本稿は、小島俊一『2028年 街から書店が消える日 本屋再生!識者30人からのメッセージ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■「販売の生命線」が絶たれる衝撃
世の中の方々には、「コップの中の嵐」に過ぎないでしょうが、昨年、出版界というコップの中で大きな嵐が起こりました。
コンビニの雑誌は取次の日販やトーハンが物流と決済機能を担っています。日販はローソン・ファミリーマートと取引があり、トーハンはセブンイレブンと取引があります。そんな中、日販が2024年にローソン・ファミリーマートとの取引を中止するという話があり、それが出版社に伝えられました。日販にとって大きな赤字部門であるコンビニとの取引から撤退したい強い意向が示され、出版界は大騒ぎになりました。
本稿では、この顛末と共に「街に書店を残す処方箋」の一部をお伝えます。
出版社にとって、コンビニの雑誌販売は広告料収入の面から言っても、雑誌販売の生命線です。その中でローソン・ファミリーマートの販売占有は大きく、この販売ルートを失うことは、出版社にとって大打撃になり、雑誌存続にも関わります。
日販の奥村景二社長は、「コンビニルートの2023年度売り上げは280億円で赤字が40億円にもなる見通しだ」と話されています。日販全体としても2023年度通期でもかなり厳しい決算が見込まれています。この現状に鑑み日販はローソン・ファミリーマートとの取引辞退を決めたのでした。
■「コンビニ配送のついでに書店に本を運んでいる」
これに対してトーハンは、川口雑誌新センターに42億円もの投資をしてでも取次事業を守り全国の書店に寄り添い続けるとして、ローソン・ファミリーマートとの取引は2025年7月から始めることになりました。
出版流通は雑誌配送が根幹になっています。特に全国に5万軒あるコンビニルートがその中心です。極端な言い方をすれば、「コンビニ配送のついでに書店に本を運んでいる」状態です。日販が手放したローソン・ファミリーマートとの取引をトーハンが引き継ぐのは、その使命感ともいえるでしょう。
日販はその後の物流をどんな風に構築されていくのか、大変に興味深いものがあります。物流系のコンサルタントが入っておられると聞いていますので、何らかの見通しはお持ちの上での決断かと思いますが、トーハンは雑誌配送を守りこれまでの流通ルートを守り、日販は新たな書籍を中心とした流通ルートを見据えているように思えます。
経営者が死力を尽くすトーハンと日販のどちらの経営戦略が正解なのかは、部外者が軽々に論ずることはできませんが、そう遠くない時期に結論は出ると思われます。
■出版社にも抜本的な対応が求められている
出版社が、これからも再販売価格維持制度(再販制)を守ってゆくのであれば、出版物の価格の15%前後のアップと取次卸し正味の10%下げは避けられません。その2%を取次に8%を書店で分配するか、同等のバックマージンを支払うことが疲弊する取次と書店の経営改善に繋げるのには一番の早道と思います。
この考え方に異論があることは私も十分に承知していますが、まずはそこから出版界でタブーとなっている正味についての議論を始めることはできないでしょうか? 正味を下げて書店の粗利益率拡大ができないならば、出版社は再販制度を放棄して、価格決定権を取次と書店に委ねるほかに出版界が生き残る道は残されていません。
営業面では、取次の協力も得て「新刊事前受注」に対応した仕組み作りとDXの推進を強力に推し進めてゆくことが肝要です。もう既に取次には見計らい配本をする余裕もメリットもありません。
編集面では、現状の経営者が編集者へ「一定期間内の出版点数を求める」のではなくて、「一定期間内で担当する本の販売数」を求めるようなマネジメントに移行することが欠かせません。それが、読者も書店も求める「売れる本」への入り口になります。出版社が良心に従って良いものを作り続けることがロングセラーを生み出し、出版界を再び活性化させてゆきます。
■この時代になっても書籍の取り寄せが遅い理由
読者諸氏の多くが持つ出版界への最大の不満は「なぜ注文した書籍の入荷が遅いのか?」だと思います。この原因は明確です。出版流通は取次が担っていますが、この流通網は元々雑誌配送を基盤にしています。その雑誌配送網は安価で全国津々浦々まで精緻に張り巡らされているので、取次は長年この仕組みに書籍の配送も併せ載せる形で使ってきました。
書籍の注文品はこれにバイパスを作るようにして対応してきたので迅速性に欠け、書籍の注文品がほかの流通網に比べてスピードで大きく劣っていました。これが原因ですが、この現状にようやく変化の兆しがハッキリと見えてきました。
2023年はトーハンと日販がその経営方針について別の方向に大きく舵を切った年になりました。もう、両社は「取次」という言葉で一括りにできない業態になってゆきます。トーハンは今後も出版物のホールセラー(wholesaler)として出版販売会社であり続ける意思を明確にしました。
日販は出版販売会社としての機能を縮小して、輸配送と代金回収による手数料収入を柱とするディストリビューター(distributor)としての方向性を明確にしました。傍証ではありますが、2023年の両社トップの発言を見てゆきましょう。
■同じ取次でも、まったく違う戦略を選んでいる
トーハン近藤敏貴社長は、「ドイツ型モデル」を参考にして経営を進めてゆく。具体的には①書籍新刊の書店からの事前発注を受け付ける。②注文品出荷のスピードを上げる。この二つのマーケットインの思想で取次事業を再構築し始める。書籍販売の課題は返品率の高さと流通コストにあり、これは是正してゆかなければならない。
日販奥村社長が表明されている「新しい形の取次」は推測するほかないのですが、紀伊國屋書店、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA)と日販が共同出資して立ち上げたブックセラーズ&カンパニーでの役割は従来の販売会社としての卸しの機能は捨て、配送と集金の手数料収入でのビジネスモデルで参加しています。
この新会社が日販取引書店にも参加を求めていることから考えると、事業の柱をこちらに移行されようとしていると考えて間違いないでしょう。
その時に日販は、雑誌の配送はどうするのか? 書籍の配送網をこれから新たにどんな形で構築しようとされているのかは現時点で全く不明ですが、もしそうであるならばトーハンとは好対照な経営戦略になり興味深いです。

■生き残りを賭け、新しい取次の業態を模索している
日販の奥村景二社長に期待する書店さんは多いです。久しぶりの営業現場出身の社長であるし、その気さくなお人柄も慕われている。そんな中で大きな赤字(2022年30億円)を出し2023年上期決算では前期よりも赤字幅を増やしていて一刻の猶予もない事情も理解できます。
奥村氏に周囲の思惑を気にしている暇(いとま)はないのですが、ローソン・ファミリーマートとの取引中止の手続きについて一定程度の瑕疵(かし)があったことは否めません。そのことで大手出版社が日販に不信感を持つことも理解できますが、「坊主憎けりゃ袈裟(けさ)まで憎い」かのように、日販が紀伊國屋書店、TSUTAYAと一緒に立ち上げたブックセラーズ&カンパニーまで全否定するようになることは行き過ぎに思えます。日販も新しい取次の業態を模索して生き残りを賭けています。
トーハンはドイツ型取次を標榜し、日販は書籍の取り扱いマージン制移行を視野に入れている以上は、両社共に書籍専用の出版流通の仕組みの再構築は両取次の喫緊の経営課題に思えます。
■国による地方書店の振興プロジェクトも始まった
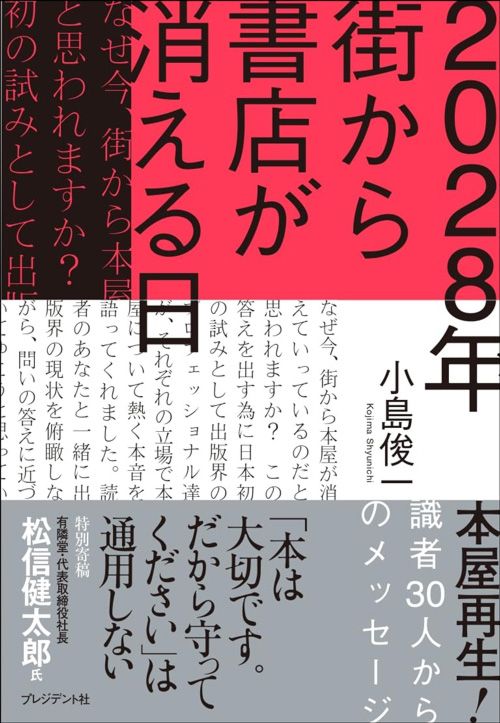
書店がなくなっている現状を憂う声は出版界の内外を問わず大きいものがあります。全国の自治体の4分の1にはすでに書店がありません。1年間で1兆5000億円程度の小さな業界がなぜ、こんなにも注目されるのか? それは、きっと書店空間にはネット書店には無い暗黙知や集合意識が宿っているからだと思います。その場が消えてなくなるのは、日本の知性の危機なのかもしれません。
そこで、今年3月には齋藤健経産大臣肝いり「経済産業省書店振興プロジェクトチーム」が発足しています。行政だけでなく書店を愛する方々が書店の現状に関心を持っていただき声を出してくださる事が、必ずや風前の灯火の書店を救う一助になることでしょう。
----------
中小企業診断士/元気ファクトリー代表取締役
出版取次の株式会社トーハンの営業部長、情報システム部長、執行役員九州支社長などを経て、経営不振に陥っていた愛媛県松山市の明屋(はるや)書店に出向し代表取締役就任。それまで5期連続で赤字だった同書店を独自の手法で従業員のモチベーションを大幅に向上させ、正社員を一人もリストラせずに2年半後には業績をV字回復させる。著作に『崖っぷち社員たちの逆襲』(WAVE出版)、『会社を潰すな!』(PHP文庫)がある。
----------
(中小企業診断士/元気ファクトリー代表取締役 小島 俊一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
日販アイ・ピー・エス、小規模出版社のお悩みを解決する「出版流通代行サービス」の紙出版物支援実績が5,000点を突破
PR TIMES / 2024年6月24日 17時45分
-
「半年に1回しか売れない本」が山積みになっている…日本の書店がアマゾンに侵食された根本原因
プレジデントオンライン / 2024年6月24日 16時15分
-
大量閉店のミニストップもコンビニ再編の波に飲まれる? 顧客を置き去りにしたファーストフード化するコンビニに未来はあるのか
集英社オンライン / 2024年6月19日 8時0分
-
作家も悲鳴、KADOKAWA「サイバー攻撃」の深刻度 ニコ動は復旧に1カ月、損失はどこまで膨らむ?
東洋経済オンライン / 2024年6月18日 8時40分
-
高齢者ばかりの過疎地でも「令和型書店」ならやっていける…広島県庄原市に出店を決めた「総商さとう」の勝算
プレジデントオンライン / 2024年6月4日 10時15分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
-
5カルビー×KFCのポテトチップス期間限定で発売! 「コレは気になる」「絶対買う」SNS期待の声
J-CASTニュース / 2024年7月2日 18時39分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください