スマホのせいで人類は「ドーパミン中毒」に陥っている…現代人をひそかに蝕む「脳内の悪魔のカクテル」
プレジデントオンライン / 2024年6月13日 17時15分
※本稿は、デヴィッド・JP・フィリップス『最適脳』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■ドーパミンの「ベースライン」は下がっていく
ドーパミンは私たちにどういう影響を与えているのか。〈天使のカクテル〉の視点から見ると、モチベーションや勢い、何かを手に入れたいという欲求を生み、満喫させ、長期記憶にも重要な役割を果たす。正確に言うとドーパミンを合成するニューロンは4種類あるのだが、ここでは報酬を制御するニューロンと、意志の強さや決定など実行機能を制御するニューロンを取り上げたい。
先ほどすでにドーパミンの「ベースライン」という言葉を使ったが、これは非常に重要な概念だ。スタンフォード大学の神経科学者アンドリュー・D・ヒューバーマン教授がわかりやすい解説をしているのでそれを引用すると、ドーパミンは私たちにもっと探させ、学ばせ、向上させるために、活動の「前」と「間」に増えるが、活動「後」はベースラインより低くなってしまう。このベースラインは人によって違うが、ここでは1~10のレベルで5としておこう。
■動画を観終わると精神状態が悪化するプロセス
そのレベルが上がるような活動、例えばインスタグラムで面白い動画を観たりすると6まで上がる。しかし観終わるとすぐに4.9まで下がり、その人にもっとドーパミンが増えるものを欲しくさせる。そこであなたはもう1本動画を観る。それも1本目と同じように面白かったが、観始めた時のレベルが低かったので5.9までしか上がらない。しかも観終わると今度は4.8まで下がってしまう。
その調子で動画を観続けてしまい、最後には飽きて、もう面白いと思えなくなる。その頃にはベースラインは4まで下がっていて、動画を観始める前よりも精神状態が悪くなっている。
ただし、必ず精神状態が悪くなるわけではないと思う人もいるだろう。動画を観た方がドーパミンの効果で元気に前向きになれることもある。では、観たらやる気が湧くような動画はどう違うのか。
■クイック・ドーパミンとスロー・ドーパミン
ドーパミンには2種類あると言えばわかりやすいかもしれない。名づけてクイック・ドーパミンとスロー・ドーパミン、短い効果しかないドーパミンと効果が長く続くドーパミンだ。実際にはそんな名前のドーパミンはないが、わかりやすくたとえるとそうなる。クイック・カロリーとスロー・カロリー(ゆっくり消化吸収される健康的な糖質)のような感じだ。

白いパン、パスタや砂糖など吸収の速い炭水化物は素早くエネルギーをトップまで持っていけるが、あっという間にクラッシュしてしまう。ドーパミンの場合、それがインスタグラムの動画に相当する。
一方、スロー・カロリーは全粒粉のパンや玄米、レンズ豆、雑穀から得られ、エネルギーが長く持続する。スロー・ドーパミンを放出させてくれるのはどんなものかというと、その瞬間だけでなく将来的にも役に立つような活動や体験だ。
大事なことだからもう一度書くが、スロー・ドーパミンの特徴はその瞬間だけでなく将来的にも役に立つような活動や体験から得られるという点だ。そして祖先が体験していたドーパミンの多くはスロー・ドーパミンだったはずだ。ではここでスロー・ドーパミンの例を見ていこう。
■読書や運動、セックスはスロー・ドーパミンを放出する
知識やエネルギー、モチベーションを与えてくれるような動画は人生において長期的な燃料になる。何かを変えたい、創造したいという意思や願望を与えてくれるし、人生を前に進める力をくれる。その逆は、その瞬間だけ楽しませてくれる動画を何百本もスクロールし続けること。後には虚しさだけが残る。
小説を読むのもスロー・ドーパミンが出る活動だ。読書の効果がその瞬間だけではなくその後も長く続く。ストーリーの中で起きることをシミュレーションするから想像力が養われ、脳の大部分を使うし、読み終わるまであらすじやキャラクターを覚えておかなくてはならないから記憶力も鍛えられる。
何かを学ぶことでもスロー・ドーパミンが出る。知識は記憶を鍛えてくれるし、新しい知識はクリエイティビティにもつながる。新しいアイデアというのは古いアイデアを組み合わせたものだからだ。知識のおかげで周囲の世界を理解しやすくなるし、様々な社会的状況で他人と会話する能力にもつながる。知識があればあるほど、さらに知識を積み上げることができる。
運動もスロー・ドーパミンを放出してくれる。運動の効果は挙げればきりがないが、最も重要なものだけを書いておくと、心血管疾患のリスクが減り、体力が養われ、睡眠の質が上がり、神経可塑性も高まり、免疫系が強化され、とりわけ精神の健康においては他に類を見ないほど重要だとされている。
セックスによってもスロー・ドーパミンが放出される。セックスの効果は(お互いに望んだ上でのセックスであれば)、最長で48時間もパートナーとの関係が良好になったと感じさせてくれる(*1)。有酸素運動の一種でもあるし、セロトニンとオキシトシンのレベルが上がるから〈天使のカクテル〉の材料として秀逸だ。
*1 Quantifying the Sexual Afterglow: The Lingering Benefits of Sex and Their Implications for Pair-Bonded Relationships by Andrea L. Meltzer, Anastasia Makhanova, Lindsey L. Hicks, Juliana E. French, James K. McNulty, Thomas N. Bradbury(2017)
■ネット普及前はスロー・ドーパミンが大半だった
私は講演でよくこう尋ねる。「テレビの娯楽番組やインターネットができる前にやっていたことは、ほとんどがスロー・ドーパミンを出すものでした。皆さんはインターネットができる前には何をしていました?」
返ってくる答えは、人と過ごす、趣味に打ち込む、家で料理をする、本や新聞を読む、ボードゲームをする、家や庭の手入れをする、踊りに行く、創作活動をする、ものをつくる、クロスワードパズルを解くなどだった。
そしてある人がこう答えた時には全員が爆笑した。「好きなアーティストのアルバムを最初から最後まで聴いた!」そう、そうだった――昔はアルバムを最初から最後まで聴いた。新しく買ったCDをうやうやしくプレーヤーに入れ、全員が静まり返り、一曲一曲を堪能したものだった。
しかしそれはもうずっと前のことで、今の私たちは別の世界、クイック・ドーパミンに溢(あふ)れた世界に暮らしている。そのせいで問題がたくさん起きているが、特にスロー・ドーパミンはエネルギーを要し、自ら動かないと得られないから苦労する。
クイック・ドーパミンならソファに座ってチョコレートを食べるだけでも出せるし(ベースラインから150%もアップする)、他にもファストフードを食べる、テレビドラマを観る、スマホでゲームをする、SNSを見る、ビットコインや株価をチェックする、ネットニュースを読むなどいくらでも手軽な方法がある。
■本能的に楽にドーパミンを得ようとする
しかしスロー・ドーパミンを出すには場合によっては相当な努力が必要だ。趣味に打ち込む、クロスワードパズルを解く、ボードゲームをするというのは時間とエネルギーを奪うし、脳はそもそも必要以上にエネルギーを使うことを避けようとする。エネルギーは進化の過程で最も価値のある資源だったからだ。
今度駅やショッピングセンターに行ったら、エネルギー消費の調査をしてみると面白いかもしれない。階段ではなくエスカレーターを使う人が何人いるかを数えるのだ。私はのめり込む性質なので、カフェに座ってメモを取ったこともある。すると大多数が階段よりもエスカレーターを選んでいた。下りでさえもだ。
日常で身体を動かすことがどれだけ大切かは誰もが知っている。それを考えると矛盾した現象だ。しかしながら進化の見地から考えれば当然で、エネルギーを節約するのは食料を蓄えようとするのと同じことだ。食料をたくさん蓄えておけば、危険を冒して食料を集めなければならないことも減る。日常でエネルギーを節約する例としては次のようなものがある。
・徒歩や自転車ではなく車を使う。
・公共交通機関ではなく車を使う。
・公共交通機関ではなくキックボードを使う。
・自分で料理を作らずに出来合いの物を買う。
・電話する代わりにメールやチャットを送る。
・空港で普通に歩かずに「動く歩道」を歩く。
・手動の芝刈り機ではなくエンジン式あるいは自動芝刈り機を使う。
楽できる選択肢があるおかげで、やりたいことにもっと時間を使えるという意見もあるだろう。しかしたいていの場合は無意識に、太古の昔からの本能に従ってエネルギーを節約できる方を選んでいるのだ。
■「ドーパミンの重ね掛け」は危険
クイック・ドーパミンをくれる活動に依存してしまうと、それが〈悪魔のカクテル〉になる。スロー・ドーパミン、つまり長期的に良い効果を生む活動から遠ざかってしまうのだ。しかも、簡単に手に入るクイック・ドーパミンには二次的な悪影響もある。耐性ができてしまって、楽しいものをひたすら求め続けてしまうというものだ。
ユーチューブを見ながらゲームをし、スナックを食べ、ソフトドリンクを飲む――知り合いにもそういうことをしている人がいるだろうし、あなた自身もやっているかもしれないが、これは4つのドーパミン源を重ねている状態だ。そんな人に他のドーパミン源なしで不朽の名作『カサブランカ』を観させたりしたら拷問でしかないだろう。1942年には映画館で観客を夢中にさせ、当時としては最高にエキサイティングでドラマチックな映画だったのに。
この「ドーパミン重ね」を自制する能力は人生において必須で、健康的な〈天使のカクテル〉をつくるのにも欠かせない。ここで〈天使のカクテル〉のつくり方に入る前に、「ドーパミン泥棒」についても説明しておこう。

■企業はクイック・ドーパミンで金儲けしている
ドーパミン泥棒とは何者で、どこに隠れているのか。実はそこら中にいて、人生最愛の相手よりも近寄ってくることがある。それは我々の時間(=ドーパミン)を奪って金を儲けようとする企業だ。例えばゲームアプリの会社は次のような手段を使っている。
2.アプリを長い時間使わせ、アップグレードやアップデートに課金しやすくする。
3.多くのユーザーからドーパミンを盗むほどユーザーが増え、アプリやホームページ、企業の価値が高まる。
職人技とも言えるこの乗っ取り行為が成り立つのはユーザーに可能な限りのクイック・ドーパミンを出させるからだ。そのために企業は人間の認知機能、心理、生理的な反応を研究してゲームやカジノアプリの開発をしている。色や音、フォルム、アニメーションを駆使してクイック・ドーパミンを最大限に出させるのだ。
では、そういった企業はスロー・ドーパミンに着目しないのだろうか。なぜありのままスロー・ドーパミンの価値を提供しないのか。それは「エスカレーター現象」が起きてしまうからだ。すでに「エスカレーター」を使っているユーザーは、別の企業に新たに「階段」を提供されても、余計なエネルギーを投じなければならないだけだ。それは進化の過程で一番避けてきたことではないか。
■おいしそうな食品パッケージもあなたを狙っている
ドーパミン泥棒がうようよしているのはスマホの中だけではない。スーパーであなたに食品を買わせるには他の商品より美味しそうに見せればいい。まずはパッケージのデザインにこだわって消費者に唾を湧かせる。商品を手にして良い気分になることも重要だ。消費者の興奮がスーパーの天井を突き破り、クイック・ドーパミンが増加する。次の瞬間、同じブランドから新商品が出ているのに気づけば、ドーパミンはさらに増すだろう。
家に帰るとパッケージを開け、健康なおやつと謳(うた)われる新商品を試す。するとけっこうな砂糖含有量のせいでドーパミンがほとばしり、素晴らしい気分になり、「これは美味しい。次も買おう」と覚え込む。しかしすぐにドーパミンのベースラインは下がり、脳は「こんな気分じゃ嫌だ!」と叫び出す。「もっとドーパミンをくれ!」
■「ドーパミン泥棒」に捕まると最後はうつになる
普通ならば人から何かを盗むことには抵抗がある。特に子供から盗むなどあり得ないと思うはずだ。スウェーデンには「子供からお菓子を盗むくらい簡単」という慣用句があるが、この場合「子供からドーパミンを盗むくらい簡単」と言えるかもしれない。
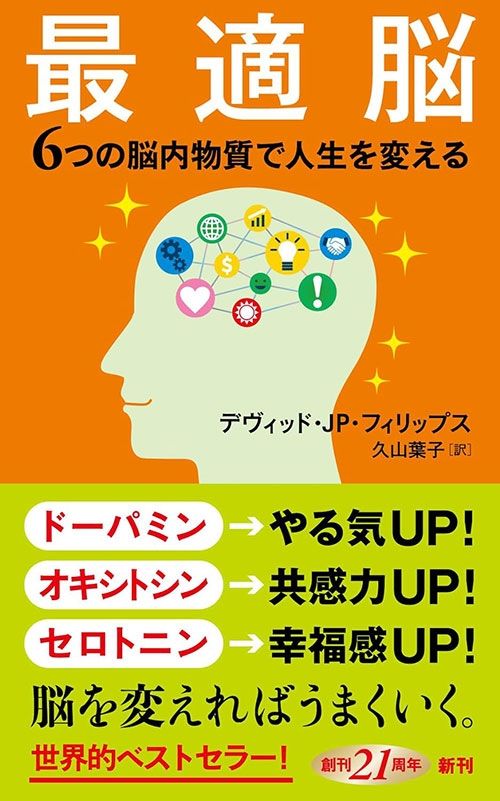
子供たちのドーパミンを極限まで出させるのが目的でアプリやゲームを開発しているとはあまりに非道な行為だ。大人ならまだ我慢するという選択肢がある。脳の前頭葉が成熟しているおかげで合理的に考える能力があり、子供やティーンエージャーよりも意志が強い。
おかげでクイック・ドーパミンではなくスロー・ドーパミンを選ぶこともできるのだが、それでもドーパミン泥棒に捕まっている大人が多すぎるように思う。捕まったが最後、ゆっくりとドーパミンのベースラインは下がっていき、何かを満喫したり純粋なモチベーションを感じたりすることは減っていく。それが虚無感、気分の落ち込み、最悪の場合にはうつにつながる。
----------
1976年スウェーデン生まれ。プレゼンテーションのスキルを伝授する企業などを創立したレクチャラー(講師)。TEDトークの総再生回数は1000万超。
----------
(パブリックスピーカー デヴィッド・JP・フィリップス)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「年寄りにはわからないから」と敬遠していると脳が老いる…高齢者が本当に使うべき「デジタルツール」とは
プレジデントオンライン / 2024年6月26日 10時15分
-
今、「希望通りの人生」になっていない人。幸福感に満ちた毎日にするために、試してほしいたった1つのコト
OTONA SALONE / 2024年6月24日 11時31分
-
なぜ人間には「浮気をする人」と「誠実な人」が存在するのか…人間が「完全な一夫一妻制」とは言い切れないワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 17時15分
-
OIST、脳が酸素不足となった際に記憶障害が生じるメカニズムの一端を解明
マイナビニュース / 2024年6月10日 19時35分
-
なぜ仕事をしなければいけないのにスマホをいじってしまうのか…良習慣は続かず悪習慣が続く根本原因
プレジデントオンライン / 2024年6月3日 7時15分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
-
3若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
4Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成
isuta / 2024年6月29日 18時0分
-
5「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












