国内では「猟奇的」と非難された…「世界初の内視鏡心臓手術」を実現した医師が日本の医療界に言いたいこと
プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分
■「大きく切る手術」は医師にとってラク
心得 「常識」は永遠には続かない
「名医ほど大きく切る」
医療を扱ったドラマや漫画で、こんな言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。昔の医療現場では実際に、そんなふうに言われていました。
本当にそうだろうか? と、私はずっと疑問に感じていました。
バイパスを1本つなぐだけの手術で、なぜ大きく切る必要があるのか?
手術は、医師の固定観念にとらわれて行われるべきものではありません。患者さんの病気を治す、病状を改善させる、さらには術後の回復を早めることが大前提です。ならば、切るのは最小限にとどめる必要があるのではないかと。
大きく切れば、手術はしやすい。でも、それでは患者さんの術後の回復が遅れる。小さく切るなかで的確な手術を行うことこそが、外科医に求められることだと思いました。
医療現場で患者さんたちに接していると、さまざまなことがあります。思わぬ事態で、心が痛くなったこともありました。
■入院期間が長くなり会社を解雇された患者がいた
まだ私が医者になって間もないころのことです。胸骨正中切開で、たった1本の冠動脈バイパス手術を受けた患者さんの回復が遅れたのです。入院期間が長くなり、職場復帰までに時間がかかりすぎたため、その患者さんは会社から解雇を言い渡されてしまいました。理不尽なことだと感じると同時に、私にとって考えさせられる出来事でもあったのです。
私は、冠動脈バイパス手術における小切開のやり方を模索し、さまざまな方法を開発しました。以前なら正中切開をしていたのを、わずか6~7センチ程度の切開での手術を可能にしたのです。
こうした技術を習得すると、それが当たり前になります。
「これまでの大きく切るやり方は楽で簡単だったな」と思えます。
でもその簡単なやり方は、医師側の視点でしか考えられていなかったものでした。患者さんにとっては、体に大きな負担をかけていた方法にほかなりません。
当たり前を疑わずに、これまでの方法の上であぐらをかいているようでは、患者さんが本当に望んでいることを実現することは不可能です。当たり前と向き合いましょう。
その視点は、医療の現場だけで役に立つものではありません。必ず、新しく見えてくることがあるはずです。

■小さく切る手術を模索した
心得 成功は次の挑戦の始まり
これまでのやり方を踏襲する。決まっていることをそのとおりにやる。
それが、仕事のすべてだと思っている人が多くいます。
もちろん、一つひとつの作業を丁寧に行うことは大切なことですが、それだけでは、お客さんや仕事相手は充分には満足しない気がします。
なぜ、「このやり方でやれ」と教えられたのか?
なぜ、「この決まりごと」があるのか? 誰が決めたのか?
もっと、効率を上げ、質も高められるやり方があるのではないか。
私たちの生活は、格段に進歩してきました。たとえば1953(昭和28)年にテレビが登場し、数年後にカラー放送が始まりました。
その後、ビデオテープで録画ができるようになり、DVD、ブルーレイへと移行します。携帯電話の登場、スマートフォンへの進化。インターネットの普及と動画配信サイトの確立。そしてAIは、これからさらに進歩しようとしています。
それだけではなく、私たちの生活に直結する衣食住のレギュレーションも大きく変化してきました。これは現状に甘んじることなく「もっといいやり方に変えられるのではないか」と、あくなき探求心を持った者が成し遂げてきたことです。
■世界初の内視鏡手術を成功させたが…
小切開手術を突き詰めながら、私も考えました。患者さんの体への負担をもっと軽くする手術方法はないのか、切開することなく手術はできないものか、と。
そして私は、内視鏡で心臓手術ができれば、小切開手術よりもさらに患者さんの体に負担をかけない手術ができると思いあたりました。
いや、じつはそれ以前に消化器系、呼吸器系の手術に内視鏡が用いられるようになったときに、「どうして心臓分野では、内視鏡を使った診察や手術がないのだろう」と、不思議に感じてもいたのです。
でも、心臓という生命に直結するデリケートな箇所を切開することなく手術するという発想は、当時、日本はおろか世界のどこにもありません。それでも富山医科薬科大学病院(現・富山大学附属病院)時代、勤務をしながら、私はずっと内視鏡心臓手術の研究を続けていました。
内視鏡で心臓の外側だけを眺めるのではなく、心臓を包んでいる分厚い膜の中に内視鏡を入れるなどして実験、心臓の表面を走る冠動脈をそこで見据えたときに確信しました。(ここまで血管が鮮明に見えるのか。冠動脈バイパス手術なら内視鏡で可能だ)と。
その後も実験、手術の手順の考察を重ねました。そして、1999年に私は内視鏡手術(完全内視鏡下冠動脈バイパス手術)を世界で初めて成功させるに至ります。
人工心肺を使用せず、胸の横に小さく開けた穴から内視鏡を挿入して行う手術は、時間が短く済むだけではなく、切開しないことで患者さんの体への負担を軽くできました。脳梗塞や心不全の原因にもなる重篤な心臓疾患の治療も、画期的に改善できたのです。
■日本の外科医たちは「猟奇的だ」と批判した
心得 満足感に浸り続けてはいけない
ただこのとき、周囲が諸手を挙げて私の成功を喜んでくれたわけではありませんでした。従来の術式に固執したがる日本の外科医たちからは、批判的な声も上がりました。
「猟奇的だ」
「安全は担保されているのか」
しかしその後、高い手術成功率を示すと批判の声は小さくなり、やがて耳に届かなくなります。そして今度は皆がやりたがりました。
世間の反響も大きなものでした。私が内視鏡心臓手術について書いた論文が、世界的に有名な医学誌『ランセット』に掲載されたのです。『ランセット』は1823年にイギリスで創刊された週刊医学雑誌で、世界中の医師たちが読んでいます。心臓外科医が論文を書くのは珍しいことでしたが、これにより内視鏡心臓手術は世界に広まり、その後のロボット手術へとつながっていきます。
日本国内でも「世界で初めて内視鏡で心臓手術をした外科医」とNHKがニュースで報じてくれました。いくら患者さんたちのためになる術式を開発しても、志をともにする仲間たちから評価されたとしても、それが時として旧態依然とした勢力からは認められず、排除の方向に向かわされることもあります。

■医師の保身、既得権益…
新たな発見や開発は、それまで既得権益を有してきた人たちにとっては邪魔な存在でしかなかったりするのです。
でも、医師が対峙するべきは、自らの地位を得るための権力闘争などではなく、目の前にいる患者さんです。
私が「完全内視鏡下心臓手術」を行ったことをメディアが大きく報じてくれたことは、その思いを後押ししてくれました。
ただ、人は満足感を得ると心が満たされます。満たされたとき、それは一種の快感としてそこに浸り続けたくなります。これだけ大きなプロジェクトを成功させたんだ。こんないい取引先との商談をまとめたんだ。いままでにない事業を立ち上げて軌道に乗せたんだ……。
すばらしい活躍をしたときこそ、すぐに次の一歩を踏み出しましょう。心が満たされた状態を続けていると、そこから抜け出せなくなり、いずれ周りからの期待とのギャップに心が苦しむことになります。
大きなチャンスをつかんだとき、成功をつかんだとき、それは心が次の成長のステップに進むための準備が整ったということです。その機会を逃してはいけません。
■心臓手術は大きく変わった
心得 昨日よりも今日。今日よりも明日。明日よりも明後日
心臓手術――。この言葉に、みなさんはどのようなイメージをお持ちですか?
「怖い」
「生死をさまよう手術」
「術後も退院までに長い時間がかかる」
そんなふうに思われているのではないでしょうか?
当たっている部分もあり、そうではないこともあります。
実際に以前は、命の危険と背中合わせの大手術とされてきました。心臓手術が成功したとしても大きな傷跡が残り、入院期間が1~2カ月かかるのは当たり前で術後には痛みに耐えねばならないものだったのです。
従来の胸を大きく切り開く手術を行うと、一緒に切った胸骨がもとの状態に戻るまでにかなりの時間がかかります。そのぶん、入院期間は長くなり痛みも伴う。それだけではなく、広くメスをふるったことで傷口から細菌等が入り込み、感染症を引き起こすケースも多々ありました。
ですが、医療技術は進歩し続けています。胸を切り開く手術は、過去のものになりつつあります。いま世界の外科手術の潮流は、体にメスを入れる範囲をできる限り小さくしようとする方向に進んでいるのです。切る箇所を小さくできれば、患者さんの体の負担は軽くなる。よって術後の回復は早まり、社会復帰もスムーズになります。

■術後3日で退院する患者もいる
心臓外科手術は近年、大きく変わりました。それは、ロボット手術(ロボット支援下内視鏡手術)が出現したからです。いまでは、胸を大きく切り開いて心臓手術を行う必要性はほとんどありません。胸に小さな穴を3つ開けるだけで手術を行うことが可能になったのです。
このロボット手術では出血を少なくし痛みも軽減でき、手術痕もすぐに塞げます。以前は考えられなかったことですが、術後3日で退院していく方もいらっしゃいます。
体に優しいロボット手術により救命率が上昇、さらに脳梗塞をはじめとする重篤な合併症の発症も高い確率で抑えられるようになってきました。
2014年に「ニューハート・ワタナベ国際病院」を開設して以降、これまでに4000件を超える心臓手術を行ってきました。その半分がロボット手術で、全体の手術の成功率は99.6%を上回ります。
日本もアメリカも、平均死亡率は2.5%といわれていますから、この数字は世界的にも最高レベルであり、患者さんに安心して手術を受けてもらう環境を作り上げたと自負しています。また、術後から退院までの時間も大きく短縮、早期の社会復帰も実現しました。
■日本では旧式の手術を行っている病院が多い
ただ、このロボット手術が日本において心臓手術の主流になったかと言えば、そうではありません。いままで知らなかった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
じつはいまだに旧式のやり方、つたない腕で手術を行っている病院が数多くあります。「ダビンチ」と呼ばれる手術ロボットが導入されていないため環境が整わず、また手術を行える医師の数も極めて少ないからです。
これは、患者さんにとって不幸なことでしょう。ロボット手術を受けていれば体に与えるダメージは少なく、その後も長く健康でいられたのに、そうでなくなるケースもままあるからです。
■進歩を恐れてはいけない
「技術の発展は日進月歩」という言葉を聞いたことがあるかと思います。絶えず進歩することを表す言葉ですが、現代は江戸時代の1年分、平安時代の一生分の情報量を、たった一日で受け取っていると言われるほど、情報を取り巻く社会全体のスピードが加速しています。
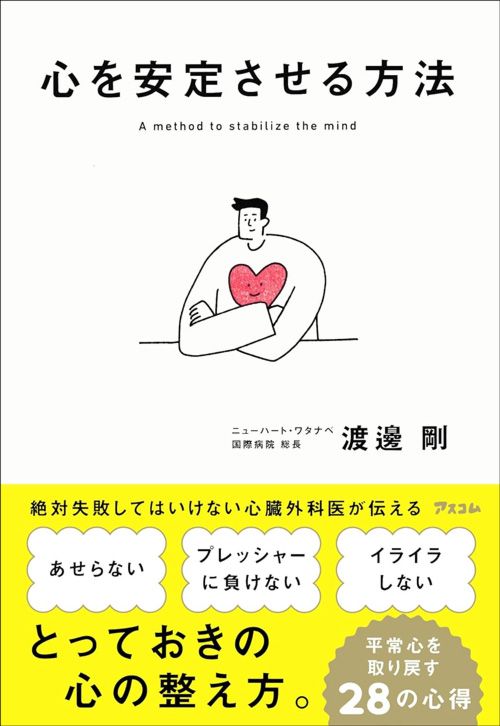
昨日よりも今日、今日よりも明日、明日よりも明後日、医師は不安でいっぱいの患者さんの気持ちを理解し、意識して、動かなければいけないですし、それは、どんな分野の仕事でも同じでしょう。
そもそも仕事は、目の前の、あるいは誰かの「喜ぶ顔を見るために」「悩みを取り除くために」必要なことを提供し、対価としてお金を受け取るものです。
これまでのやり方が一瞬で古くなる時代に、患者さんやお客さんの想いに応えるために、進歩を恐れず踏み出してください。
----------
心臓血管外科医
1958年、東京都生まれ。心臓血管外科医、ロボット外科医(da Vinci Pilot)、医学博士。日本ロボット外科学会理事長、日伯研究者協会副会長。麻布学園高等学校卒業後、医師を志す。金沢大学医学部卒業後、金沢大学第一外科に入局する。海外で活躍する心臓外科医になりたいという夢を叶えるためドイツ学術交流会(DAAD)奨学生としてドイツHannover医科大学に留学。金沢大学心肺・総合外科教授、国際医療福祉大学三田病院客員教授などを経て、2014年にニューハート・ワタナベ国際病院を開院。著書に『医者になる人に知っておいてほしいこと』(PHP新書)などがある。
----------
(心臓血管外科医 渡邊 剛)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「一流の外科医は周りがどんな状況でも自分の力を発揮できる」チーム医療を超えた単独手術…~『ブラックペアン』監修ドクターが解説 vol.25~
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月21日 8時0分
-
医師の使命とは?苦戦する外科医の教育~『ブラックペアン』監修ドクターが解説 vol.21~
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月19日 17時0分
-
「世界初の手術」成功した医師のシンプルな原動力 「名医ほど大きく切る」は患者のためにならない
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 18時0分
-
医誠会国際総合病院 心臓血管外科のロボット手術件数が約半年で27件に到達
PR TIMES / 2024年6月27日 16時45分
-
世界最高峰の心臓外科医が留学後に受けた「屈辱」 「白い巨塔」にはびこっていた"排除の力"とは
東洋経済オンライン / 2024年6月23日 19時0分
ランキング
-
1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て
東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分
-
2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分
-
3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…
日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分
-
4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?
オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分
-
5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度
読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











