なぜ武田信玄と上杉謙信は10年にわたり「川中島の戦い」を続けたのか…名将がこだわった「信濃国」の本当の価値
プレジデントオンライン / 2024年6月16日 18時15分
※本稿は、本郷和人『喧嘩の日本史』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
■なぜ戦国大名たちは領地拡大を始めたのか
戦国時代、特に武田信玄らが登場してきた頃になると、次第に「領地を拡大する」ということを真面目に考える戦国大名たちが出てきます。
それ以前は基本的に自分の本拠地である領地だけを守ることを大名たちは重視していました。武田で言えば、甲斐国を守る。今川で言えば、駿河国を守る。本書でもこれまで述べてきたように、土地は武士にとってそこから財を得るための最も重要なものです。
長年にわたって統治してきた本拠地を守ることを重視するのは当然のことと言えるでしょう。だからこそ、武田信玄の本拠地はずっと甲斐国ですし、今川義元にとっては駿河国でした。彼らは決して、自らの居城を動かしたりはしていません。それは自分の領地を守ることを一番に考えていたからです。
しかし、応仁の乱を経て、戦国大名たちは拡大路線を取るようになります。自分の本拠地が敵国と隣接していると、国防上のリスクもあるため、その間に緩衝地帯を持ちたいと考えた場合、隣国を自分の領地にしてしまえばいい、というわけです。
当然、土地を得られればその土地が生み出す生産物によってさらに国も富むことになりますから、「領土を広げるのはおいしい」ということを戦国大名たちもわかってきたのです。
■今川義元は駿府から離れなかった
そうなると当然ながら侵攻した先の土地では、たとえば土地の人間を皆殺しにして略奪するようなことはできなくなるわけです。拡大した土地を自分の領地に組み込み、きちんと運営して統治しなければならなくなります。
今川義元は、父・氏親の代ですでに駿河国の隣国である遠江国まで、ある程度、制圧を完了していました。さらに義元が家督を継ぐと、その支配を三河国にまで広げ、駿河・遠江・三河の三国を今川領としました。しかし、今川義元にとって最も大切なのはもともとの本拠地である駿河ですので、居城はあくまでも駿府で、そこからは動かしませんでした。
駿河・遠江・三河の三国を均等に統治するならば、駿府は東側に寄りすぎています。それにもかかわらず、本拠地を動かさなかったとすると、やはり今川義元にとって駿河国が重要だったということがよくわかります。
■武田信玄が信濃を攻め続けた理由
武田信玄もまた、10年もかけて信濃国を制圧したものの、甲府から本拠地を動かすことはありませんでした。北信濃に上杉の脅威が迫っているのだとすれば、その対応を迅速に行うためにも、もっと北に本拠地を置いてもよいところです。しかし、武田信玄は甲府を本拠地とし、海津城がなんとか食い止めている間に甲府から兵を出すという選択をしています。
これもあくまでも信濃へ領土拡大をしたのは、本拠地である甲斐国を守るため、と言えそうです。それほどに戦国大名にとって本拠地というものは重要だったのです。
しかし、武田信玄は、ただ単に緩衝地帯として信濃国全域を必要としたと言ってよいのでしょうか。10年もかけてそれを実行する必要があったのか、疑問は残ります。おそらく、武田信玄には別の意図があったのではないでしょうか。
それでは武田信玄はなぜ、信濃国を制圧することにそこまでこだわったのでしょうか。思い出していただきたいのは、武田信玄の本拠地である甲斐国は海に接していない内陸の土地だったという点です。だからこそ、武田信玄は何としても、海を手に入れたいと思ったのではないでしょうか。欲しかったのは、海運を使った貿易によって得られる利益です。
■「敵に塩を送る」が意味すること
そのためには当然、海運の重要な拠点となる港が必要になります。信濃国の先には、上杉謙信の越後国があるわけですが、謙信は直江津を中心とした海上交易によって莫大な利益を得ていました。それゆえ、謙信にとって直江津は最も重要な拠点だったのです。

北信濃まで手に入れれば、直江津は目と鼻の先です。これに武田信玄は目につけたのではないでしょうか。
上杉謙信と武田信玄の間では、「敵に塩を送る」ということわざの語源となった「塩絶ち」の物語が有名です。これは、今川氏や北条氏による塩留めによって、内陸国だった甲斐国が塩不足に陥り、そのため、宿敵である武田信玄に塩を送り届けたとして、上杉謙信の「義の人」のイメージを印象付けた逸話です。
これは、江戸時代に創作された物語だとされていますが、一定の真実を反映しています。甲斐国も信濃国も海がないため塩が取れないわけで、結局、他国との交易で得るほかなく、自活ができないという問題があったのです。だからこそ、武田信玄は、海を目指したのではないか。そのための信濃国制圧だったのではないでしょうか。
■直江津は金の卵を産む鶏
当時、日本の重要な港を指す言葉に、「三津七湊(さんしんしちそう)」というものがありました。三津は大坂の堺、福岡の博多、そして三重県の津(安濃津)、あるいは鹿児島の坊津を入れる場合もありますが、ともかく、この三つの有力な港のある土地を指します。
これに対して七湊は、すべて日本海側にありました。それだけ、当時の日本海の交易がいかに盛んだったかがよくわかりますが、そのうちのひとつが、上杉謙信の越後国にあった「今町湊(直江津)」だったのです。
日本海側でつくられる焼き物を積んで、蝦夷地(北海道)で売買すると、今度は蝦夷地で仕入れた海産物などを積み込み、直江津へと戻るわけです。さらに越後は青苧(あおそ)という植物がつくられており、これを積荷として載せた船が京都へ行き、また交易を行います。
この青苧は、木綿が一般化するまでは衣服の原材料として広く重宝されていた品でした。直江津さえ押さえれば、このような海を通じた交易権から得られる利益を手中に収めることができます。
上杉謙信が亡くなったときには、上杉の蔵には莫大な金が蓄えられていたとされるほどですから、直江津はまさに金の卵を産む鶏だったのです。
■春日山城は直江津を守るための城
地理的に見れば、現在の県庁所在地である新潟市はもっと東、県全体の中央に位置します。それに比べると直江津は西に寄りすぎており、越後国全体を治めるにはやや不便な場所とも言えます。しかし、そうまでしても自分の本拠として春日山城を置いたということは、やはり直江津を必ず押さえなければならないということだったのだと思います。

春日山城は、上杉謙信の居城にして、直江津を守るための城だったのです。ですから武田信玄が北信濃にまでその領域を拡大し、海津城を築いて、信頼を置く春日が虎綱をそこに置いたのも、10万石の同地で兵を養い、ここを拠点にして、隙あらば春日山城を攻め、直江津を手に入れて、海へ出ようとしたのではないかと思うのです。
ですので、武田信玄がどうしても手に入れたかった「○○○」とは、「直江津」のことなのです。
上杉謙信も直江津の重要性をよく理解しているため、繰り返し北信濃へと侵攻し、緩衝地帯として上杉領に組み込むべく、およそ10年にわたって川中島の戦いを繰り返したのです。
■謙信のライバルは信玄ではない
しかし、そもそもで言うと、上杉謙信の一番の敵は誰かと考えた場合、実は武田信玄ではなかったと思います。前章で関東管領や鎌倉公方について述べましたが、上杉謙信こと長尾景虎は、上杉氏の養子となり、家督を継ぐとそのまま関東管領に就任します。
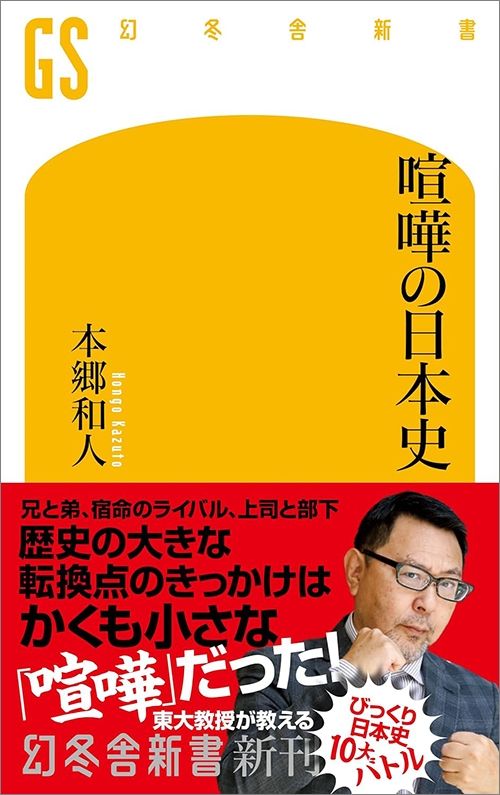
越後から関東へとやってきて、関東地方の平定のために後北条氏(以後、北条氏)と戦うのです。その意味では、関東管領としての上杉謙信の最大のライバルは、実は武田ではなく北条なのです。
ですから一生懸命、上杉謙信は軍を率いて三国峠を越え、関東地方へとやってきたのです。言ってみれば、上杉謙信は武田と北条の両者と同時に戦う、二正面作戦を行っているようなものです。しかし、なぜそのような無理をしたのでしょうか。
上杉謙信という人は、当初は官職や肩書に対して、ある種の信頼感を持っていた人なのではないかと私は考えています。
当たり前のようですが、将軍という肩書があれば将軍として振る舞えるということを、謙信は重視していたのではないでしょうか。
上杉謙信の場合、関東管領に就任するわけですから、関東管領としての権限を行使することができるわけです。事実、上杉謙信が関東へやってきたとき、北関東の武士たちを中心に兵を募ることができました。
第四回の川中島の戦いの前年に上杉謙信が関東へとやってきた際には、関東の武将たちが集まって、10万もの大軍になったと言われています。この大軍をもって、北条氏の小田原城を取り囲んだわけです。
しかし、関東の武将たちも完全に関東管領に恭順していたわけではありませんから、小田原城を落とすことはできませんでした。結局、上杉謙信は鎌倉の鶴岡八幡宮で、山内上杉氏を継ぎ関東管領に就任する儀式を行い、越後へと戻っていくわけです。
実際のところ、上杉謙信はどう思っていたのかはわかりませんが、関東管領の肩書を得たところで、関東に領土を得ることはできないのです。関東の武将たちが関東管領と主従関係を結び、本質的に上杉謙信の支配下に入るというわけではないのです。
言ってみれば、関東管領というのはあくまでも関東の武将たちの兄貴分であって、親分ではないということです。いや、それよりも重要なのは、「肩書」の価値が低下していたことです。
世は下剋上の戦国時代で「肩書」を本当にありがたがる武将はいませんでした。関東に行き、関東管領としていくら頑張っても自分の領地は増えない。確かに将軍を立てて頭を下げるなど「肩書」を重視してきた上杉謙信ですが、さすがに「肩書」だけではダメだと気づいたのではないかと思います。
----------
東京大学史料編纂所教授
1960年、東京都生まれ。東京大学・同大学院で日本中世史を学ぶ。史料編纂所で『大日本史料』第五編の編纂を担当。著書は『権力の日本史』『日本史のツボ』(ともに文春新書)、『乱と変の日本史』(祥伝社新書)、『日本中世史最大の謎! 鎌倉13人衆の真実』『天下人の日本史 信長、秀吉、家康の知略と戦略』(ともに宝島社)ほか。
----------
(東京大学史料編纂所教授 本郷 和人)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「井伊の赤鬼」と恐れられた直政は実は名将ではなかった…関ヶ原の合戦後42歳で死んだ徳川四天王最年少の生涯【2023編集部セレクション】
プレジデントオンライン / 2024年7月2日 7時15分
-
巨人・阿部監督 大勢を守護神で固定する方針 本人に自覚「求められているものは高い」
スポニチアネックス / 2024年7月2日 5時2分
-
本能寺の変は決して無謀なクーデターではなかった…明智光秀の計画を狂わせた2人の武将の予想外の行動
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分
-
ダイナミックな遺構に戦乱の痕 菅谷館(後編) 山城ガールむつみ 埼玉のお城出陣のススメ
産経ニュース / 2024年6月21日 14時19分
-
秀吉が山崎合戦で光秀に圧勝した決定的理由…織田家唯一の軍法を作った光秀は「策士策に溺れる」典型だった【2023編集部セレクション】
プレジデントオンライン / 2024年6月9日 8時15分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












