税の優遇措置なんてオマケでしかない…新NISAブームで株投資を始める人たちが絶対に知るべきこと
プレジデントオンライン / 2024年6月19日 16時15分
※本稿は、榊原正幸『1冊でまるわかり 50歳からのトレーダー入門』(PHPビジネス新書)の一部を再編集したものです。
■「新NISA」ブームに性急に乗っていいのか
日経平均株価が上がってきていることもあり、政府の思惑通り「新NISA(少額投資非課税)制度」は大きな話題となって、株式市場への新規参入者や「返り咲き投資家(=昔は株式投資をしていたけれど、最近はしていなかった個人投資家)」が2024年になって大挙して株式市場に資金を投下し始めたようです。
私が最も危惧しているのは「その、株式投資を始めたタイミングが、日経平均株価がすでにかなり高い水準になってからだった」ということです。
私は、日本ではこれからも趨勢的(すうせいてき)なインフレが続くと考えていますので、日経平均株価は4万円どころか、5万円や6万円になっていく未来もあると考えています。決して楽観的とか強気とかではなく、それが「インフレ」というものだからです。
たとえば、日経平均株価の水準が2023年の2倍の6万円になったとしたら、それと並行して、喫茶店の珈琲代も2023年の500円の2倍の1000円になる。これが「インフレ」を前提とした経済社会です。
ですから、株式投資のような「インフレ対抗力がある経済活動」は早晩、始めておかないとインフレに負けてしまうのです。「インフレに負けてしまう」というのは、正確にいうと、「実質的な購買力が目減りしてしまう」ということです(「インフレ負け」の詳しい説明は、『1冊でまるわかり 50歳からのトレーダー入門』105ページにあります)。
■「非課税や税の優遇」はただのオマケにすぎない
ですから、インフレに負けてしまわないためにも、株式投資を始めておかなければならないわけなのですが、さりとて、株式投資を長年続けてきている私からすると、「何も、今このタイミングで始めなくても、もう少し割安なタイミングを待ってから始めた方がよいのでは⁉」と思うのです。

そもそも課税制度における「非課税や税の優遇」というのは、「オマケ」なのです。私は「税務会計論」を専攻して日本で修士論文、イギリスで博士論文を提出していますし、税理士の資格も保持しています。また、東北大学の助教授・教授時代には税務会計論講座を担当していましたから、色々な課税制度をみてきています。それらの経験に基づいて私が至った結論は、「課税制度における非課税や税の優遇というのは、オマケでしかないと思っておいた方がよい」ということなのです。
■高値づかみをしてしまう方が大問題
「新NISA制度」に限らず、たとえばいわゆる「住宅ローン控除」もオマケです。なので、住宅を取得する際に第一に考慮すべき点は「家が必要かどうか」で、税額控除が一番の理由になってはいけません。
なぜ国がオマケをくれるのかというと、住宅取得の促進は強力な経済活性化策になるからです。「新NISA制度」も、国が「貯蓄から投資へ」という資産形成の自助努力を後押ししたいから、オマケをくれるのです。
つまり私が一番強調したいのは、「新NISA制度にほだされて、高値づかみをしてしまう方がよっぽど大問題なので、たいしたことない非課税制度にほだされるのではなく、しっかりと株式投資の勉強をしてから始めた方がよいですよ」ということです。しかも、「新NISA制度」は恒久化されましたから、慌てて株式投資を始める必要はないのです。
■株価が安くなる局面を冷静に待とう
株式投資は、株価が割安な時に買い始めるのが基本のキです。
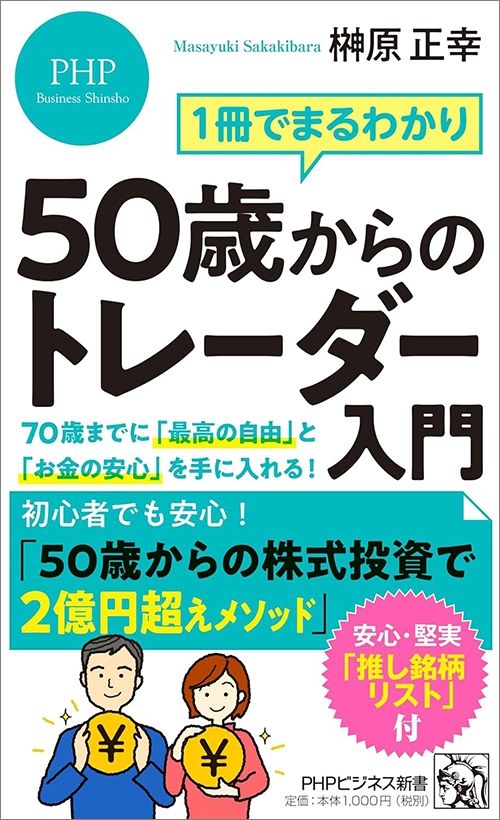
日経平均株価は、4万円前後でいったん調整する(=やや下落気味になる)でしょう。2024年3月時点の企業業績の水準から判断する限りでは、それが妥当な株価推移だからです。
とはいいつつも、『1冊でまるわかり 50歳からのトレーダー入門』が世に出るころに日経平均株価が4万円を超えてどんどんと上がっていたとしたら……それは「強いインフレの予兆」ですから、その後に来るのは厳しいインフレによる生活苦です。それこそ、かなりヤバいですね。
正常な経済状況の下では、日経平均株価といった「一国の経済指標」が一方向にどんどん進んでしまうことはあり得ませんし、好ましくもありません。であれば、株価が安くなる局面もあるはずですから、「新NISA制度」の導入とは関係なく冷静に、割安なタイミングを図るべきです。
■新NISAに最適の銘柄選びを考える
『1冊でまるわかり 50歳からのトレーダー入門』第4章でも述べていますが、私の投資手法は「定量的要因」(数値で分析できる要因)に重きを置いています。
しかし世の中の多くの方は、株式投資をする時に「定性的要因」(性質的なことに基づいた要因)に重きを置いているようです。「何をやっている会社か」、「社長の優秀さや理念」、「成長しそうな分野かどうか」といった「定性的要因」を主軸にして、あれこれと思考を巡らせながら投資対象の会社を選んでいます。これを、「定性的アプローチ」といいます。
一方、「定量的アプローチ」は「数字の世界」ですから客観的ですし、一定の手法を身につけてしまえばかなりの程度で再現性も確保できます。そのため、株式投資では「定量的アプローチ」の方が上手くいきやすいのです。
しかしそんな「定量的アプローチ好き」の私が今、唯一注目している「定性的要因」があります。それは「インド関連」です。向こう10年かそれ以上の間に、インドが爆発的に成長しそうだからです。これには、経験に基づく明確な根拠があります。
■かつての中国のような爆発的成長をとげる国はどこか
2004年ころから2020年に新型コロナウイルス感染症が蔓延するころまでの16年間で、中国経済は爆発的に成長しました。新型コロナ不況と不動産不況により、2021年以降の中国の経済成長は明らかに鈍化しましたが、そうなるまでの勢いには目を見張るものがあったのです。そしてその爆発的成長を遂げた2004年ごろの中国と2024年のインドは、その「成長の熱気」という点における雰囲気が非常に似ているのです。

著名な投資家であるジム・ロジャーズ氏の新著『2030年 お金の世界地図』(SBクリエイティブ)では、「インドは中国とは色々な面で異なり、社会制度などにも問題が多いので、あまり高く評価していない。モディ首相の政権運営に失望して、持っていたインド株は売ってしまった」と述べています(同書59~64ページ)。そんな同氏も、「今や中国を抜いて世界一の人口大国となったインドは、人口ボーナス期の恩恵を受け、経済成長のまっただ中にある」と述べています。
■インド市場に上場された株は買いにくいが…
私は、この「人口ボーナス期」に着目しています。「人口ボーナス期」とは、「人口が増える時期には、それに伴って経済も成長する」という意味です。そしてこれは向こう数年~10年は続くでしょう。人口構成というのは、1年や2年で急に変わりはしないからです。
ですから私は、この「インド関連」は息の長い「相場の柱」になると直感しているのです。
なお、インドは成長が見込める国だからといって、インドに上場する企業の株を買うのはおすすめできません。ジム・ロジャーズ氏も述べているように、インドには社会制度などの面で色々な問題もあるようですし、そもそも(私が調べた範囲では)インドの市場に上場する株を日本人が直接買うことはできないようです。成長が著しい国家では、資本を海外から入れたくないのかもしれません。
ですから、私がおすすめするのは「日本×インド」、すなわち「インドに進出している日本企業」のうち、安全性が高い企業の株を買うことです。そうすることで、インドの社会的な問題も加味した上で、インドの経済成長の恩恵を受けることができると考えるのです。
■「日本×インド」で注目すべき銘柄はズバリこれだ!
さて、先ほど「新NISA制度はたいしたことはないので、タイミングを熟慮することが大事です」と述べましたが、そんな中でも「新NISA制度」にうってつけの投資を考えると、実はそれこそが「インド関連銘柄への長期投資」です。
「インド関連銘柄」と一口にいっても、さまざまな銘柄があります。「インド関連銘柄」で検索するだけでも山ほど出てきます。その中で私が注目しているのは「スズキ(7269)」です。皆さまご存じ、自動車メーカーのスズキです。
この会社は財務的にも健全で、国際的にみても優良な銘柄ですし、何といっても、大企業の中でインドに進出した草分け的な企業です。「インド関連銘柄」には他にも「ダイキン工業(6367)」などの優良企業がありますが、株価が比較的割安な水準にある「インド関連銘柄」の代表格がスズキです。
ただし、このスズキの配当利回りは2024年3月末の時点では2%未満で、あまり高くはありません。市場参加者が「成長株である」と見なしている銘柄は株価の値上がり(キャピタルゲイン)への期待が大きいため、配当利回り(インカムゲインの利回り)は、どうしても低めになりがちなのです。
■新NISAを上手に使いこなすスキームの例
最後に、もし私が「新NISA制度を上手に使いこなす」とするならば、考えるであろうスキームをご紹介していきます。
まずは、スズキの株を毎年240万円ずつ買います。スズキの株価は2024年3月上旬現在、「6600円前後」で推移しています。そして、スズキは2024年3月31日(曜日の関係で、実質的には同年3月29日)を基準日として、1株につき4株の割合で株式分割をすることが決まっています。
2024年3月上旬現在の株価よりも、たとえば1割くらい下がった6000円を買いの目標株価にするとします。そしてそれが4分割されると株価は1500円になるので、240万円なら1600株買えるということになります(手数料は度外視した概算です)。これを、たとえば16年保有し続けます。
■「10倍に値上がり」も夢ではない?
中国経済は16年で24倍になったので、インドも16年で24倍になるとすれば、スズキもかなり成長するでしょう。スズキの商圏はインドだけではないので、24倍とまではいかないでしょうけれども、10倍くらいになるのは、まんざら夢でもないかもしれませんね。まさに「テンバーガー」(短期間に株価が10倍に値上がりした銘柄のこと)です。
もしそうなったとしたら、単純計算で240万円は2400万円になるので、2160万円もの利益が得られます。これに対する税額は、現行制度ではおよそ439万円にものぼりますが、「新NISA制度」を活用すればこれを非課税にできるのです。
しかも、これは「1年分」でしかありません。たとえば向こう5年にわたってこれを続けて、16年後にスズキの株価が10倍になったとすると、スズキ株の総資産額だけで軽く1億円を超えますし、節税額も軽く2000万円を超えます。
■「成長株の長期保有」こそ新NISAの有効な使い方
これはもはや「オマケ」とはいえませんね。「新NISA制度」による非課税の240万円は「成長投資枠」という名前です。ですから、こういった「成長株」と見込まれる株を長期的に保有し続けて、たっぷりと非課税にしてもらうことこそが、「新NISA制度」を有効に活用するということなのだと思います。
より掘り下げて考えれば、「1年で1回転までが非課税」なのであれば、1年周期で高値で売って、安値で買い戻すことを繰り返すのが最も節税額(と利益額)が大きくなるのです。しかし、そういうことを上手くやってのけるのは上級者でもなかなか難しいので、「新NISA制度の成長投資枠は、長期保有」と決めて長期投資で巨額な利益を得て、それを非課税にするのが、最も楽で、かつ非課税の効果を最大化できる活用方法でしょう。
「新NISA制度」は「株式投資を始める理由」ではなく、「少なくとも1年以上保有する長期投資による多額の利益を非課税にできる」ということに、その本質があるのであろうと考えています。
----------
会計学博士
1961年、名古屋市生まれ。名古屋大学経済学部、大学院経済学研究科を経て、同大学経済学部助手。東北大学経済学部助教授、同大学院経済学研究科教授、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授を経て、21年3月に退任。現在はファイナンシャル教育の普及活動を続けている。著書に『株式投資「必勝ゼミ」』(PHP研究所)の他、『現役大学教授が教える「お金の増やし方」の教科書』(PHP研究所)、『会計の得する知識と株式投資の必勝法』(税務経理協会)などがある。
----------
(会計学博士 榊原 正幸)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
株式投資で最もやってはいけないことの1つとは?
MONEYPLUS / 2024年7月3日 7時30分
-
新NISAでもETFに投資できる! リアルタイムで売買可能なメリットの一方、デメリットも? ざっくり解説!
Finasee / 2024年7月1日 19時0分
-
国内株式投信は「高配当」「金融」で確実なリターン狙う動き 円建て資産の魅力再認識か
Finasee / 2024年6月28日 16時0分
-
定年退職、おつかれさまでした。でも、まだ大事な話が…元サラリーマンの人生第2ステージ、経済評論家が教える重要ポイント
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 9時15分
-
新NISA“成長投資枠”で狙いたい「米国高配当株」10選。配当金の再投資で大きく増やす
日刊SPA! / 2024年6月14日 8時51分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」
乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












