なぜ人間には「浮気をする人」と「誠実な人」が存在するのか…人間が「完全な一夫一妻制」とは言い切れないワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 17時15分
※本稿は、アンジェラ・アオラ『不倫の心理学』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■人間は一夫一妻制か乱婚制か
生殖と繁殖はそれぞれの種にとって極めて重要である。効率的に繁殖するために、種によって異なる進化を遂げてきた。動物界で最も一般的な繁殖戦略の1つが乱繁殖である。95~97%の種が行っていて、残りの3~5%が社会的一夫一妻制を実践している。
XとYが出会い、一緒になり子供を作り、共に子育てをする。互いに忠実であるのは表面上だけだ。機会があればその裏で他と交尾をするのが普通だ。研究者の中ではこの種の浮気は「日和見主義の浮気」と呼ばれ、生物学上の父親ではない、社会的父親のもとで育つ子供やその数に関係があると言われている。
研究対象の小動物の1つがプレーリーハタネズミだ。社会的一夫一妻制をとる小柄な動物である。この小さなハタネズミは生まれ、成長し、思春期を過ぎた頃にパートナーを見つける。ハタネズミは一生の間に何匹もの子供を産み、育てる。一緒に巣を作り、縄張りを守り、餌を与え、子供の世話をする。互いにそばにいて、離れると分離不安を見せる。
■表向きは社会的一夫一妻制でも裏では浮気する
交尾をするとメスはオキシトシン、オスはアルギニンバソプレッシン(オキシトシンとバソプレッシンに似た神経化学物質)の放出が誘発され、両方とも報酬中枢を刺激しドーパミンが放出される。これで両者は複数の異なる相手ではなく、特定の1匹の相手を好むようになる。
このつがいの形成には脳のオピオイド系とドーパミンやその他の神経系も関与している。つがいで行動するハタネズミは一生を共に過ごし、表向きは忠実で社会的一夫一妻制だが、機会があれば浮気をする。
動物をテーマに話を続けよう。乱繁殖のシロアシネズミやアカゲザルはつがいを持たない。特定のパートナーとの結びつきがないのだ。彼らは一夫一妻制のハタネズミにある、ある種の受容体が脳内の同じ場所に見当たらない。
■乱婚種が一夫一妻制になる遺伝子がある
このことを確認した研究者たちは、ハタネズミのつがい形成に関連する遺伝子を導入することで、乱婚種を一夫一妻制にできるか調べようとした。この遺伝子を乱婚種のマウスに導入すると、それまでは様々なマウスに求愛していたにもかかわらず、突然特定のマウスに執着するようになった。研究者たちは他の種でもまったく同じ実験、つまり乱婚種の動物を一夫一妻制にする実験を行った。結果は同じであった。
最も興味深い発見の1つは、つがいの結びつきの強さに寄与する特定の遺伝子が存在することで、この遺伝子はどれだけ一夫一妻制を続けられるかに影響する。
ヒトは一夫一妻制なのか、それとも乱婚種なのかという問いの答えを探し続けていると「不倫――いつ、どこで、なぜ」という興味深い研究論文に出くわした。これは、人が何に惹かれるかに影響を与える、さらなる要因について説明している。
■共通の遺伝子を多く持つカップルほど浮気しやすい
典型的な“汗ばんだTシャツ”の実験では、研究者たちは様々な男性が着用したTシャツの匂いを女性に嗅がせた。その後、女性たちに最も惹かれると思うTシャツを選んでもらった。

興味深いことに、それぞれの女性がお気に入りとして選んだTシャツは、免疫系の特定の部分にその女性とは異なる遺伝子を持つ男性が着ていたものだった。汗をかいたTシャツに含まれる女性に影響を与えた物質はフェロモンと呼ばれ、体内で生成される化学物質である。フェロモンは皮膚から汗として分泌され、周囲の空気中にしばらく漂う。
ニューヨーク、ロンドン、ロサンゼルスで“フェロモン・パーティー”が企画されたことがあった。参加者は4日間、毎日新品のTシャツを着て眠り、着用者のフェロモンを吸収したTシャツはジップロックバッグに入れられる。
このイベントは参加者が「嗅ぎ分ける」ことで完璧な遺伝子によるマッチングを行うのだ。ただこの戦略がどの程度、成功したかについての数字はない。分かっているのは、自分と似た遺伝子を持つ男性と結婚した女性は、浮気する確率も高いという研究結果があるということだ。
つまり自分と似た遺伝子を持つ男性をパートナーとする女性は、自分とは異なる遺伝子を持つ男性と浮気をするのだ。「パートナーと共通の遺伝子が多ければ多いほど浮気する可能性が高まる」というのは、シンプルに言ってしまうと、浮気は問題解決――パートナーと同質の遺伝子が多すぎるという問題の解決――のための無意識の戦略となっていると言える。
免疫システムにおいて、似たような遺伝子が多すぎるということは、妊娠や生殖能力に関わる合併症のリスクの増加を意味するからだ。
■矛盾する働きを持つ脳の3つの機能
脳の構造も浮気に関係している。研究者のヘレン・フィッシャーは主に脳内の3つの機能について述べている。
第1は性欲で、脳は様々な人との性行為へと駆り立てるように進化した。第2は恋愛で、特定の相手にエネルギーを向けるように進化している。第3はパートナーへの愛着であり、少なくとも2人の間に生まれた子供が乳幼児期を乗り切るのに充分な期間、共に過ごす動機を与えてくれるように進化している。これら3つを駆動する基本的な神経系は、脳内の他の神経構造と様々に連係して機能する。
これら3つの脳の領域は、それぞれ異なる動機や感情をもたらし、繁殖と人類の発展のため、私たちの行動を様々な方向へと導く。繁殖と生存は種にとって最も重要な目標であり、人類が今日存在する理由でもある。
最も興味深いのはこれら3つの脳の領域が矛盾しあう働きを持っていることだろう。多種多様な相手に向けられるはずの性欲は1人のパートナーに向ける愛着や愛情と対立している。したがって一時的な満足を得るには性欲は他の2つを危険にさらすことになる。
この多面的で柔軟な脳の仕組みによって人間はパートナーに対して深い愛着を感じながらも、同時に第三者(浮気相手)に対して激しい恋愛感情を抱き、性的な欲望を抱くことが可能になる。
■社会的一夫一妻制と性的な非一夫一妻制
もちろん、生物学的に説明がつくとしても、特定の行動が“正しい”ことを意味するわけではない。8000を超える種のうち、実に90%がつがい形成を行う鳥類を見てみよう。つがい形成は子供の世話を楽にする。しかし哺乳類では一般的につがい形成は珍しい。哺乳類のわずか3%で、この中にプレーリーハタネズミも含まれる。
一夫一妻制の種であっても浮気は起こりうるのは先に述べた。研究者たちはいわゆる一夫一妻制の鳥類や哺乳類を100種以上研究し、浮気が非常に広範かつ頻繁に起こっているため社会的一夫一妻制と呼ぶようになっている。誰かと同棲している人がパートナー以外の人と場当たり的なセックスをすることもあるだろう。
ヘレン・フィッシャーは社会的一夫一妻制(同棲パートナー、夫、妻、ガールフレンド、ボーイフレンドなどの組み合わせ)でありながら、同時に日の目を見ない秘密の関係を1つ以上持つ生殖戦略を「二重生殖戦略」と呼ぶ。社会的一夫一妻制と性的な非一夫一妻制を組み合わせたものだ。
■「浮気は人類の種の発展に貢献した」と考える研究者もいる
社会的一夫一妻制と呼ばれるのは、生涯にパートナーが何人もいたとしても、正式なパートナーは常に複数ではなく、1人であることに変わりはないからである。こうしたあり方から、一部の研究者は浮気が人類の種の存続に貢献したのだろうと結論付けている。社会的忠誠と性的な不貞の組み合わせは種にとっては生産的なのだと。
これは、人間のすべての行動が種に利益をもたらすために進化したという意味ではない。また、人間の行動のすべてが進化の結果であるという意味でもない。偶発的な行動もあれば少数派もいるからだ。
人間は社会的一夫一妻制と性的非一夫一妻制を組み合わせて暮らしている。通常は1人のパートナーと暮らすが、浮気をする人もいる。浮気を決してしない人もいれば、ほとんどのパートナーシップで浮気をする人もいる。父親が“正式な”父親でない子供の数は0~11%で、中央値は1.7~3.3%と推定されている。鳥類では20%を超える。
これは生物学的見地から見て、人間が鳥類よりも一夫一妻制の種であると言えるのだろうか。それとも、人間の一夫一妻制の度合いが高いのは生物学的現象ではなく、浮気はいけないことだという規範の表れなのだろうか。
■人間の睾丸は完全な一夫一妻制の種のオスよりも少し大きい
他の指標も見てみよう。1つは体に対する睾丸の大きさである。この比率は精子の生産速度を決定し、パートナーの数に関係してくる。人間の女性がある男性と性交したとする。例えば同じ日に次に性交する男性は前の男性に精子の生殖機能において勝る、あるいは取って代わる必要がある。人間の睾丸の大きさは完全な一夫一妻制の種のオスよりも比率としてはわずかに高い。だが、最も乱婚な種ほど高くはない。
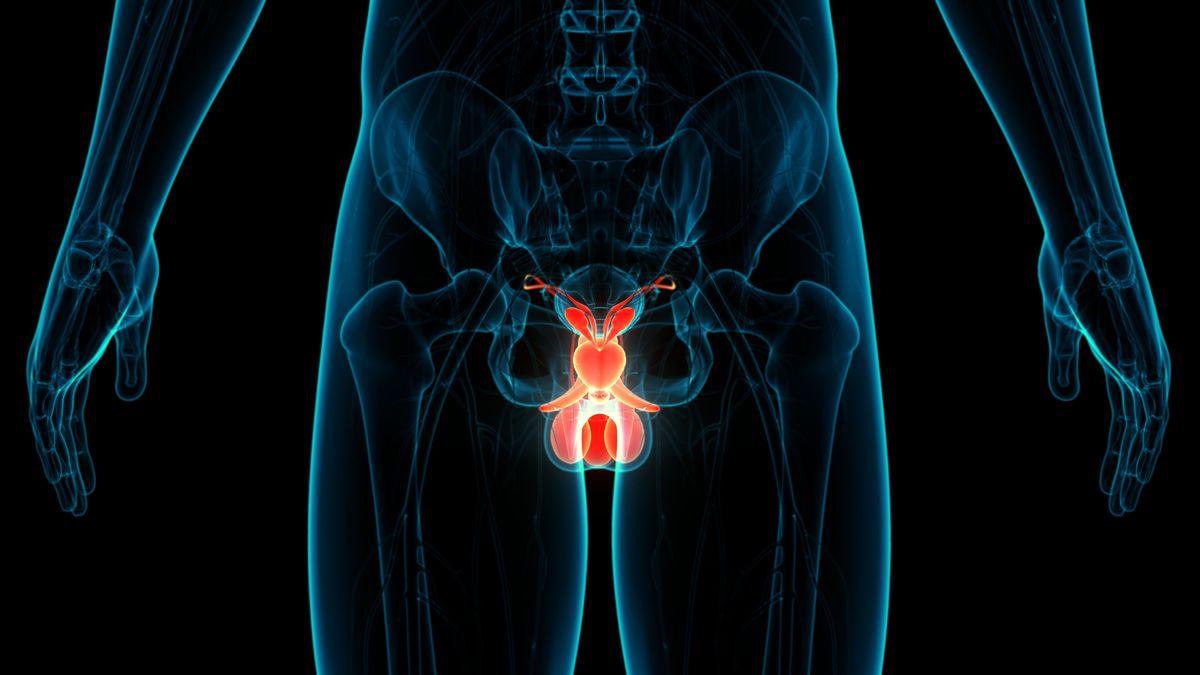
次の生物学的指標は人間の“隠された”排卵である。女性に排卵があるかないかで男性の反応が微妙に異なるという研究結果がある。動物の一部の種では、排卵期に性器の色や大きさが変化するが、人間は比較的隠されていて、これは一夫一妻制にとって有利だと考えられている。排卵が目に見えにくければ、男性は次の排卵期までの1カ月、いつでも妊娠するだろうと気を抜かずに求愛とセックスをし続けなければならない。
■人間は完全な一夫一妻制でも乱婚でもない
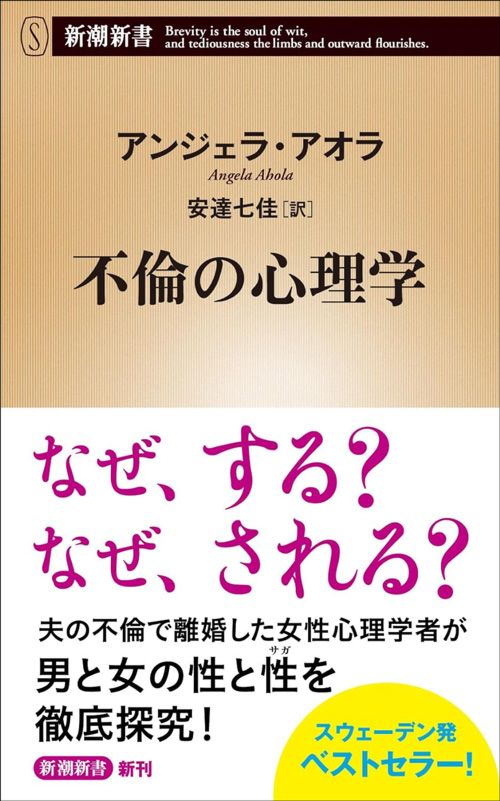
人類が本質的に一夫一妻制の種なのか、それとも非一夫一妻制の種なのかについて、研究者たちの意見が歴史的に一致してこなかった理由はいくつかある。人間には実に様々な行動パターンがあり、文化や時代によって様々な種類のパートナーシップの形があった。
短期的な交際もあれば、長期的なパートナーシップもあり、ポリアモリーな関係や死が2人を分かつまで同じパートナーと暮らす生涯一夫一妻制のほか、連続単婚やポリアモリーであるのに社会的一夫一妻制でいることもある。つまり不倫である。このようなパートナーシップの形のいくつかは、宗教、規範、文化、そして私たち人間が実際はどうあるべきかについて抱いてきた様々な考え方に突き動かされている。
要約すると、人間は完全な一夫一妻制でもなければ、著しく乱婚でもない。完全に誠実であり続けようとする者もいるだろう。また、誰と暮らしても浮気する人もいるということだ。
----------
1974年スウェーデン生まれ。心理学博士。ストックホルム大学にて心理学を学ぶ。専門は知覚心理学。著書多数。現地ではメディアへの登場も多い。
----------
(心理学者 アンジェラ・アオラ)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
徳島大など、ニワトリ胚の雌雄を卵の外から早期に判別可能な方法を開発
マイナビニュース / 2024年7月2日 18時49分
-
更年期世代も「まだ恋愛をする」理由とは?脳の仕組みから考える「極めて明快な理由」【脳科学者・黒川伊保子先生に聞く】
OTONA SALONE / 2024年6月29日 20時0分
-
不倫の発覚には平均4年かかる…「浮気専用サイト」の会員1000人に調査した意外な結果
プレジデントオンライン / 2024年6月20日 17時15分
-
東大など、「クマムシ」の標的遺伝子を改変した個体の作製に成功
マイナビニュース / 2024年6月17日 17時9分
-
最強動物「クマムシ」のゲノム改変を可能に
PR TIMES / 2024年6月14日 10時45分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












