商売は人間のクズがやることだった…武士の国に資本主義を根付かせた新札の顔「渋沢栄一」の天才的発想
プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分
日本銀行金融研究所貨幣博物館内に展示されている新1万円紙幣。新紙幣の流通開始は2024年7月3日。20年ぶりのデザイン変更となる(=2024年5月27日、東京) - 写真=picturedesk.com/時事通信フォト
※本稿は、井沢元彦『歴史・経済・文化の論点がわかる お金の日本史 完全版 和同開珎からバブル経済まで』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
■商売人のイメージは「覚せい剤の密売人」
渋沢栄一はなぜ官僚をやめ、実業家になろうと思ったのか?
「お上」が指導するだけでは、決して近代資本主義社会は成立しないからである。そもそもヨーロッパはすべて民間主導である。自由主義経済というのはそういうものだ。だが元武士たちはそのことを理解せず、あまつさえ叩き込まれた朱子学によって「商売は人間のクズのやる悪事」と思い込んでいる。
武士階級の出身者が多い新政府の役人も「商売を盛んにしないと国が豊かにならない」と頭では理解していたものの、やはり心の奥底で「商売は悪事」という偏見は持っている。だから渋沢は同僚から非難された。
たとえばあなたの会社の同僚が「会社を辞めて覚醒剤の密売人になる」と言えば、「バカなことはやめろ」「頭がおかしくなったのか」と制止するだろう。それと同じ感覚である。これは決して大げさな言い方でないことは、本書の読者ならよくわかるだろう。また歴史書に書いてある「渋沢は日本近代資本主義を構築した」などという「一行」は事実ではあっても、そうすることが当時不可能に近い難事であったことを忘れてはならない。
一体どうすればいいのか? 自分の頭で考えることがお好きならば、ここでいったん読むのをやめて考えていただきたい。ヒントは次頁の写真である。
■朱子学の功罪
「商売は悪事」という偏見をもたらしているのは朱子学だから捨ててしまえばいい、と言うのは簡単だが、実際にはその朱子学がもたらした天皇への忠義が明治維新を成し遂げ「天皇の下での平等」も確立した。
朱子学を完全に捨てることは難しい。もちろん朱子学を排除した新しい教育を始めるという手もなくはない、福沢諭吉の『学問のすゝめ』や中村正直の『西国立志編』はそうした方向性を示してはいた。だが一刻も早く西洋諸国に追いつくためにすぐにでも資本主義を確立しなければいけないのに、それでは時間がかかりすぎる。
■渋沢の天才的発想
そこで渋沢は考えた。
歴史的に見れば朱子学とは儒教の一派で、儒教の開祖である孔子(こうし)の説を「発展」させたものと言われている。だから武士階級は朱子学を学ぶ前に孔子の教えを必ず学ばされる、それは武士階級にとっての常識である。ところが、英語では孔子の教え、つまり本来の儒教をConfucianism(直訳すれば「孔子主義」)と呼ぶのに対し、朱子学はNeo Confucianism(「新孔子主義」)と呼ぶ。両者は実際にはかなり違うものなのだ。
百科事典などには小難しい理屈が書いてあるが、両者の違いは私に言わせれば「朱子学は本来の儒教に比べてヒステリック」なのである。なぜそうなったか、歴史的理由があるのだが、それを解説するには紙数が全く足りない。この点に興味のある方は『絶対に民主化しない中国の歴史』(KADOKAWA刊)を読んでいただきたい。
ここでは要点だけ述べるが、孔子の儒教では「商売は人間のクズのやる悪事」などと決めつけておらず、それをヒステリックに叫んだのは朱子なのである。ならば儒教の根本である孔子の教えに戻ればいい。孔子の言行録である「論語」には「商売のすすめ」とも受け取れる言葉がたくさんある。肝心なことはこれなら元武士たちも抵抗なく受け入れられるし、新たな教育も必要ないということだ。まさに天才的発想である。
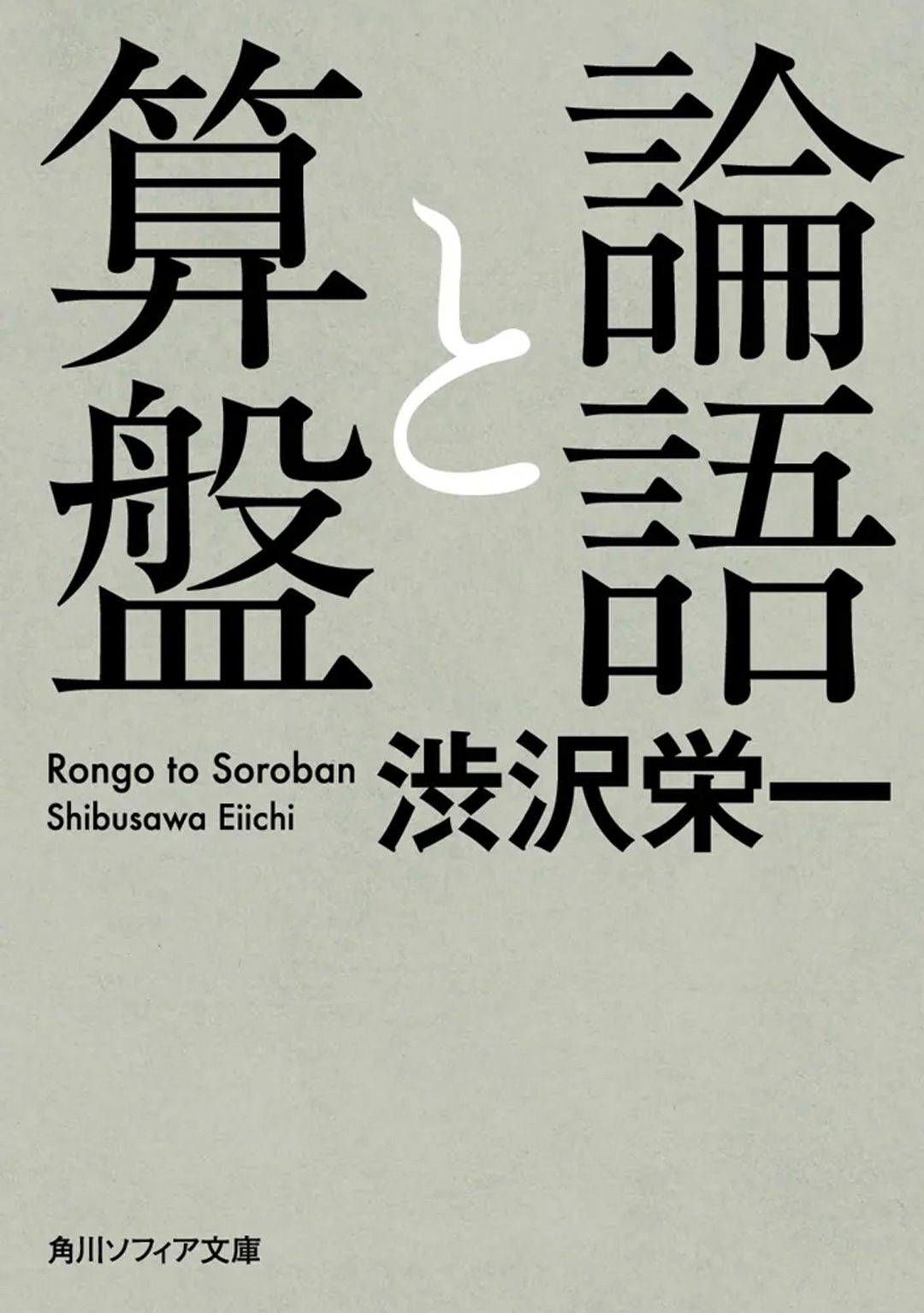
■水と油をこじつけた『論語と算盤』
渋沢栄一の著書『論語と算盤(そろばん)』を悪意をもって評するなら、もともと「水と油」である「論語(儒教)と算盤(商売)」に深い関連性があると「こじつけ」たものである、という言い方もできるだろう。
本来の儒教では孔子に次ぐ聖人である孟子(もうし)の言葉に「恒産(こうさん)無くして恒心(こうしん)無し」というのがある。「恒」という字は訓読みでは「つね」と読むが、安定した職業や財産をもたない人間は(生活に追われるから)しっかりした道徳心を持てない、という意味である。
渋沢のやり方は、この言葉を「だからこそ、われわれは定期収入を得られる商売をおろそかにしてはいけない、孟子はそう言っている」という言い方である。そのように拡大解釈できないとは言えないが、実際には孟子はそこまで言っていない。
■商工業にも「武士道」はある
朱子学は士農工商にやかましいが、本来の儒教も士つまり学問で儒教を身につけた人間は、ほかの農工商つまり民衆より優れているという感覚があった。逆に言えば農工商には道徳などないということで、日本でも士つまり武士はやはり武士道という道徳を身につけており、その点で農工商とは違うという感覚があった。
だからこそ渋沢は商人になることを同僚に強く反対されたのである。だが、それ以後渋沢は「孔子の真意はそうではない」という言い方で倫理を説き、日本の資本主義を構築していった。ここは本人の言葉を引用しよう。

■「渋沢なき資本主義」は「倫理なき資本主義」
泰西(ヨーロッパ)の商工業者は必ず契約を守るが、日本の商人は必ずしもそうではないということなのである。契約を守ることは近代資本主義社会の最低成立条件でもある。渋沢はまさに「そこから」始めなければならなかった。

「商売は悪」の社会では商人はギャングと同じで、約束を守らなくても暴利をむさぼってもいい。非難はされるにしても、道徳に従えとは誰も言わない。道徳を守らないのが悪人だからだ。しかし渋沢は儒教にことよせて近代資本主義の道徳を確立した。企業がその利益を社会に還元すべきだという考え方も、一部の良心的な商人にはあったが、商工業界全体の倫理ではなかった。全体をそのように変えたのは他ならぬ渋沢である。
では渋沢がいなかったら、日本はどうなっていたか? 恰好の例がある。「渋沢なき資本主義」で一度は近代国家をつくった中国だ。孫文が清朝を倒した辛亥(しんがい)革命(1911年)である。
しかし、この「ブルジョア革命」はうまくいかなかった。倫理なき弱肉強食の資本主義が横行し国民党は腐敗堕落し、「資本主義打倒」をスローガンにした共産党にとってかわられた。そして今、中国共産党は資本主義を「採用」したが、相変わらず「渋沢栄一」はいない。
「倫理なき資本主義」が今後どうなるか、現代世界の不安定要因の一つであろう。
おわかりだろう、日本史に渋沢栄一が存在したこと自体一つの奇跡なのだ。
■「新常識」をつくる天才の宿命
渋沢栄一の『論語と算盤』は今も読み継がれるべきかという質問には、「必ずしもそうではない」と私は答えるかもしれない。
ケチをつけるわけではない。
これは名著であり紛れもなく明治時代の日本にとって絶対に必要な書物だった。目的は商工業の世界に武士道つまり倫理を確立することである。それが成功したのは、日本製品の品質が世界で高く評価されていることからもわかるだろう。しかしこれが天才の宿命だが、極めて困難な改革を成し遂げるとそれが常識となるため、それ以前がいかに大変だったか忘れ去られてしまう。
■渋沢が生涯貫いた商工業の倫理
渋沢は野に下った後、民間人として、新設された第一国立銀行の頭取に招かれた。当時の日本にはまともな銀行すらなかったのである。これを皮切りに渋沢は様々な業種の会社を設立した。東京証券取引所、東京ガス、東京海上火災保険、王子製紙、東急電鉄、京阪電気鉄道、帝国ホテル、東洋紡、明治製糖等々すべて渋沢がその設立にかかわったか、かかわった会社の「子孫」で他にも数えきれないほどある。
特筆すべきは、渋沢がそれらの企業をグループ化して三菱財閥のような財閥を作らなかったことだ。この点、渋沢は三菱の創設者である岩崎弥太郎とは考えを異にしていた。
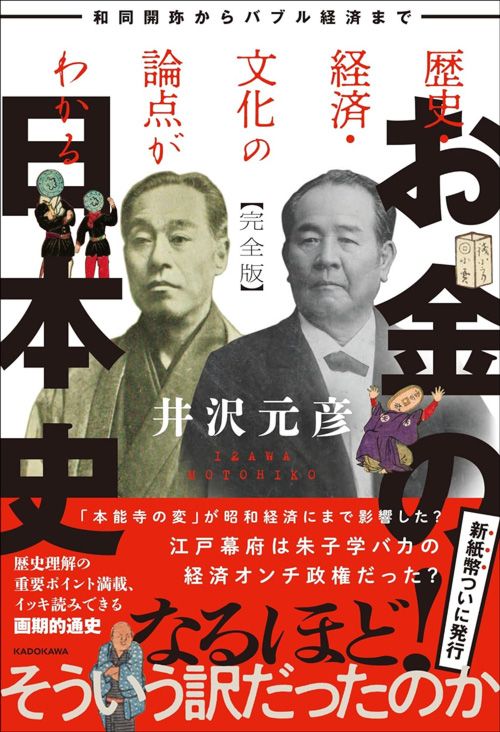
渋沢がそうしたのは商業道徳、企業倫理を確立するのが生涯の念願だったからだろう。もちろん直接の敵は朱子学である。渋沢はのちに「朱子学の罪」と題する講話の中で、孔子は必ずしも商業を悪とはしなかったのに、その教え(教旨)をゆがめたのは朱子だと厳しく批判している。原文を引けば「この孔子の教旨を世に誤り伝えたものは、宋朝の朱子であった。孔子は貨殖富貴を卑しんだもののように解釈を下し、貨殖の道を志し富貴を得る者をついに不義者にしてしまった」(『渋沢百訓』角川ソフィア文庫より一部抜粋)。
これではソフトバンクの孫正義さんも「ホリエモン」こと堀江貴文氏も全部「極悪人」になってしまう。もちろん現代人はそんなことは夢にも思わないだろう。渋沢の意識改革が完全に成功したからである。
----------
作家/歴史家
1954年、名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、TBSに入社。報道局在職中の80年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞。退社後、執筆活動に専念。独自の歴史観からテーマに斬り込む作品で多くのファンをつかむ。著書は『逆説の日本史』シリーズ(小学館)、『英傑の日本史』『動乱の日本史』シリーズ、『天皇の日本史』『絶対に民主化しない中国の歴史』(いずれもKADOKAWA)など多数。
----------
(作家/歴史家 井沢 元彦)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
<話題の本>新紙幣で関心高まる 『現代語訳 論語と算盤』渋沢栄一著、守屋淳訳
産経ニュース / 2024年7月21日 8時0分
-
だから「20人の婚外子」と「500の会社」を作った…「新一万円の顔・渋沢栄一」が最晩年まで守り続けていたこと
プレジデントオンライン / 2024年7月18日 10時15分
-
日本人ならスラスラ説明できて当たり前…20年ぶりに刷新された「新札トリオ」のとんでもない功績
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 10時15分
-
【7月3日から新紙幣発行へ】肖像3人、渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎を知る3冊を紹介
マイナビニュース / 2024年7月3日 7時0分
-
正しさを忘れた渋沢栄一etc.「新紙幣の偉人たち」知られざる“やばい”一面とは
日刊SPA! / 2024年7月1日 8時51分
ランキング
-
1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て
東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分
-
2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】
オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分
-
3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…
日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分
-
4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?
オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分
-
5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度
読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください











