「反共主義」のためならナチスの残党も利用する…長らく"孤立主義"だったアメリカを大きく変えた「2つの脅威」
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 9時15分
※本稿は、佐藤優監修『米ロ対立100年史』(宝島社)の一部を再編集したものです。
■「共産主義の拡大を封じ込めなければならない」
「共産主義の拡大を封じ込めなければならない」――アメリカ政府内では、このような認識が急速に広がる。きっかけは1946年2月、モスクワのアメリカ大使館に赴任していた外交官のジョージ・ケナンが、本国に送った長文の電報だ。ケナンは東欧で急速に勢力を拡大するソ連の動きを正確に分析して、政府に警告した。
この頃、東欧諸国がソ連の実質的な支配下となるなか、ギリシアとトルコでもソ連の支援を受けた共産党が急速に勢力を伸ばしていた。第二次世界大戦中、イギリスはヨーロッパ各地で反ファシズムかつ反共主義の勢力を支援していたが、枢軸国との戦いに多くの資金や人材、武器を投入したことで、国力に余裕がなくなっていた。そこで、反共主義勢力を支援する役割は、アメリカに引き継がれることになる。
■「トルーマン=ドクトリン」と冷戦の本格化
1947年3月、アメリカのトルーマン大統領は、ソ連に対抗するため、4億ドルの巨費を投じてギリシアとトルコへの経済的・軍事的な援助を行なうことを議会で訴える。トルーマンは、自由主義に対する共産主義の脅威を強調した。これには、無神論を掲げる共産主義が信教の自由を脅かすことも含まれ、アメリカ国内のキリスト教会関係者の多くは、トルーマンの方針を強く支持した。こうして確立されたソ連との対決姿勢は「トルーマン=ドクトリン」と呼ばれ、ここから冷戦が本格化する。
同年6月、国務長官ジョージ・マーシャルの主導によって、アメリカが戦後のヨーロッパ諸国の復興に大規模な援助を行なう「マーシャル=プラン」(欧州復興計画)を発表する。
100億ドル以上もの資金が投じられたが、支援金によってヨーロッパ諸国がアメリカの機械類や農産物を購入する形になり、アメリカ経済にも恩恵をもたらすものだった。ソ連とその勢力圏の東欧諸国は参加を拒否し、東西の分断が確定する。
旧枢軸国のドイツも米、英、仏の占領地域はマーシャル=プランの支援対象となる。問題はソ連が占領する東部地域のなかにあるベルリンで、市街の西部のみが米、英、仏の占領する「飛び地」となっていたことだ。1948年4月、ソ連は西ベルリンと外部地域の境界線に検問を設置して交通を制限し、封鎖された西ベルリンは陸の孤島と化した。
■ソ連に対する共同防衛のためNATOが発足
「これで米、英、仏が西ベルリンから撤退するだろう」、ソ連側はそう期待したが、アメリカは西ベルリン市民と駐留部隊のため、大々的に物資の空輸を行なった。その回数は延べ27万回、輸送量は1949年春には1日あたり8000トンにも及んでいる。結局、米ソ両国の交渉を経てソ連が譲歩し、1949年5月にベルリン封鎖は解除された。
この直後、米、英、仏の占領地にドイツ連邦共和国(西ドイツ)が成立し、同年10月には、ソ連占領地でドイツ社会主義統一党が政権を担うドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立した。東西ドイツはヨーロッパにおける冷戦の最前線となる。
この間にイギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの西欧5カ国は、ソ連に対する共同防衛のため、1948年3月に西ヨーロッパ連合条約を結んだ。翌年には、これをさらに拡大させて、アメリカ、カナダ、イタリアなど計12カ国が参加する北大西洋条約機構(NATO)が発足する。
こうした国際的な冷戦の進行は、同時期の日本にも影響を与えた。敗戦後の日本はアメリカの占領下で農地解放、財閥解体、女性の政治参加などの民主化が進められたが、アメリカは共産主義陣営の拡大を懸念して占領統治方針を改め、労働運動や共産党員の活動を厳しく取り締まるようになる。その反面で、軍国主義的と見なされて公職追放された元軍人や官僚の復権を許した。こうした一連の措置は「逆コース」と呼ばれる。
■スパイ映画で有名なCIAもこのとき発足した
アメリカの西部劇には、ときおり、住民たちが保安官に頼らず自力で犯罪者を捕らえて制裁を加える場面が出てくる。このように、アメリカは開拓時代から政府機関の力が弱く、自由放任と地方分権を基本とする国家だった。ところが、冷戦の進行によって、共産主義に対する国際戦略のため、大統領府への権力集中が進む。
1947年7月、国家安全保障法が成立した。これにより、外交政策と国防政策を連動させるべく、大統領、副大統領、国務長官(諸外国での外務大臣に相当)、国防長官が参加する国家安全保障会議(NSC)が設置される。また、陸軍と海軍、そして大戦後に成立した空軍を統合する国防総省と統合参謀本部が設立された。
スパイ映画で有名な中央情報局(CIA)も、このとき発足した。第二次世界大戦中の諜報機関である戦略事務局(OSS)は終戦直後に解散していたが、その人員や技術を引き継ぐ形で組織が編成された。アメリカでは陸軍、海軍、国務省がそれぞれに諜報機関をもっていたが、CIAはそれらを統合する大統領直属の機関だ。

■CIAによる最初の海外での秘密工作
CIAによる最初の海外での秘密工作といわれるのが、1948年4月に行なわれたイタリアでの選挙介入だ。終戦前後のイタリアでは、ファシスト党への抵抗運動を通じて共産党が急速に勢力を伸ばしていた。そこでCIAは、カトリック教会を支持母体とし、反共主義を強く唱えるキリスト教民主党に巨額の選挙資金を提供した。
じつは、海外のカトリック教会とアメリカの諜報機関の間には、かねてより協力関係があった。終戦直後にOSSは、旧ドイツ陸軍の情報将校ラインハルト・ゲーレンなど、ソ連事情に通じたナチス関係者の身柄を確保し、戦犯として裁判にかけることなく密かにアメリカへ移送し、ソ連に対抗する諜報活動に協力させた。反共主義のため、アメリカはナチス残党も利用したのだ。ゲーレンらを秘密裏にドイツから出国させるときには、ヨーロッパのカトリック教会関係者が手助けしたともいわれる。
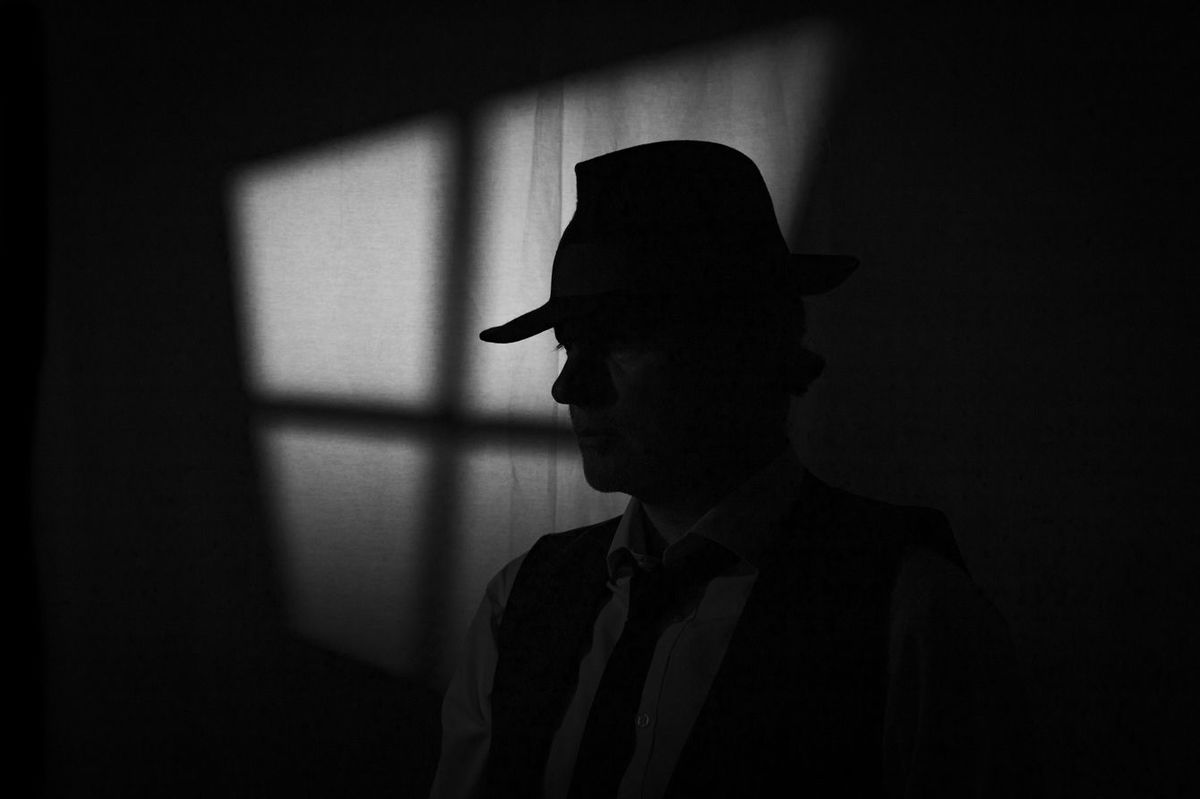
■国防強化を背景に形成された「軍産複合体」
19世紀から長らく孤立主義を採ってきたアメリカが、このように軍事面や諜報活動で海外への積極介入に転じた背景にあるのは、共産主義への脅威だけではない。それまで、アメリカは大西洋と太平洋に挟まれ、地理的にほかの大国から離れており、大きな戦争に巻き込まれる可能性は低いという前提があった。ところが、第二次世界大戦の末期には、長距離を飛行できる大型爆撃機や弾道ミサイルが実用化される。これらの兵器が進化すれば、いずれアメリカ本土が脅かされる可能性も否定できない。
こうした懸念から、アメリカの国防が強化されるなか、政府機関や軍と軍需産業に従事する民間企業が強く結び付いた「軍産複合体」が形成されていく。1950年代には、アメリカの国家予算のうち、軍事費が50%以上を占めるようになった。
国防重視と反共主義の思想は、アメリカ国内でもとくに南部から中部で強く支持された。この地域は、第二次世界大戦中から国防関係の公共事業で多大な利益を得ていた。たとえば、テキサス州のダラスは戦時下に軍用車や戦闘機の工場を誘致して発展した。ニューメキシコ州のロスアラモスには、マンハッタン計画に際して原爆開発の施設が築かれ、大量の科学者や軍人とその家族が移住したことで発展した。加えて、南部から中部では聖書の価値観を重視するキリスト教福音派の信仰が非常に根強かった。
■人種差別を改善させていった「本当の意図」
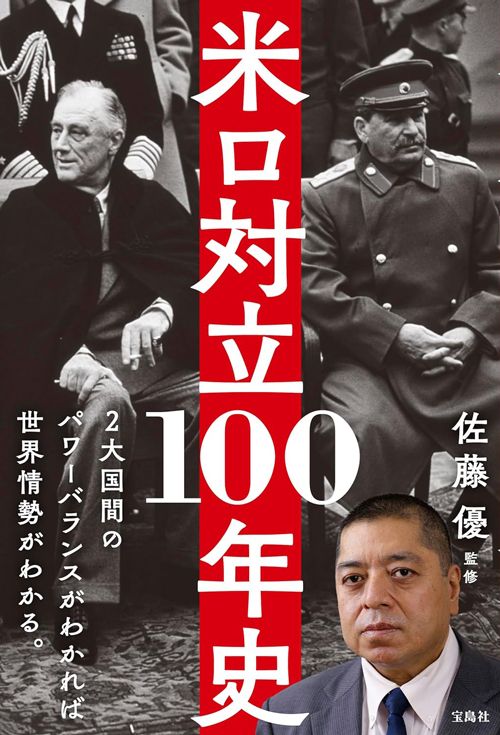
アメリカ南部は保守的な気質から黒人差別の根強い地域でもあるが、意外にもトルーマン大統領は、1948年の選挙で軍内の人種差別を改善するなど、黒人の市民権向上を唱えている。じつは、これも反共主義への支持を得るためだった。
当時、1946年7月にフィリピンがアメリカから独立し、翌年8月にはインドがイギリスから独立するなど、アジアやアフリカでは民族自決権に基づく独立運動が進みつつあった。そのなかには、欧米大国による植民地帝国主義への反発から共産主義が台頭した地域もあり、ベトナムでは1945年9月にインドシナ共産党を率いるホー・チ・ミンがベトナム民主共和国の独立を宣言し、これを認めないフランスと敵対した。アメリカ国内での人種差別の改善には、有色人種の国家を味方に引き込む意図があった。
----------
作家・元外務省主任分析官
1960年、東京都生まれ。85年同志社大学大学院神学研究科修了。2005年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『獄中記』(岩波書店)、『交渉術』(文藝春秋)など著書多数。
----------
(作家・元外務省主任分析官 佐藤 優)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
平和主義者、同性愛者まで弾圧の対象に…大酒飲みマッカーシーの"赤狩りリスト"の驚くべき適当さ
プレジデントオンライン / 2024年6月27日 9時15分
-
「侵攻の引き金」を引いたウクライナの"失策" 対立の根底には2つの「ロシア人像」がある
東洋経済オンライン / 2024年6月25日 20時0分
-
プーチンはスターリンの「21世紀の生まれ変わり」だ 「スターリン秘録」著者 斎藤勉
産経ニュース / 2024年6月23日 10時0分
-
農産物も家畜も奪われ、人肉食に手を染めた者も…ウクライナ人が今も忘れない「ソ連の大飢饉」への怒り
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 9時15分
-
なぜ広島・長崎に「人類史上最悪の兵器」が落とされたのか…「降伏しない日本が悪い」というアメリカの詭弁
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 9時15分
ランキング
-
1朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分
-
2「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分
-
3約300万円の「エヴァ」巨大フィギュア、発売中止 発送予定から“2年後に”告知と謝罪
ねとらぼ / 2024年6月28日 20時35分
-
4トヨタ「プリウスα」なぜ消滅? 「復活」の可能性はある? “ちょうどイイサイズ”に3列シート装備で「画期的」だったのに… 1世代限りで生産終了した理由は
くるまのニュース / 2024年6月28日 20時10分
-
5すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












