日本の医師は「利権」のために児童を虐待している…群馬の「陰毛視診」問題で若手医師が抱いた違和感
プレジデントオンライン / 2024年6月24日 9時15分
■男性医師が下着の中を覗いて「陰毛」を確認
群馬県みなかみ町の小学校で実施された健康診断において、複数の児童が男性医師に下着の中を覗かれたと訴え、問題になっています。
この学校医は児童に対して、保護者の同意なく「陰毛があるか」などの視診を行っていました。
批判を受け、地域の教育委員会は保護者説明会で謝罪、学校医は交代するとしています。
報道によると、医師はあくまで善意で、医学的な必要があると考え視診を行ったようではあります。ただ、少なくとも事前の説明と同意が不十分だったように思われます。
プライバシーが重視されるいまの時代、医師の側には診察を受ける人の羞恥心への一層の配慮が求められています。
■文部科学省は「原則着衣」と指示している
今年1月、文部科学省から出た通知では、「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮」という言葉が繰り返され、「検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆」うことと指示されています。
ただ筆者はこの通知に強い違和感を持っています。着衣を指示したからではなく、「正確な検査・診察に支障のない範囲で」という条件が当たり前のように入っているからです。
そもそも、「正確な診察」とは何を指すのかが明確にされていません。
どんな診察方法でも、どんな検査を使っても、病気ではないのに病気があると判定してしまう(偽陽性)とか、病気があるのに見逃してしまう(偽陰性)といった「誤り」はゼロにはなりません。
■「検査結果が間違っている」ことはよくある
ゼロではないどころか、「よくあること」です。
比較的優秀とされる検査でも、偽陽性や偽陰性が数割程度も発生することは珍しくありません。
有名な例では、新型コロナウイルスのPCR検査は感度が70%程度。つまり感染している人の30%は検査を受けても見逃されるのです。
まして医師の肉眼による視診は個人的技能に大きく依存します。もちろん熟練した医師が条件を整えて行う診察のほうが、そうでない場合より「正確」かもしれませんが、イメージで言えば「30%の見逃しを27%に減らす」といった程度がいいところでしょう。その程度の小さい違いのためにどんな代償を求めるかは合理的に考えるべきです。「正確」という言葉は「完璧」「絶対」を連想させますが、現実はほど遠いのです。
こんな言葉が使われること自体、文部科学省や医師の側が、診断について誤ったイメージに基づいていることを示しているように思います。

■「早期発見」に効果があるかわからない
そもそも健康診断の目的は「正確な診断」ではありません。
よく小説やマンガで予知能力を持つ人物が登場して、悪い予言を聞いた人が予防策を打ってもけっきょく予言のとおりになってしまう、という展開がありますが、診断にも似たところがあります。
診断して「病気」を発見したものの、それがいい結果につながらず、むしろ悪い結果をもたらすこともあるのです。
「病気」の中には強いて治療しなくても困らないもの、発見したところで治療法がなかったり、治療してもあまり効果がないものもあります。
診断によってそういう「病気」を見つけたところで、あまり意味がないのです。目的は早期発見・早期治療によって悪い結果を減らすこと、特に死亡を減らすことです。
冒頭の例ではSNSで「思春期早発症を見つけようとしているのではないか」という憶測が出回りましたが、調査によれば小学生の年齢で診断される思春期早発症は全国で1000人程度と、比較的まれな病気です。その中でも「その方法でしか診断できず(年齢不相応な身長の伸びなどがはっきりせず、かつ、年齢不相応な陰毛があり、かつ、本人が気付いていないか質問しても答えてくれない、かつ、視診には同意する)」かつ「その時点での介入により悪い結果を防げる」例となるとさらに少なくなります。
そもそも思春期早発症による悪い結果というのはたとえば成人したときの低身長ですが、低身長でも不自由なく生活している人は大勢いますし、ホルモンの異常による低身長に対して薬物治療がどんな利益になりえるかは議論があるところです。
■「健康診断のおかげで助かった」かはわからない
私がこう説明すると、反論されることもあります。
「健康診断で重い病気が見つかり、助かった人を知っている」、さらには「私自身がそうだ」と言われることもあります。
でもそうした例が本当に「健康診断のおかげで助かった」のかどうか、科学的に判定するのは困難というか、不可能です。
健康診断をしなくても、そのうち自覚症状が出て、自分で診察を受けていたかもしれません。あるいは発見が早かろうが遅かろうが、治療の結果にはあまり関係がなかったかもしれません。
また、積極的に治療しなくても、特段困ったことにならないような病気だったのかもしれないのです。
もし健康診断がなければどうなったか、過去に戻って試すことはできませんから、個別の例についてはなんとも判断できないのです。
■アメリカの基準なら「日本の学校健診は過剰」
健康診断に意味があったかどうか、健康診断をするグループとしないグループを追跡した試験がたくさん行われています。
そうした試験結果をまとめる専門家団体の米国予防医学作業部会(USPSTF)が、どんな診察なら適切かをまとめています。
結論から言いますと、USPSTFを基準にすると、日本で行われている学校健診は大幅に過剰です。

■検査が推奨されているのは「HIV・梅毒の検査」など
例えば、前述の文部科学省通知では「特に留意が必要」なものとして「脊柱の疾病」「胸郭の疾病」「皮膚疾患」「心臓の疾病」をあげています。
ただ、USPSTFはこれらの検査を支持していません。
USPSTFが「小児(Pediatric)」または「思春期(Adolescent)」に対して検討している検査は55件。
そのうち一斉検査に対して最高ランクの「A」がついているもの(つまり、検査するよう推奨しているもの)は、HIV・梅毒の検査と、対象者が妊娠している場合に限って血液型不適合とB型肝炎ウイルスの検査だけです。
次の「B」ランクも検査推奨ですが、これにあたるのは「不安」、「うつ病」、「クラミジア」、「淋菌」、「B型肝炎ウイルス」、「親密なパートナーによる暴力」、「弱視(3歳から5歳のうちに1回以上)」、「肥満」です(妊娠している対象者についての推奨、18歳以上についての推奨を省きます)。
■「5歳未満の虫歯検査」はすべきでない
その他の検査は、「C」(個人ごとのリスクを判断して検査の有無を考える)、「D」(検査をしないよう推奨する)、「I」(エビデンス不十分で分類できない)のいずれかです。
たとえば5歳未満に対する「虫歯の検査」は「I」ランク。エビデンスがないため検査すべきでないということです(こう言うと「データがなくても明らかに必要」と言う人が出てくるのですが、どうせすぐ抜ける乳歯の検査の目的はなんなのでしょう。歯磨きで虫歯を減らせるというエビデンスはありません)。

もちろんアメリカの状況と日本の状況は異なるため、アメリカの基準が日本でそのまま当てはまるわけではありません。
HIVの広がりに対する危機感は日本とアメリカでかなり差があります。肥満についても同様です。
■日本の学校健診にはエビデンスがない
日本では、「学校保健安全法施行規則」において学校健診の内容が決められています。
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 その他の疾病及び異常の有無
一見して、USPSTFの推奨とほとんど一致していないことがわかると思います。
「脊柱及び胸郭の疾病」に含まれる側弯症はUSPSTFでは「I」ランク、つまり検査が有効であるというエビデンスがないと判定されています。
もちろんなんでもアメリカに合わせるのがいいわけではありません。
ただ、USPSTFは詳細なデータを公表していますが、日本の学校保健安全法施行規則にはなんのエビデンスも添えられていません。
■古い時代の健診がズルズル続いているだけ
ちなみに、前述の文科省通知で参照している「児童生徒等の健康診断マニュアル」には引用文献がひとつも挙げられていません。
なぜ日本の学校健診はこんな残念なことになっているのでしょう。
その理由は、リストに「結核」があることから察せられます。
このリストの原型ができたのは1958年。
要するに、データに基づいて健診の「利益」と「害」をちゃんと評価するという思想がまだなかったころに学校健診のやりかたを細かく決めたまま、検証されることもなくズルズル続いているのです。
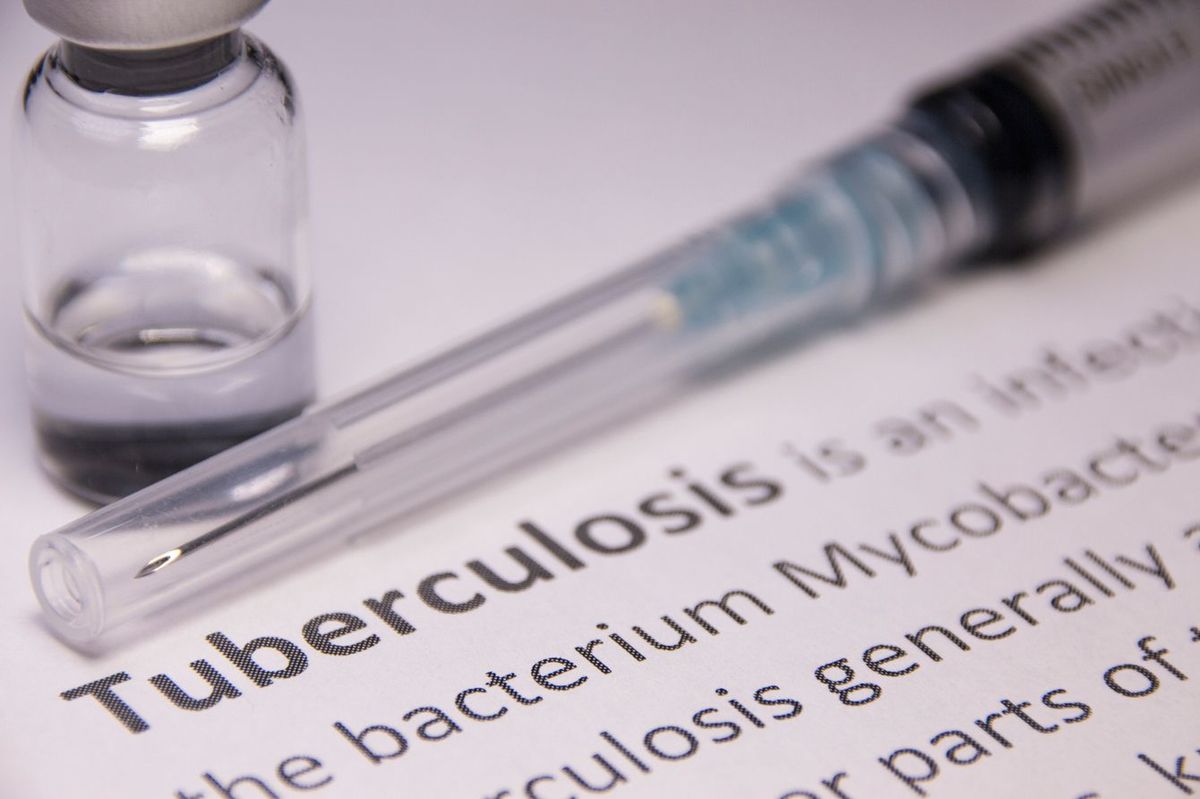
■世界では健診の見直しが進んでいる
一方、世界的には健診のあり方を見直す動きが進んでいます。1960年代以降、世界保健機関(WHO)やアメリカ、カナダの団体が健診の検証を呼びかけたことが、USPSTFなどの事業につながりました。その運動の中にいたデイヴィッド・サケットという人がのちに「エビデンスに基づく医学の父」と呼ばれるようになります。
一方、日本の学校健診はエビデンスに基づいていません。「診察はやればやるほどよい」という安直な考えがまかり通り、冒頭に紹介したようなトラブルを引き起こしています。
■医師の利権のために子供を虐待している
「過剰な検査」は「過剰な治療」に結びつきます。
本当は要らないはずの無駄な薬、無駄な手術を行うことは、健康のためどころか有害です。子供に副作用のリスク、手術合併症のリスク、重い病気ではないかという不安を与えるだけでなく、重い病気を診断されたという事実が将来の結婚・就職・保険加入に不利に働くことも考えられます。
また、無駄な診察のために大量の公的資金と貴重な医療従事者の労働力が費やされていることも問題です。
私はまず学校健診を完全に廃止すべきだと思います。効果不明で逆効果の疑いさえある健診によって、リソースが無駄遣いされるだけでなく、子供の心身を危険にさらしているからです。
そのうえで、健診の効果を検証するために、それぞれの検査項目が本当に必要なのかどうか、検査するグループとしないグループを作って比較する必要があります。この試験を実行するためには、前提として一斉健診が廃止されていなければなりません。
合理的な検証ができなければ、日本の医療体制は医師の利権のために子供を虐待しているのだと批判されても、言い返すことはできないでしょう。

----------
医師
1983年、大阪府に生まれる。東京大学医学部卒業。出版社勤務、医療情報サイトのニュース編集長を経て医師となる。首都圏のクリニックで高齢者の訪問診療業務に携わっている。著書には『「健康」から生活をまもる 最新医学と12の迷信』、訳書にはペトルシュクラバーネク著『健康禍 人間的医学の終焉と強制的健康主義の台頭』(以上、生活の医療社)、ヴィナイヤク・プラサード著『悪いがん治療 誤った政策とエビデンスがどのようにがん患者を痛めつけるか』(晶文社)がある。
----------
(医師 大脇 幸志郎)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
群馬の学校健診問題で注目 見落としがちな「思春期早発症」の怖さ
毎日新聞 / 2024年6月30日 9時1分
-
小児科医が伝える「学校健診」の現状 小学校との打ち合わせの機会「ないことが多い」【学校健診問題を考える(下)医師の見方】
J-CASTニュース / 2024年6月26日 10時0分
-
問題相次ぐ「学校健診」 校医に求めるのは「いやな検査があったら『やめてほしい』と言っていい」許可【学校健診問題を考える(上)教師の見方】
J-CASTニュース / 2024年6月25日 10時0分
-
「なぜ学校健診で脱衣が必要なのか」と問う保護者に知ってほしい学校健診の役割と「脱衣」の解釈
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 8時15分
-
下半身診察「想定せず」 学校健診で日医見解
共同通信 / 2024年6月19日 19時41分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
-
5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由
NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












