なぜ渋沢栄一は子供たちに財産を残さなかったのか…日本資本主義の父が理想とした「合本主義」とはなにか
プレジデントオンライン / 2024年6月21日 8時15分
※本稿は、渋沢寿一『森と算盤 地球と資本主義の未来地図』(大和書房)の一部を再編集したものです。
■渋沢栄一の理想は「資本主義」ではなく「合本主義」
渋沢栄一は3年という短くも濃い官僚生活を経て、1873(明治6)年に下野します。33歳のときでした。その後、古希を目前に69歳で多くの企業の役員を辞するまで実業家として活動し、平和な世を目指して民間外交にも精を出すようになります。
栄一が実業家として活動していく際、精神的支柱としたのが、幼い頃から慣れ親しんだ『論語』でした。論語で説かれていた考え方や倫理観は、自分の理想とする「合本(がっぽん)主義」を実現するためにも必要だと考えていたようです。
栄一は「資本主義」ではなく、より公益を求める意味で「合本主義」という言葉を用いていました。
資本主義とは、資本がサービスの生産・流通の主体となる経済体制のことですが、合本主義とは「公益を追求する使命に最も適した人材と資本を集め、事業を推進させる」という考え方です。
栄一が唱える合本主義は、資本主義よりも強い規範を伴い、公益の追求、つまり人と人がつくり出す豊かな社会の形成が主軸に置かれていました。
■集大成『論語と算盤』に書かれていること
栄一の思考の集大成として出版されたのが『論語と算盤』です。1916(大正5)年、76歳のときでした。栄一は、当時高まっていた経済偏重と個人の利益重視の風潮を敏感に感じとり、この本の中で、利潤を追求するだけではない「道理正しい経済」を説きました。
人々が利益追求へと暴走しそうになったときに『論語』がそのストッパーの役割を果たしてくれると考えたのです。
『論語と算盤』の冒頭には、「論語と算盤は、甚だ遠くして甚だ近いものである」とあります。これは栄一の「経済道徳合一」、つまり、経済と道徳のバランスについて端的に述べた表現だと思います。
■商売をするうえで最も重要なこと
孔子は、『論語』の中でこう述べています。
富貴とは、これ人の欲する所なり。その道をもってせずしてこれを得れば処(お)らざるなり。貧と賤しいとはこれ人の悪む所なり。その道をもってせずしてこれを得ざれば去らざるなり。
訳「人間であるからには、だれでも富や地位のある生活を手に入れたいと思う。だが、まっとうな生き方をして手に入れたものでないなら、しがみつくべきではない。逆に貧賤な生活は、誰しも嫌うところだ。だが、まっとうな生き方をして落ち込んだものでないなら、無理に這い上がろうとしてはならない」
(『現代語訳 論語と算盤』守屋淳訳、ちくま新書)
ここでは富貴を言下に否定するようには書かれていません。
「その道をもってせずしてこれを得れば処らざるなり」(まっとうな生き方をして手に入れたものでないなら、しがみつくべきではない)とあるように、道徳のないやり方で得た富を戒めていたのです。
栄一自身も「真正の利殖は仁義道徳に基づかなければ、決して永続するものではないと私は考える」と述べています。商売で重要なのは道徳であり、個人の利益のみを重視しては長く続けていくことはできないことを、栄一は見抜いていたのでしょう。

■子孫や後継者に資産を残さなかったワケ
渋沢栄一にとって経済とは、平等な社会を実現させ、公益を最大化させるためのツールに過ぎなかったことがわかります。
生涯をかけて、自身の蓄えや利権を大きくするためではなく、よりよい社会をつくるための経済活動を実践しようとしました。
栄一は生涯で約500の企業の設立に関わりましたが、そうした自分の関わった会社や膨大な不動産などの資産を、子孫や後継者たちに残すことには関心がありませんでした。
しかし、人間はどうしても「もっともっと」と自分の富を求める方向に進んでしまいます。そこで栄一は『論語と算盤』で、そうならないためのストッパーとして道徳観、倫理観をベースとした経済活動を行うことの重要性を説きましたが、「論語と算盤」的経済活動が社会に定着することは叶いませんでした。
晩年に記した「米寿を迎えた喜び」という文章からは、経済発展に伴って人々の精神が向上していかないことへの苛立ちが感じ取れます。
■渋沢栄一の苛立ちの対象
遺憾なのは、精神方面の改善進歩の見るべきものがないことである。(略)これは日本のみでなく世界的に面白からぬ状態にあると言えよう。これがため私の常に力説している経済道徳合一の必要があるのである。物質の進歩に精神が伴うて初めて完全なる文明が生まれるのである。(中略)
ただ今日のごとく自分さえよければ他人はどうでもよいというふうで、物質のみを主とすることのないようにありたい、さりとて唯心的になり経済観念を忘れるようでは困る。どうしても両々相俟って進むことが必要である。一言に尽くせば、道理正しい経済を進めることが必要である。
(「米寿を迎えた喜び」『渋沢栄一自伝』角川ソフィア文庫所収)
栄一の願いも虚しく社会の経済偏重は進み、現在は完全にお金で物事の価値が計られるようになりました。
しかし、彼の価値観は栄一の薫陶を受けた経営者たちには引き継がれました。私は、その最後の世代の経営者たちに実際にお会いしてお話しする機会を得ました。彼らは戦争を体験した世代でした。
1970年代の経済界の重鎮たちの中には、自分の会社の利益について語る人はいませんでした。どういう社会、どういう日本をつくるかということを語っていたのです。
■この40年間で消えてしまった「公益」
みなさん口を揃えて仰っていたのは、会社を経営することは「戦争で死んだ友人のためでもある」ということでした。戦時下では、優秀な者が次々と戦地で亡くなっていきました。それを目の当たりにした人たちには、自分たちが生き残ったのは亡くなった優秀な友人たちの夢を実現させるためだ、という考えが根底にあったのです。
だからこそ、未来につながっていく社会をどうつくっていくべきか、という理念を体温のある言葉で語ることができたのだと思います。
しかしバブル崩壊後、日本経済が低迷期に入り、さらにリーマンショックが追い打ちをかけ、経営者も理念どころではなくなります。自分たちが生き残ることに必死になり、世の中のことや公益について考えたり、投資したりする場合ではなくなってしまいました。
1970年からわずか40年で、栄一が重視していた公益という概念は日本からほとんど消えてしまいました。

■環境と経済の共存は可能なのか
そして今、渋沢栄一も予期していなかった新たな課題が現れました。
環境問題です。
栄一は、社会の平等を実現させ、持続させていくために、経済に道徳というアナログなものを取り入れようとしました。ただ、彼の時代にはまだ環境問題は表面化しておらず、無尽蔵な地球環境の中で、暮らしと経済活動のバランスを取ることさえできれば、より良い社会が実現すると考えていました。
しかし、現在、自然が有限であることに気づいた私たちは、日々の暮らしと経済活動に加えて、地球環境も加えた三者のバランスを見出すことが必要なフェーズに入ったと言えるでしょう。
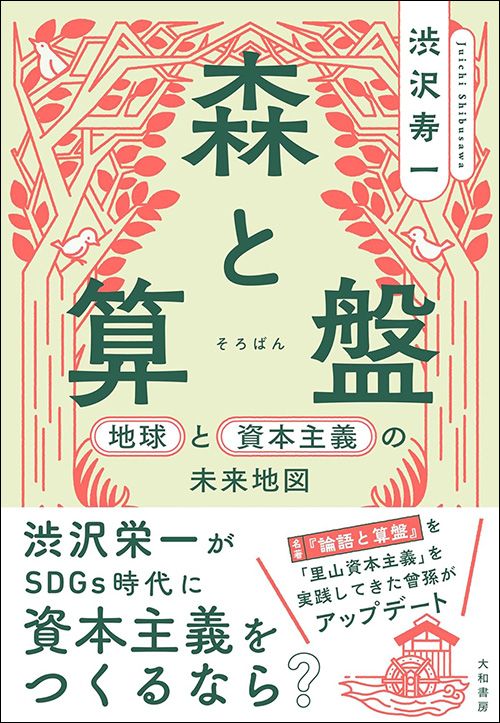
これまでの経済活動も続けながら、自然と共生することは可能なのでしょうか。
渋沢栄一が論語(=道徳)と算盤(=経済)の両立を唱えたように、「森」=有限な地球と、「算盤」=経済を共存させることは可能なのでしょうか。
環境問題と渋沢栄一は、一見結びつかないように思えるかもしれません。しかし、自然を守り、次世代につなげていくことは、栄一が生涯を通して成し遂げようとした「公益の追求」につながるものだと考えています。
これは、資本主義やお金を否定する、ということではありません。
■いまこそ渋沢栄一の合本主義を
資本主義を完全に否定するのではなく、資本主義の中で生活しながらも、それだけではない価値観を、この有限な地球の中で、自分たちでつくり上げていくということです。
自分たちの足元にある地域の価値を創造し、確認し合う。目の見える範囲の人と「心ののりしろ」を重ねていき、文化を積み上げていく。地域間を肉体的に横断していき、ときにはSNSも使いながら結びついていく。
このように、限界を迎えた地球環境の中では、経済ではなく「想い」をグローバル化することこそが、渋沢栄一が唱えた「合本主義」を実現することではないかと私は考えています。
----------
NPO法人共存の森ネットワーク理事長
1952年生まれ。1980年、東京農業大学大学院博士課程修了。農学博士。国際協力機構専門家としてパラグアイに赴任後、循環型都市「ハウステンボス」の企画、経営に携わる。全国の高校生100人が「森や海・川の名人」をたずねる「聞き書き甲子園」の事業や、各地で開催する「なりわい塾」など、森林文化の教育・啓発を通して、人材の育成や地域づくりを手がける。岡山県真庭市では木質バイオマスを利用した地域づくり「里山資本主義」の推進に努める。
----------
(NPO法人共存の森ネットワーク理事長 渋沢 寿一)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【7月3日から新紙幣発行へ】肖像3人、渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎を知る3冊を紹介
マイナビニュース / 2024年7月3日 7時0分
-
正しさを忘れた渋沢栄一etc.「新紙幣の偉人たち」知られざる“やばい”一面とは
日刊SPA! / 2024年7月1日 8時51分
-
商売は人間のクズがやることだった…武士の国に資本主義を根付かせた新札の顔「渋沢栄一」の天才的発想
プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分
-
新1万円札の顔となる、渋沢栄一の経営哲学がわかる!『決定版 論語と算盤がマンガで3時間でマスターできる本』6月12日発売
PR TIMES / 2024年6月12日 10時45分
-
【1873(明治6年)年6月11日】第一国立銀行設立
トウシル / 2024年6月11日 7時30分
ランキング
-
1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」
読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分
-
2マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌
毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分
-
3かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」
カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分
-
4殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう拘留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人
STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分
-
5能登半島地震 災害関連死 氏名初公表
テレ金NEWS NNN / 2024年7月2日 19時28分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












