道長の嫌な性格がよくわかる…東宮の「添い寝」に選ばれた妹の不倫疑惑を確かめるためにとったまさかの行動
プレジデントオンライン / 2024年6月23日 17時15分
※本稿は、山口仲美『千年たっても変わらない人間の本質 日本古典に学ぶ知恵と勇気』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。
■藤原道長の「強気な性格」が良くわかるエピソード
どんな人にも、不遇な時代があります。道長も、権力を掌握するまでには、不遇な時代がありました。でも、道長の逞しいところは、そんな時でも、「今に見ていろ」精神を持っていることです。
こんなエピソードが語られています。兄の道隆が関白になり、その息子の伊周は21歳で内大臣に任命されました。それに対し、道長は左京大夫でしかない。
そんな時、道隆邸で弓の競射をしていた。そこに道長がやって来て、伊周との一騎打ちになった。普通は、位の高い人に勝ちを譲るのが礼儀ですが、道長は遠慮などしない。
二番延長された競射で、まずは一矢目を放つ時に道長は唱える、「道長が家より帝(みかど)・后(きさき)立ちたまふべきものならば、この矢あたれ(=この道長の家から、天皇・后がお立ちになるはずならば、この矢当たれ)」と。
矢は、なんと的のど真ん中に当たった。伊周は、気後れして、矢を放ったが、的の近くにさえ行かなかった。
続く二矢目。道長は、「摂政・関白すべきものならば、この矢あたれ(=この私が、将来、摂政・関白になるのが当然ならば、この矢当たれ)」と唱えて、矢を放つ。
矢は、的が割れるほどに、同じ真ん中を射とおした。道隆は、顔面蒼白。その場は、白けに白けた。
不遇にあえいでいるのに、それをものともせず、兄一族に立ち向かっていく道長の覇気は、並外れています。道長の、こうした自負心は、若い時から見られます。
■どんな相手でも負けるつもりはない
道長の父・兼家が存命であった時のこと。兼家といえば、この本でも取り上げた『蜻蛉日記』の作者の夫です。兼家自身も、灰汁の強い人物ですが、道長も、父に負けず劣らず。
父が、当代きっての才人・藤原公任をほめたたえ、「わが子どもの、影だに踏むべくもあらぬこそ口惜(くちを)しけれ(=我が子たちが、彼に追随することさえできないのは残念なことだ)」と言うと、道長の兄たちの道隆・道兼はもっともなことだと受け入れ、わが身を恥じている。
それに対して、道長は言ってのける、「影をば踏まで、面をや踏まぬ。(=追随などしないが、あの面をば踏まずにおくものか。)」
その頃、諸芸に秀で、順調に昇進している公任は、貴族たちの羨望の的だったのです。道長は、公任と同い年だったので、余計に競争意識があります。強気で、今に見返してやるという覇気丸出しです。
■妹にした「まさかの行動」
三条院がまだ東宮であった時のこと。道長の腹違いの妹・綏子が東宮の夜の副臥(東宮に添い寝する少女)に上がられた。ところが、綏子のところに、源頼定が通っており、妊娠したという噂が立った。東宮は、道長に事の真偽を確かめるように、依頼なさった。
道長は、直ちに、綏子の部屋に行き、「世間の噂が事実無根でおありかもしれないのに、噂が事実だとお信じになるようなことがあっては、お気の毒ですから」とおっしゃって、綏子に胸を出させる。

原文を示しておきましょう。
御胸をひきあけさせたまひて、乳(ち)をひねりたまへりければ、御顔にさとはしりかかるものか。
(=綏子さまのお胸をひき開けられ、乳房をおひねりになられたところ、なんとまあ、道長さまのお顔に乳がさっとほとばしりかかったではありませんか。)
妊娠しているのは事実だったのです。道長は、東宮に事実を報告し、ご自分のなさったことを申し上げる。東宮は、道長の余りにも乱暴なやり方に、可哀そうなことをしたとお思いであった。
綏子も、道長が帰った後、「自分からしたこととはいえ、ひどくお泣きになった」と傍で見ていた女房が語ったと言う。道長は、人に対する情愛が薄いことが分かるエピソードです。
■子どもは権力を握るためのコマ
また、こんなこともあります。彰子に皇子がなかなかできなかった時、亡くなってしまった中宮定子の息子である敦康親王を彰子にかわいがらせて、彼を手なずけておきました。政権を握るためには、敦康親王を味方につけておく必要があったからです。
ところが、彰子に敦成親王が誕生すると、道長は、敦康親王を放り出しています。道長にとっては、敦康親王は、権力を握るためのコマにすぎなかったことがよく分かります。
大勢いる子供たちに対しても、道長は権力を握るためのコマに見ている節があります。道長は、まだ12歳にしかなっていない長女の彰子を一条天皇に入内させているのも、その例に該当しそうです。
一刻でも早く彰子に皇子を生んでもらい、外戚になって権力をふるいたいのです。
でも、彰子は、まだ、幼くて、天皇と男女関係はなかなか持てなかったと言われています。そのせいか、子供も9年間もできません。9年目に、ようやく皇子を授かりました。その時の道長の喜びようは、並一通りではありません。皇子におしっこをかけられても喜ぶ姿が、『紫式部日記』に記されています。
誕生した皇子がかわいいのはもちろんですが、その嬉しさは、外戚になって権力をふるう道が確保できた喜びに裏打ちされています。道長は、一人一人の人間に対する情愛は、極めて薄いと言えます。個々人の気持ちまで考えていたら、権力者にはなれないという面がありますからね。
■藤原家の健康状態
権力者としての最も大事な資質の一つに、健康が挙げられます。というのは、道長の兄2人が、病気で若くして亡くなってくれたからこそ、道長に権力が転がり込んできたのですから。
正暦5年(994年)、疫病が大流行しました。大臣・公卿が大勢亡くなりました。その下の身分の貴族たちで亡くなった人の数は数え切れません。長兄・道隆は4月10日に亡くなりました。
ただし、「これは、その時の流行の疫病でお亡くなりになったのではなく、偶然、時が同じだっただけのことです」と『大鏡』は語っています。
道隆の酒豪は有名でした。平素の大酒飲みがたたって体が弱っていたところに、疫病にかかってしまってあっけなくこの世を去ったという可能性もあります。そのあと、次の兄の道兼が関白になりましたが、宣旨を受けて7日目に疫病で亡くなったので、七日関白などと呼ばれています。
それに対して、道長はいたって健康です。権力者になるためには、健康であることが必須です。
■道長の運を開いた女性とは
兄たち2人が亡くなり、さあ、道長の出番と思いきや、一条天皇が立ちはだかります。一条天皇は、道隆一家と仲が良かった。道隆の娘・定子は、天皇の寵愛を受けていたし、道隆の息子・伊周とは馬が合う。
それに対して、一条天皇は、道長が好きでない。だから、道長以外の候補者から後釡を選ぼうとしていらっしゃる。
それを知ったのは、道長を可愛がっている姉の詮子。彼女は、一条天皇の母でもあります。母であっても、天皇の前では、下位です。天皇の気持ちを覆すことは、容易ではありません。
詮子は、道長に宣旨を下ろそうとなさらない天皇の寝所に自ら出向き、直談判をしました。長い時間がたつ。外では、道長が固唾をのんで待っている。詮子がついに天皇の部屋からお出ましになった。その時の詮子の様子を原文で示しましょう。
御顔は赤み濡(ぬ)れつやめかせたまひながら、御口はこころよく笑(ゑ)ませたまひて、「あはや、宣旨下(くだ)りぬ」とこそ申させたまひけれ。
(=詮子さまのお顔は赤らみ、涙に濡れて光っていらっしゃりながら、お口の辺りは喜ばし気にほほえまれて「ああ、やっと宣旨がおりましたよ」と仰せられたことでした。)
■誰にも相談せずに出家
詮子が、一条天皇を泣き脅ししたことが分かる表情ですね。天皇の前で、母は泣き、道長を権力者にする宣旨を出すように取り付けたのです。
道長の運は、詮子によって、切り開かれたと言っても過言ではありません。運を開いてくれる人を持つことは、重要です。道長は、詮子に恩義を感じ、詮子が亡くなった時は、ご葬儀を誠心誠意を込めて執り行なっています。
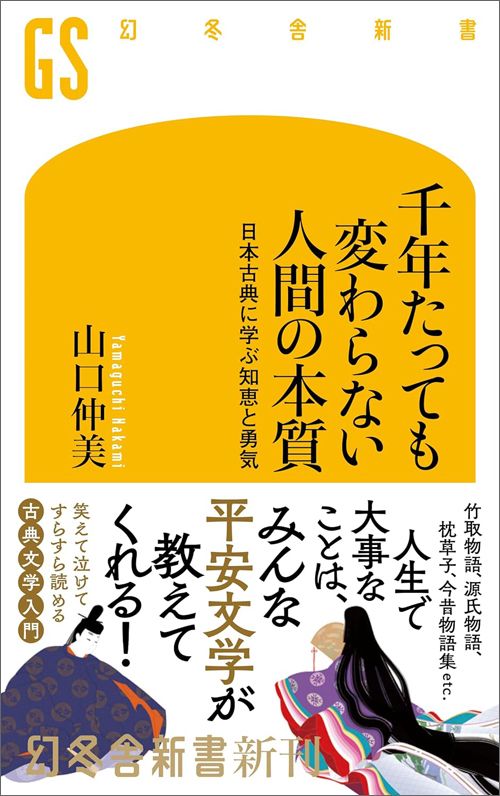
道長は、54歳になり、3月21日夜半、少し胸が痛みました。すると、翌日の午後に、突然起き出して、氏神である春日明神に向かってお暇乞いをし、誰にも相談せずに、いきなり出家してしまいました。道長らしいですね。決断したら、直ちに実行です。
周りの人たちは、一様に茫然。その後、天皇・東宮・后の宮に知らせました。道長は、一人で沈思黙考し、決断し、実行に移すという性格であることが分かります。
ですから、子供たちの将来も、道長によってほとんど決められてしまったわけです。まあ、権力者にとって「決断力」は、最も大事な資質ですから、それを持っていたことは、当然ですね。
----------
埼玉大学名誉教授
1943年生まれ。日本語学者。お茶の水女子大学卒業。東京大学大学院修士課程修了。文学博士。日本語検定委員会理事。2021年文化功労者。古典語から現代語までの日本語の歴史を研究。とくに擬音語・擬態語の歴史的研究は、高く評価されている。論文「源氏物語の比喩表現と作者(上)(下)」で日本古典文学会賞、『平安文学の文体の研究』(明治書院)で金田一京助博士記念賞、『日本語の歴史』(岩波書店)で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。また、「日本語に関する独創的な研究」が評価され、2022年に日本学賞を受賞。2008年紫綬褒章、2016年瑞宝中綬章を受章。
----------
(埼玉大学名誉教授 山口 仲美)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
NHK大河の道長像はリアルとはいえない…道長がまだ幼い長女を一条天皇に入内させた本当の理由
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 18時15分
-
天皇になれる血筋だったのに、20歳で夭逝…「藤原道長の壁」を超えられなかった「定子の息子」の悲劇
プレジデントオンライン / 2024年6月23日 18時15分
-
定子が皇子を産んだと聞いて急性胃腸炎で倒れる…困難な状況を迎えるたびに体調を崩した藤原道長の病弱体質
プレジデントオンライン / 2024年6月23日 16時15分
-
孫を皇太子にした道長を恨む"意外すぎる人物" 一条天皇は定子の子供も、後継者で揺れる宮中
東洋経済オンライン / 2024年6月23日 8時40分
-
道長も困惑した「一条天皇」暴走する"皇后への愛" 花山院の藤原忯子への寵愛も格別なものだった
東洋経済オンライン / 2024年6月9日 10時30分
ランキング
-
1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】
オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分
-
2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須
NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分
-
3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴
プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分
-
418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分
-
5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」
まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












