なぜ「早稲田=マスコミ」のイメージができたのか…給与が東大生の3分の1だった明治時代の早大生の進路
プレジデントオンライン / 2024年6月22日 9時15分
※本稿は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
■東京大学と早稲田大学にあった大きな格差
東京専門学校の法律科も、1888年に文部大臣の認可を受けた。卒業生の進路を拡充させるためにはやむを得ない措置である。しかし帝国大学は、私立法律学校よりもはるかに大きな「特権」を享受していた。
この時点では行政官、司法官とも無試験任用である。私学の主戦場ともいえる代言人のち弁護士の試験は普通に受験すれば合格率数パーセントの超難関だが、帝国大学法科大学とその前身校の出身者は無試験で資格が得られた。
帝大法科の卒業生には高級行政官僚または判事・検事の道が開けているのに対し、早稲田は中級・下級官僚の座か、受験資格しかもらえない。文部大臣の認可を受けることは、セカンドクラスとしての扱いを受け入れることを意味する。実は、東京専門学校内部では政治科の学生が特別認可に猛反発していた。セカンドクラス扱いを拒絶したのである。
法律科と同様に政治科でも認可を得ようとする学校側の動きを察知した政治科の学生たちは、演説会を開き、評議員を訪問して反対運動に決起する。
結局、高田早苗をはじめとする学校当局は、妥協策として政治科では認可を願い出ず、法律科と新たに創設する行政科(第二法律科)の二科で認可を求めることとなった。したがって政治科の学生には国家試験や兵役上の特典はない(真辺前掲書)。
■初任給は東大の3分の1が相場
1899年刊行の村松忠雄『早稲田学風』には、「嘗て文部省指定学校の制を設け、専門学校の政治科亦指定の二字を冠らせられんとせしや、彼学生等は憤然として曰く、我輩は独立の学生なり我校の主義は学問の独立に在り、我輩は国家の人材を以て任ず、豈に指定を受けて俗吏の群に入り、腰を五斗米に屈せんやと」とあるのはその経緯を記したものであろう。
文中にある「五斗米」とは少しの俸禄、という意味である。認可によって得られる特典が判任官見習への無試験任用ではなく、帝国大学と同じ高等官の試補への無試験任用だとしても同じように決起したかどうかはわからない。
しかし「国家の人材」を自負する政治科の学生たちが、帝大を頂点とする秩序に組み込まれてセカンドクラス扱いされることを拒絶したのはたしかである。
早稲田の出身者に対するセカンドクラス扱いは官吏登用にとどまらない。資本主義が発達するにつれ企業が就職先の主流を占めるようになるが、民間の世界でも出身学校による差別は常態化していた。
たとえば、初任給は卒業した学校によって違った。戦後に東大文学部事務長を務めた尾崎盛光の著書『日本就職史』は、明治末期の官立私立学校卒業生の初任給(文系)の格差を「帝大一〇〇に対して一橋六〇~七〇、慶應五〇~六〇、早稲田は三〇~四〇、といったところ」と見積もっている。
会社が採用活動を行う場合、出身学校によって初任給に差をつけるのはごく自然なことだった。
■東大→一橋→早慶という序列
『日本就職史』は、1905年に早稲田大学法学科を卒業し、ラサ工業の社長を務め、戦後には参議院議員となった小野義夫の談話を記録している。
「卒業生の月給相場は、東大(赤門と呼ぶ)医科は七〇円~八〇円で地方の病院長とか部長という地位に羽根が生えて飛ぶような状況であり、法科も四〇~五〇円、まず赤門には売れ残りはもちろんない。……つぎは一つ橋の三〇円内外が相場、慶応が二五円ぐらい。ところで早稲田の法科は大学第一回卒業生で相場がない、買い手まかせに月給などは何程でもよろしい、ただ御採用を……。奉職の口のあった連中は二割にも達しない。その相場は一七円ぐらいが普通」。
小野自身がその卒業生だから、信憑性のある証言ではある。
早稲田法科の卒業生は東大法科の3~4割程度の値段しかつかなかった。帝国大学を卒業するまでの年限は長くかかるので速成の専門学校より高くなるのは当然だが、それにしても差が大きすぎる。
大正期にも厳然とした給与格差があった。たとえば第一次大戦好景気時代の日本郵船では、帝国大学、商科大学(現・一橋大学)卒業生の初任給は80円、早慶と地方高等商業学校が60~65円、早慶を除く私立大学が50~55円である(寿木孝哉『就職戦術』)。
概して、帝大・商大・早慶・その他私大という具合に序列化され、新入社員は同じ企業に就職しながら差別待遇を甘受していた。
是正の動きが出るのは、1918(大正7)年公布の大学令によって単科大学や私立大学の設立が認められて以降である。
■依然として続く差別
1920年に慶應義塾大学と早稲田大学が正式に大学に昇格、続いて明治・法政・中央・日本・國學院・同志社も昇格した。それを受けてか、1923年には三菱が直系企業の待遇差別を改めたことが報じられた。
それまで帝大工学部が100円、その他の帝大が80円、高等商業・高等工業が70円、早慶が65円、明治・中央・同志社が55円であったところ、この年の4月から帝大・東京商大・神戸高商(現・神戸大学)・早慶を75円、その他の専門学校と私立大学を65円、私大専門部を55円、中学校・実業学校程度を35円に改めた。将来的にはその他の私大、専門学校も75円に引き上げるという。
この決断の背後にはケンブリッジ大学卒の三菱総帥・岩崎小彌太の決断があったようである。

岩崎は「学校の程度に依つて、その出身者に最初からハンデキヤプをつける事は間違つてゐる」「東京商大は東京商大、東京高工は東京高工、又早稲田大学は早稲田大学といつた風に、各学校の特色と歴史を、重んじて貰ひたいものだ」と語った(「実質的に愈々認められた私立大学出の学士」『受験と学生』一九二三年七月号)。
だがその3年後の同じ雑誌では、三菱系の日本郵船の顧問である寺島成信が「今日では余程差等がなくなつたと云ふけれども、未だゝである」と述べているように、全面的な差別撤廃を推し進めることは簡単ではなかった(「官立大学と私立大学との比較」同一九二六年一一月号)。
■なぜ早稲田出身の記者が多いのか
戦後に首相となる石橋湛山は、専門学校時代の早稲田大学の文学科を1907年に首席卒業し、特待研究生として宗教研究科も修了、『東京毎日新聞』を経て東洋経済新報社に入社した。
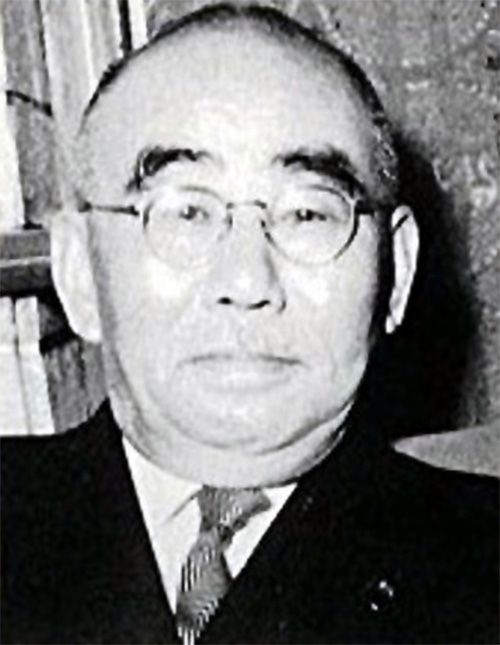
自伝『湛山回想』によると月給は18円で、4歳年上の小野義夫がいう早稲田法科の相場17円とほぼ同じである。下宿の一人暮らしでも少々足りない金額だったという。その石橋も、早稲田に対する差別待遇に憤っていた。
中等学校教諭は文学科の就職先としては最良の部類だが、石橋によれば公立校には帝大と高等師範の学閥があり、早稲田出身者は少し昇進するとクビにされたらしい。大正の中頃まで早稲田出で公立中等学校校長の地位にいたものは一人もいなかったという。
慶應義塾と違って早稲田には実業界の勢力もない。「いっこう引っぱってくれる先輩がなく、はなはだ、みじめなものであった」と石橋は回想する。例外は「新聞界」と「文芸界」である。
「官学出で、これらの方面に志すものは、いたって少なかった」というのが大きな理由で、実際に石橋は新聞記者の道に入った。
東京専門学校草創期、政治科の学生たちは、判任官見習への無試験任用など二流の「特権」を拒絶した。彼らは下級官僚の卵ではなく「国家の人材」を自負していたのである。その自負心を満足させうる進路こそが、新聞記者であった。
■現代の記者と明治の記者の違い
当時の記者は、現代のサラリーマン記者とは違う。学校が創設された明治10年代は、自由民権運動の時代である。民権派は新聞を利用し、時に政府を激しく糾弾しつつ自陣営の主張を世間に浸透させようとした。
「記者・投書家であり、演説家であり、同時に党員・社員であるという人びと」が新聞を舞台に言論戦を展開していたのである。
1881年に自由党が、翌年に立憲改進党が結成されると、有力紙も民党系機関紙と化した。改進党系の新聞には『郵便報知新聞』(のち『報知新聞』)『東京横浜毎日新聞』『読売新聞』などがある(山本武利『新聞記者の誕生』)。
東京専門学校の首脳部を占めていたのはいうまでもなく改進党員で、彼らはもちろん新聞と深い関係を持っていた。小野梓は『読売新聞』で論陣を張り、高田早苗は1887年から『読売新聞』主筆を務めた。『郵便報知新聞』は、改進党の結成に加わりのちに東京専門学校校長も務める前島密の発案で創刊され、「明治十四年の政変」以後には矢野文雄が買収した。尾崎行雄、犬養毅もこの新聞に依拠した。
のちに大隈重信が「野に下つた我輩は種々とやつて見たが、大概は皆失敗で今日残つて居るのは、此学校(早稲田大学)と、報知新聞」と回想したほど、大隈系と強く結びついていた(『大隈侯昔日譚』)。
■「国家の人材」を自負する早大生の行き先
十四年の政変で下野して改進党結成に参加した島田三郎は、東京専門学校議員であると同時に『東京横浜毎日新聞』を拠点とし、やがて社長となった。政治活動家であり、言論人であり、最高度の知識人である人々が創設し、運営する学校ということ。教壇にも姿をあらわす彼らの存在は、「国家の人材」を自負する学生にとってまたとないロール・モデルとなる。
村松忠雄の『早稲田学風』によれば、草創期の早稲田の学生は、東京の官立私立の学生の中で「最も弁論に長し最も文筆に巧みに、且つ一種のヂクニチーを保つ」と称せられたという。
彼らの演説の仕方、文章の書き方、さらにはディグニティ(威厳、気品)のあり方は、要するに改進党員でありかつ早稲田の経営者や教員でもある人々から伝染したものだった。
同書には「其演説議論及びヂクニチーなるものは、矢野小野鳩山嶋田〔島田三郎〕尾崎高田等の諸先輩が……社会の上に一種の異彩を放ちて、所謂『改進党気取』を始めしものが、次第に学生を感化し、学生をして同一スタイルたらしめたるによる歟」とある。
そして、学生が渇仰する政党人であり新聞人であり教育者である高田らは、多数の卒業生を自分の関与する新聞社に送り込んだ。石橋湛山が最初に就職した『東京毎日新聞』は『東京横浜毎日新聞』の後身であり(現在の『毎日新聞』とは異なる)、早稲田大学教員の田中穂積が経営に参画した新聞である(河崎吉紀「新聞界における社会集団としての早稲田」)。
こうした流れによって、明治末期にはメディアにおける早稲田の優位が公然と語られるようになった。
■「天の川の星の数より多い」
早稲田出身の作家、河岡潮風は1909(明治42)年に著した『東都游学学校評判記』で次のように述べている。
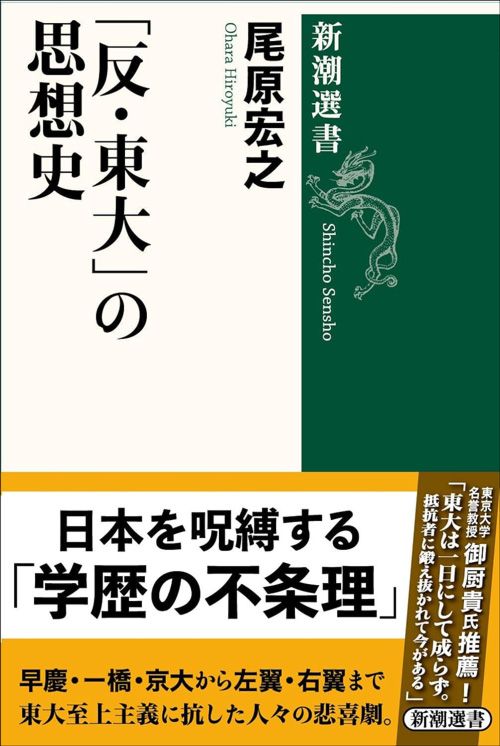
「〔早稲田出身者は〕一体に政府の事業では左程成功して居らぬ。法科でも判検事弁護士にも得意の腕を振へるもの少なし。商科にしても当分は日本銀行や何んかに向かぬ……其代り、新聞雑誌業には日本第一の大便宜を有し、他校が勢力を張らぬ間に、この方面に発展したものだから、有力な先輩多く、陣笠連に至つては、天の川の星の数より多い位。北は雪深き樺太の涯より、南、生蕃躍る台湾の端に至るまで、新聞と云ふ新聞、雑誌といふ雑誌には、少くとも一両名は早稲田出身者がゐる盛況。操觚者たらんには、本校に敵する修養所はない」。
早稲田は政府や商業関係では不調で、法曹界でも中央や明治などよりも実績が劣った。だが、新聞・雑誌への進出は早かったため、どの会社にも有力OBがおり、ヒラ記者にいたっては星の数ほどいる。表現者を志すなら早稲田に敵う学校はない、と河岡はいう。
----------
甲南大学法学部教授
1973年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。日本放送協会(NHK)勤務を経て、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(政治学)。専門は日本政治思想史。著書に『大正大震災 忘却された断層』(白水社)、『軍事と公論 明治元老院の政治思想』(慶應義塾大学出版会株式会社)、『娯楽番組を創った男 丸山鐵雄と〈サラリーマン表現者〉の誕生』(白水社)など。
----------
(甲南大学法学部教授 尾原 宏之)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
新・親も知らない今どき入試 「早慶の現役実合格者数ランク」 実合格者数、早稲田111人・慶応104人で渋谷教育学園幕張が首位 2位と4位は公立高校
zakzak by夕刊フジ / 2024年6月28日 15時30分
-
超大手・人気企業への就職に強い大学ランキング トヨタ、ソニー、キーエンスなど8社の就職上位校
東洋経済オンライン / 2024年6月27日 7時0分
-
「有名400社への就職に強い大学」ランキング50 23年卒生で集計、「2強」に割って入る存在登場
東洋経済オンライン / 2024年6月25日 7時0分
-
GMARCHで「ネームバリューが高い」と思う大学ランキング! 3位「学習院大学」、2位「明治大学」、1位は?
オールアバウト / 2024年6月9日 20時45分
-
帰国子女、ハイレベル校にアッサリ合格の納得理由…富裕層の移住の第一選択肢〈シンガポール〉で展開される受験対策に「なるほど」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月6日 11時0分
ランキング
-
120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も
日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分
-
2「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分
-
3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分
-
4イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目
ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分
-
5医薬品の販売規制案にドラッグストア反発の事情 市販薬のオーバードーズ問題に有効な規制とは
東洋経済オンライン / 2024年7月2日 12時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












