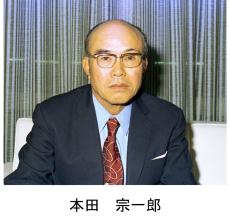遊んでいない人間に、売れる商品は作れない…本田宗一郎が「芸者の話は仕事の話より大事」と語った意味
プレジデントオンライン / 2024年6月26日 8時15分
■本田宗一郎が「会社で一番大事」と語ったこと
人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。在任中の功績の「A面」だけでなく、独自の価値観や知られざる人柄など「B面」がある。むしろ、経営者のB面こそが企業文化を形作っているといってもいいだろう。本連載では経営者のB面に光を当て、令和のビジネスにも通じるヒントを探る。
自動車各社は円安を追い風に過去最高益を軒並み叩き出す一方、トヨタ自動車など5社では、車の「型式指定」に関する認証不正が見つかった。
「良品に国境無し」と語ったのはホンダ創業者の本田宗一郎だが、そのホンダも5社に含まれていた。本田がもし生きていたならば、何というだろうか。
本田宗一郎といえば自動車メーカーのホンダの創業者であり、松下幸之助と並ぶ戦後日本が生んだ最も高名な経済人でもある。自動車業界でホンダは「技術のホンダ」とも呼ばれるが、これは小卒のたたき上げの技術者であった本田のイメージも影響しているだろう。
だが、本田を「技術の人」と捉えてしまうと彼の凄さを見誤る。本田は「会社で一番大事にしているのは技術ではない」といってはばからなかった。「技能よりもアイデアをいかにだすかにもっていかなければならない」と売るためのアイデアを重視した。
■「物作り」ではなく「いかに物を売るか」
いかにつくるかではなく、いかに売るか。
令和の今では当たり前に思えるだろうが、昭和30年代にこれを看破していた。「つくれば物が売れる」時代に、物を売るための方法を徹底的に考えていた。
「つまり、それってマーケティングでしょ?」と指摘されそうだが、本田のマーケティングとみなさんのイメージするマーケティングは違うかもしれない。彼はデータをあまり重視しなかったことでも知られる。専門家がなぜ素人に意見を聞かなければいけないのだといってはばからなかった。
「僕は、市場調査を、過去の足跡をたしかめること、自分の意見を大勢の社員に納得させる場合の手段として使うこと以外には考えていない」
市場データだけに執着する令和の管理職には耳が痛い言葉かもしれない。
では、本田はどのようにして売れるアイデアのヒントを探ったのか。それは結果的には「遊び」によるものだった。彼の言葉を要約すると、以下のようになる。
データとにらめっこしているのではなく、遊ぶことが人間を知ることになり、まわりまわって商売にもなる。そのためには、自分を型にはめず、行動する――。
■「芸者の話は仕事の話より大事」の意味
いかにして本田はそうした思考にいたったのか。
本田は1906年、静岡県に生まれる。1922年に高等小学校を出ると、東京・湯島の自動車修理工場「アート商会」に勤め、自動車の修理技術を身につけた。28年に故郷・天竜近くの浜松に戻り、アート商会浜松支店を設立する。当初は堅実にお金を貯めようとしていたが、芸者遊びが止まらなくなる。
「収入がふえてくるとそれだけに遊びも激しくなり、金をためようという気などはどこかへ行ってしまった」
時代が時代である。お金があれば芸者遊びも珍しくないが本田の場合は度が過ぎていた。
アート商会を経営していたころの有名なエピソードがある。
宴席で芸者の言動に腹を立てた本田はその芸者を料亭の2階から外に放り出してしまう。奇跡的に途中の電線に引っかかったため、生命に別条はなかったが、本田は「危うく殺人罪になるところだった」と述懐している。また、飲酒運転で橋げたに突っ込んで芸者と一緒に川に落ちたこともあった。

「とんでもない男だ」と非難する人もいそうだが、注意しなければいけないのは、本田は芸者を軽んじていたわけではない。むしろ逆だ。
宴席で芸者そっちのけで仕事の話をしていた部下を翌日呼び出し、「芸者の話は仕事の話より大事だろ」と雷をおとしたこともある。どんなときでも相手に寄り添い、耳を傾ける。当然、芸者にもモテた。
■突然、1年間仕事をしない宣言
本田はのちにこのころの遊びが自分の商売人としてのベースを形成したと語っている。
「花柳界に出入りしていると、人の気持ちの裏街道もわかってくるし、いわゆるほれた、はれたの真ん中だから、人情の機微というものも知ることができる。私がただまじめ一方の技術屋とはいささか違うところを持っているとすれば、こんなところに元があるといえそうだ」
戦前に修理業が軌道に乗ると、エンジン部品のピストンリングの製造に乗り出し、成功を収めた。納入先はトヨタだった。経営は安定していたが、戦争が終わると会社を売り払ってしまう。
本田はその理由を「戦時中だったから小じゅうと(舅)的なトヨタの言うことを聞いていたが、戦争が終わったのだからこんどは自分の個性をのばした好き勝手なことをやりたいと思ったからである」と振り返っている。
そこから、ホンダのサクセスストーリーが始まるかと思いきや、ホンダの前身となる「本田技術研究所」という名で個人事業を始めるのは1946年の9月。ピストンリング製造会社の株を売却してから、1年余りの時間があるのだ。
何をしていたのか。何もしなかった。ただひたすらぶらぶらと遊んでいた。45年9月に「仕事はしない、1年間、遊んで暮らすから、食べさせて」と妻のさちに言った。時に本田宗一郎38歳、不惑手前の妻子持ちとは思えない発言である。
■決して「敗戦ボケ」ではない
「会社を売ったのならば金があるし、生活に困らなかったのでは」と思うかもしれないがそれは違う。株の売却額は45万円(現在の価値で1億円以上)だったが、本田は「これは大切なお金だから、つかっちゃいかん」と全く手を付けなかった。
妻のさちは生活費を貰えなかったので、自宅敷地で野菜をつくり、米は自分の実家から調達した。一方の、本田はドラム缶入りの医療用アルコールを買い、自家用の合成酒を作って友人と飲み、昼は尺八のけいこや将棋に励んだ。といっても、1日は長い。やることがなければ、軒下で1日中座り、何もせずにぼんやりしていた。

本田は仕事が嫌になったわけではなかった。世間の急激な変化に何も考えずに身をまかせることができなかったのだ。1年間のぶらぶら遊びは世の中の変化を考えるための期間だった。
「女房らは、私が遊んでばかりいていつまでたっても本気で事業にとりかからないのを見て心配しはじめた。私が敗戦ボケでふ抜けになってしまったのではないかと思ったらしい」と語っている。
環境を変えることで新たな視点が生まれ、何かを思いつくことはある。
■どうやって新しい技術を生み出したのか
技術が先にあるのではなく、人を知ることで必要な技術がうまれ、ものがうまれる。そうした本田ならではの観察眼をいかして、戦後の混乱の中で生み出した製品が「バタバタ」の愛称で知られるエンジン付き自転車だ。
ホンダといえば戦後にオートバイの成功で会社を一気に大きくしたイメージがあるかもしれないが、「エンジンのホンダ」の原点はバタバタである。ここに目をつけたのが生活者の視点をもった本田らしい。
きっかけはたまたまだった。友人の家に遊びに行った際に転がっていた旧陸軍の無線機発電用のエンジンを見て、アイデアを思いつく。そういえば、妻も自転車で買い物に行くのに苦労していたな。これを自転車につければいいと。
軍用の使われていないエンジンは敗戦に伴い用途がなく、そこらへんに余っていた。エンジンをいじるのはお手の物だ。問題はお金だ。会社の売却益はあったが、当時は超インフレの環境下にあった。日銀の卸売物価指数によるとインフレ率は終戦から1年で約5倍、2年で約16倍、5年で70倍を超えた。
お金の価値がみるみる減っていくわけだから、手元の資金だけでは十分でなかった。父親が所有していた山林を売り払って、事業に踏み切った。
■だから晩年にF1参戦した
エンジン付自転車は戦前に海外でつくられていて、一部は輸入されていたが、広がりはなかった。バスや電車、金があれば自家用車に乗ればよかったからだ。
戦後、「これからは自動車の時代」と誰もが思ったが、本田の見立ては違った。バスや電車は常に混雑し、ガソリン不足から自動車の運転もままならなかった。自転車が移動手段になっていたが、主婦たちが買い出しに使うには当時の自転車はペダルが重かった。
ガソリン不足が続きそうな現状を踏まえれば、みんなの足になっている自転車の利便性を高めればいい。エンジンをつければ売れるはずだ。
常識を疑い、世論に流されない。そのためには自分の頭で考える。それがバタバタの開発につながった
ここぞと思えば一気に勝負に出る。後の四輪車参入やF1参戦に見られるように、それが本田の金の使い方だった。

本田の読みは的中し、業者が遠方から買い付けにくるほどだった。バタバタの生産台数は月に200台、300台と右肩上がりになり、最終的には1000台近くまで増えた。ただ本田は満足しなかった。「もっと馬力のあるオートバイをつくりたい」と考え1949年にオートバイ事業に、そしてのちに自動車事業に参入する。
■「耳鼻科の先生」として飲み屋に通う
会社が成長しても本田は社長としてではなく、一個人として世の中を観察し続けた。還暦を過ぎても料理屋や飲み屋にひとりで通った。
「僕は、もともと好奇心のある方だから、いろんなものをいじるのが好きだし、いろんなところへ顔を出すようにしている。一杯呑み屋にもよく出かける。それが自分の固定観念をうちこわすには大いに役立っている。(中略)商品である以上、大勢の人が対象だから、みんながどういう欲望をもっているかを見抜かなければ話にならない」
上野の飲み屋では素性を隠して「耳鼻科の先生」として常連になった。当然、会社の仕事の話をするわけもなく、偉ぶることもなかったので女将も信じ切って本田と無駄話に興じていた。なぜ「耳鼻科の医者」だったかというと、「耳鼻科といえば、まず質問される心配が無い」からだという。
ある日、本田が何人かの連れに「社長」と呼ばれ、訝しがっていると、バカ話ばかりする「耳鼻科の先生」が本田宗一郎であることを知らされた。後日、本田のもとに女将から「本田技研の社長さんであることを全く知らず大変失礼な事をした」と丁重な詫び状が届いたというから、いかに本田が相手の属性を問わずフラットに接していたか、遊んでいたかがわかる。
■「数字ばかりおっかけていないんで、人を見るんだぞ」
「仕事につながるから遊べ」「仕事のために飲みに行け」と本田はいいたいわけではない。遊びの効用を考えた時点で遊びは遊びではなくなる。仕事になってしまう。遊びが仕事に活きると考えたらいけない。目的を考えずに遊びに夢中にならなければいけない。それが結果的に仕事のアイデアにつながったり、経験を重ねたことが仕事の役に立ったりすることもあるのだ。
「そりゃ年をとってからは「遊びの効用」なんてことを口にするようになりましたが、それはこの二、三年であって、若い時は要するに遊びたいから遊んだんです。理屈なんかありゃしない。遊ぶのに理屈をつけるのは卑怯だな。遊びたいから遊びたい。」
遊びたいから遊ぶ。遊べば人間を知れる。人間が社会や経済を回しているんだから、人間を知ることは実は何をするにしても不可欠だ。本田の教えはいたってシンプルだ。
先行き不透明な時代は守りに入りがちだ。企業も二番煎じの商品や過去データを重視した商品などをこぞって投入する傾向にある。だが、そうした時代は今までの延長戦の発想は通用しにくい。本田は「市場ではなく人を見ろ」と常に言い続けた。「人間」を知らない技術屋の増加に警鐘を鳴らした。
最近の自動車業界の不正は企業の極端な生産性の追求が現場を圧迫していたことが原因のひとつだろう。本田ならばこう説くはずだ。「数字ばかりおっかけていないんで、人を見るんだぞ」。
参考文献
本田宗一郎『俺の考え』(新潮文庫)
本田宗一郎『夢を力に』(日経ビジネス文庫)
伊丹敬之『人間の達人 本田宗一郎』(PHP研究所)
----------
ライター
1980年東京都生まれ。2005年、横浜国立大学大学院博士前期課程修了。専門紙記者を経て、22年に独立。おもな著書に『人生で大切なことは泥酔に学んだ』(左右社)がある。
----------
(ライター 栗下 直也)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
喧嘩の弱い、遊びを知らない「優等生」の話など誰も聞きたがらない…新聞・テレビの「正論」が皆つまらない理由
プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分
-
ホンダは大丈夫か?
財経新聞 / 2024年6月27日 17時47分
-
50cc以下原付の生産終了へ…ホンダは電動二輪実用化に巨額投資(重道武司)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月27日 9時26分
-
衝撃的…「昭和世代が想像する老舗」と「令和の老舗」のすごいギャップ
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 9時0分
-
「学校に通うのは反対じゃ...」松下幸之助の父が、奉公をやめさせなかった理由
PHPオンライン衆知 / 2024年6月11日 11時50分
ランキング
-
1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小
時事通信 / 2024年6月29日 15時49分
-
2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分
-
3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!
乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分
-
4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分
-
5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?
東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください