「なぜ生物は死ぬのか」という問いは間違い…生物学者の東京大学教授「死ぬものだけが今存在している」深い理由
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分
■生物の死と老い
死というものがなぜあるかといえば、それが生物の持っているプログラムだからです。
生物の誕生に大きな役割を果たしたと考えられるRNA(リボ核酸)と呼ばれる物質は、単純な構造で、生物ではないのに自己複製でき、また変化していろいろな種類のものを作り出す能力を備えていました。RNAは壊れやすいため、作っては壊れ、壊れてはまた作り直すということを繰り返してきましたが、そのうちに自然に効率よく増えるものが残ってきました。結果的にそれが進化のプログラムだったのです。
「変化」していろいろなものができる。そして、その環境に適したものが「選択」的に生き残る。この「変化と選択」が進化のプログラムです。これがたまたま、地球で動き始めたんですね。適したものが生き残り、そうでないものは壊れる。この「壊れる」ということが死の始まりです。
■「変化と選択」の繰り返しが生物の進化のプログラム
RNAや、タンパク質の材料となるアミノ酸などは、原始の地球の熱水噴出孔のようなところで化学反応により生まれたと考えられています。そして、RNAはアミノ酸をつなげてタンパク質、スライムのようなドロドロした塊である「液滴(えきてき)」を作るようになりました。
これは生産効率のよいRNAの自己複製マシーンなのですが、その中に偶然、「袋」に入るものが出てきます。液滴は化学反応が起こりやすい水溶性で、袋は水に溶けない脂溶性。この袋の中ならば、より安定した環境で自己複製でき有利です。効率よく自己複製するその袋入り液滴が、徐々に増えて支配的になり、やがて袋ごと増えるようになり、最初の細胞の原型になっていったと考えられます。
DNA(デオキシリボ核酸)はRNAの材料である糖の種類が変化してできました。DNAの方が安定しており壊れにくいので、それもまた変化と選択で、DNAがRNAに取って代わり遺伝物質になっていったのです。
細胞が誕生してからも、変化と選択は繰り返されます。はじめは単細胞生物。そのうちに単細胞がいっぱい集まって、それぞれが分業するようになる。これが多細胞生物です。多細胞化した方が生き残りやすかったものもいたのでしょう。
■進化しないものは絶滅し、多様性ある生物が生き残った
生物は突然降って湧いたわけではなく、単純なものから少しずつ変化と選択を繰り返しながらできていきました。進化のプログラムの根底には、常に「作っては壊し」があり、死ぬものだけが進化できたといえます。
ですから、「私たちはなぜ死ぬのか」というのは問いとして間違っていて、「死ぬものだけが今、存在している」というのが正しいと思います。逆説的な話ではありますが、死なないと進化のプログラムが動かず生命の連続性を維持することはできなかったのです。
進化をやめて「死なない」という選択肢を取るものもいたかもしれませんが、多くは絶滅したと推察されます。中には、不死とまではいかなくても、死ぬというプログラムがなかなか動かず、ものすごく長生きになってしまったものはいます。
北極海などに生息するニシオンデンザメとかアイスランドガイという二枚貝は400年くらい生きるといわれています。そのような動物は概してあまり環境が変わらないところに住んでいるために、昔ながらの形態のままでもよかったのかもしれません。
ただ、そういう場所以外の地球の環境は変化がありますから、長生きするよりも「ちゃんと寿命が決まっていて、世代交代して多様性をいつでも作れるような生物」の方がよかったでしょう。加えて有性生殖により、親と少し違う子どもを作るようなライフスタイルの生物が、最終的に生き残ってきました。
生物には多様な種が存在し、生態系が複雑になるほど、いろいろな生物が生きられるようになります。そして、それぞれの生物はいろいろな戦略で生き残ってきました。
例えばキリンの首は戦略的に伸ばされたわけではなくて、突然変異で長い個体が生まれ、たまたまその個体のいた所にいい具合に食べ物があったのでしょう。普通に考えれば、首が長過ぎると不便でしかないのですが、彼らの生きる環境ではその方が有利だったから選択されたと思われます。進化とはそういう偶然の繰り返しなのです。

■シニアの存在が集団を強くし、人間の寿命が徐々に延伸
人間はどうでしょうか。
人間は他の大型霊長類と違ってなぜか体毛が抜けてしまい、さらには木にも登れなくなりました。それぞれが弱いので、生き残るためには皆で協力する必要がありました。人間が他の霊長類よりも長生きになったのは、長生きする方がその集団の力が強くなったから。つまり、シニアがいい仕事をしたのです。
例えば、この見方で一番有名なのが「おばあちゃん仮説」。チンパンジーなどの場合、体に毛が生えているので、生まれてすぐにお母さんにしがみつけます。つまり、お母さんは子どもがいても両手が空くのです。でも人間の場合は、生まれて2~3年は誰かが抱っこしたり、ついていたりしなければいけないですよね。そういうときに親以外で誰が頼りになるかといえば、祖父母。おじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見てくれる方が、親に余裕ができて圧倒的に子沢山になる、という理論です。加えて、若い人だけの集団よりもシニアがいる集団の方が、話がまとまる。若い頃は生きるための欲に満ち溢れていますが、シニアになるとそういうことから解放されてきて、人のために何かしようと思うようになるからかもしれません。
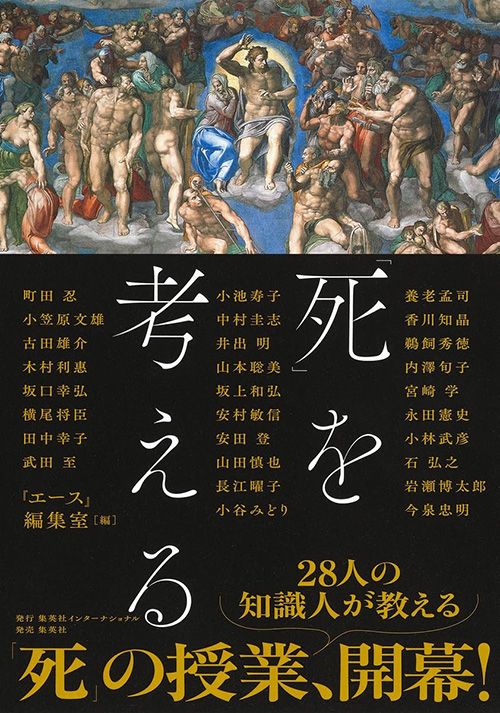
ゴリラやチンパンジーのメスは死ぬまで生理があるし、オスも死ぬまで生殖しますから、人間のような利他的な存在にはなりません。彼らの中にシニアはいないのです。生物としては、生殖に関わらなくなった個体がいるのはほぼ人間だけ。これもまた変化と選択で、たまたま生殖機能を失っても生きている人が出てくるようになり、そういう人には孫がたくさんできた、それが長寿化の原因の一つになっていったということなのだと思います。
人間の寿命は社会によって決まります。その社会が何を選択するかによって進化の方向は変わるのです。昔は集団(コミュニティー)を大切にしたためにこういう進化を遂げてきたけれど、今はどうでしょう? コミュニティーに属さなくても基本的には生きていけますから、今後の人間が違う進化の道筋をたどる可能性は十分あると考えられます。(以下、後編に続く)
----------
東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野)
1963年、神奈川県生まれ。東京大学定量生命科学研究所教授、日本学術会議会員。九州大学大学院修了(理学博士)、基礎生物学研究所、米国ロシュ分子生物学研究所、米国国立衛生研究所、国立遺伝学研究所を経て現職。日本遺伝学会会長、生物科学学会連合代表を歴任。著書に『生物はなぜ死ぬのか』『なぜヒトだけが老いるのか』(ともに講談社現代新書)、『寿命はなぜ決まっているのか 長生き遺伝子のヒミツ』(岩波ジュニア新書)などがある。
----------
(東京大学定量生命科学研究所教授(生命動態研究センター ゲノム再生研究分野) 小林 武彦)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
注意されても、酒もタバコもやめなくていい…和田秀樹が「医者の言いなりでは人生を損する」と説く理由
プレジデントオンライン / 2024年6月29日 10時15分
-
人間の神秘!生物学者・小林武彦さん『生物学者が死生観を語る』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!
PR TIMES / 2024年6月28日 12時45分
-
「高齢でもヨボヨボにならない人」は明らかにその"数値"が低い…最新研究でわかった人間の寿命差を生む要因
プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時16分
-
【中部大学】世界初、難しかった3個以上の染色体断片を結合させることに動物実験で成功--壊れた遺伝子を修復する技術の開発を目指す--
Digital PR Platform / 2024年6月10日 14時5分
-
生物学者が歳をとってわかった「人生の意味」 人間にとって「自我」こそ唯一無二のものである
東洋経済オンライン / 2024年6月6日 18時0分
ランキング
-
1約300万円の「エヴァ」巨大フィギュア、発売中止 発送予定から“2年後に”告知と謝罪
ねとらぼ / 2024年6月28日 20時35分
-
2トヨタ「プリウスα」なぜ消滅? 「復活」の可能性はある? “ちょうどイイサイズ”に3列シート装備で「画期的」だったのに… 1世代限りで生産終了した理由は
くるまのニュース / 2024年6月28日 20時10分
-
3気になる汗悩みを解決!40・50代におすすめの制汗剤4つ
つやプラ / 2024年6月28日 12時0分
-
4年金不安、シニア破綻は他人事ではない「老後ビンボー」を防ぐ《50代からのマネーの心得》
週刊女性PRIME / 2024年6月29日 7時0分
-
5内情を暴露しても日本企業の被害は減らない…「KADOKAWA VS. NewsPicks」騒動で本当に重要なこと
プレジデントオンライン / 2024年6月29日 7時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












