「開かずの踏切の死亡事故」の責任は誰にあるのか…「ペナルティを与えればミスは起きない」が大間違いなワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月29日 9時15分
※本稿は、松尾太加志『間違い学 「ゼロリスク」と「レジリエンス」』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■「罰則を設ければミスはなくなる」ほど単純ではない
エラーを防止する際に安易に考えやすいのは、人間が引き起こした失敗なのだから、人間を何とかすればよいのではということである。ヒューマンエラーは本来であればできたはずなのにできなかったのだから、人間が悪いんだというわけである。
その結果、ヒューマンエラーを起こした人にペナルティを与えるようにすればいいのではないかと考えてしまう。ペナルティがあることがわかっていれば、それが抑止力になって気をつけるから、エラーがなくなるのではないか。
残念ながら、そんなに単純なものではない。人間を悪者にした対策では何も解決しないのである。
■「開かずの踏切」の遮断機を上げた保安係
【事例】遮断機を上げざるをえなかった開かずの踏切の事故
2005年に起こった踏切事故の例である。踏切の保安係が列車が接近しているのに遮断機を上げてしまい、通行した人が亡くなった事故があった。現在のほとんどの踏切の遮断機は列車の接近に伴い自動で上げ下げされるが、当時は保安係という人が遮断機を操作している所があった。といっても、目視で列車の接近を確認していたわけではなく、列車の接近情報は機器上に表示されるため、それに応じて操作することになる。
これだけだと保安係が遮断機を上げてしまったことが問題のように思えるが、その背景要因を考えると、彼だけを責めるわけにはいかない事情があった。
■「ルール違反」を犯した運用で通行待ちを緩和
この踏切は開かずの踏切だった。列車が通過して遮断機が上がると思ったら、すぐに反対方向から列車が来てしまい、遮断機が下がったままで次の列車の通過を待たないといけなくなり、その繰り返しが続く。
この踏切は上下合わせて5本の線路があった上に、すぐ近くに駅があったため、いつまでたっても遮断機が上がってくれない。ただ、列車が通過後反対側からの列車が来るまでの間には、待っている人間の感覚では意外に時間があり、この間に遮断機が上がらないのかと通行待ちの人は思ってしまう。
安全上それはできないのだろう。事故が起こったこの踏切には早上げ防止鎖錠装置というのがついていて、通過後早く遮断機を上げてしまわないようにロックがかかるしくみになっていた。
しかし、そのしくみをそのまま運用してしまうと、いつまでたっても通行できない。そこで、保安係がロックを解除して遮断機を上げるようにしていた。もちろんこれは業務上はルール違反である。
保安係は、列車接近が列車接近表示灯により確認できるので、通行者の利便を考えてタイミングを見計らって、遮断機を上げていたようだ。それは通行者と保安係の暗黙の了解であったのだろう。

■「業務」と「通行者」との板挟み
朝夕のラッシュ時には列車の本数も多くなる。開かずの踏切になってしまうと長時間待たされる。事故は夕方の午後5時近くの時間帯であった。保安係は、下りの準急が通り過ぎたら、次の下りまで1分半時間があるから、その間に遮断機を上げれば通行できると考えた。ところが、このとき、上りの準急が来ることを確認していなかった。列車接近表示灯の確認をせず、ロックを解除し、遮断機を上げてしまった。
そこに上りの準急が入ってきた。電車は急ブレーキをかけたが間に合わなかった。2人が負傷し、2人が亡くなった。
問題なのは開かずの踏切になってしまったことである。保安係は決められた通りに作業を行えばいいはずだが、その通りにやっていたら、いつまでたっても通行者は渡れない。そうすると、遮断機を上げてくれと詰め寄ってくる通行者もいるだろう。
事故報告書でもそのような事情は説明されていた。「通行者からのプレッシャーを感じることもあった」と記されていた。業務として決められた通りにやらないといけないが、一方で通行者も通してあげなければならない。その板挟みになっていたのだ。そこをうまく調整するにはルール違反をするしかなかったのである。
■「開かずの踏切」がそもそもの欠陥
開かずの踏切を作ってしまったということ自体が明らかにシステムの欠陥である。列車の運行のことだけしか考えておらず、近隣の通行者のことを考えていない。一方で、列車に乗る人のことを考えると、列車の本数を減らすわけにはいかない。列車の運行と通行者の立場を調整するのは現場の人間になってしまう。システムの欠陥の調整役が現場に求められた。
安全だけを考えれば自動で遮断機が動くようにしていればいいはずである。しかし、そうすると、ますます開かずの踏切になってしまい、誰も通れなくなってしまう。そこに人が介入すると、列車の通過の隙間をうまく見つけて通行できるようにすることが可能になる。
こうして、現場の保安係は調整を暗黙に任されていたのである。しかし、もともと欠陥のあるシステムなので、その調整がいつもうまくいくとは限らない。うまくいかなかったとき、ヒューマンエラーという形で出てくるのである。
そのとき、その人間を責めることができるだろうか。自分が同じ立場で同じ役割を担わされたときに、絶対にミスをしないと言えるだろうか。この役割を任せられたら、この保安係と同じようなことを誰しもがしたかもしれないのだ。
先の患者取り違えの事故(註)の場合、2人同時にストレッチャーで運ぶのが問題であって、それがなければ事故は起きなかったと考えられた。しかし、それは業務体制の問題である。同じ時間に手術が集中していて、病棟の看護師は限られた時間の中で、患者さんを手術室に運ばなければならなかった。当人だけが責められる問題ではない。
(編註)1999年に看護師が患者2人を取り違え、それぞれに異なった手術を行った事故
■保安係を懲戒解雇、実刑では何も解決しない
この踏切事故の保安係は実刑判決を受けてしまった。会社も懲戒解雇となってしまった。遺族の心情としては何も責任が問われないことになるのは容認できないだろうが、実はこれでは何の解決にもなっていない。開かずの踏切という欠陥のあるシステムは何も改善されないからである。
この踏切の場合、直後の対策として、近くにエレベータ付きの歩道橋の設置などがなされた。さらに、時間がかかったが高架化され、踏切はなくなった。それが根本的な解決の道だった。
ヒューマンエラーは、往々にして不完全なシステムを使うことを余儀なくされた人間が起こしてしまうものである。普段はなんとかだましながら調整して行っていたのだが、ちょっとしたひずみが生じたときに、うまくいかなくてエラーを起こしてしまうのである。
■必要なのは罰則ではなくモノやシステムの改善
現場の人間は、勤務体制や扱っているシステムからの要求、そのサービスを受ける人などからの要求も含め、さまざまな要求を迫られている。通行者からは早く遮断機を上げてくれと言われる。一方でロックを解除することはやってはいけないという圧力がある。人間の裁量でうまく調整するしかない。しかし、バランスが崩れるとどこかにヒビが入る。それがヒューマンエラーとなって表出した。
そのとき、すべきなのは人にペナルティを与えることではなく、体制やシステムそのものを改善することなのである。
エラーを起こした人をどう改善に導くかが重要だと思われがちだが、人に改善を求めることが余計な負荷をかけることになっているのが現実である。エラーを起こしたくて起こしているわけではなく、そのとき置かれた場面では必然的になした行為や判断がヒューマンエラーとなっている。
ある意味、その場面だけを考えると、合理的な行為や判断であったことになる。それを局所的合理性ということもある。開かずの踏切で通行者を通してあげるために、遮断機を上げるというのは、あの場面では合理的であった。
つまり、ヒューマンエラーを起こしてしまうことが合理的になってしまう場面を改善しなければならない。その場面を作り出しているのは人を取り巻くモノやシステムなのだ。もちろん、人間側に対する対策も必要となるが、それよりも人間が使うモノやシステム、組織の体制などの対策が先行されるべき重要課題となる。
■罰則は隠ぺいを生み、根本解決から遠ざかる
それでも、エラーを起こした人に対して、ペナルティを与えようとしてしまう。それはやってはならない。
一般には、罰は故意に行った行動の抑制にはなるが、ヒューマンエラーのように意図的に行っているわけではない場合はまったく効果がない。
罰則を前提にすると何が生じるかというと、エラーの低減ではなく、隠ぺいにつながっていく。隠ぺいされてしまうと、潜在的に存在している問題が解決されないままで、小さなエラーで済んだものが大きなものとなって顕在化してしまう。
先の踏切事故のようなケースは隠しようがないが、医療現場、製造現場などの場合、当事者にしかわからないことも多く、場合によっては隠ぺいされかねず、問題の解決につながらなくなってしまう。
■アメリカのパイロットは航空機事故において「免責」される
ヒューマンエラーが生じた場合、それを引き起こした要因が何であるのかを突きとめ、解決することが重要である。人を罰するのではなく、そのエラーを教訓として、今後同様のことが生じないようにすべきである。
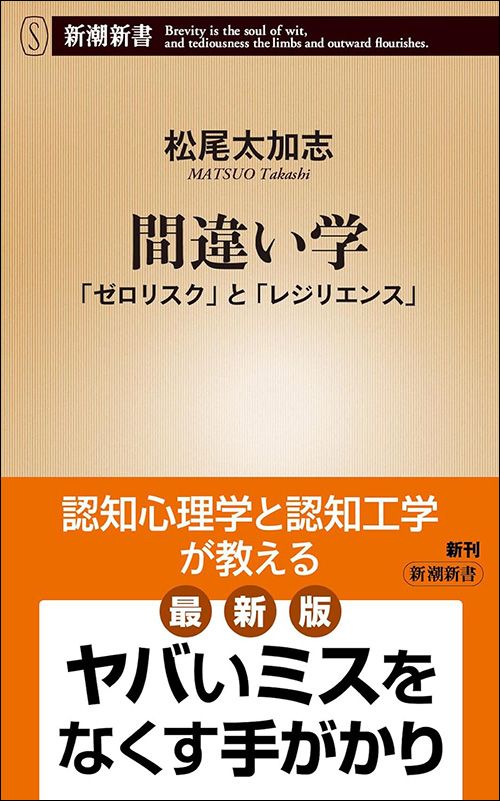
アメリカでは航空機事故の場合に、当事者に対しては免責が与えられる。航空機事故では、コックピットの中で生じたことはそのクルーにしかわからないことが多い。事故の要因を調べるにはクルーに正しく証言をしてもらわなければならない。自分のミスが誘因となって事故が生じた場合もあるからだ。
その際、そのミスに対して罰が与えられるとすると、自分のミスを隠ぺいしてしまい、ミスを隠すために事実でないことを証言してしまう可能性がある。その結果、本質的な問題が解明されないことがある。すると、潜在的に抱えている問題が解決されない。そして、何も改善されないまま再び航空機の運航が続行されてしまうと、将来的により大きな事故につながる可能性は十分にある。
■将来のより多くの乗客の命を守るための選択
1人のパイロットを免責にすることで正しい証言をしてもらう。そう判断をするのが賢い選択である。それによって、将来、大勢の人が遭遇し、より多くの命を失ってしまう可能性のある事故を防ぐことができる。公共の利益を優先するのである。1人のパイロットを免責するのか、将来起こりうるであろう多くの尊い命の犠牲をとるのかという選択なのである。
繰り返すが、ヒューマンエラーは意図的に行った行為ではない。本人がおかれた業務の体制、環境要因、システム、モノ、その人をとりまくさまざまな要因がそろったときに生じている。その人自身を罰することは何の解決にもならない。
もちろん、エラーによって生じてしまった損害は補償しなければならない。ただし、その補償は原則的に組織が負うべきであり、個人に責任を転嫁してはいけない。
----------
北九州市立大学特任教授(前学長)
1958(昭和33)年福岡市生まれ。九州大学大学院文学研究科心理学専攻、博士(心理学)。著書に『コミュニケーションの心理学 認知心理学・社会心理学・認知工学からのアプローチ』など。
----------
(北九州市立大学特任教授(前学長) 松尾 太加志)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
どれだけ機械化してもミスは起こる…コンビニの「10個のところ100個仕入れちゃいました」がなくならないワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 9時15分
-
警報機だけで遮断器ない踏切で死亡事故、緊急点検で「窓閉め切った車内では警報音が聞こえない」
読売新聞 / 2024年6月24日 17時9分
-
JR五能線の踏切で列車と軽トラックが衝突する事故 軽トラックの79歳男性が死亡 現場は遮断機のない踏切
ABS秋田放送 / 2024年6月20日 18時53分
-
警報機も遮断機もない第4種踏切、神奈川に25カ所 5カ所は存続方針、鉄道事業者は頭悩ませ
カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年6月8日 22時24分
-
“山手線の踏切”なんてまだマシ? 都会に残る「開かずの踏切」5選 行ってわかった深刻さの“違い”
乗りものニュース / 2024年6月2日 9時42分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
-
3若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
4Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成
isuta / 2024年6月29日 18時0分
-
5伊藤沙莉、「優三さんが…」 直道&花江“再会”の裏で起きていた出来事に「エモい!」「泣けます」の声
Sirabee / 2024年6月29日 17時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












