どれだけ機械化してもミスは起こる…コンビニの「10個のところ100個仕入れちゃいました」がなくならないワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月30日 9時15分
※本稿は、松尾太加志『間違い学 「ゼロリスク」と「レジリエンス」』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
■機械は人間の機能が「外化」されたもの
18世紀の産業革命は人間の生活や社会に大きな変化をもたらした。そして、それ以降のさまざまな技術の進展が私たちの生活スタイルを変え、仕事の内容も変わってきた。
これまで人間が行っていた仕事の中には、機械に置き換わっていったものも少なくない。それは、機械のほうが効率的で間違いをしないからである。人間が行えば必ずヒューマンエラーを起こしてしまうなら、機械に任せたほうがよい。そのため、これまでに人間の仕事の数々が奪われていったとも言える。
そして、ITやDXの進展による情報化は、単に産業革命の延長線上にあるのではなく、質的に大きな変化をもたらしている。さらに人工知能が実用的に利用されるようになると、特定の仕事だけが機械化されるということではなく、ドラスティックに人間の仕事や役割が変わってしまう可能性を秘めている。
機械は、人間のある特定の機能が外化されたものにすぎなかった。車や飛行機は人間の歩くという機能が外化したものであり、さまざまな工作機械は人間の手足の動きが外化したものである。そして、コンピュータは脳が外化したものと言われていたが、AIやロボットは人間そのものが外化されてしまうような存在であり、さまざまな場面で人間に代わって仕事をするようになるかもしれない。
では、もっと人間が関わらなくなれば、ヒューマンエラーは今よりも減るのだろうか。
■人とのやりとりを極限まで減らしたAmazon
ヒューマンエラーをなくす究極の方策は、人間が何もしないことである。もっとも、それは現実的ではない。ただし、人を介さないことでヒューマンエラーは低減する。とくに人と人とのやりとりをなくすことである。現在、実現している技術を見てみよう。
●ネットでのオーダー
Amazonに代表されるように、今や実店舗に行かずにネットで注文してどんなものでも購入することが日常になっている。人と人とのやりとりをせずに注文が済んでしまう。IT化されると、電話や対面での口頭のやりとりでのミス、手書きによる書き間違いや読み間違いなどがなくなる。
モノの注文の場合、ITによってシステム化してしまえば、客が最初のオーダーの入力さえ間違えなければ、途中に人が介することなく、メーカーあるいは物流業者に正しくオーダーが届けられることになる。物流も自動化されていて、自動的に倉庫からオーダー品がピックアップされるというしくみも可能であり、最後にはじめて人間が最終チェックをして梱包し配送することになる。
さらに、さまざまな手続きもオンラインで可能となっている。モノの注文でない場合は、一切人が介することなく完了させてしまうことができる。銀行などのようにお金の入出金をするような場合は、インターネットバンキングによってすでに実現している。また、航空券や電車の切符、コンサートやイベントなどのチケットもネットで購入し、QRコードがスマホに送られれば、紙の切符やチケットも必要がない。
途中でいろいろな人が関わると、そのプロセスの途中でヒューマンエラーが生じてしまうが、このように人が介在しなくなるとヒューマンエラーは低減される。
■飲食店ではタブレット端末で注文、精算はセルフレジ
●自ら端末でオーダー
対面の場合はどうしてもヒューマンエラーが起きてしまう。飲食店で食事の注文をしたときに、間違ったモノが出てきたことはないだろうか。客が口頭でフロアスタッフに注文したときに、注文がうまく通っていないことがある。
ところが、最近はタブレット端末が各テーブルに置いてあったり、スマホでQRコードを読み込んだりすることで、食事注文のアプリが起動し、客自身でオーダーできる。これだとフロアスタッフを介さずにオーダーできる。

そして支払いもセルフレジで各テーブルのQRコードをかざして人を介さずに済ませることが可能になっている。人間同士のやりとりの場合、コミュニケーション・エラーが発生する可能性があるが、そのようなエラーはなくなる。
ファストフード店でも、店に設置してある端末で注文をしたり、自分のスマホでモバイルオーダーによって注文をするようになっており、店員は注文された品物を渡すだけで、客からの注文を直接受けないようになっている。使い方がわからない客がいても、口頭での注文を受けるのではなく、端末に誘導して、端末で操作をしてあげる。そうすることがオーダーのミスを防ぐことになる。
フロアスタッフの仕事は、注文を受けた食べ物を運ぶだけになっている。運ぶこともいずれロボットに任せられれば、人間はいらなくなる。回転寿司などで注文した寿司を自動的に届けるようなシステムを構築しているところもあり、人手がいらなくなっている。無人化は夢ではなくなりつつある。
■エラーを気付かせる「電子アシスタント」
人を介さないことでヒューマンエラーが低減できるが、最初の入力の段階でエラーが生じてしまう可能性は残っている。そのため、入力に間違いがないかをチェックし、間違っていれば気づかせるしくみが必要となる。
電子アシスタントの場合、エラーをチェックするというのは、機械的なチェックであれば簡単にできる。たとえばメールアドレスを入力する場合、ドメイン名の前に「@」がつくことになるため、「@」が含まれていなければメールアドレスとして認識されず、間違いであると指摘できる。
郵便番号、電話番号などもある程度はチェックできる。桁数が多いとか少ないとか、数字以外のものが含まれていると明らかに間違いだとわかる。その間違いをどのように指摘するかも重要である。
ユーザビリティ(使いやすさ)の第一人者と言われるニールセンは、10の原則を提案しており、この中でエラーに関することにも触れているのが「エラーメッセージを具体的に」というものである。
ネットでなんらかの手続きをする際、入力ミスが生じた場合、「正しく入力されていません」といったエラーメッセージが示されることがある。どの項目がどのように間違っているのか具体的に指摘をしてもらわないと外的手がかりとしては有用性が低い。
■「IDかパスワードが間違っています」のもどかしさ
よくあるのが、ログイン時の「IDかパスワードが間違っています」というメッセージである。セキュリティ上の問題でどちらが間違っているかを明示的に示せないのであろうが、ユーザからすると、IDが間違っているのか、あるいは、IDは存在しているがパスワードが違うのかを知りたいはずである。
また、パスワードを設定する場合、パスワードの文字列には、いくつかの条件が決められている。8文字以上、大文字と小文字、数字を含める、記号を含めるといったことである。
ユーザが入力したパスワードの文字列がこれらの条件を満たしていない場合、警告を出すことになる。その際、ただ「パスワードが適切ではありません」といったメッセージではなく、「大文字が含まれていません」や「8文字以上ではありません」というふうに具体的に何が問題なのかを教えてあげる必要がある。
家電製品などでエラーを記号だけで示したり、音のパターンで示したりしただけではどんな間違いなのかわからない。電子アシスタントであれば、具体的に何が間違っているのかを的確に示すように設計することが可能なはずである。
■桁を間違える誤発注がいまだに防げない理由
機械的なチェックでなくても、常識的に考えて不自然な場合に気づかせるようにすることもできる。たとえば、注文の数量が多い場合、発注者に警告を出すようなことは可能である。注文の数量を一桁間違い、10のところを100としてしまったとする。常識的に考えて多すぎるので警告を出すことができる。
しかし、その数量が多いか少ないかはモノによって異なる。たとえば、パソコンを5台注文した場合、個人では多すぎるが会社だと十分にあり得る。数は品物によって常識的な範囲が異なる。ボールペンを10本といった場合、個人でも購入する可能性はある。
誰がどのようなモノを注文するかによって常識的な数量かどうかが異なる。それを一律に、ある数量以上は警告を出すようなことをすると、わずらわしくなるし、その数量チェックでは引っかからないエラーも出てくる。
実はこの「常識的に考える」というのは機械は苦手である。人工知能を利用すればある程度「常識的に考えた場合」に近づけることができるが、人間のように細かく配慮することは難しい。人間ならばいろいろなことを想定して、間違いではないかどうかをチェックしてくれる。

■「細やかな判断」はまだまだ人間に軍配
私の経験だが、スマホオーダーのホルモン居酒屋にひとりで行ったとき、ミックスホルモンを頼んだ。そのホルモンが出てくる前に、メニューを見ていると焼きモヤシというのがあったので、それを追加で注文した。
しばらくすると店員さんが、「ミックスホルモンにもモヤシが入っていますけど、焼きモヤシも注文いいですか?」と尋ねてくれた。ミックスホルモンにモヤシが入っていたのは知らなかったが、野菜をたくさん食べたかったので、それでかまわなかった。
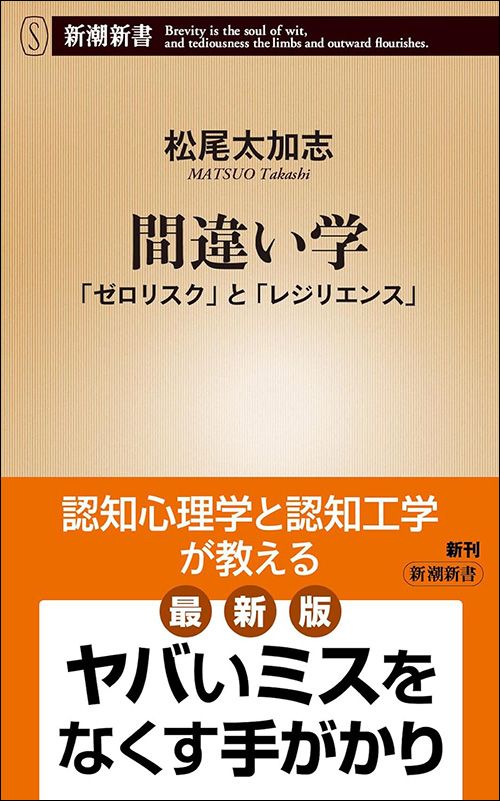
こういう細やかな判断ができるのは人間でしかない。ただし、これも、複数の客であればそのような注文もおかしくないと考えられ、ひとり客であるから、尋ねてみてくれたのだろう。何気なくやっていることであっても、人間はいろいろな情報から的確な判断をすることができている。
電子アシスタントでこのような場合のチェックまでできるだろうか。AIで過去の注文のビッグデータを活用して対応できないことはないが、よけいなおせっかいになりそうな気がする。
電子アシスタントでエラーに気づかせるには限界がある。人間の意図と実際の入力内容に相違があったとしても、電子アシスタントではその違いに気づくことは難しい。それに気づくのはやはり人間でしかない。その点を改善するには、電子アシスタントの設計を人間と機器が関わるインタフェースにおいて、「人間」がエラーに気づきやすいようにするしかない。
----------
北九州市立大学特任教授(前学長)
1958(昭和33)年福岡市生まれ。九州大学大学院文学研究科心理学専攻、博士(心理学)。著書に『コミュニケーションの心理学 認知心理学・社会心理学・認知工学からのアプローチ』など。
----------
(北九州市立大学特任教授(前学長) 松尾 太加志)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分
-
「開かずの踏切の死亡事故」の責任は誰にあるのか…「ペナルティを与えればミスは起きない」が大間違いなワケ
プレジデントオンライン / 2024年6月29日 9時15分
-
サイゼリヤのスマホ注文が合理的なワケ 実体験で分かった“利用者ファースト”な仕組み
ITmedia Mobile / 2024年6月9日 6時5分
-
飲食業界の人手不足問題を解消! レジメーカーが独自のノウハウをもって券売機市場に新規参入 新紙幣対応クラウド型タッチ券売機を新発売
PR TIMES / 2024年6月3日 10時45分
-
「月商100万円以下」では採算が合わない…零細飲食店が頑なに「モバイルオーダー」を導入しない切実な理由
プレジデントオンライン / 2024年6月1日 17時15分
ランキング
-
1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」
Sirabee / 2024年6月29日 4時0分
-
2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分
-
3水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策
ananweb / 2024年6月29日 20時10分
-
4忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選
日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分
-
51年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方
東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください












