「小学校卒の学歴」だからではない…田中角栄が毛沢東から"無教養"を皮肉られた本当の原因
プレジデントオンライン / 2024年10月24日 18時16分
■「漢文不要論」こそ不要である
――中国社会では、日本人が思っている以上に歴史や古典といった教養が重んじられるようですね。
一定以上の知識レベルの人は、会話の途中にしばしば「中国にはこういう言い回しがある」と言って古事成語や古典、歴史の知識を持ち出してきたりします。日本も昭和の頃まではそうでしたが、政治家でも経営者でも、リーダーたる者は十分な教養を備えるべきという教養主義が中国ではなお健在です。
いっぽうで日本ですが、本来日本には近代以前からの漢学の蓄積があり、中国の歴史や文化に関する知識は、もともとは世界のなかでトップクラスです。韓国やベトナムも漢字文化圏ですが、現在は漢字を使っていない。欧米については、『フォーリン・アフェアーズ』などを読んでいても、ときには研究者レベルでさえ中国の歴史や文化への理解がかなり乏しい人がすくなくないと感じます。
本来、中国史や漢文の知識は、世界のなかで日本が圧倒的なアドバンテージを持つ強みでしょう。SNS上ではしばしば「漢文は役に立たない」と「漢文不要論」が取り沙汰されますが、わざわざ全世界で唯一持っている武器を自分から手放すのはナンセンスだと思います。それらは、現代中国を分析して対峙(たいじ)していくうえでも有用な知識だからです。
■中国が「沖縄独立論」を煽る深い理由
――最近では、沖縄(琉球)独立を煽るフェイクニュースがネット上に大量に投下されましたが、中国の関与が指摘されています。こうした動きも、歴史と関わりがあるんでしょうか?
中国の沖縄工作の活発化は、直接的には昨年6月の習近平の発言がゴーサインになっているのですが、深層心理としては歴史への認識もあると思います。
ご存知の通り、近代以前の沖縄は琉球王国として中華王朝から冊封(形式上の君臣関係)を受けて朝貢(皇帝に貢物を献上し、返礼品を受け取る外交・貿易関係)する関係にありました。江戸時代以降は清朝と江戸幕府への両属関係です。近年の中国の沖縄介入には、習近平体制に入ってからの中国外交に漂う「王朝時代の朝貢関係の結び直し」という思想も無縁ではないでしょう。

中国の外交姿勢からこうした思想を感じ取れるのは、有名な「一帯一路」政策です。これは内陸ユーラシアの「陸のシルクロード」とインド洋沿海諸国を中心とした「海のシルクロード」の各国との関係を強化する習近平政権の外交戦略です。近年は中国の景気低迷もあり、すこし低調ですが、とはいえ言葉としては提唱され続けています。
■「一帯一路」政策の背景にある“古代王朝”
23年5月に広島でG7サミットが行われた時、中国では“裏番組”のような形で、習近平をホスト役とする「中国・中央アジアサミット(中国中亜峰会)」が開かれていました。カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの中央アジア5カ国が陝西省の西安、つまり唐の時代の長安に招待され、唐代の宮殿を模した建物で唐代風の儀礼で歓待されたのです。
このときに呼ばれた各国の大部分は、唐の最盛期には西域(さいいき)と呼ばれ、現在の国土のすくなくとも一部が唐の勢力範囲内に入っていた歴史があります。当時の唐の皇帝は、中央ユーラシアの国々から「天可汗(てんかかん)」の称号で呼ばれ、西域諸国の朝貢を受ける立場でした。現在の「陸のシルクロード」からは、当時の紐帯関係の復活を望むような意思を感じ取ることができます。
一帯一路政策の「海のシルクロード」も同様で、これらの対象諸国は、明代に南海遠征をおこなって各国の朝貢を勧誘した鄭和の航路とかなり一致する。習近平はインド洋各国との外交の現場で鄭和の事績にしばしば言及しており、こちらも往年の朝貢国の結び直しの意思を感じます。
■形を変えていまも残る「朝貢関係」
――現代においても、「朝貢」という意識がどこかにあるのでしょうか?
もちろん、中国も「主権国家間の平等」という近代の国際関係の基本は知っているのですが、それをどこかで相対化しているというか、「西側が作ったただのタテマエでしょ」と冷ややかに見ているところがあると感じます。

中国は経済がかげった現在でも、アフリカ諸国にお金をばらまいて強力に経済援助を推し進めています。あれも中国の国際貢献ということになってはいますが、現代における形を変えた「朝貢関係」と見ることもできると思います。
中華帝国は朝貢関係を持った国に対して、基本的に内政干渉はしないし自治も認めますが、一方で中国の徳を慕って尊敬することを求める。そうすれば、採算度外視で恩恵を与えるという関係です。
そもそも主権国家間の平等という発想が薄く、強い中国を認めて尊重すれば世界は平和であるというのが伝統的な中華帝国の国際関係観なのですが、問題は現代中国の世界とのかかわりかたにその発想が復活したように見えることです。
■「対等な外交関係」をまったく経験してこなかった
近代に入り、日清戦争をはじめとした対外戦争の敗北のなかで朝貢システムは段階的に破綻していきます。中国の版図は欧米列強に蚕食され、最後は日本の侵略を受けました。
中国の悲劇は、近代に入っても対等な国家間関係のモデルを習得できなかったことです。朝貢関係のように相手の上に立つか、あるいは自分たちが劣位になって列強から搾取されるか。冷戦期を経てから、西側諸国の外資を受け入れた改革開放政策も、胡錦濤時代ごろまでは、まだ貧しかった中国が劣位に立つことで成立していた面があると思えます。
結果、自国が強くなった習近平時代になると、中国はどうやって他国と国際関係を結んでいいかわからなくなった。そこで出た答えが、「自分たちは強いんだから、他国は尊重して然るべきだ」「それこそ世界を平和に保つ国際関係だ」という、朝貢体制期の世界観の復活なのではないかと思えます。
もちろん、欧米や日本は「主権国家間の平等」という近代の国際関係が頭にありますから、こういう中国の思考が理解できない。いっぽうで中国も過去の王朝ほど鷹揚(おうよう)ではないので、ヒステリックに西側諸国を非難し、関係をより悪化させる。負のスパイラルですよね。
■「春眠暁を覚えず」の罠
――教養が欠如していると、中国では軽んじて見られてしまうそうですが、具体例はありますか?
近年は世代交代で減りましたが、私たちが20代後半くらいまでは、中国のビジネスの現場で「中国古典が好き」な団塊世代以上の偉い人がけっこういましたよね。それ自体はとてもいいことなのですが、自分が思う「教養」が中国人から尊敬され得るものかは別の話です。
たとえば、日式カラオケ店で「春眠暁を覚えず」で有名な漢詩『春暁』を中国語で暗唱してみせるおじさん。当然、お店のお姉さんや取引先の人たちは仕事なので「すごい」と感心したフリをするわけですが、内心は非常に戸惑っていたと思われます。
というのも、中国では時にやり過ぎなまでに、子供に大量の漢詩を学ばせます。なかでも『春暁』は幼稚園児でも暗唱させられる。なので、いい年したおじさんが暗唱するのは、日本人の感覚に置き換えると『くじらぐも』や『スイミー』の朗読くらいの感じになります。
もちろん本人が悦に入るのは構わないとはいえ、客観的にはかなり痛いですよね。教養をひけらかしたいときは、その「教養」が相手の国ではどのくらいのレベルとして見られるのかを想像する慎重さも必要になります。
■角栄の漢詩、毛沢東の皮肉
――日中の外交史においても同様の事例はあるのでしょうか?
1972年の日中国交正常化の際、田中角栄は毛沢東向けてこんな「漢詩」を送っています。
修好再開秋將到(修好再開 秋まさに到らんとす)
鄰人眼温吾人迎(隣人 眼 温かにして吾人を迎え)
北京空晴秋氣深(修好再開 秋将に到らんとす)
漢詩として見た場合、文法や平仄(ひょうそく)がめちゃくちゃで、それっぽく28個の漢字を羅列しただけのシロモノです。田中角栄が自分で作ったことは感じられるので、この点は誠実ともいえるのですが、詩人としても知られる毛沢東は反応に困ったと思います。プロの漫画家が、素人がチラシの裏に書いた落書きを持ってこられるようなものですから。
毛沢東はこの時、田中に『楚辞集注(そじしっちゅう)』を送り返しています。戦国時代の楚の詩集『楚辞』に南宋の朱熹が注釈を加えた書物です。近年、日本のSNS上などで「漢詩を基礎から勉強しなおせ」という意味だったとする巷説も流れていますが、実際はもうすこし複雑なメッセージが込められていたようです。
この訪中時の晩餐会で、田中角栄は往年の戦争被害について「ご迷惑をお掛けし」と発言し、中国側から「迷惑どころではない」と強い反発を招いていました。いっぽう、楚辞には「迷惑」という単語のルーツとなる表現が含まれています。
中国側の報道を読む限り、毛沢東が『楚辞集注』を送ったのは「迷惑」の意味を考え直せというメッセージだったようです。もっとも、さすがにハイコンテクストすぎて常人には解読不能なのですが……。

■「シナ学」が抜け落ちている現代日本
――そもそも、中国史の視点から現代中国を解説するという本書の発想はなぜ生まれたのでしょうか。
日本には伝統的に「シナ学(シノロジー、中国学)」と呼ばれる、東洋史(中国史)・中国文学・中国哲学を柱として中華世界の総合的な理解を試みる学問があります。戦前、東亜同文書院や満鉄調査部など日本の中国研究シンクタンクは当時の世界ではかなり高い研究水準を誇りましたが、これも研究者たちのシナ学的な素養と無関係ではありません。
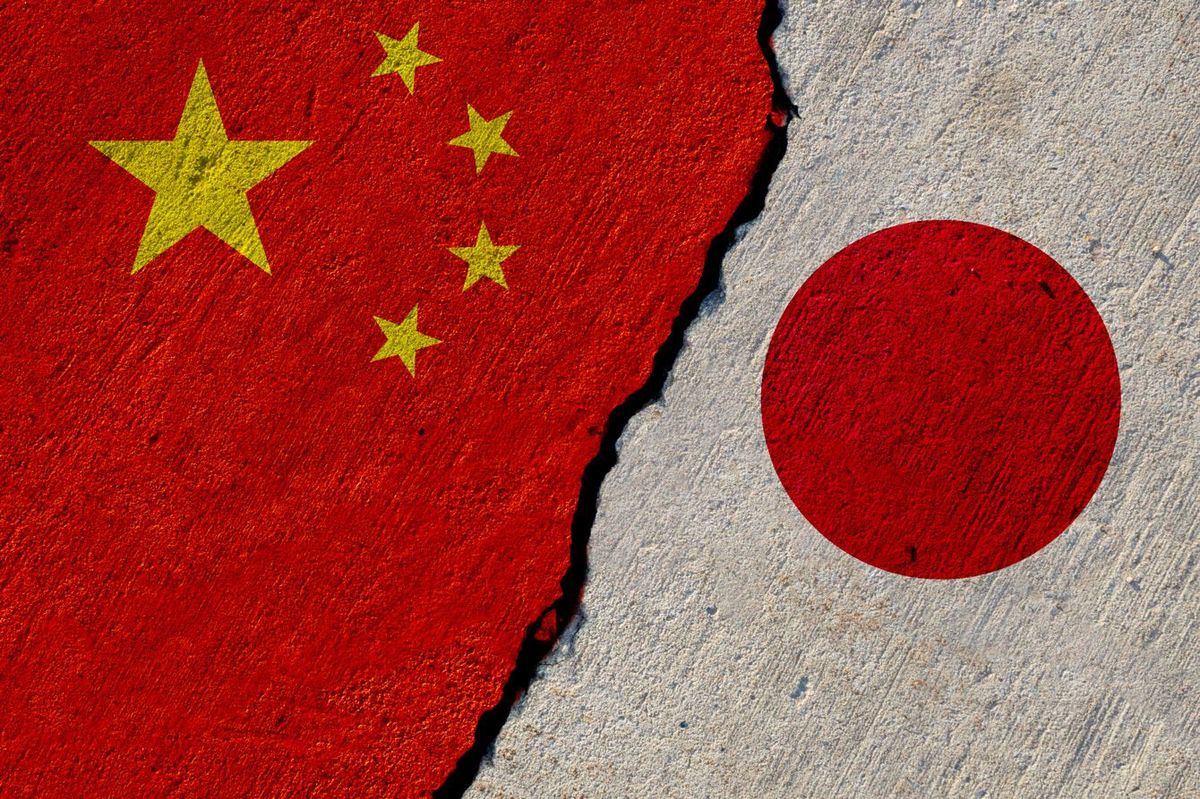
不幸なことに、こうした知見は中国侵略や諜報の武器としても使われたため、戦後はその反省から、伝統中国の知見に基づいて現代中国を分析する手法が学術界でなかばタブー視されるような風潮が生まれました。
ただ、「シナ学」が現代中国を分析するうえで有用であることに変わりはありません。にもかかわらず、外交官やジャーナリスト、経済アナリスト、現代中国研究者といった中国社会を分析する人たちのあいだですら、伝統中国の世界についての知見があまり共有されていない印象です。このことは非常にもったいないと感じてきました。
テレビのワイドショーなどでは、1980年代の改革開放政策以降の流れを把握できているならまだ良いほうで、ともすると前政権の胡錦濤時代の中国像すら抜け落ちた状態のまま、中国を語ろうとする論客さえいる。中国に対する憎悪や蔑視感情を刺激するだけの単純な言説も目立ちます。こうした言説は、中国という現実的な脅威に対する正確な理解を妨げるという意味で、むしろ有害と言えるでしょう。
■「名球会」と「エアプ勢」の中国史論
――中国学によって現代中国を読み解く本は、過去にはなかったのでしょうか。
過去の東洋史学者では宮崎市定。近年の故人ではモンゴル史研究者の杉山正明氏や、中国文学の高島俊男氏。現役の研究者では岡本隆司氏などが、現代社会にも目配りのある素晴らしい著作を多く残されています。
ただ、こうした先生がたはいずれも、野球でいえば「名球会」レベルの名選手。逆に言えば、東洋史関連のアカデミックの世界は、身を修めぬ者が天下を論じるのはおこがましいという感覚が強すぎるのか、「普通のプロ選手」や「競技経験者」がそれを語ることを遠慮する空気がありました。これは学問的姿勢としては美徳なので、評価が難しい部分もありますが。
また、「名球会」選手の解説は素晴らしい水準なのですが、名選手だけに人数が限られる。結果、かえって「競技未経験の素人(エアプ勢)」の跋扈(ばっこ)を許してしまうという問題があります。そのため、日本の一般向けの中国史言説では、野球でいえば「ホームランが多い選手はえらい」ぐらいの、非常に雑な解説が蔓延しています。OPSも盗塁数も守備率も、全然見ないで語るレベルの自称解説が、名球会の専門的な解説を押しやってしまっている。
■「実用的な中国知識」が不足している
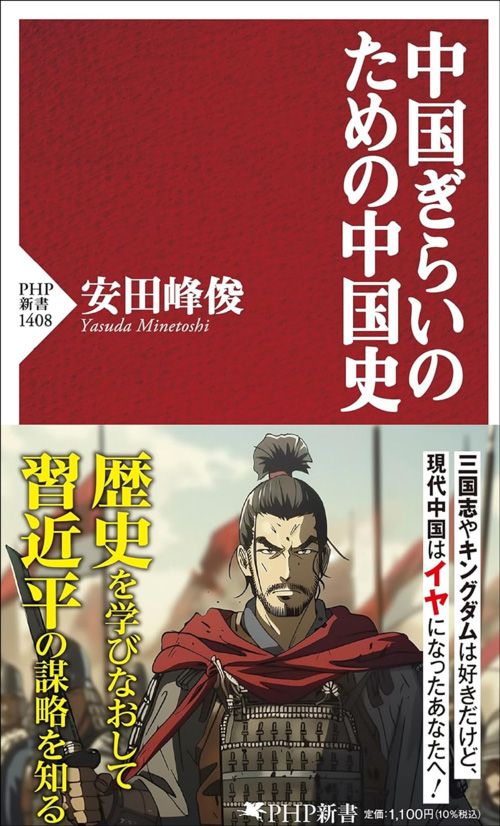
一方、私は現代中国のジャーナリズムのプロとされますが、中国史を学んでいたのは修士課程までです。学問的な水準については、プロ選手どころか「高校野球の地方大会準決勝敗退のピッチャー」くらいでしょう。ただ、それでも体系的に学んだことがある競技経験者ですから、エアプ勢よりは正確なことを話せる。
ビギナー向けのコーチなら、「競技経験者」のほうが向いていることだってありますし、競技人口の裾野を広げるためにもそうしたほうが好ましい。しかも、多くの人にとっては趣味にとどまる野球と違って、中国学はその範囲にとどまりません。一人一人が現代中国の性質を知って分析するうえで役に立つ実用的知識ですから、多くの人に知られるべきだと思うんです。本書を世に出した動機はこれですね。
----------
紀実作家(ルポライター)、立命館大学人文科学研究所客員協力研究員
1982年生まれ、滋賀県出身。広島大学大学院文学研究科博士前期課程修了。著書『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』が第5回城山三郎賞と第50回大宅壮一ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。他の著作に『現代中国の秘密結社』(中公新書ラクレ)、『八九六四 完全版』、『恐竜大陸 中国』(ともに角川新書)、『みんなのユニバーサル文章術』(星海社新書)、『中国ぎらいのための中国史』(PHP新書)など。
----------
(紀実作家(ルポライター)、立命館大学人文科学研究所客員協力研究員 安田 峰俊 聞き手=西谷格)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
5泊8日南米出張…石破外交で3つの「意外」とは
日テレNEWS NNN / 2024年11月21日 6時30分
-
日中首脳会談…3つの「舞台裏」
日テレNEWS NNN / 2024年11月17日 14時3分
-
日本は「華夷(かい)秩序」を重んじる中国にどう向き合うか? 答える人 拓殖大学顧問・渡辺利夫
財界オンライン / 2024年11月7日 18時0分
-
中国の教科書には絶対に載せられない…習近平がひた隠しにする「偉大な中国史」の"不都合すぎる真実"
プレジデントオンライン / 2024年10月25日 16時15分
-
「三国志」の劉備でも「西遊記」の三蔵法師でもない…中国人が愛してやまない「本当の英雄」が"クズ集団"なワケ
プレジデントオンライン / 2024年10月24日 18時15分
ランキング
-
1【冬の乾燥対策に】ドラッグストアで手軽に買える! ハンドクリーム5選
マイナビニュース / 2024年11月21日 17時0分
-
2書店に行くとなぜか急にトイレに行きたくなる「青木まりこ現象」とは?
マイナビニュース / 2024年11月21日 16時2分
-
3【風呂キャンセル界隈】医師「心身が疲れた時こそ入浴を」 - 安全で健康的な方法とは
マイナビニュース / 2024年11月21日 11時0分
-
4とんでもない通帳残高に妻、絶句。家族のために生きてきた65歳元会社員が老後破産まっしぐら…遅くに授かった「ひとり娘」溺愛の果て
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月21日 8時45分
-
5生産性を上げ、まわりと差がつく5つの栄養素 ライバルを出し抜くために必要なのは「食事」
東洋経済オンライン / 2024年11月21日 10時30分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










