「クマがかわいそうだから殺すな」と抗議するのと同じ…クジラが「海の靖国問題」と呼ばれるようになった背景
プレジデントオンライン / 2024年10月30日 18時15分
■捕鯨は「日本文化」ではない
――捕鯨論争でひんぱんに耳にするのが、捕鯨を容認する側の「捕鯨は日本文化だから継続すべき」と考え方です。
意外に感じる人が多いかもしれませんが、捕鯨が日本文化と語られるようになったのは、ここ30年程度です。
確かに、日本では江戸時代から捕鯨を続けていました。しかし捕鯨を行っていたのは、和歌山県の太地町や、千葉県房総半島南部、高知県、九州北部から山口県などのごく限られた地域でした。正確には、捕鯨や鯨食は、日本文化というよりも、地域文化、もしくは地場産業です。「全国民的な日本文化」とは決して言えません。
その意味では、江戸時代から捕鯨を続けてきた地域には、捕鯨や鯨食は伝統文化として根付いていると言えるでしょう。
では、戦中の中断を挟みながらも、1934年から2018年まで南極海に船団を送り込んで続けた母船式捕鯨は日本文化と言えるのか。
江戸時代から続いた古式捕鯨とは異なり、南極海での商業捕鯨は長く見積もっても90年ほどの歴史しかない経済行為です。あるいは32年続いた調査捕鯨は水産庁の主導で実施されました。日本沿岸で行われてきた捕鯨と南極海での大規模な母船式捕鯨を一緒にして、日本文化と語るにはムリがあるのではないでしょうか。
■「日本は鯨をキレイに使ってきた」わけではない
日本文化論の最たるものが「欧米人は油だけ取って肉を捨てたが、日本人はクジラを余すところなく利用してきた」という誇張された言説です。
しかし現実には、日本が戦前に行った南極海での捕鯨では、欧米と同様、鯨油の生産が重視され、鯨肉の一部を捨てていました。
また、1980年代になると鯨類の生息数の減少が国際問題になり、商業捕鯨の継続ができなくなりました。そこで日本は、商業捕鯨の再開を目指して、鯨類の生態や生息数を確認するための調査捕鯨に舵を切ります。
当初、調査捕鯨では鯨体をすべて利用しなければならない決まりになっていましたが、やがて鯨油などの原料になる骨などの部位は捨てるようになりました。海の汚染を防ぐマルポール条約によって加熱などの処理をした部位の投棄が禁じられたからです。令和になり、日本のEEZ内で行われる商業捕鯨でも、在庫の調整のために内臓など需要が少ない部位を捨てています。
――調査捕鯨時代の2000年代、反捕鯨団体が、捕鯨船から鯨体の一部を投棄される写真を示して「クジラをムダにしている。日本はまたルール違反をしている」と批判していました。
捕鯨論争は、建設的な意見交換と言うよりも、批判のための批判になっていましたからね。2000年代だとすれば、マルポール条約が発効したあとですから鯨骨などは加工せずに捨てなければならなかったはずです。

■反対派が作り上げた「スーパー・ホエール」
――容認派は捕鯨を「日本文化」と主張し、捕鯨に反対する人たちは「クジラは特別な動物だから保護しなければ」と訴えます。しかしクジラと一括りに言っても、90近くの種が存在します。多様な人間とのかかわり方、さまざまな特徴を持つ種がいるのに、捕るか、護るか、と問題が抽象化されている気がします。
とくに捕鯨に反対する人たちは、クジラを「The Whale」と単数で語る傾向にあります。「クジラは世界最大の動物であり、大きな脳を持つ。人なつっこくて、歌を歌いもする。そんなクジラが人間によって脅かされている」と。
しかしこの特徴をすべて兼ね備えた種のクジラは存在しません。世界最大の動物はシロナガスクジラで、大きな脳を持つのはマッコウクジラです。人なつっこいのはコククジラで、歌うとされているのはザトウクジラ。絶滅に瀕しているのは、セミクジラです。
独り歩きしてしまった架空のクジラ像は、1990年代初頭にノルウェーの人類学者・アルネ・カッランが、反捕鯨の主張を否定するために提唱した「スーパー・ホエール」という概念です。

実際に数が回復して、持続的に利用できる種がいたとしても「スーパー・ホエール」だからすべての鯨類は捕っていけないという理屈になる。
その点を踏まえれば、捕鯨や鯨食の地域性や、鯨類と住民とのかかわりの多様さを無視し、なんでもかんでも日本文化に落とし込んで単純化させる言説は「逆スーパー・ホエール」とも言える現象かもしれません。
■捕鯨が「海の靖国問題」になってしまった
――南極海の捕鯨まで日本文化に含まれてしまった背景にはどんな事情があるのですか?
私は、反捕鯨国の主張や、シーシェパードなどの反捕鯨団体の抗議活動に対するカウンターパンチだと考えています。
1990年代前半、南極海での商業捕鯨が再開される可能性がありました。しかしIWC(国際捕鯨委員会)で、反捕鯨国に反対され、再開は頓挫してしまいます。そんななか日本の捕鯨を正当化する言説として「捕鯨文化論」が登場しました。いろんな偶発性が重なったものと考えていますが、1980年代に危機をいだいた関係者が、広告代理店などを巻き込んで鯨食文化を喧伝していたことも少なからず影響しているはずです。
日本は、国際世論や反捕鯨陣営に対抗するために、反論しにくい「文化」を持ち出したわけです。その結果、日本各地に点在していたいくつもの小さな捕鯨文化や、太地や和田浦の歴史が覆い隠されて、ないがしろにされてしまったのではないかと感じます。

たとえば、和田浦ではツチクジラという種類を捕獲しますが、ツチクジラ漁と南極海の捕鯨はなんの関連性もない。鯨肉を食べるという共通点だけで、果たして日本の捕鯨文化とひとまとめに語っていいのか。
文化と位置づけてしまうと、捕鯨がひとつの産業として社会にどれだけ資するのか、どんな問題を抱えているのか、検証する機会が奪われてしまいます。一方で捕鯨反対派は「スーパー・ホエール」だから捕鯨はダメだと譲らない。
交わることがない議論が延々と続き、一般の人は触らぬ神に祟りなし、と捕鯨に対して関心を失ってしまった。ある反捕鯨の識者が、捕鯨問題を「海の靖国」と評しました。靖国神社も、戦争責任や歴史認識の問題、諸外国への配慮などいくつもの問題が複雑に絡まり合っています。反捕鯨の識者と私とでは、捕鯨に関する考え方は異なりますが、「海の靖国」は言い得て妙だなと感じました。
■捕鯨と食料安全保障
――2019年に日本はIWCを脱退し、日本のEEZ内で商業捕鯨を再開しました。令和のいま、捕鯨を続ける意味や意義をどうお考えですか?
私はこの夏にデンマークのフェロー諸島で、400年続くヒレナガゴンドウという鯨類の追い込み漁を調査してきました。日本の捕鯨同様、シーシェパードからの妨害活動に遭うなど批判にさらされています。

批判や反対する人の主張は、次の3つ。これは日本の捕鯨や、太地で行われる追い込み漁への批判と同じです。
1つ目が、スーパーなどには十分な食料があるのだから、クジラを捕る必要がないこと。
2つ目が、残酷で非文明的なこと。
3つ目が、食物連鎖の頂点に立つクジラには水銀が蓄積するから健康被害の恐れがあること。
反発を受けながらも、なぜ、フェロー諸島では捕鯨を続けているのか。そこには、食の主権や、食の安全保障がかかわっています。
■フェロー人にとっては「離島で生き抜く術」
離島であるフェロー諸島には、週に1度、船でコペンハーゲンからの生活必需品や食料が届きます。
しかし今年の春、労働組合がストを起こし、船の運航を一時的に取りやめました。フェロー諸島では、食べ物や生活必需品が手に入らなくなった。島で都市生活を営む人は非常に困りました。フェロー諸島を調査するオックスフォード大学の大学院生は「物資不足で私たちは本当に大変な目に遭った」と話していました。一方で、「フェロー人は涼しい顔をしていた」というのです。
流通が機能する平時は、フェロー諸島の人々も、われわれ日本の都市生活者と同じで、スーパーなどの小売店で生活必需品を購入して暮らしています。ただ彼らがわれわれと異なるのは、有事に自給できる術(すべ)を持っていること。
フェロー諸島では、追い込み漁に参加した人なら、ヒレナガゴンドウの肉が平等に分配されます。老人や身体が不自由で漁に参加できない人にも分けられる。フェロー人は、そうして配られたヒレナガゴンドウを干し肉にしたり、飼育する羊をハムにしたりして、いざというときに保存食として利用してきた。それこそが、400年にわたって培われた離島で生き抜く知恵なのです。

■異なる環境で暮らす人びとへの想像力が欠如している
その話を聞き、思い出したのが、コロナ禍の日本です。
コロナ禍で冷凍食品が買い占められているというニュースを知り、近所のスーパーに様子を見に行きました。すると、本当に冷凍食品の売り場が空っぽになっていた。
食料自給の問題が浮き彫りになったのは、コロナ禍だけではありません。ロシアがウクライナに侵攻したら、小麦や食料油の値段が上がりました。今年の夏も気候変動や、インバウンドの増加によって米不足に見舞われました。
サプライチェーンが機能する平時、食料自給の必要性を意識する機会はほとんどありません。多くの人が、クジラを食べなくても、ほかに食べる物はいくらでもあると受け止めています。
しかしフェロー人たちの生き方を知った私は、島国である日本は、海の生物資源に依存しなければ生きていけないのではないかと改めて感じました。しかもフェロー人たちは、400年間、続けてきた自分たちの生き方に誇りを持っている。
それを都市生活者のわれわれが安易に「残酷だ」と批判するのは厳しい環境に住んでいる人を無視した極論だと言わざるを得ません。
クマが人を襲う被害に悩まされている秋田県に「クマがかわいそうだから殺すな」という抗議の電話が殺到したのは記憶に新しいでしょう。電話の主はいずれも「クマが出没した地域以外の人」だというのです。
死傷者が出ている秋田県の人にとっては「かわいそうなどと言ってられない」というのが本音でしょう。クジラも同じで、私は「自分とは異なる環境で暮らす人びとへの想像力が欠如している」点を危惧しています。捕鯨にも、その生活をしている人たちにしかわからない意義があるのです。
■量は少ないが、ゼロでないことが大切
――しかし、商業捕鯨を行う捕鯨会社・共同船舶が生産する鯨肉は1600トン前後に過ぎません。有事を支える食肉にはなりうるのは難しい。
確かにそれはそうなんです。ノルウェーやアイスランドからの輸入を合わせても、国内に流通する鯨肉の量は年間で2500トンほどですから。日本国民にあまねく行きわたらせたとしたら、1人16グラムほど。焼き鳥1本分にも満たない量です。その点では、捕鯨だけで、食の安全保障をまかなえるわけではありません。
ただ食の安全保障で重要なのは、選択肢をいくつも持つこと。
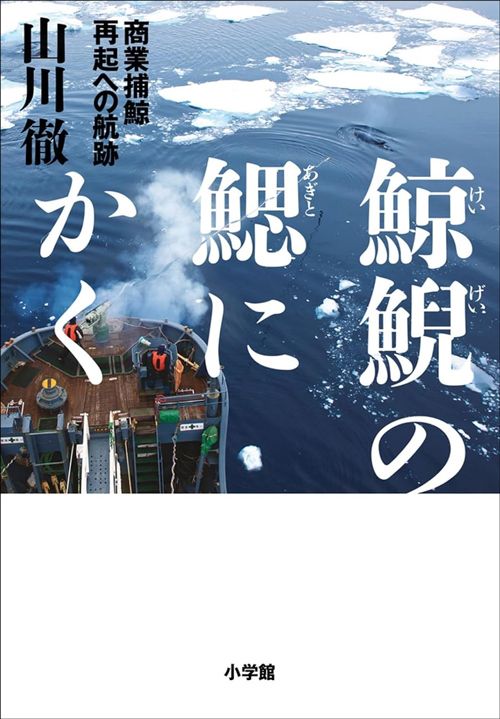
私は2021年に捕鯨母船・日新丸に乗り込んで日本の商業捕鯨の現場を調査しました。クジラを探す技術、クジラを捕る技術、クジラを解剖する技術(捕鯨の現場では解体を解剖と呼ぶ)、または鯨肉の質を見極める目……。特殊な技術や知識の累積で成立する捕鯨という産業を目の当たりにしました。
ふだん鯨肉を食べないから捕鯨は必要ない。そう考える人も多いのでしょうが、一度、捕鯨の技術が途絶えたら復活は難しい。捕鯨をやめたら鯨肉は生産できなくなってしまいます。
ゼロか、わずかでも捕り続けられる技術と設備を維持するのか。量的な問題以上に、食の多様性を守るために選択肢を持つことが大切だと感じるのです。
■ヒトが雑食である以上避けられない
――日本文化だから捕鯨を続けるのではなく、生きるために必要な食の多様性や選択肢を守るための捕鯨ということですね。
もちろん動物の権利や動物倫理の観点からすれば、捕鯨に限らず、動物を利用し、消費することへの是非について考え続けなければなりません。草食動物は草さえあれば生きていけます。肉食動物は、ほかの動物を食べて命をつなぐ。
われわれヒトは雑食だから、植物も動物も必要とします。ヒトは多様な食に、もっと言えば、生物多様性によって生かされていると言えます。生物としてのヒトが、雑食である以上、植物だけではなく、動物を食べるという行為から離れることはできないのです。
----------
一橋大学 大学院社会学研究科 教授
一橋大学大学院社会学研究科教授。専門は東南アジア地域研究・食生活誌学。ナマコ類と鯨類を中心に野生生物の管理と利用(消費)の変容過程をローカルな文脈とグローバルな文脈の絡まりあいに注目し、あきらかにしてきた。著書に『ナマコを歩く 現場から考える生物多様性と文化多様性』(新泉社、2010)、『鯨を生きる 鯨人の個人史・鯨食の同時代史』(吉川弘文館、2017)『生態資源 モノ・場・ヒトを生かす世界』(山田勇・平田昌弘との共編著、昭和堂、2018)、『クジラのまち 太地を語る 移民、ゴンドウ、南氷洋』(英明企画編集)などがある。訳書にアナ・チン『マツタケ』(みすず書房、2019)などがある。
----------
----------
ノンフィクションライター
1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館)、『それでも彼女は生きていく 3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子』(双葉社)などがある。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社)で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。Twitter:@toru52521
----------
(一橋大学 大学院社会学研究科 教授 赤嶺 淳、ノンフィクションライター 山川 徹)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
尾の身がキロ当たり20万円!新捕鯨母船「関鯨丸」捕獲のイワシクジラ初競り
KRY山口放送 / 2024年11月14日 11時51分
-
反捕鯨だけじゃない、犬、虫、カエル…他国食文化への反対運動
もぐもぐニュース / 2024年11月7日 12時59分
-
クジラ生かしてまちづくり 和歌山・太地でフォーラム
共同通信 / 2024年11月2日 17時18分
-
日本一の食が集まる下関 光がつなぐ、煌めく食と歴史の下関 「第4回 三つの日本一ふく、くじら、あんこう祭り」開催 ~111日間開催!~
PR TIMES / 2024年11月1日 10時45分
-
親子で鯨の持続的利用や鯨食文化を学ぶ「たべるくじらのがっこう」を横浜みなとみらいで開催
PR TIMES / 2024年10月30日 12時15分
ランキング
-
1「無人餃子」閉店ラッシュの中、なぜスーパーの冷凍餃子は“復権”できたのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月20日 6時15分
-
2ブランド物を欲しがる人と推し活する人の共通点 囚われの身になってしまう、偶像崇拝者たち
東洋経済オンライン / 2024年11月21日 14時30分
-
3食用コオロギ会社、破産へ 徳島、消費者の忌避感強く
共同通信 / 2024年11月22日 1時18分
-
4「サトウの切り餅」値上げ 来年3月に約11~12%
共同通信 / 2024年11月21日 19時47分
-
5さすがに価格が安すぎた? 『ニトリ』外食事業をわずか3年8カ月で撤退の原因を担当者に直撃「さまざまな取り組みを実施しましたが…」
集英社オンライン / 2024年11月21日 16時49分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![]()
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする

エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください










